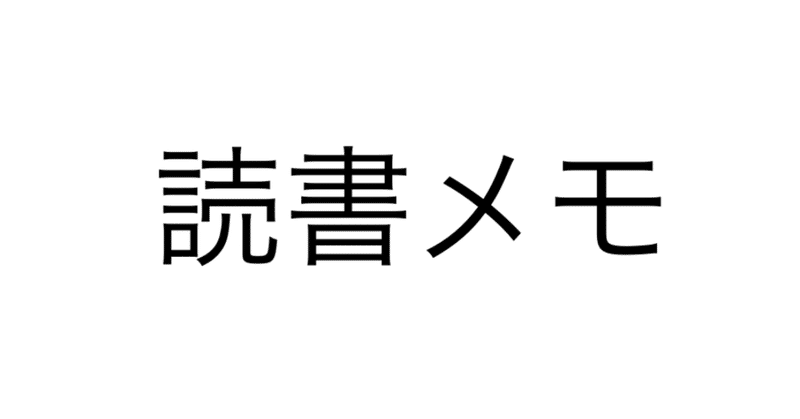
【読書メモ】会計の世界史 イタリア、イギリス、アメリカ――500年の物語
会計そのものを学ぶのにはこういう歴史から振り返ってみるのも良いかと思いチョイス。
ざっくりまとめ
・移動手段の発展や流通・文化の拡大化に伴い、財務会計や管理会計の概念が整ってきた(銀行→簿記→会社→財務会計→利益→管理会計)。
・時代が進むにつれて、なぜその概念が必要になったのか(例えば減価償却など)が書かれていてとてもわかりやすい
・現在日本は日本基準・IFRS・US基準のいずれかを選択して決算書を作る
感想
時系列に話が進んでいくことに加えて、 タイトル通りの世界史や音楽、アートなど例えなどがストーリーとともに紹介されていてわかりやすく、読み物としてもとても面白い。
会計計算、株主配当、コーポレート・ガバナンスの整備、など物流の発展、経済の発展と深く関連づいていることがよくわかる。
鉄道が世界初の固定資産が多い株式会社の資金調達・運用の実験でもあり、利益の概念の誕生や、財務会計と管理会計の歴史を変えるきっかけやになった。
バランスシートを読む時のコツとして「イギリスの金がアメリカの鉄道へ」というのは、とても覚えやすい。
EBITDAがM&A取引において重要になってきたのは、それが「キャッシュに近い」利益だったから。
コストかリターンか、どちらも重要な論点だが、そこのせめぎ合いから企業価値を重視した会計が誕生した。
最後まで読んでいただきありがとうございます! いただいたサポートは僕が読みたい書籍代に使います!!
