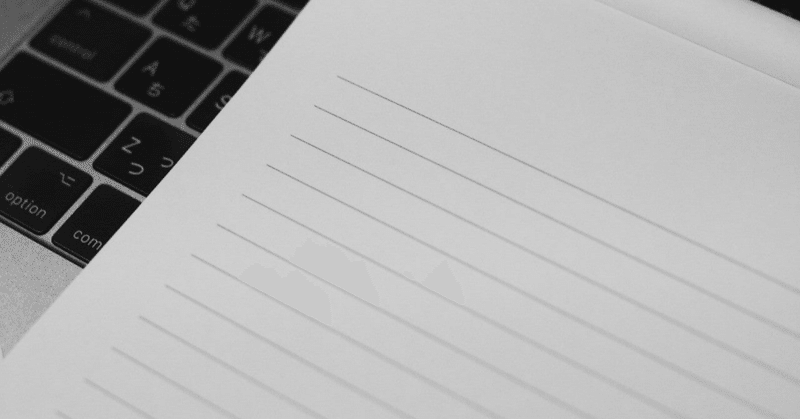
30代シングルマザー、遺言書を残す③
さてさて、ようやく遺言書の中身に突入します。
何気に時間がかかった遺言書作成。
作成しないならしないほうが良いのだろうけど、人生何が起こるか分かりません。
もし作成しないといけないとなった場合に、参考になるといいなと思っています。
よかったら②も読んで見てください!
遺言書の内容
行政書士にお願いし、遺言書の文面を考えてもらうことにしましたが、おおまかな内容はこちらから提示しました。
・子どもたちの親権について
・自分が持っている財産をどう振り分けるのか
・未成年後見人について
・遺言者執行人を誰にするか
ヒヤリングシートをもとに記載していき、さらに自分が載せたいと思っている内容を記載して送りました。
最初は親権のみ考えていましたが、ちょうど良い機会だなと思ったので、自分の財産に関しての分け方も記載することにしました。
我が家は賃貸なので不動産所持はありませんが、不動産所持しているとだいぶややこしいようです。
未成年後見人をつける
わたしが亡くなったときに、親権を元主人に渡すことは避けたい。
そうなったときに「未成年後見人」を指定するということを知りました。
未成年後見人について、分かりやすいなと思った説明を引用します。
未成年後見人とは、未成年者に対して、親権を行う者がいなくなってしまったときに、未成年者の法定代理人となる者をいいます。
未成年者に対して親権を行う者(親権者)とは、通常は、未成年者の両親の両方または一方であることがほとんどです。そして、親権者は、未成年者の法定代理人として、未成年者の財産を管理したり、未成年者に代わって契約を締結したり、未成年者の法律行為に同意をしたりします。
また、未成年後見人が必要な場面として、やはり両親が離婚し、一方の親が親権者であったがその親が亡くなったとき、と言う風に記載がありました。
我が家の場合、これに当てはまります。
他にもこういう場合は未成年後見人が必要になると説明があったので引用します。
こちらのサイト、分かりやすかったな。
未成年後見人を選ぶ必要があるのは、「親権を行う者がいなくなったとき」です。
親権を行う者がいなくなったときには、以下のような場合があります。両親が親権者であったが、両親ともに亡くなったとき
両親が離婚し、一方の親が親権者であったが、その親が亡くなったとき
親権者である親が、未成年者を虐待した等の理由で親権を失ったとき
親権者である親が、重度の認知症等で後見開始の審判を受けたとき
我が家の場合、息子の未成年後見人に父、娘の未成年後見人に母にしました。
1人だけ選べば良いのかなと思っていましたが、子ども1人に対し1人、未成年後見人を指定するという形でした。
こういうことも実際やってみて初めて知りました。
まぁ、なかなか遺言書を書くってないと思いますが…笑
財産の振り分けを決める
不動産所持はありませんが、貯金だけはコツコツやってきました。
もしわたしが突然いなくなってしまったとき、子ども達の成長過程に使ってほしい。
そういう思いがあるので財産は母にと思っていましたが、こちらも行政書士に相談し、子ども達に振り分けをすることにしました。
なぜかそうしたかというと、未成年後見人を指定するということは、実際に未成年後見人がメインですることになるからです。
我が家の場合、母がメインで動いてほしいと思っているので、娘にメインバンクを振り分けることにしました。
手続等あったとき、娘に振り分けていたら母が動けることになるので、重要なものは娘に振り分けています。
最終的に、主に使っている通帳を娘に振り分け、残りを息子に振り分ける形をとりました。
わたしの場合、銀行口座を振り分けるだけだったので、「財産目録」と言う書類を行政書士が作成してくださり、財産目録を遺言書に添付しています。
自分でも準備できますが、やはり余白がこれだけあいていないとダメという決まりや、書式のこともあったので、この点も行政書士にお願いしてよかったと思っています。
ちなみに銀行口座に関しては、今ある分で記載しました。
ゆくゆくはお金を動かして口座を減らす予定ですが、そういう口座間の移動は問題ないそうです。
遺言執行者の指定
そして最後に、遺言執行者を決めました。
遺言執行者とは、わたしが亡くなった場合、誰が遺言に書かれた内容を実行するか、実行者のことになります。
すごく重要な役割ですね。
遺言執行者もわたしの場合は「母」を指定しました。
ちなみに遺言を書いて法務局に預けているということは、母と妹しか知りません。
父は少し精神的に不安定な部分もあるので、遺言を書いた理由を話しても多分悲しむと思うので。笑
今回は執行者をお願いした母と妹だけに話をしています。
もし、母が先に亡くなってしまった場合、遺言執行者は父にと記載しましたが、万が一そういう場合があった時のために、妹に話をしました。
付言事項について
これは子ども達や両親に向けてのメッセージのようなものでした。
子ども達の環境が変わってしまうことがどれほど良くないことか。
わたしの想いも含め、付言事項にメッセージのような形で残しました。
付言事項を書いているとき、正直複雑な心境になりました。
今わたし、自分が亡くなったときのためにメッセージを残しているのか。
そう思うと、なんだかいたたまれない気持ちになります。笑
内容として書いたのはざっくりこんな感じです。
・子ども達と過ごせて幸せだったという感謝。
・離婚し、両親に手助けしてもらったことへの感謝の気持ち。
・子ども達の生活が変わらず、今までのように暮らしてほしいという願い。
・そのためにはわたしの父と母が未成年後見人になることが1番だという想い。
・父と母へ、子ども達を託すわたしの想い。
切ない。笑
もちろん全然これからも生き続ける予定ですが、だいぶ切なくなった瞬間でした。
ですが、この付言事項って結構大事らしいです。
こういう遺言が残っていて、母親はこのように願っている。
そう示すことが出来る部分なので、重要ですとおっしゃっていました。
ここまで書いたら、とりあえずわたしが書いた遺言書の内容は一通り終わりです。
遺言書を書くときの注意点
法務省のHPを見ると載っていますが、遺言書の書式には決まりがあります。
まずは基本的に「自筆」となります。
財産目録以外、遺言書の内容はすべて手書きです。
これがまたなかなか大変でした。
間違えないように、一文字一文字確認しながら書いていく。
書き終わったときには達成感がありましたね。
書く用紙はA4の紙。
まっさらな白の紙に書きました。
わたしの場合、ちょっと良いコピー用紙に書いていきました。
そして書くときの注意点として、余白が決まっていること。
この余白を飛び出して書いてしまうとアウトです。
上下左右、余白が決まっていて、この余白より内側に遺言を書いていく形でした。
法務局に預ける場合は、この辺りもはみ出ていないか確認があるようです。
また、封筒は自分で保管する場合は必要ですが、法務局に預ける場合は必要ありませんでした。
自分で保管する場合は封の仕方もあるので、法務省のHPをチェックした方が良いです。
とにかく決まりごとがなにげにあるので、都度行政書士に確認をとりながら作業を進めていきました。
申請書の準備
こちらも法務省のHPからダウンロードできます。
わたしの場合は行政書士がメールで送ってくれたので、そちらを印刷し、記載して持参しました。
分からない部分だけ空白にし、他は埋めて持っていったので、だいぶ時間短縮にはなりました。
可能であれば、申請書は事前に準備していくと良いです。
とにかく法務局は時間がかかります。笑
持っていくものと事前準備
法務局で保管してもらう場合の持ち物。
・遺言書(ホッチキスで止めたりせず、バラバラで持っていく)
・保管申請書
・本籍と戸籍の筆頭者の記載がある住民票の写し
(マイナンバーや住民票コードの記載なし)
・身分証明
・保管手数料(収入印紙で3,900円必要です)
事前に住民票を取っておかないといけません。
また、わたしの場合は、収入印紙も事前に郵便局で購入し、持参しました。
おそらく法務局内でも買えますが、先に全てを揃えて持っていきました。
そして盲点だったことが「予約が必要」だということ!
予約制と知らず、この日に行こうかなーとのんきに考えていたら、前日に予約制ということを知りました。
必ず事前に予約をとって行きましょう!
そして、時間はほぼ半日見ておいた方が良いです。
遺言書の内容確認に1時間半から2時間程度かかりますと言われました。
そのあとも多々確認事項があるので、半日は余裕を持ってみておくほうが良いです。
いざ、法務局へ
ここまで準備できたら、法務局へ持参します。
やっとここまで来た。笑
遺言書を書いたことをnoteに書こう。
そう思い書き始めましたが、何気に行程がありました。
書くこと多いな。
でも、なかなかない経験。
記録として残すためにも、最後まで書きたいと思うので、もしよければ見てください。
今日も読んでくださり、ありがとうございました!
今日も1日頑張った自分を褒めたたえて寝ましょう♡
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
