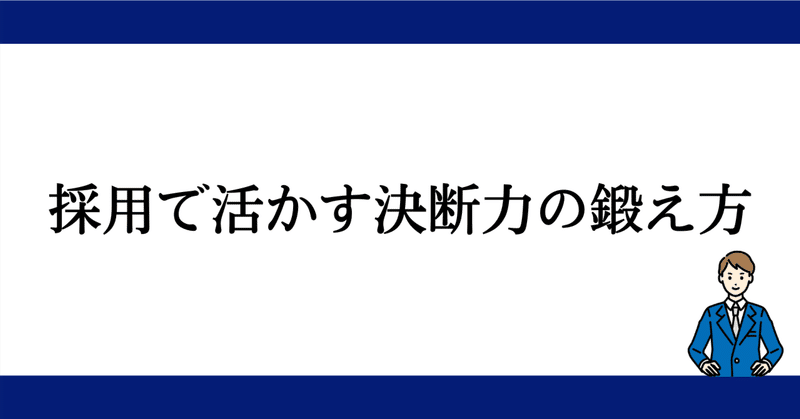
採用で活かす決断力の鍛え方
今日は「決断力」というテーマでnoteに記載しようと思います。
毎日は「決断の連続」と言われるほど、たくさんの判断をしていますよね。
採用の場面においても書類選考や面接段階にて
スピーディーに適切な判断ができれば、、、
「業務の時間効率UP」
「チャンスをつかむ」
「早期退職を防止」
「ストレス低減」
というようなメリットがあります。
反対に決断できないと、採用にかけた工数が倍にもなりますし、
採用したはいいものの、期待とはかけ離れており
マイナスな結果になってしまった経験をお持ちの方もあるかもしれません。
実際に私も先延ばしになってしまい時間だけ経過した経験もあります。
ぜひ今回の内容を参考にしてください!
①決断力とは
「問題や課題に対する対応策から、責任を持って意思決定できる力のこと」
選択肢ないものは「切り捨てる」との意味になります。
なのでリスクが大きいほど、決断には大きな覚悟と責任が必要になります。
②決断できない理由
1.自信がない
意思決定に自信がなければ、決断を後回しすることがあります。
大きな覚悟は必要となります。
2.判断軸がない
判断軸を作ることが重要です。
曖昧だと決断できないケースが多いです。
「ジャムの実験」でもあるように
現在は情報過多で選択肢が多くなってきてます。
「どのように判断するか」の軸を言語化してみるとよいですね。
3.多方面の視点がない
判断材料がないパターンになります。
自分自身の決断が「どのくらい影響を及ぼすか」
理解しておくことが重要です。
わからない場合は怖くて決断できないですよね。
ですので、様々な視点からこの決断について考えるとよいです。
3決断力を鍛える
1.失うものを意識する
「決断しない=現状維持」ではありません。
例えば、採用の場面でいうと課題や目標があり、
採用をしようとしていると思います。
タイミングを逃してしまうことで
「競合に負けてしまう」
「取引先の信用を失ってしまう」
「工数がかかってしまう」
のようにつながってしまいます。
「決断をしないと、何を失ってしまうか」
勇気を持って決断することが大切です。
2.積極的に情報収集し、未知の領域を学ぶ
判断材料を集める習慣を身につけることが大切です。
時代が急激に変わってきている現在において、
自分自身が「知らないから判断できない」となると
世の中の流れについていけなくなります。
AI・テクノロジーの進化し、情報が多い中ですが
積極的に勉強し、よりよい決断できるようにしましょう!
3.コンディションを整える
決断をするためには、睡眠不足・体調不調が大きく影響を受けます。
一つのものに執着している状況でも視野が狭まってしまいます。
生活習慣を整え、最大のパフォーマンスを発揮できるよう努めましょう。
頭がすっきりする時間帯も意識することをおすすめします。
まとめ
時代が変化する中で決断するのは、怖いことでもありますよね。
意思決定は人間しかできず、絶対に必要な能力です。
小さいことから決断する習慣をつけるようにしていきましょう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
