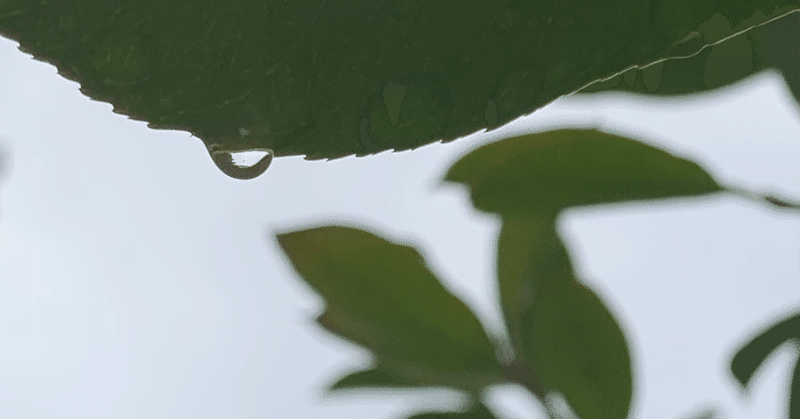
【小説】反照
※注意
がっつり性描写があります。苦手な方はお控えください。
***
恋の一つでもすれば変わるのかしらね、とうんざりしたように母は言う。
大学二年生にもなって色気づきもせず、短髪すっぴんにジーンズという少年のような風貌で毎朝出かけていく娘に対する心配と不満の嘆息。私は擦り切れたスニーカーに爪先を突っ込み、靴の踵を踏んだまま「行ってきます」と言って外に出た。
別に恋愛をしないと決めているわけじゃない。恋している人を見て特別不快になることもない。ただそうした情熱はどこか遠い、ファンタジーの世界で起こっているような感じがする。私と彼等の間に透明なスクリーンがあって、投影されたビタミンカラーの恋愛模様を見せられているような。スクリーンの向こうにある生身の彼等については、私には知りようもない。
向こう側にあるのはもしかすると純粋な肉体かもしれないとも思う。求め合う肉と肉に絡まった寂しさや支配欲や居場所を求める気持ちが蒸発し、何となく綺麗な色彩としてスクリーンに焼き付いているのだ。核になっているのはきっとセックスの相手を求める本能だ。
性欲には二種類あると思う。肉体的な欲と精神的な欲だ。
肉体的な欲なら私にもわかる。その疼きは周期的にやって来る。しかしそれは自分で触って満たしてやれば鎮まるような性質のもので、相手がいなければいけないとも思えない。どうやら私には精神的な性欲が欠けているらしかった。誰かの裸を目にしたところで触れたいと思ったことはなく、見てはいけないものを見てしまったような気恥ずかしさを覚えるだけだった。
薄いゴムの靴底が煉瓦から生えた霜を押し潰し、歩くたびに足の下でざり、と残酷な音が鳴る。一限目の授業が始まったばかりの時間、広々とした大学のキャンパスに人影はまばらで、鼻の下まで巻いたマフラーに冷気が染みる。
正門前の広場から道を逸れ、少し奥まったところにある図書館の前で、手持ち無沙汰にスマホをいじっている見知った顔に出会った。
「あれ。あー、っと、カレンちゃんだ」
顔を上げてそつなく笑いかけたのは、同級生の女子学生だ。男女入り混じった派手なグループの中心にいる人物で、確か仲間からはマツリと呼ばれていた。苗字は忘れた。彼女と違って目立たない私の名前などよく覚えていたものだと、いきなり下の名前で呼ばれて面食らった。私には不釣り合いに華美な名前を、全身にくまなく女の子らしさを纏ったマツリに呼ばれると居心地が悪い。
「あ、うん。おはよう」
挨拶だけして図書館に入ろうとしたが、マツリは私の前にひょいと頭を出して私の顔を覗き込んだ。
「図書館行くの? サボり?」
「いや、一限目授業ないから。レポート書こうと思って」
「ふーん、真面目だね。レポートなんか先輩の写させてもらえばいいのに」
そんな人脈があったら苦労しないと言いかけてやめた。彼女とは住んでいる世界が違う。
「……マツリさんは?」
「あ、名前覚えててくれたんだ。嬉しいな」
マツリは無邪気にはしゃいだ声を上げ、それからすっと目を細めた。
「男漁り、かな」
「え……」
「あはは、冗談。目が覚めちゃったからぶらぶらしてただけ」
当惑する私に彼女は顔を近づけ、耳元に囁く。
「ね、金曜の夜、空いてる?」
「空いてるっちゃ空いてる、けど……」
今週の金曜は十二月二十四日——クリスマスイブだ。母がいつもより少し豪華な夕食を用意してくれるかもしれない、私にとってはそれだけの日だ。しかし彼女にとっては違うだろう。マツリのような人なら、クリスマスは恋人と過ごすか、たまたま恋人がいなかったとしても一緒に騒げる友人くらいいるだろう。そんな彼女がわざわざ私の予定を聞く意味は何だろう。恋人がいない私のことを笑ってやろうとでもいうのだろうか。
私の警戒を裏切るように、彼女はぱっと笑顔になった。
「良かった。じゃあマツリの家に来てよ。泊まれる用意もしといてね。授業の後、待ってるから」
ロングブーツの上の白い腿を見せつけるかのようにミニスカートを翻し、彼女は寒空の下へ出て行った。私は飲み込むことのできない今しがたの出来事の意味を両手に抱えたまま自動ドアをくぐった。
二十四日の夜は友達のところに泊まると伝えると母は驚くほど喜んだ。自分が行くのでもないのに下着や着て行く服まで用意しようとするものだからさすがに止めたが、ちゃんと可愛いのを着て行きなさいよと念を押された。
「せっかくできた彼氏なんだから、だるだるのパンツなんて穿いてって愛想尽かされないようにしないと」
勘違いしている母に私は何も言わず頷いた。説明しようにも彼女とどういう関係でなぜクリスマスイブに会うのか私自身よくわからなかった。
講堂ではいつも前の席に座る。余計なものを視界に入れずに済むから。
大学の良い所は友達を作らなくても生きていけることだ。自分の教室というものはないから各授業が終わればその部屋からは出なければならず、先ほどまで同じ講義を受けていた学生と次の講義でも顔を合わせるとは限らない。ゼミに所属するまでは全員が根無し草で、一人で行動していてもさほど人目は気にならない。
その日も私は一人で授業を受けて建物を出た。すっかり暗くなった空の下で、この前とは違う赤いミニスカートのマツリが待っていた。一方の私はいつものジーンズにぺらぺらのスニーカーだ。
私と目が合うとマツリは意味ありげに含み笑いをして、「こっち」と私の腕を取った。
向かった先は街灯がぽつりぽつりと侘しく灯る駐車場だった。マツリが鞄から取り出した鍵を向けると、淡いオレンジ色の軽自動車がピピっと電子音を立ててライトを点滅させた。
「運転するの?」
私は少し驚く。
「そうだよ。この辺田舎だから、下宿するなら車必須」
親元を離れて暮らしているのか。そんなことも知らなかった。
着替えを詰め込んで普段より膨らんだ鞄を抱えて助手席に乗り込んだ。マツリの運転は結構乱暴で冷や冷やしたが、大した会話をする暇もなく車はアパートの駐車場に滑り込んだ。
冷たいコンクリートを踏んで案内された部屋は意外に質素だった。クローゼットから溢れた服や鞄がハンガーラックに掛けられ、机の片隅に化粧品類がまとめて置かれている他は、装飾的な物は見当たらない。ぬいぐるみも無ければキャラクター小物も無い。整えられたベッドシーツも単色のシンプルなものだ。
「座って」と言われ、上着を脱いでベッドの端に浅く腰掛けた。他に座る場所は無かった。
今頃になって気まずさと後悔が私の胸をさわさわと覆った。流されるままに来てしまった。でも断る機会は与えられていなかったのだ。連絡先すら知らなかったし、彼女の周りにはいつも人がいて話しかけられなかった。何となく、このことは他の人には知られないほうが良いような気がした。
「チキン買っといたから温め直して食べよ。外出たらカップルだらけだもん、うちでゆっくり食べたほうがいいよね」
マツリは暖房をつけ、紙箱ごとフライドチキンを電子レンジに放り込んだ。冷えた鶏肉がスポットライトを浴びて回る。
「……どうして私なの?」
鶏肉のステージが回転するブーンという音に紛れるように呟いた。マツリは扉の網目の隙間に目を凝らしている。
「男、探してるって言ったでしょ」
機械仕掛けの箱の中で踊る肉から目を逸らさずにマツリは答える。
「私は男じゃないよ」
「知ってる。ほんとは男じゃなくて犬が欲しかったんだ」
「犬……?」
意味がよくわからなかった。
マツリはビニール袋から細長いチューブ状の袋を取り出し、私の横に座った。濃い黄色の袋の端を切ると、蜂蜜色の澄んだ液体がとろりと流れ出し、マツリの指を伝った。
粘度の高い雫を纏った指先が私の鼻先に差し出される。
「舐めて」
見開かれた大きな目が有無を言わさず私を射竦める。甘い匂い。操られるように舌を出す。ひんやりとした指に絡む蜜が唾液に溶けて口の中に広がる。爪がこつんと奥歯にぶつかる。自分の中に別の生き物がいるという不思議な感覚。マツリの口から微かな吐息が漏れるのが聞こえたような気がした。
不躾な電子音がよくある旋律で喚き、私は思わず指を口から押し出した。
マツリはゆっくりと立ち上がり、しゅうしゅうと音を立てるフライドチキンを電子レンジから取り出した。
「食べよ?」
マツリは何事もなかったかのように明るく笑いかける。右手の人差し指が濡れたまま光っている。
マツリは再び私の隣に腰掛け、サイドテーブルにチキンを置いた。勧められるまま手に取った一切れから脂とスパイスの香りが立ち上る。口の中にはまだ甘味が残っている。その残り香を塗り潰してしまうのは惜しいような気がした。そしてそんなことを思っている自分に困惑した。
「どうしたの?」
マツリは意地悪く目を細める。からかうために私を呼んだのだろうかと考えると何だか悔しくて、カリカリの衣の付いた鶏肉を頬張った。加熱のし過ぎで硬くなっていた。
ニヤニヤしながらマツリはドーナツ型のビスケットを半分に割り、先ほどの蜂蜜を垂らした。
「あ」
どうしたのかとマツリのほうを振り向く。ビスケットの表面から蜜がこぼれ、白い手首を伝っている。
「こぼしちゃった」
わざとらしく、落ち着き払って言う。
「どうにかしてくれる?」
口元に湛えられた笑みに少し腹が立って、私はマツリの手からビスケットを取り上げ、口の中にチキンの欠片を残したまま手首に吸い付いた。マツリの手がびくりと震えた。すべすべとした皮膚に私の唇が脂を塗りたくる。甘みが消えても止めない。今度ははっきりと、彼女の吐息が聞こえる。自分の手首が疼くのを感じる。もどかしい。確かめたくて、執拗に舐める。
「こっちにもこぼれちゃった」
マツリの顔を見ると、ほんのりと上気した頬から首筋にかけて蜂蜜が垂れている。黄金色の筋に沿って舌を這わせると、マツリの唇から小さな悲鳴にも似た声が漏れた。自分の首筋がぞわりと粟立つ。鏡合わせのように、舐めているのと同じ箇所に神経が集中していく。
マツリは自分でトレーナーの裾を捲り上げ、もう隠そうともせずに臍に向けて蜜を垂らす。私は指示されるまでもなくそれを舐め取る。マツリが息を荒くし、腰を反らす。マツリの快感が私に反射する。私は興奮していた。どうしようもなく昂っていた。
開いた股の内側から、綺麗に剃られた陰部へと蜜が伝い落ちる。蜜を舌で追いかける。マツリが声を上げる。私自身のそこも熱く腫れて痺れている。下着が濡れてぬるぬると滑り、我慢できないところまで熱を高めていく。
舌を這わせたその先がふるふると痙攣し、収縮と弛緩を繰り返す。彼女の絶頂を感じて私もまた弾けたような快感の頂点を迎えた。
「上手じゃん」
息を整えながらマツリはとろりとした笑顔を見せた。口の中に残る蜜のように甘ったるい。
「マツリの犬にしてあげる」
今度はその意味がわかった。身体が勝手に頷いていた。初めて知った快感に抗えなかった。
あの日起こったことは私には上手く咀嚼できなくて、丸呑みにした不可解で背徳的な塊は私を決定的に変えてしまった。冬休みの間、マツリの声を、息遣いを、温かな肌の味を何度も思い出した。自慰では到底満足できなかった。身体が駆り立てられるようで、私は柄にもなくジョギングと称して闇雲に走り回った。休暇の終わりに焦がれ、恐れた。
年が明け、授業が始まった。いつものように一番前の席に陣取ったが、背後が気になって集中できなかった。
授業が終わると素早く筆記具を片付けて振り向いた。後列に大きな声で話しているグループがいた。その中にマツリもいる。
私には目もくれず、マツリはわいわい喋りながら教室を出て行った。私は落胆した。そしてあの日から片時も休まず性的な何かを期待し続けていた自分に気づいて戦慄した。
しかし自分の浅ましさに対する嫌悪感は長くは保たなかった。帰宅しようと外に出ると、マツリが一人で建物の前に立っていたからだ。
「来るでしょ?」
挑戦的なまでの素っ気なさも気にならなかった。
「うん。行く」
そして私はまたマツリの家に上がり込んだ。今度はチキンを食べるようなまどろっこしい真似はしなかった。
それ以来、ちょくちょくマツリの家に呼ばれるようになった。誘いは常にマツリから。一日の授業が終わると、普段は常に誰かと群れているマツリが一人で待っている。マツリの運転で部屋へ行き、マツリがシャワーを浴びて出てくるのを喉をカラカラにしながら待つ。マツリは刺激すべき場所を示し、私は忠実に従う。指示に使われるのは最初のように蜂蜜のこともあったし、マーマレードや梅酒の原液のこともあった。学内で会ってから駅まで送ってもらって別れるまで一言も口を利かないこともあった。言葉は必要なかった。私達が求めているのはそういうことではなかった。
何度目かの行為の後、私とこうなる前はどうしていたのか訊いたことがある。
マツリは嫌いな食べ物を間違って口に入れてしまったような顔をした。
「嫉妬とかやめてよね。マツリは君の物じゃないし、マツリだって別に君のこと所有したいわけじゃないし」
「そういうんじゃないよ。興味が湧いただけ」
ふーんと言ってマツリは紅い唇を尖らせた。そこにはまだ触れたことがないと思うと、一度は鎮まった欲望が再び疼いた。
「同学年にワタリ君っているでしょ。あの子にしてもらってた。勝手なことするからもう会ってないけど」
マツリは鎖骨に張り付いた髪を後ろに払った。
「この話はおしまい。わかった?」
「わかった。もう訊かないよ」
「いい子」
マツリは満足そうに私の額に口付けた。
帰宅が遅くなることが増えたのは彼氏とデートしているからだと母は完全に思い込んでいた。彼氏はどんな人か、デートはどこへ行くのかとまるで恋愛至上主義の女子学生のように興味津々で聞きたがるので困った。マツリは恋人とはとても言えないし、友達ですらないただの同級生の距離感であることは今も変わらない。密かに快楽を共有するようになった以外は。
「あんたがそんなんでも好きになってくれるんだから、相当心の広い男の子よね。隣歩いても彼氏ちゃんが恥ずかしくないように、ちょっとは小綺麗にしてあげなさいよ」
小言を垂れる母に、ん、と曖昧に返事をして箸を置く。私がマツリと何をしているか母が知ったら大騒ぎするだろう。心の扉が閉じて閂がかかる音がする。
誰にも知られてはいけない。きっと誰からも軽蔑される。
このことを知っているのはマツリだけでいい。マツリの身体をもっと知りたい。
試験が終わり、春休みに入った。
年末からの二ヶ月は麻酔がかかっていたように記憶がおぼろげだった。
長期休暇中も関係は続いた。連絡先はまだ知らなかったから、毎回別れ際に次の約束をした。
マツリの肉体に詳しくなった。蜜を垂らす順番。どこをどんな風に舐めて吸えばもっと感じるのか。息遣いで測る絶頂までの距離。
マツリの快感が私の身に刻まれていく。ただの皮膚だった箇所が、敏感な粘膜のように変わる。私がマツリの肘の内側に舌を這わす、マツリが微かに喘ぎを漏らす、すると私の肘の内側の皮膚が快楽を知る。私の身体は隅々までマツリの快感で照らされ、皮が一枚剥けたように生を感じていた。
その日も駅前で待ち合わせ、会話もそこそこに儀式を始めた。前回から日が空いて、マツリも私も昂っていた。もどかしさを感じながらようやく脚の間に辿り着く。暗い割れ目が蠢いている。ぬらぬらと、誘うように。指を伸ばす。興奮で滑稽なくらい震えている。指で透明な粘液をすくい、なぞり、——挿れた。
バチン、と耳元で激しい音がした。張られた頬が遅れてひりひりと痛む。
「それは駄目」
醒めて冷え切った視線が見下ろす。
「出てって」
裸のマツリに背を押され、追い出された。玄関の内側で鍵とチェーンをかける音。
「ごめん」
ドアの向こうに声をかけてみる。聞こえているのかいないのか。恐る恐るインターホンを押す。応答はない。
混乱したまま夕暮れの道を歩き出した。一日の終わりを知らせる町内放送の音楽がスピーカーから流れていた。内股から下腹部にかけてじんじんと疼く。挿入の感触が子宮に残っているような気がした。
マツリと会う機会を作れないまま春になり、新学期を迎えた。
初日はマツリが接触してくることはなく、次の日も、一週間経ってもマツリは私に見向きもしなかった。マツリは以前と同じように仲間と笑い合っていた。私とマツリの間は再び見えない膜で隔てられた。
ひと時の夢だったのだと思おうとした。忘れようとした。それは飢えを知ってしまった私にとって断食にも等しかった。
私の前任者であるワタリという青年のことを私は半ば無意識に探していた。そんな名前の同級生がいたような気もするが、顔は思い出せなかった。だから授業前のざわざわした講堂で「ワタリ」と呼ぶ声が聞こえた時、私は反射的に振り向いていた。
二列後ろの通路に立っていた声の主の男子学生と目が合い、怪訝な顔をされた。ワタリと思われる学生の顔を確認すると私はさっと黒板に向き直った。眼鏡をかけた地味な雰囲気の青年だった。ワタリに声をかけた学生が講堂の後ろのほうに歩いていくのが足音でわかった。
ワタリは孤独だ。きっと私に似ている。そういう人間をマツリが選んでいるのだ。
昼休みの始まりを告げるチャイムが鳴り、リュックサックにノートを詰め込んでいたワタリに声をかけた。
「ワタリ君だよね。マツリさんと——、会ってた」
マツリの名前を出した途端、ワタリの目が鋭く警戒を示した。
「もう会ってない。何の用?」
私は抑えられない動悸を感じながら、用意していた言葉を口にする。
「同じことしてみない? 私と」
工場や田畑の広がる幹線道路沿いに忽然と現れる、張りぼてのような洋館。駐車場の入口には巨大な暖簾のような目隠しがあり、中に入ると狭く薄暗いロビーに出た。
勝手がわからずきょろきょろしていると、カウンターの内側にいた中年の男性が向かいの液晶パネルを無言で指差した。部屋の内装と値段がずらりと表示されている。適当に部屋を選んで鍵を受け取り、エレベーターで部屋に向かった。
「マツリちゃんも変わった子だけど、君も大概だな」
古びた絨毯をもすもすと鳴らしながら呆れたようにワタリは言う。ワタリも私と変わらないと思ったが、否定もできないので黙って部屋に入った。
ダブルベッドと二人掛けのソファが押し込まれた窓の無い部屋。右手には広めのバスルーム。想像していたよりもずっと清潔そうだった。
ワタリを待たせてバスルームに入った。シャワーで身体を濡らしてボディソープを泡立て、途中のコンビニで買った剃刀で体毛を剃る。さりさりと音を立てて肌を滑る刃の上に、産毛と混ざって灰色になった泡が溜まる。
腕と脇と脚を剃り終え、自分の身体を見下ろして戸惑う。陰毛など剃ったことがない。
意を決して泡を塗り、下腹部に刃を当てる。太い毛がバリバリと削ぎ落されていく。椅子に腰かけて脚を広げ、鏡を見ながら股の間の毛も剃る。肩と股関節が攣りそうだ。
鏡の中でおかしな体勢で必死の形相を浮かべている自分と目が合った。私は何をしているのだろう。
ばらばらになった思考の断片が紙吹雪のように頭の中を舞っている。断片を舞い上がらせる風はマツリに教えられた欲望だ。あの日からずっと絶え間なく吹いている。
陰部はつるりとした肉の弛みになった。そこだけ子供のようで落ち着かない。排水口には黒い毛虫のような毛の塊が引っ掛かっている。私の欲望から滲んだ澱のように。
ベッドの上でコンビニのガムシロップを開けた。プラスチックの小さなカップから透明のシロップを手に落とす。
「それ、何で君が知ってるの」
ワタリはベッドに片膝を突いたまま雫を見つめる。
「私もマツリさんに誘われてやってたから。<犬>を」
「へえ」
眠たそうな目が眼鏡の奥で丸くなる。
「それで、自分も奉仕される側に回ってみたくなった?」
「……」
手首の内側に生温かくぬめった舌が触れる。鳥肌が立つ。くすぐったいような、思っていたのとは違う感覚。身体は反応している。——でも、あの沸き立つような高揚は無い。
マツリの裸体を思い描く。私の肌の上の雫を、それを追う舌を、マツリに投影する。マツリの虚像が喘ぎ、よがり、そうしてようやく跳ね返ってきた快感を私は受け取る。
「虚しいよ、こんなの。性感だけが目的の関係なんて」
言葉とは裏腹にワタリは私にのしかかるように乳房に吸い付く。想像上のマツリが声を上げる。
「じゃあ自分でマツリさんから離れたの?」
ワタリは顔を上げ、眉根を寄せた。
「……僕はマツリちゃんが好きだ。性欲だけじゃない、本当の意味で好きなんだ。だからちゃんとつながりたくて——」
「——挿入した?」
はっと顔を上げたワタリは、私と目が合うとバツが悪そうに目を背けた。
「身体中全部許されてたのに、それだけは許してくれなかった。ゴムを出した途端にキレられて追い返された。それっきりだ」
「私も。指を挿れたら縁切られた」
ワタリは私の顔をしげしげと見た。
「君もマツリちゃんが好きなの?」
私は溶けかけた脳をまさぐる。好きって何だろう。私はマツリが好きなんだろうか。
「マツリさんは気持ち良いことを教えてくれた。だから好きなのかもしれない。でもマツリさんじゃなきゃいけないってこともないかな」
ワタリは私を見下ろす。蔑むような眼差し。
「そんな汚れた感情と一緒にするなよ。僕はマツリちゃんを愛してる。愛してるから心も体も一つにつながりたいんだ」
「愛があったって二人の人間は一人と一人でしかない。わかり合うなんて錯覚。私の感じている赤色が彼女の感じている赤色と同じかどうかすらわからないのに。人はみんな孤独。孤独を忘れられるかどうかだけの違い」
ワタリはベッドから降りた。
「君のお陰で決心がついたよ。マツリちゃんに告白して、ちゃんと付き合うことにする。君みたいな冷淡な人にマツリちゃんがもう騙されないように」
ワタリは部屋を出て行き、私の粗末な裸体が広過ぎるベッドの上に残された。時間をかけてシロップを片付け、身体を洗った。憑き物が落ちたように色んなことがどうでも良くなっていた。
私の生活は元に戻った。母は何か訊きたそうにちらちらと視線を寄越してきたが、別れたと思ったのかそれを話題に出すことはなかった。
大学のキャンパス内、とっくに花を散らし終えた桜の透き通る若葉の下を歩くマツリとワタリを見かけた。二人の笑顔がありきたりな幸福をスクリーンに映していた。マツリは肉体を満たすために私やワタリのような孤立した人間を利用しているだけだと思っていたが、意外とそうでもなかったらしい。
よくわからない。私にはもう関わりのないことだ。
その夜は久しぶりに自慰をして寝た。満たされないとは感じなかった。
<了>
***
短編集発売中です。
(Kindle Unlimited 無料)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
