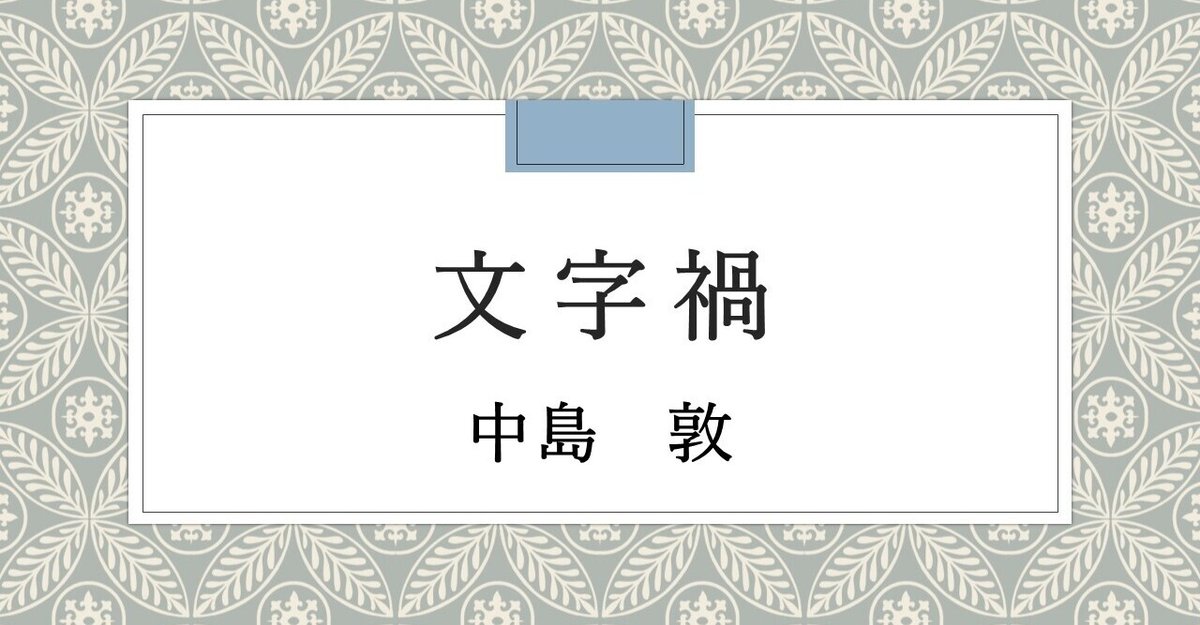
線を統合して一定の意味と音を与える「文字の霊」がいる
ほんの感想です。 No.16 中島敦作「文字禍」 昭和17年(1942年)発表
「文字禍」を読み、自分が存在するこの世界には、「実は拠り所はないのだ」と言われたような気持になりました。例えて言うと、こんな感じです。
初めての土地を歩いていると、前方から歩いて来る女性の視線を感じた。目の前まで来た彼女が、「お久しぶり」と立ち止まる。誰とも思い出せないまま、「お世話になっております」と返すと、「そんな嫌味を言うほど、元の女房に愛想がつきたの」と言われてしまった。「誰かと間違えていますよ」と否定したが、すぐに、「彼女の言う事は正しいのかもしれない」という気がしてきた。そんなことを考える自分が急に怖ろしくなった。
中島敦作「文字禍」には、アッシリアのある学者による、「文字の霊」の研究の様が描かれています。彼は、「単なるバラバラの線に過ぎない文字が、一定の音と一定の意味を持つ」ことに対し、「線を統合して意味と音を与える『文字の霊』がいる」という仮説の証明に取り組んでいるのです。
ー・ー・ー・ー・ー・ー
この作品には、「人が、じっと文字を見ているうちに、文字の構成要素がバラバラになり、意味をとらえることができなくなる」ということが描かれています。この点を、角川文庫の中島敦「文字禍・牛人」の池澤夏樹解説は、「ゲシュタルト崩壊と呼ばれる心理現象が描かれていて、その未来的洞察に驚いた」とされています。「ゲシュタルト崩壊」、なんと怖い響き。
主人公の学者は、文字の霊による禍を指摘するため、文字が無かった頃の、人の明晰な知覚を、次のように記しています。
文字の無かった昔、ピル・ナピシュチムの洪水以前には、歓びも知恵もみんな直接に人間の中に入って来た。今は、文字の薄被(ヴェイル)をかぶった歓びの影と智慧の影としか、我々は知らない。
そして、主人公が、「文字」だけでなく、「概念」にも疑いを向けたとき、「私がいるこの世界は存在する」と考えることに、「その拠り所はない」と言われたような気持になりました。これは、昨今の変化で、ただでさえ弱っているメンタルにとって、かなりしんどい。
そんな恐怖の土俵際で、今ある概念が生まれたとき、それは、もっと少ない要素で統合されていたように思えてきました。ならば、すべて無かったものとみなすことはできないけれど、今よりはもっと簡素な統合を考えることも、有意ではないか。そんな気がしました。
バラバラになった文字の線や、概念の要素が、長い長い列を作って、大浴場に向かっています。汚れと垢を落とし、時代遅れとなったものは捨てて、コンパクトな統合をしてみましょうか?
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
