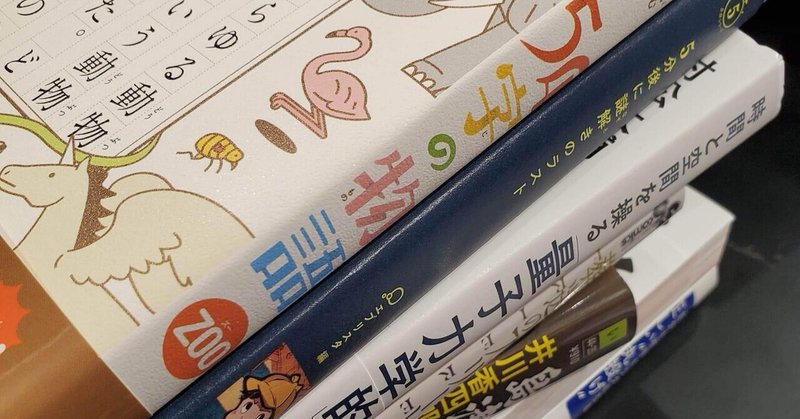
「子どもには本を無制限でパパが買ってあげる」が我が家のルールです。
我が家の子どもたちは、本屋さんで欲しい本がある場合、無制限でパパが買ってあげる謎ルールがあります。
連休中、パパがインプット期なため本屋さん行きたかったので、家族で本屋さんへ。
パパビジネス書2冊・歴史小説1歳。
次男・マンガ2冊
長男・自分が好きな本2冊
ママ・便乗して1冊(のちほどパパに支払い)
値段はあんまり見ないで買うので、なかなかなお値段になってましたw。
僕の熊本の実家は児童書の専門店です。
東京浅草生まれの出版社勤務だった父と熊本から上京していたこれまた出版社勤務の母が、三男である僕が1歳半の時にサラリーマンを辞めて立ち上げた小さな書店です。
だもので、当然僕の物心がついた時には
そこに本がありました。
この環境を人に話すと「素敵ですねー」とか言われるのですが
物心ついた頃からある。というのは「当たり前」ということ。
素敵なことだという自覚はありませんが
そのおかげで、冒頭のように息子たちは自由に本を買わせる謎ルールが設定されております。
本は買うものではなく、在るもの。という感覚なのでしょう。
小さい頃は寝る前に2.3冊ほど店から拝借して
母に布団の中で読み聞かせしてもらいました。
おかげで字が読めないうちから、好きな本の物語を
諳んじたこともありました。
その結果、小学校の勉強がひどくつまらないものに感じる。
という副作用もありましたけど。
なので、今の私の言語力はたぶんに育った環境によるものです。三つ子の魂というやつでしょうか。
僕と全く同じ環境を2人の息子には作れないけれど
せめて、本屋さんには親しんで欲しいなと思っています。
Amazonでも買えるし、ネット記事で出会う本もあるけれど
本屋さんでは偶然の出会いがある。
なにか相談したいな。という時に
膨大な知の蓄積をされた先人や友人が並んでいて
無料でパラパラと眺めることできる。
この人の話をしっかり自分に取り込みたい。
というものだけを手に取り、ゆっくり自宅で頂く。
それは人生のポイントポイントで
必ず自分を暗闇から救い出してくれる一筋の光になる。
だから、息子たちには
マンガだろうが、雑学本だろうが、今は何でもいい。
本屋さんが身近な場所である。ことが刷り込まれればいい。
さっそく長男が
モグラが土の中で穴を掘り進む速度がカタツムリが地上を這う速度より遅いことや
カンガルーが後ろに歩けないことを教えてくれました。
本屋は今度からパパ1人で行こう。と思っていましたが
仕方ない。また家族で行こう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
