
【ブルアカ】愛への賭けをめぐって【隠されし遺産を求めて】
スマホゲーム『ブルーアーカイブ』のイベント『隠されし遺産を求めて』の感想・考察です。メインストーリーの一部(ハナコとミヤコ)にも言及があります。
また話の補足として、以下の別作品を軽く紹介、内容に触れています。
・アニメ『ばらかもん』 第5話:うんにおえぎいっ
・アニメ『ぼっち・ざ・ろっく』 第6話:八景
・シャニマス『MAGIA L'Antica ~アンティーカの5つの魔法~』
・シャニマス アンティーカ ファン感謝祭
画像は特に注釈がない限り「© NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc.」になります。サムネは下記より:
https://twitter.com/Blue_ArchiveJP/status/1683048393684439040
ブルアカで未だに腑に落ちていなかったことがありました。それは【先生が躊躇なく生徒たちを「信じる」と言い切る】ことです。今までこの行為の背後にある理屈があまり明瞭に見えず、なんとなく超法規的に「先生だから」となってしまっていました。しかし、今回のイベント『隠されし遺産を求めて』にて、ハナコが主題になったことで、その理屈がようやく見えた気がします。この【先生が躊躇なく生徒たちを「信じる」と言い切る】行為の背後にある理屈を「愛への賭け」と称したいと思います。
なぜハナコが主題になったことで視界が開けたのかというと、ハナコの主題がこの「愛への賭け」をめぐった問題だったからです。またハナコの水着姿、もとい露出狂的な立ち振る舞いは見事にシナリオとして昇華されており、彼女の賭けれなさがよく表現されています。
この――ようやく見えた――【先生が躊躇なく生徒たちを「信じる」と言い切る】行為の背後にある理屈を言語化していこうと思います。
ウイとヒナタ、ウイとサクラコ
『隠されし遺産を求めて』において、2種類の人と人との関係の有り様が示唆されます。ウイと他者の関係はかなり見分けやすいため、このシナリオにおいてはウイが一種の基準点としてメルクマークになっています。ウイは本を「この子」と形容し、我が子を慈しむように大事に扱います。一方で図書館外の人を「外の人」と若干侮蔑的に呼称し、真正面から取り合わないようにしています。ただ例外的なのが、元々「外の人」扱いであったヒナタが前回のイベントを通して、ウイの中で「この子」側に変わっている状態になっていることです。
人と人との関係の有り様として、前者の「この子」関係は「身内的(性愛的)関係」であり、後者の「外の人」関係は「他人的利害関係」になります。ブルアカではメインシナリオも含めて、この2種類の関係性が二項対立として散りばめられています。
『隠されし遺産を求めて』では、例えば「身内的(性愛的)関係」とは無条件に「信頼」している関係であり、「わがまま」も互いに許容でき、本音を言い合える関係です。また例えば訓練を一緒抜け出すというルール無視=法外の「共犯」をして、一緒に「遊び」ができる関係です。民族内的とも呼ばれます。やり取りは非損得的であり、「贈与/シェア」がなされます。この関係は情動的で、性愛的雰囲気が漂います。ウイとヒナタの関係にその匂いを感じることができると思います。
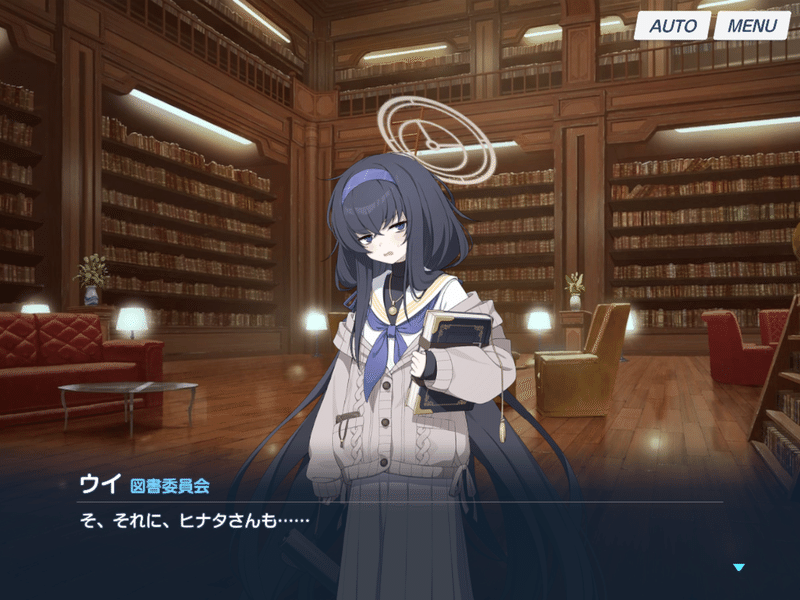
一方で後者の「他人的利害関係」は「仕事」関係であり、言葉=「経典」=契約で関係が区切られるという「法内」の関係です。一般的な意味で大人の関係ですね。またこのシナリオでは「訓練」も仕事の一種でしょう。この関係において、相手が私に接してくるのは「利害」=損得からの関係であり、必ず何か裏がある(はず)と身構えるのがデフォルトになります。損得だけで関わり合う関係であり、とても非情動的、表面的な関係になります。民族間的とも言われます。メインストーリーでは「カヤとジェネラル」の関係が典型的ですが、このシナリオでは、ウイからサクラコへの関係がその例でしょう。ウイは「外の人」と見なしてしまう人と接するとき、裏があるはずと勘ぐってしまうのです。


しかし、ウイにヒナタという例外的存在が出来、ウイに対応の必要性が現れます。ウイはヒナタには荷物を預けれるなど「この子」感を感じることができるのですが、癖でどうしても「外の人」とも感じて「外の人」対応してしまうことがあるのです。例えば「2m離れて」など。ハナコには「ウイさんの問題」と言及されています。ウイはヒナタを「外の人」として扱ってしまう行為が大事なヒナタの心を傷つけてしまう行為だと分かっているからこそ、ウイも自分の問題だと認識し、治そうと意識して先生にも注意してほしいと依頼します。先生は「慣れるよ」と楽観的でしたが、ウイはヒナタは身内でも、その裏の「シスターウッド」が影で操って云々とまで考えてしまうようで、根は深そうですね。。
浦和ハナコ(~『エデン条約編』)
上述の、ウイと他者の関係性を下地にして、他の生徒たちを見てみると、生徒たちの状態の見通しがつきやすいです。
ハナコは、持ち前の聡明さをもって相手の裏を勘ぐる力に長け、また誰に対しても裏があるかのような雰囲気を出して、本音を悟らせないように接しており、どこか腹を割って話し合える気がしない人付き合いをしがちです。ハナコは「外の人」の関係が人付き合いのデフォルトに近いのです。(ウイも図書館外の人にはデフォルトは「外の人」です)
一方で、ヒナタは表裏のない性格で真っすぐに「身内的(性愛的)関係」を築くタイプですね。
「外の人」がデフォルトになるのは、ウイとハナコが気質として近い所がある、というだけでなく、土地柄の影響も強いと思われます。どちらかというと、ヒナタが例外でしょう。

トリニティ総合学園。複数の学園が統合して出来上がったという成り立ちや3つの派閥を代表とした統治方法など、派閥間の「利害関係」が常に絡み合って監視を利かせる学園になります。メインストーリーでも派閥単位での暴走などがありましたね。
このような土地柄だと、個人で1対1の親密な関係を作ろうにも、派閥間/組織間の利害関係が先に前に出て、(特に違う派閥だと)「外の人」の関係がデフォルトになってしまいがちだと想定されます。(ブルアカは舞台(社会)設定と社会から個への影響の記述がしっかりしており、その社会の中で生きる個の苦悩を描いているから説得力が強いんですよね)
トリニティ総合学園に”居る”状況を感覚的に掴むとすれば、例えば、少し極端ですが、ある国家機関に所属している場合を想像すると良いと思います。そこはスパイ/多重スパイが存在しうることがもはや当たり前の機関だとします。そこに、ヒナタのような表裏のないように見える同僚がいたとして、果たしてあなたは彼女を「信頼できる」と断言できますか? このような場所では「まずスパイかもしれない」と常に前提を置いて、心の底では腹を割らないのがデフォルトになるでしょう。
今回『隠されし遺産を求めて』の副題が「トリニティの課外活動」なのは、このような裏の読み合いから離れた場所での話、という意味合いもあるのでしょうね。
ハナコの話に戻りますが、ハナコは「外の人」の関係がデフォルトですが、メインシナリオを追っていくと、内面的に情に厚いタイプの人間――例えば今シナリオにおいてもコハルを呼んだのは彼女の配慮です――だということが見えてきます。人と人との有り様に関しては、間に入って手助けする姿から「身内的(性愛的)関係」の方を希求しているのが伺えます。そして、彼女自身も心のどこかで他者との関係はそうありたいと願っているように見えます。
しかし、トリニティ総合学園という「利害」関係が渦巻く学園では、ハナコは「身内的(性愛的)関係」を築くことはできなかったようです。有能な彼女は特に使える「道具」としての関係を強く求められたのでしょう。失望したハナコはどこの組織に属することなく、トリニティ総合学園という性愛の欠片も見つからない、くそったれな学園――ハナコは「監獄」と形容していました――から離脱する「退学」という手段を選びます。これが『エデン条約編』での、ハナコのスタート地点になります。

『エデン条約編』では、ハナコはアズサの覚悟との出会いを通じて、このくそったれな世界の中でも、自分の手に入れたいものを手に入れるために「足掻く」ことを覚悟します。また補習授業部の面々とは、欲しかった関係性を築きます。ここでは、補習授業部との身内的(性愛的)な関係は「水着パーティ」という出来事で刺し止められている、とだけ引っ張っときましょう。
『エデン条約編』含む、メインストーリーでのハナコについては下記の方の記事が詳しいです。
しかし、『エデン条約編』含むメインストーリーにおいて、ハナコが補習授業部という身内的な関係に触れられたのは、一連の事件による偶然でしかありませんでした。関係に触れられたものの、それを作る力――このくそったれな学園の中で、ウイとヒナタが実行できた身内的な関係を作る力――を彼女はまだ手に入れれてないのです。
それは隠されし遺産と最後の敵に彼女はまだ顔を突き合わせていないから。
ここからイベント『隠されし遺産』のシナリオに入ります。
『隠されし遺産』
「仕事」の裏の「遊び」
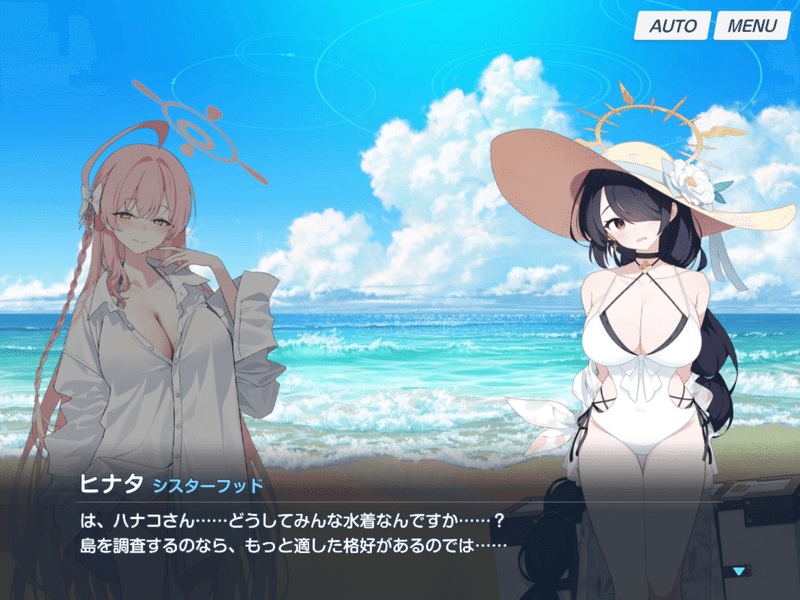
冒頭、ウイとサクラコの内緒話にこっそり潜り込み、ハナコは勝手に話をまとめてウイたちは遺跡に調査に行くことになります。正直、このときのハナコはかなり強引です。サクラコは遺跡のことなど一切言及していなかったですし、ウイに対してのお目こぼし条件として、サクラコにとっては遺跡調査より他の条件の方が良かったかもしれません。そんな中、ハナコは勝手に遺跡の話を持ち出し、Win-Winの損得の話に持ち込み、勢いでOKを出させました。イベント終盤でサクラコも言及していたように、ハナコに遺跡調査へと強引に誘導されたのは間違いないです。
さらに遺跡調査自体は百歩譲っても、なぜか遺跡調査なのに水着姿で調査を進めることになります。怪我の心配なども考えると合理性の欠片もありません。ゲームユーザ視点からは「夏の定番水着イベントだからだ」とメタ的に笑って済ませられますが、実は内部的にも筋が通っています。中盤、先生がハナコの内心を引き出したように、ハナコはただ「遊び」たかっただけなのです。そして、ハナコにとってただ「遊び」合える関係性の象徴が「水着パーティー」だったので「わがままに」水着にこだわったのは容易に想像できます。ウイたちを説得する場面は描かれませんでしたが、ハナコにとっては適当な理由をでっちあげるのは造作もないことでしょうね。
※公式4コマから、ウイとヒナタの水着はハナコが買ったようですね。
ハナコは「仕事」としての遺跡調査の体で、自身の行いたかった「遊び」を秘密裏に実現させていたのです。自分の本当の目的=本心を悟られずに目的を達成する政治的手腕は◎です。ただ1つ問題をあげるならば、裏を返せば、ハナコはただ「遊び」たいから「遊び」たいとお願いすることができなかったということです。真っすぐに行きたいから行きたいとお願いできなかったということです。

また人選についても理にかなっています。ハナコがここには砂漠しかないと見限って抜け出そうとしたトリニティ総合学園にて、ウイとヒナタが身内的(性愛的)な関係を築いているですから。ハナコにとっては――ウイを応援したいのと同時に――観察したい、最大の関心対象だったでしょう。(メタ的にはウイのイベントが2つ目になり、公平性から違和感を抱いた方もいるかもしれないですが、ハナコを主題においたとき、この過程にあるウイが自然と入って来てしまったのかなと思います)
コハルを誘った理由については、以前のトリニティ生徒たちの水着イベント『真夏のウィッシュリスト』が下地になっています。

以前のイベントでは、正義実行委員会の面々と補習授業部のヒフミとアズサの二人が海に「遊び」に行きました。それを背景に、ハナコは一緒に行けなかったから、自分も(コハルを誘って)行きたかったと内心を吐露しています。
またハナコとコハルの二人ですが、素直に気持ちを認められていないところがとても似ています。コハルは明らかに性愛的なものに惹かれているにもかかわらず、あるいは惹かれているからこそ「エッチなのはダメ!禁止!●刑!」と過度に反射的に抑え込んでしまう子だというのは分かると思います。コハルの、赤面しながらの「エッチなのはダメ!禁止!●刑!」という態度は「YES」であると同時に「NO」という両価性を孕んだ態度です。それは、コハルの中で、風紀を守る使命という大事にしたいことと、性愛的なものへの興味関心の2つがぶつかっているからです。性愛的なものへの興味からすると「YES」ではあるものの、風紀を守る態度からは「NO」であり、その上で、性愛的なものへの興味の方を抑え込んで言葉の上では一貫性を保とうとしているのです。「YES」かつ「NO」という状態は――心理的にはあっても――論理的には存在しませんから。コハルは、風紀を守る使命とはぶつかる場合もある、性愛的なものへの興味関心が自分の中にあることをどこかまだ真っすぐと認められていない――コハル自身から隠されている――からこそ、自身の中で分別をつけれていない状態なのです。あるものはあると認めさえすれば、どう折り合いをつけるかを考えられるようになりますからね。
聡いハナコですから、補習授業部だけでなく、正義実行委員会にも属するコハルに対して、ハナコは自分以上にコハルは寂しい思いをしていたのではないかと推測、素直じゃない彼女の気持ちを察して、多少強引に誘ったのではないかと思われます。(ハナコは「コハルちゃんの希望」と刺し止めています)

コハルが「自分が気遣われている」と気負わせないようにするための、配慮にも見えます。
どこか建前に聞こえてしまうのが勿体ない。
実際、コハル側もまんざらでもなかったのかな、という感じです。
正義実現委員会の一人として、風紀を乱すものを許さない!という使命感を持っているが、島でのバカンスも悪くないと思っている模様。
似た者同士の二人ですが、とても大きな違いもあります。コハルは傍から分かりやすいんです。言葉の上では断っていても、態度からアンビヴァレント性も含めた本音が見えやすい子です。一方でハナコですが、(上のコハルへの配慮のように)本音さえ建前っぽくしてしまい、おくびにも見せません。この対比から分かるのは、ハナコは気持ちを汲んでもらえる隙も見せれない子ということです。
言表内容と、それに伴う言表行為(=意図や思い)について:アニメ『ばらかもん』第5話から
自分から言い出せず、相手にも汲ませらせれないハナコ。話の中盤、先生はハナコにただ「信じてる」「話してくれると嬉しい」という言葉を掛けることで、彼女の内面と対峙します。なぜこの「信じる」という言葉/行為が、ここまで頑なに内面を見せれないハナコの心を動かしたのでしょうか。
少し遠回りですが、先生の「信じる」という言葉/行為の裏側にあるものから、考えてみましょう。
私たちは言葉の意味内容(言表内容)に加えて、その言表行為(=発話の意図や思い)も汲み取って、コミュニケートします。
例えば、大人が子どもたちを引率して海水浴に行ったとしましょう。そして、この際に大人から子どもたちに「飛び込みは禁止するように」と言い渡されたとしましょう。飛び込みを禁止するのはもちろん危ないからですが、この言葉の裏にはいろんな意図や思いが読み取れます。純粋に子供たちに怪我をしてほしくないという思いだけでなく、「他の人に迷惑をかけたり、事故などの面倒事を起こすな」だったり、果てはルールはルールだからと思考停止で押し付けてきているなと感じるときもあるでしょう。子どもたちから見れば、大人の勝手な都合や、合意もしていない大人のルールを一方的に押し付けられ、私の愉しみが奪われるように感じられれば「そんなの知らん」という気持ちにもなります。
アニメ『ばらかもん』の第五話は上記のような状態の話で、書道家の先生が監視役として、島の子どもたちの海水浴に着いて行く話になります。「危ないからやめろ」という先生に対して、子どもたちは無視して思い思いに遊び、先生は振り回されます。ひとしきり𠮟り終わった後、先生は大の大人なのに、持ち前の素直さからみっともなく「本当に心配だった」と半べそ泣きするんですよね。その様子を見て、子どもたちは本当に身を案じてもらっていたんだなと痛感して「先生…私も心配かけないから」と気持ちを改めるのでした。


©ヨシノサツキ/スクウェア・エニックス・「ばらかもん」制作委員会
言葉の内容だけでなく、その裏にある意図や思いまで受け取って初めて、「飛び込み禁止」は、私の愉しみを奪う命令ではなく、私のことを大切に思ってくれている人との約束になったのです。
先生の「信じる」における、2つの言表行為について
上記のように、言表内容だけでなく、言表行為(=意図や思い)も含めて、相手とやり取りがなされ、相手に影響が及ぼされます。また同じ言葉でも伝わる言表行為(=意図や思い)は往々にして異なります。
例えば「信じる」という言葉も、もし強権的な親や大人が発した場合は、往々にして「私(親や大人)のやってほしいことを察して実行しろ」という意図となっているでしょう。もちろん(ブルアカの)先生の「信じる」はそれとは全く異なる言表行為が伴っています。
先生の「信じる」には、2つの言表行為(=意図や思い)があるように見えます。1つは、生徒自身が心の底からしたいことを生徒が選択することを求める、先生の欲望。もう1つは先生の、愛への賭けです。
先生の欲望
先生はメインストーリーから一貫して「生徒自身がどうしたいか」という思いを第一にして、生徒たちが世界や社会の内で選択を迷う中、心の内から湧き上がってくる、生徒自身が最も望む選択を優先することを後押ししてきました。
メインストーリーの中でも特にわかりやすいのは『カルバノグの兎編』のミヤコですね。
シナリオで、カヤが実権を握った社会システムの中で正義とされることと、ミヤコが個として信じる正義が乖離します。このとき(社会的地位の安定も加味して)「法(社会)に従うという正しさ=カヤの正義」か「自身の心の中で感じている正しさ」のどちらを選択するかをミヤコは迫られます。普通の大人は「法(社会)に従うという正しさ」を取ることを生徒たちに要求しますが、先生は「自身の心の中で感じている正しさ」を優先することを(思いとして)生徒たちに要求します。この選択肢を取るように後ろ押しをするのが先生の欲望です。なぜなら先生は知っているからでしょう。後者を捨てれば、心が腐っていくことを。ブルアカでは「捻れて歪む」と表現されています。
このような葛藤は社会と”私”の間だけでなく、生まれの偶然など、生徒自身があずかり知らぬことと”私”の間などでも起こります。作中、ずっと先生は生徒たちが世界や社会、他者にとっての正しさより、生徒が己にとっての正しさを優先するように立ち回っていました。大人として、この欲望をもって生徒を後押しすることが「大人の責任」であると言及されている、と思っています。
先生の「信じる」という言葉には、生徒の「心の内から湧き上がってくること」自体の正しさと、生徒がそれを選択すること、また、その結果自浄作用的に物事が良くなっていくことまでも「信じる」、という含みがあるように感じます。
先生の「信じる」を受けた生徒は、その言表行為として「心の内から湧き上がってくること」の方を選択してほしいという思いも受けるわけです。
『隠されし遺産』のシナリオでは、ウイがこの欲望について代弁しているように見えます。なぜなら、ウイから「この子たち」への思いが、先生から生徒への思いとそっくりだからです。
この子たちの意志を尊重したいのであって、歴史を記録し、伝え残したいわけではないんです。
(中略)
そういった(歴史を後世に残したいという)意志のもとに残された物もありますが……思い出として、その地に自分たちの足跡を残したいという、純粋な気持ちもあるはずです。
(中略)
たとえ誰の目にも触れなかったとしても、大切な思い出として残したかった。
……それが、あの子の使命であり、責務だったのだと思います。
それをわざわざ掘り起こして、保管庫に収めたり、博物館に展示するのは……あの子を軽んじる行いです。
(中略)
せめて、タイムカプセルくらいは。
あの子だけでも、最後まで役目を果たしてほしいという、私のわがままです。
一方で、先生の欲望を受けるハナコ側の状態はというと、冒頭の誘導時のように、「遊び」たいから「遊び」たいと言えない、どこか自分の中でその気持ちを一番にできないでいた状態でした。
(先生に本音を漏らす直前の自問自答の様子から、もしかしたら、冒頭の遺跡調査への誘導も、ハナコ本人としては意識的ではなかった=無意識でなんとなく程度だった可能性すらあるなと思います)
タイトル名にもなっている「隠されし遺産」とは、ハナコ自身にも今や真っすぐ見えなくなっている、「遊び」たいから「遊び」たいという気持ち、およびそう言い合える、甘えられる関係を欲する気持ちではないかと思います。ハナコにとって、ある意味ハナコの存在自体そのものに近いようなもの。それは「遊び」の中で埋められたタイムカプセルの、空っぽの中身で代理表象されているように見えます。詰めた物は風化してしまいましたが、詰めた時の思いは見えない形でもそこにあるのです。「隠されし」には「実際に隠されていたこと」と「見えなくなっていること」がかかっているのでしょう。
ハナコは、対外的にも自分自身にも何かと理由をつけないと、自分の思いを思いのままに実行することができません。ウイと先生は、ハナコがその気持ちをハナコ自身の根底に置くこと、自身にとって一番大事なものだと認め、第一の目的にすることを望むのです。「遊ぶ」理由は「遊び」たいからでいいのです。
ウイ(と先生)の欲望はタイムカプセルに羊皮紙を添えるという形で代理表象されているように思います。

愛への賭け
ブルアカのストーリー中で目を引くことの1つが、先生が間髪入れず躊躇なく生徒を「信じる」と言い切ることだと思います。なにか理屈を超えており、妄信に見えるため「まぁ先生だから」となりがちですが、この先生の態度は「愛への賭け」と言って良いのではないかと思います。
最初から「身内的(性愛的)関係」同士の関係になれるのは、幼少の子同士だったり、相手が裏がないと分かるペット相手だったりで、ある程度の年齢以上同士になると、自然と「利害関係」寄りのフラットな関係からスタートになる人が多いのではと思います。ここからお互いを信頼し合えて、本音を言い合える関係になりたいとき、同時に本音を言い出すことはないですよね。どちらからが何らかの形で打診するような形で先に言い出す(意図的か、気が緩んでなどで)必要があります。
先生の「信じる」は、率先して本音を言い合える立ち位置に自ら立っていることを宣言し、生徒たちが握り返せるように待っているのだと思います。全面的に信頼するのは、先生側が線を引いたら(多くの)生徒はそれ以上入って来れないからでしょう。だから先生自らは線は引かず、そのうえで、生徒たちの線を無理には踏み越えない態度を取っています。押し入りはしないけど、来るもの拒まず、ですね。この立ち位置は一般的には悪意を持った相手に利用されやすい危ない位置です。その位置を率先的に取って相手が握り返してくるのを待つのです。この方法が「利害関係」から「身内的関係」へ――「囚人のジレンマ」を超えて――辿り着くための、唯一の経路なのでしょう。
※23/10/21追記 鬼怒川カスミによってもう1つの経路が示されました。
「身内的関係」は腹を割って本音を話し合える関係だとして、そもそも目の前の相手が信頼できるか、腹を割って話し合ってくれるかどうかをどのようにして判断できるのでしょうか。実は疑い出したら厳密には信頼できるかどうかは判断できません。私は相手のすべてを知ることはできない。上のスパイの話のように、裏の裏の裏の……を読みだすと切りがないからです。この一線を超えるには、最後の最後は理屈で「信頼できるかどうか」の判断をするのではなく、結果を期待して「信頼する」と言い切るしかない。ええままよ!と飛び越えるしかないのです。ある意味で理屈を捨てないといけないのです。


このような意思決定は「不確かな状況での選択」と呼ばれ、「〇〇の賭け」と評されます。有名なのは「パスカルの賭け」で、神はいるかいないは判断できない(不可知)が、神がいる方が期待値的に良いとして、神がいる方にパスカルは賭けるのです。
相手が信頼できる相手かどうかは究極にはわかりませんし、相手と身内的な関係を築けるかどうかもわかりません。自分は腹を割っているが、相手は腹の底では本音は隠して話しているかもしれません。しかし、身内的な関係性を求めるならば、最後は賭けに出るしかないのです。これは先生側だけの話ではなく、生徒側も同様です。生徒側も握り返す=賭け返すときに、この一線を越えないといけないのです。何しろ先生が裏切る可能性も、頭の上でいくら考えても0にはならないのですから。
実はここにハナコにとって、とても残酷な事実がありますが、一旦置いときましょう。
私がこの賭けを「愛への賭け」と評するのは、性愛的な関係を求めての賭けだから、ということもありますが、もう1つ思うところがあります。プラトンが『饗宴』で挙げた愛の在り方の1つに「愛される者が、突如として愛する者へと変貌する」ものがあり、ここには「果物に手を伸ばすと、果物から手が生えてそれを迎える」類の奇跡があります。先生側から見て生徒へ「信じる」と言い切る行為は「生徒が信じ返してくれる」という、この類の奇跡の種を撒いているように見えるからです。
また、先生の間髪入れない「信じる」には、個人的に――若干過大評価気味かもしれませんが――もう1つの、生徒が賭け返す際のハードルを下げる効果があるように思います。
まず前提としてですが、先生は生徒の友達ではありません。そのうえで、生徒と本音を言い合う関係性を作るとなれば「先生」として受ける度量がなくてはなりません。人生の言葉/魂の叫びは重いです。普通の人なら目を逸らしてしまうほどに。親に嫌われるかもしれない、期待に応えられない、私はこの世界に必要とされていない、私は愛されていない、一人は寂しい、ずっと褒められたかった、何のために生きてゆくのか、etc……。今回ハナコも「本音を素直に認められない、打ち明けられない」と言外で叫んでいるのです。このとき、友達や同僚関係のように愚痴を聞いて相槌を打って終わり、ではありません。「先生」に対して話す以上、ただ聞いてもらうこと以上の期待があるはずです。先生はこの叫びを受けるとき、狼狽せず、茶化さず、真っすぐに向き合って、なんらかの道を照らせる人でなければなりません。
逆に考えてください。あなたが生徒だったとした場合、頼りなさそうな大人に心の底根を吐露できますか? ロクでもない先生ならば話さえもロクに聞いてくれないかもしれません。問いに向き合えず、茶化して誤魔化したり話を逸らしたりしてしまう人もいるでしょう。ありきたりな言葉をズレたタイミングに繰り返されたりするかもしれませんし、聞きたくないと心の叫びを抑えつけられるだけかもしれません。本音を話しても真正面から受けてくれない、というのは思った以上にショックなものです。
先生の「信じる」態度の表明には、生徒たちからのどんな言葉でも真正面から受ける覚悟と度量、それに応えれる自分の言葉を持っている表明でもあるように見えます。
要はダサい大人じゃないよ、腹くくってる大人だよ、とも言っているわけです。だからこそ生徒たちから見て、打ち明けても大丈夫かもと、ハードルが下がるのだと思います。
ハナコさんの問題とハナコちゃんの希望
先生の欲望と愛への賭けがどう影響したのか、見ていきましょう。

レモン農園。ハナコが二人っきりになったタイミングで、先生は「ハナコのこと、信じてるから」と声と掛けたあと「話してくれると嬉しい」とハナコの問題意識に対して、本音を話す機会というクリティカルな誘いをします。それに対してハナコは最初、どこか言葉尻を濁しながら「ウイさんの問題とコハルちゃんの希望……」と口にします。確かにこのイベントではウイとコハルのこともあるのですが、明らかにこの2つはハナコ自身の問題でもあるんですよね。
惹かれる気持ちがあるのに素直に認められないコハル、ヒナタに対してつい「外の人」の距離感で接してしまうときがあるウイ。つまり、「遊び」たいという気持ちに向き合って素直に「遊び」たいと言えないハナコと、どうしても他の人との距離感を「利害関係的」の枠で捉えてしまい、心の根を晒すことができないハナコのことです。このタイミング、抑圧しながらも、何かハナコ自身が答えに触れようとしているのが感じられます。
先生が後押ししたのは、この2つです。「ハナコの希望」と「ハナコの問題」。身内的(性愛的)な関係性を求めるならば、理屈で相手が絶対信頼ができると答えが出ない以上、最後の最後は「信じるから信じる」という、論理を超えた賭けに出る決断が必要になります。そして、賭けに乗り出させるには「関係を求める気持ちを高める」こと、また、この人だったらきっと大丈夫そうだと「ハードルを下げる」のが必要なのです。先生は、ハナコ自身が持っている身内的(性愛的)な関係を求める気持ちを肯定してほしい(先生の欲望)と思いを当てつつ、「愛への賭け」を率先して持ち出して――諸々のストーリー上での信頼獲得も含めて――生徒たちから見てハードルが下げるように努めていたのです。
それと今イベントは単純にシチュエーション(エデン条約編が終わってひと段落していることや遺跡調査だが実質バカンス)が緊張感を低めていたのもあるでしょうね。
見えない心と見える肌色
ここまで丁寧にハナコの話が描かれているので、彼女の露出癖、引いては今回の水着衣装についても、シナリオから解釈できます。

彼女の露出癖、水着衣装は、男性受けが良い身体的フェチ的な装いであるというだけでなく、彼女の内面の現れにもなっています。それはハナコの甘えたいのに甘えられない心。相手を全面的に信用できない、心を開くことができない心です。それが抑圧され、心を開きたい、子どものように無邪気に周りと接したいという思いが、無意識的に彼女の服からの解放=露出に至っていたというのが、ひしひしと感じられるのです。今回の水着衣装、露出した水着の上に男性用(=理屈的)シャツを羽織っています。求めているのに、頭で考えて賭けに出られない、ハナコの心の有り様がまざまざと描かれているようです。
もちろん普通に男性用の方がそそる、というのもあると思います。フェチ的な趣味趣向と心が繋がるフュージョン系の趣味趣向を両立させてるのがやべーです。(個人的にこれは文句なしのフェス限ですね)
最後の敵
一方で「愛への賭け」などの内在ロジックが見えてきたからこそ、ハナコにとって残酷な事実も見えてきます。かつてハナコは性愛の欠片も見つからないくっそたれな学園から退学しようとしていました。しかし、そんな学園の中でも、ウイとヒナタは身内(性愛)的な関係を築けているのです。この差はなんでしょうか。運なのでしょうか。
確かに最後は運なのだと思います。ただ幸運に至るには「賭ける」という過程が必ず必要なのです。身内的な関係を築くには、己が自ら本音を先に晒す「賭け」を相手に贈るか、贈られた時に賭け返すかしか道はありません。補習授業部でも、アズサの「こくはく」が1つの端緒となったです。土地柄、機会が少なかったのは確かでしょうが、ハナコがトリニティで身内(性愛)的な関係を一切作れなかったのは、賭け続けたが本当に誰も乗ってくれなかった不運でふさぎ込んでしまったか、そもそも賭けに出れなかったかどちらかです。ハナコは明らかに後者でしょう。性格も含め、補習授業部以前にどこの機関/組織にも所属していなかったというのが彼女の賭けれなさを体現しています。つまり、ハナコが身内的な関係を作れなかった最後の壁は己が「心を開く」という賭けに出れなかったこと。ハナコにとって最後の敵は、トリニティ学園という場所ではなく、賭けに出れないハナコ自身だったということです。「監獄」から外に出る鍵はハナコ自身が持っていたのですね。
別作品ですが『ぼっち・ざ・ろっく』にて、先輩ベーシストの廣井と主人公のぼっちちゃんが初めて出会った回の主題が全く一緒で、このときの廣井の指摘が端的に的を得ています。
敵を見誤るなよ
抑圧、敵との邂逅、「隠されし遺産」の回帰
敵との戦いを見ましょう。先生に「話してくれると嬉しい」と言われた後、ハナコはしばらく一人で話を続けます。ハナコと先生の会話に見えて、この場面、ハナコがハナコと会話しているようにも見えます。
……。
ふふ……。
……そう言われると、弱りましたね。
これでバトンは私に渡ったのでしょうか?
自分から何かを打ち明けるのは、あまり慣れていませんが……
せっかく気にかけてくださっているのですから、
今日は先生の仰る通りにしましょう。
……夏ですからね。
(暗点)
――おそらく先生は
この状況を、ウイさんやコハルちゃんのため、私が用意したと思っているのでしょう。
私が詳しいお話をせずとも、取り立てて心配する素振りを見せず、信じてくださったわけですから。
捉えようによっては、ここはリゾート地と言えますし。
ここでなら、ちょっとしたバカンス気分を味わえますよね。
遺跡を調査する名目で訪れましたが、みんな水着姿で過ごしているわけですし。
ウイさんの問題とコハルちゃんの希望……
その2つを同時に解決できるピッタリの計画になっている、と
……先生は、そう思ったのではないでしょうか。
その認識で、概ね間違ってはいません。
(転換点)
…………。
ですが、先生
もし……もしもの話ですが。
このような時間が必要だったのは、ウイさんやコハルちゃんだけではなかった。
……としたら、どうでしょう。
先生「それって……。つまり……?」
(回帰)
そうですね……まあ、つまり……
私も、年相応の女の子ですから。
周囲からどう思われているかは別として、心は一人の平凡な少女。
たまには肩の荷を下ろして、みんなと笑って楽しい時間を過ごしたいと思っても、おかしくないでしょう?
2人のためというのは……自分に対する良い訳です。
その実、心では誰よりもこんな時間を望んでいた。
……みんなと海に行きたかった。
ふふっ。ただ、それだけのお話です。
(転換点)でハナコが行っているのは、常に逃げ道を残しつつ気持ちを述べる婉曲的な表現であるのと同時に、どこか自分自身への詰問のようにも見えます。自分の気持ちを述べるときに普通こんな言い方はしませんよね。まるでハナコのほかにいる、もう一人の犯人ハナコについて言っているかのよう。でも最後は逃げなかった。ここで、ハナコはハナコと向き合ったのです。言い訳をするな、そうじゃないよね?と。
そして、転換点の後、堰を切ったように「心では誰よりもこんな時間を望んでいた」ハナコの気持ち――「隠されし遺産」――が言葉として溢れ出てきます。


どこか軽く漂う甘い香り。話してくれてありがとう。ハナコは賭けに乗り出せたのです。
大切なのは、心、常に自分自身と向き合うのが大切なのだと……
心境の変化:ハナコに必要だったこと
遺跡調査から戻ってきた後、ハナコの言動にはいくつかの変化がありました。

まず1つ目はサクラコから遺跡調査に誘導した理由を尋ねられたとき「私の気まぐれ」と答えたことです。以前のハナコならば、なんらかの利得的な理由をこしらえて答えていたはずです。サクラコに詳細には話さなかったものの、私の「遊び」たい気持ちが原因で目的だと自身の中で言えるようになったのです。

またもう1つは、ウイからの(アイスアメリカーノの贈与を介した)歩み寄りに対して、とても素直に肯定的に返していることです。今回タイムカプセルの処遇について、ウイは「仕事」よりも「この子たちの意志を尊重したい」という「わがまま」を優先し、それを赤裸々にハナコたちに「こくはく」しました。上述したようにタイムカプセル自体がどこかハナコ自身のメタファー的な要素だったが故に、ハナコはウイのタイムカプセルへの思いを噛みしめていたように見えましたが、それと同時に、この機会はウイの人となり――どういう人物なのか――を実直に示す機会でもあったように思います。ハナコは利害関係の計算は脇に置いておいて、相手の人間性を信じて、賭け返せるようになったのかなと思います。
ハナコに足りなかったこと。それはまず自分の欲望を認めることと、歩み寄ってくれる相手の人となりを信じて賭け返す勇気だったのかなと思います。まだ相手に私の人となりを信じてもらえることを祈って、少しだけ自分から先に自分をさらけ出す=甘える勇気――先生のように自分から賭ける勇気――までは持てれてないけれど、少なくとも、これからハナコがこのくそったれな社会で、身内的(性愛的)な関係を築いていくための、スタート地点に立った、のではないかと思います。
共犯:ヒナタと先生とハナコ~3つの魔法~
最後に。神話に繋げるために「身内的(性愛的)関係」自体についての話を少しします。作中「共犯」というキーワードが出てきますが、これは「身内的(性愛的)関係」側のワードになります。
「信頼」し合う関係の方に、法を犯す「共犯」があり、「疑い」合う関係の方に正しさを規定する「法」があるという、一抹の気味悪さがあるのですが、これは何のための「法」かという視点によるものです。
少し話が戻りますが、レモン農園での出来事のあと、ヒナタと先生が敵(ミメシス)に襲われる場面がありました。その際、二人は他の人の調査時間を取ってしまうことを嫌い、「何もなかった」と嘘をつきます。傍から見て明らかに嘘であり、ものすごく怪しい。ウイは絶対に裏があると声を荒げる一方で、ハナコは察してウイをその場から引き離します。
この場面、見えていることはヒナタと先生が「明らかに嘘をついている」ことだけです。見えていることに対して、ウイのように何か裏があると見るのか、ハナコのように先生のことだから大丈夫だと信じるのかは、嘘の意図をどう読むかという、それぞれの心持の問題しかありません。
ハナコもどういう意図で先生が嘘をついたのかを、察しはついているかもしれませんが、確定的には本当のところは知り得ません。ただハナコの前提にあるのは先生が私たちにとって悪くなるようなことをするような人じゃないという信頼です。何か物的証拠があるから信じているわけではないのです。「そういうことする人じゃないから」という感覚で、相手の人間性を担保に信じられるのです。もちろん(スパイの話のように)人間性さえ騙されて勘違いさせられている可能性も0ではない以上、結局どこかに「まぁ大丈夫だろう」という飛躍があるわけで、つまるところ「(こういう人だ、と)信じる」から「信じる」という、厳密な論証にはなっていない、証明しえてない(=楽園の証明の不可能性を持っている)ロジックなのです。でも、それでも信じれる。この「信じる」から「信じる」という状態はもはや理屈を超えており、ある種の魔法にかかっているとしか言いようがありません。
このときかかっている魔法の記述として、ある作品の題名が的確に表現しています。シャニマスの『MAGIA L'Antica ~アンティーカの5つの魔法~』です。アンティーカは五人組の身内的な関係性を持っているユニットです。身内的というとグループ全体に1つの魔法がかかっているような印象を与えますが、実際は相手を「信じる」から「信じる」という奇跡的な状態は個々人の心の中で起こっているのです。だから人数分、5つの魔法なんです。その上で、個々の「信じる」から「信じる」という法外の魔法で5人は繋がっているのです。

同じ主題(身内的性愛的関係)を扱っているコミュ
本文からは読み取りにくいですが、
題名やエロティックな表題イラストから同じ主題が読みとれます
シナリオとしては摩美々の話が彼女が身内的な関係を感じているとわかりやすいです
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
逆に、今回のウイのように何か裏があるに違いないと思った場合、私たちは何に頼るのかというと法です。今回ならば「嘘をついてはいけない」という法=「経典」です。それは神の言葉であり、正しいから正しい言葉です。もしウイがこの法をもって問いただしたとすれば、ヒナタと先生はしぶしぶ理由を説明して謝ったでしょう。ただそうしてしまうと、ヒナタと先生からの法外の繋がりは切れてしまうのです。法を介する関係は、法に対する忠誠あるいは従順はあれど、相手に対する信頼はないのです。むしろ疑いがある。信頼ができない=疑いがあるから法で縛る。法で縛ろうとするから、前提として疑いがあることを含んでしまう。これが法を介した関係性の在り方の陥るところです。
ヒナタと先生は「嘘をついてはいけない」という法よりも、相手の時間を無駄に使いたくないという配慮から、法を犯して嘘をついているのです。ハナコは意図を信じて、嘘をつくという侵犯を些細なこととして見逃しているのです。彼女らは法を犯している/侵犯を見逃している「共犯」であり、法を超えたところ=法外で繋がっている関係です。法よりも大事なところで繋がっているのです。
つまり、「信じる」者同士は、法外で繋がって身内的な「共犯」であり続けるのに対し、疑いが挟まると、法で縛ろうとして法を介した融通の利かない、利害的な関係に陥ってしまう、ということです。
とはいえ、実際的に「身内(性愛)的関係」を維持し続けることは不可能なことで、時に疑いの心が立ち上がって、その度修復していくのが普通です。

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
一度関係が出来上がったら終わりではなく、ちゃんとメンテしていく必要があります。「雨降って地固まる」という言葉がありますが、信じきれなかった相手を信じれるようになっていく過程のことなのでしょうね。
ちなみに「身内(性愛)的関係」を特に容易に壊しやすい話題は金銭関係と男女関係で、扱いに細心の注意が必要です。やはり所有は悪では。
役目

性愛の子、浦和ハナコ。
ブルアカのキャラクターには元になったモチーフがあることが知られています。例えば、シロコはアヌビス神がモチーフであり、メインストーリーでも披露されています。キャラクターの凸素材の名称が「神名文字」ということもあり、おそらくすべてのキャラクターでモチーフがあると考えられています。
今回のハナコをメインとしたシナリオの主題や、彼女の愛読書が性愛論書『カーマストーラ』であることなどを加味すると、十中八九、ハナコのモチーフはギリシャ神話の愛の神エロスでしょう。
エロス「疑念がある限り、愛は成り立たない」
ここに作中の役目という言葉が強く共鳴します。しかし、ハナコにとっては、役目であると同時に――このシナリオを通して――もはや本望にもなっているでしょう。
ところで、あなたはハナコの賭けの結果を1つ知っているはずです。半ば先生に背中を押される形になりましたが、ハナコは先生の方に向かって賭け返しました。
レモン農園でハナコが「誰よりもこんな時間を望んでいた……みんなと海に行きたかった」と赤裸々に言葉にしていたとき、あるいはシナリオを読み終わったとき、ハナコに対して「ああ、この子はこういう子なんだな……」と、好感度が上がったような感覚、少し甘ったるい、温かい気持ちにならなかったでしょうか。それが、ハナコが欲しかった人と人の心の繋がり方の感情――「性愛(エロス)」と呼ばれるものです。
この機会に性欲と区別できるようになっときましょう。
ハナコは賭けに勝ちましたか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

