
【ブルアカ】カルバノグの兎編(~2章)の感想と「デカルト」という夾雑物について
ブルーアーカイブのメインストーリー『カルバノグの兎』編(~第二章)の感想になります。
記事中の画像は上記ゲーム画像になり、「© NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc.」になります。
現在、私たち人間は社会と関わりなく生きることはできない。人の集まりである社会の中で、私たち個人は、社会が存続・腐敗しないようにするために、所得の再分配などの、法へ遵守を求められたり、その社会の中での道徳的・倫理的な規定を身に受けることになる。社会と私たち個人の関係は、上記のように、抜き差しならない緊張感を持ったものになっている。
『ブルーアーカイブ』の世界設定やシナリオは、社会やこの「社会と個人の関係」への言及がとても上手い。トリニティとゲヘナという民族的な対立。レッドウインターという某北の国を連想させる学校(社会主義=左翼=赤)。カイザーコーポレーションという資本主義の象徴。こう(直接的に)文章化してしまうと、恐らく今の日本では多くの人に忌避されてしまい、シナリオは読まれないのではないだろうか。その点、『ブルーアーカイブ』はその最初の躊躇を取り除くために脱思想化、脱宗教色が徹底されており、間口を広くとることに成功している(「法と正義」という堅苦しそうな題名の本より『カルバノグの兎』という題名の美少女たちの物語の方が取っつきやすいでしょ)。
しかし、しっかりと「社会と個人の関係」への問題提起は残っているため、地に足のついたシナリオになっており、その社会の中で私たち個人はどう生きるべきかという主張(先生の欲望)にも説得力を感じられる。『ブルーアーカイブ』のシナリオが評価されている一端は、このあたりにあるだろう。
『カルバノグの兎』編

メインストーリー『カルバノグの兎』編は、その中でも「法と正義」の関係について言及したシナリオだろう。簡単に流れをおさらいする。
SRT特殊学園はキヴォトスのあらゆる自治区への介入ができることを目的に、キヴォトスの最高権力である連邦生徒会長直属の学園組織として法の下に創設された学園であった。あらゆる権威的なしがらみにとらわれず、純粋に”正義”を執行する機関としてSRT特殊学園は描かれる。しかしながら、連邦生徒会長が失踪し、SRT特殊学園は責任者が不在となってしまい、強大な武力を誇る機関が責任者がいない状態で放置されていることへの懸念から、SRT特殊学園は閉鎖が決定されてしまう。
SRT特殊学園は、所属する生徒たちにとって自身の信念やアイデンティティの基盤となる場所であったため、生徒たちは各々に閉鎖反対デモや復活の行動に乗り出す。ミヤコ率いるRABBIT小隊は閉鎖反対へのデモを起こし、ユキノ率いるFOX小隊は、学園復活を天秤に、防衛室長のカヤの命令の下で、彼女らの正義ならざるものに手を染めていく。
カヤによるクーデターの後、連邦生徒会長代理となったカヤが学園復活を約束していることをRABBIT小隊は知らされる。RABBIT小隊としてはデモをする理由がなくなったため、公園でのデモはやめ、FOX小隊に吸収されることを選ぶ。しかし、カヤがテロ事件を画策し、FOX小隊がその命令に従って実行しようとする姿に、ミヤコは離反し、先生と共にテロを阻止しようと動く――。

ここに至って、学園復活の目的の下に”武器”として行動するユキノと、己の中の正義に従い、カヤによる学園復活の約束は捨てて行動するミヤコが対立する。
『カルバノグの兎』の主題は一言で言うと、SRT特殊学園の閉鎖デモを起こし復活を希望していたミヤコが、法の下の”正義”の執行機関であったSRT特殊学園は、かつて己の中の”正義”を実行できた、ただの場所――社会のシステム内での地位――に過ぎないと気づくことだろう。”正義”はSRT特殊学園の名の下にあるのではなく、己の中にあるだと。
カヤが責任者となったSRT特殊学園が復活しても、かつてのように、ユキノやミヤコが望む”正義”を実行できるような機関となることはないだろう。この社会の最高権限を持つカヤの命令の元で為される行為は、社会として正しいと是認される行為になるにも関わらず、だ。
ミヤコは最初から振り切ることはできず、どう立ち回るかという葛藤があった。それは「法に従うという正しさ」と「自身の心の中で感じている正しさ」のどちらを優先するべきなのかを、ミヤコの中で解決できないでいたからだろう。法が名指す正義が己の中の正義と一致している間は問題にはならないが、ずれた場合にその葛藤が心の中に湧いてくる。社会の中で生きる以上「法に従う」のは社会の約束事である。特に軍隊的な色が強い、規律の厳しい組織にいればなおさらだろう。ユキノは「法に従うという正しさ」に身をゆだね、ミヤコは「自身の心の中で感じている正しさ」に従う。この選択の違いによって、行為の責任の所在も変わってくる。
例えば、ある生徒がいたとしよう。私が彼に「〇〇してほしい」と頼み、彼は、それは彼にとって良くないことだと感じていても、頼まれたから実行したとしよう。そして、その結果、良くないことが発生したと非難されたとしよう。責任を追及された時、彼はこう答えないだろうか。「言われたことをやっただけだ」。責任は依頼した側にあり、彼自身にはないと。
このような在り方は”武器”として言及される。テロを実施するユキノの”武器”状態ははっきり言って、”凡庸なる悪”と言って差し支えないだろう。
第二次大戦中に起きたナチスによるユダヤ人迫害のような悪は、根源的・悪魔的なものではなく、思考や判断を停止し外的規範に盲従した人々によって行われた陳腐なものだが、表層的な悪であるからこそ、社会に蔓延し世界を荒廃させうる、という考え方。
ユキノは「法に従うという正しさ」を遵守することや社会というシステム中での地位の維持の方(SRT特殊学園の復活)に固執してしまうことで、自身の内発的な良心を抑えつけてしまっている。このように、生徒が自身の正しさを抑えつけて、”武器”状態になってしまっている有り様をブルアカは「捻れて歪む」と表現しているようだ。
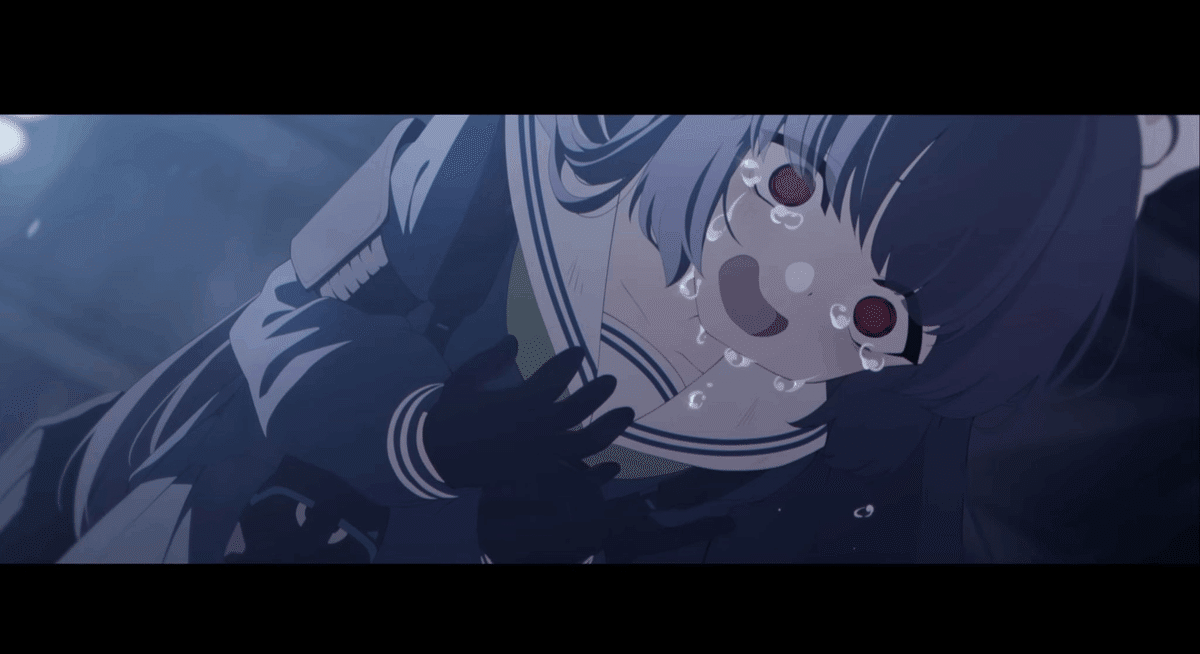
https://www.youtube.com/watch?v=4rDOsvzTicY

逆に「自身の心の中で感じている正しさ」に従った場合、責任を取れるのは自分自身しかいない。また社会の正しさと反していた場合、私は社会というシステム内での地位も失うかもしれないだろう(逆に言えば法に従っておけばシステムの中での地位は確保される安牌となる)。故に「法に従うという正しさ」か「自身の心の中で感じている正しさ」かを安易に決めることができず、葛藤が起こる。
そして、ミヤコのこの葛藤を解消したのは先生であった。先生は「自身の心の中で感じている正しさ」を優先することを推奨し、生徒たちの背中を押す。

また先生自身が「責任を取る」と言っているのは、事態の結果に対して責任を取るという意味合いだけでなく、「自身の心の中で感じている正しさ」を優先するように背中を押したことに対して、私(先生)が責任を取ると言っているのだ。

【生徒が「法に従うという正しさ」よりも「自身の心の中で感じている正しさ」を優先し、捻れて歪まないように在ること】。これが、先生個人の(心の中で感じている)正しさであり、先生の欲望である。普通の大人は「法に従う」ことを要求するが、先生は「自身の心の中で感じている正しさ」を優先することを要求する。故に先生は”変な大人”と呼ばれる。
※もちろん先生は「法を無視しろ」とは言わない。あくまで優先度の問題であって、内発性の正しさを優先しつつ、法とは上手く付き合えという態度である。駅が封鎖された時のカンナの対応が良い例だろう。
生徒に対して、”武器”化するな、責任を法に押し付けるな、己の正しさに従え、という態度を取る以上、ポリシーとして、先生自身としても、責任を法に押し付ける立ち位置に立つわけにいかない。故にシャーレの責任を法的に連邦生徒会になすりつけることができるようにするというカヤからの提案を、先生は受け入れる事はない。生徒たちに示しがつかないのと同時に、それは楽であるが、社会の正しさと私の正しさがずれた場合に、心が腐っていくことになるから。


このような先生の欲望に背中を押されて、生徒たちは、「社会から押し付けられる正しさ」よりも、「自らの正しさ」を元に道を歩めるようになっていく。
先生は今までも(『カルバノグの兎』以前のシナリオでも)生徒たちに対して「自身の心の中で感じている正しさ」を優先するように背中を押し続けてきたのだった。(最終編の感想・考察でまとめている)
ただし、今までのシナリオは法という硬いものよりも、もっとふわっとした「社会などの外界から押し付けられる正しさ」に対して、「個人としての正しさ」を保つように、というような内容であった。
「社会などの外界から押し付けられる正しさ」とは、法だけでなく、倫理的な規範や同調圧力も含む。得てして私の外側からの命令のように感じられる、押し付けられているように感じられるもの全般を指す。例えば、朝食を普段食べない人が「朝食を食べた方が健康的」と聞けば――善意からの助言であったとしても――そこに(僅かでも)「朝食を食べろ」という圧を感じるだろう。または運命のような、私のあずかり知らぬところで決められた私の”性別”のような属性――例えばアリスにとっての「名もなき神々の王女」――さえも、外部からの押し付けとも言える。
※ラカンの、法としての「大文字の<他者>」が概念として一番近いだろう。
『カルバノグの兎』編は、メインストーリーの中で「社会などの外界から押し付けられる正しさ」と「個人としての正しさ」の対立を、SRT特殊学園という”正義”=正しさを執行する学園を巡って「法と正義」という対立の観点で先鋭化させて見せつけたシナリオと言えるだろう。正義は――道は――己の中にある。
「勇敢で純粋な心の持ち主のみ――カルバノグの洞窟で道を見つけられるだろう」

設定やシナリオに落とし込むの上手すぎでは……。
以下は蛇足だけど、逆に落とし込むのが上手いからこそ個人的にしっくりこない存在がいる。それは「デカルト」である。立ち位置がなんか変なのだ。
法で結んだ関係と法外で結んだ関係
社会は法から成る。法は定住段階から発生したと言われる。定住段階とそれ以前(遊動段階)では、下記のような対立が見られ、『カルバノグの兎』編では、その対立が散りばめられている。

カヤが連邦生徒会会長代理に就任後、大量のルール(法)を施工して、犯罪率の低下を図ろうとする(この有り様は、現在の日本の安全・安心・秩序を求める様を揶揄しているようで苦笑いが止まらなかった)。いきなり融通が利かない法の施行に社会は混乱する。
特徴的な例としては、キリノが遭遇した駅の検問である。警官であるキリノの顔見知り(=身内)が体調不良で困っている状態なのだが、(いきなり当日に施行されたことさえも加味してくれず)、カイザーコーポレーションは検問を通る資料がないと、一切融通を利かせない。身内ではなく、信頼のない他人扱いなのだ。信頼がないからルール(法)で縛るのだ。(雇われのカイザーコーポレーションの対応としては妥当だろう。ここで問題なのは、社会として全部が全部この信頼のない他人同士の関係になってしまうのは大丈夫なのか?ということだ)
この信頼のない他者関係が顕著に表れているのが、カヤとジェネラルの関係である。彼女らの関係は利害関係だけで結ばれている。裏切られても利用価値があるならば、情動的な側面は捨てて、関係を保つ。逆に言えば、利用価値がなくなれば、関係を持つことはないし、相手が困っていようとも、利がなくては助けることはない。言うまでもなく資本主義がこの関係の旗手であり、民族間的=国際的政治には友情はなく利害だけがあると言われる所以である。
逆に身内的=民族内的関係というのは、(圧倒的な)贈与と剥奪関係で結ばれる。例えば、家族の中で食事にお金を払わせるだろうか。先生はRABBIT小隊のいる公園に足げく通い、お弁当を提供する。贈与と剥奪がセットなのは、シェアだからである。貰えることあるし、与えることもある。この関係では、相手が困っていたらシェアして助け合える。
『カルバノグの兎』編で途中に話題に出される「囚人のジレンマ」は、利害関係=損得関係として結びついている囚人が裏切る選択肢を取るということであって、この囚人がもし双方、身内的な関係を結べていれば、相手を信頼する最も良い選択肢を取れるのだ。先生がまず「自分が信頼する」と言ってはばからないのは、自身が生徒とは、利害関係=交換関係ではなく、身内的な関係を結びたいという意志の表明であり、生徒が手を握り返してくれれば最も良い結果になりうるからだ。

ブルアカはこのあたりの関係のリアルさと、先生の”変な大人”感が熱い。
非-非所有の「デカルト」

この表で、所有-非所有の対比が入ってくるのは、定住を開始した際に、所有を確保するために法ができたと言われるからで、それまでは獲物などは非所有(=シェア)だった。
非所有の道を説く「デカルト」は、この表では明らかに先生側の存在である。しかし「デカルト」は三流的な人物として記述されている。それがとても奇妙なのだ。というのも、ブルアカの主義主張として、ミヤコが勝ち、先生は圧倒的に(指揮官として)強い存在として描かれている。シナリオで先生側が肯定されている。なのに、主義として先生側だろう「デカルト」はモブで三流である。敵だったり味方だったりする。そのうえ、妙に強い名前が付けられている。なんだこいつ。
個人的な解としては、おそらく命名自体がギャグなのだろう。
ブルアカは聖園ミカに代表されるように、ヒトの捉え方が現代ヨーロッパ哲学風である。ハイデガーやラカンを潮流とした無主体的な主体の持ち主としてヒトを捉えている(下記ミカの記事を読めば雰囲気はつかめるはず)。この捉え方は批判的な立場からは「自我殺し」とも呼ばれている。
ラカンの元では自我は「たまねぎの皮」に例えられる。自我は「たまねぎの皮」のような衣服をまとっているが、すべてを取り払うと何も残らない。
言うまでなく哲学者としてのデカルトはデカルト的自我の提唱者であり、自我を保持する側の存在である。
おそらく、ブルアカの「デカルト」の命名は、非所有の道を説いているのに、自我という所有物を捨てれない存在という皮肉なのだろう。そして、実態として非所有の道に至れてないから、先生側ではない扱いなのだろう。確かに彼はたまねぎの皮を被るように、コロコロと自身の思想・肩書を変えて登場してくる。
ただ個人的に楽しみなのは「デカルト」は今後どうなっていくのかわからないという点だ。カヤでさえ、生徒であるということから、「どうやって」は見当がつかないが、「どういう方向に」先生が導くかは予想がついてしまう。しかし、生徒でもないし、在り方も中途半端な存在である「デカルト」は、ギャグ要因として放置されるのか、先生側に至るのか、ブルアカが今後どう料理していくのか注目だ(注目しなくて良い)。
なんか「デカルト」で話が終わるの嫌だな。
『カルバノグの兎』編、設定とシナリオに”社会と個”を落とし込むのがめっちゃ上手い、というのが伝われば幸いです。
そのうえで、先生はやっぱメシア的な立ち位置なんだろうなと感じるのでした。先生から「大人の責任」は最終編から受け取りましたが、『カルバノグの兎』編の感想を書きながら、自分から「信頼する」ことの大切さが――あるお金持ちが何回騙されたことがあっても、信頼しないと始まらないと言っていたことを思い出しながら――なんとなく分かった気がしました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

