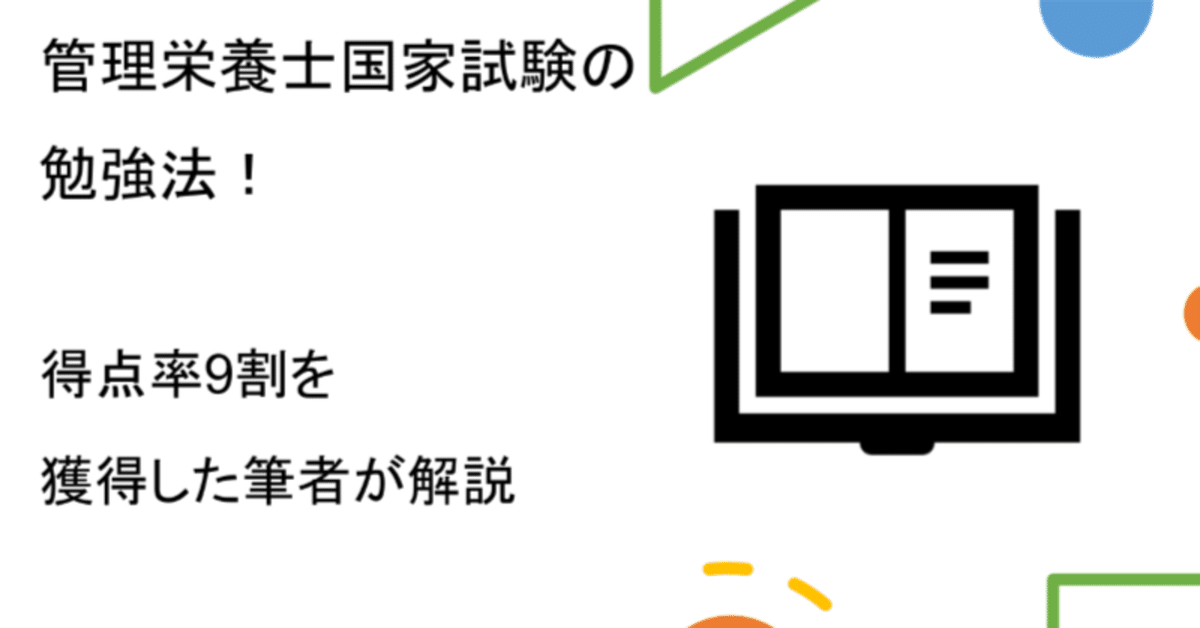
管理栄養士国家試験の勉強法!得点率9割を獲得した筆者が解説
先輩の国家試験が終わった
春から4年生になった
先生から国家試験について言われるようになった
など、ここにきたあなたは様々な理由で、管理栄養士国家試験を意識し始めたのだと思います。
管理栄養士の国家試験ってどうやって勉強すればいいの?
範囲が広すぎて、勉強が終わる気がしない(;_:)
スケジュールはどうすればいいの?
効率的な勉強法はないの?
など不安がたくさんあると思います。
今回はそんなあなたに、国家試験に合格するための勉強法をお伝えしていきます。
わたしは、管理栄養士国家試験の本番で9割の得点率を獲得したので、その経験で少しはお役に立てるのではないかと思います。
ベースとなる参考書を1つに絞る
管理栄養士の国家試験対策用の参考書はたくさん販売されていますが、ベースとなる参考書を1つに絞ったほうが良いです。
情報がバラバラになると効率的な勉強ができなかったり、試験間近になって不安になったりするからです。
もちろん、教科書で調べたり、他の参考書を使って補足情報を得たりすることもありますが、ベースの参考書に情報を集約し、試験間近で「この参考書を見れば大丈夫!」という状態にしておくことが大切になります。
オススメの参考書を3つ紹介するので、他の参考書と合わせて、自分に合っていそうなものを選んでください。
1つ目は「クエスチョンバンク」です。
管理栄養士の国家試験対策でオススメの参考書を聞くと、ほとんどの人がクエスチョンバンクと答えると思います。
QBと略して書かれることもあります。
イラスト付きなので、分かりやすいと評判です。
最新版が発売されるのは7月上旬になっています。
2つ目は「国試の達人」です。
重要なポイントがまとめてあり、各科目ごとに過去問で正解となった、あるいは正解となる文章が記載されています。
ポイントと正しい文章を覚えることができるので、わたしは、国試の達人をベースの参考書にしていました。
クエスチョンバンクに比べて、イラストは少ないですが、厚さが半分なので持ち運びしやすいです。
国試の達人は普通の書店では入手できず、以下の2つのどちらかの方法で入手することができます。
RDC管理栄養士センターのサイトで購入する→4,600円(12/25までに申込むと3,220円)
RDCの模試を2回以上受験する→無料でもらえる
国試の達人の最新版が発行されるのは11月上旬です。
3つ目は「管理栄養士国家試験頻出ワード別1問1答」です。
科目順ではなく、過去5年間の国家試験の頻出ワードがランク分けされていて、出るとこ順にまとめてあります。
国家試験で押さえておきたい基礎データと新しいトピックも掲載されているので、既卒の方にもオススメです。
軽くて小さいので持ち運びしやすく、出るとこ順にまとめてあるので、わたしは国試の達人と並行して、こちらも使っていました。
管理栄養士国家試験頻出ワード別1問1答の最新版が発売されるのは8月下旬です。
過去問を解く、模試のやり直しをする
管理栄養士国家試験の対策の王道は、過去問を解くことです。
国家試験は、過去問と同じものやアレンジされたものが出題されることが多いので、過去問を解くことが、合格への近道です。
古すぎる過去問を解いても、問題の傾向が変わっている可能性があるので、過去5年分の過去問を繰り返し解くようにしましょう!
過去問や模試を解いた後は、分からなかった部分を参考書や教科書で調べます。
間違っている文章は、正解の文章にするにはどうすればいいのかを考えて、書き込みます。
問題を解くだけではなく、間違っているものを正解の文章にすることによって、1つの問題でいろいろな知識を身に着けることができます。
覚えるためのコツをおさえる
国家試験に合格するためには、かなりの量の暗記が必要です。
覚えるためのコツはいろいろとありますが、わたしが実践して効果があったものを紹介します。
イラストをかく
覚えたいことをイラストで表現して、イメージで覚える作戦です。
例えば、下の画像のように酸塩基平衡の状態を人の表情や腎臓の気持ちで表現することができます。
絵心がないのは許してください( ノД`)
イラストにしたり、表にまとめたりするのは書くときも見るときも覚えやすくなるのでオススメです。

語呂合わせを調べる、作る
語呂合わせはかなり活用しました。
「管理栄養士 ゴロ」などで調べると、いろいろ出てくるので、それを参考書にどんどん書き込みましょう!
語呂合わせが見つからず、どうしても覚えられないものがあったら、自分で語呂合わせを作ってしまうのも良いです。
エビングハウスの忘却曲線を意識する
忘却曲線という言葉、聞いたことがある方もいらっしゃると思います。
意味を持たない3つのアルファベットの羅列を被験者に覚えてもらい、どれくらいのスピードで忘れられるのかを研究した結果から、理論を導き出しています。
その研究によると、人は1時間後には覚えた内容の56%を忘れ、1日後には66%も忘れてしまうそうです。
※正確に言うと、エビングハウスの忘却曲線の縦軸は節約率(=100%-再び覚えるのにかかった時間(%))で、覚える時間がどれくらい短くなったかを表しています。覚える時間が短くなったことを「覚えていた」と解釈して、人が時間の経過にしたがって、どれくらい忘れているかを伝えるために利用されることが多いです。
頑張って覚えて、1日後にはほとんど覚えていないなんて悲しいですよね(;_;)
ですが、人間は忘れる生き物なので、そこを嘆くより、どうやったら覚えることができるかを考えたほうが良いです。
それでは、どうすれば記憶が定着しやすくなるのでしょうか。
それは、エビデンスの忘却曲線に合わせて復習をすることです。
エビングハウスの忘却曲線を導き出した研究で、被験者に覚えてもらったのは意味を持たないアルファベットの羅列ですが、わたしたちが国家試験に向けて覚えるのは意味のあるものなので、忘却曲線がゆるやかになると考えられます。
そこでわたしは、以下のタイミングで復習をしていました。
1日後、3日後、7日後、14日後、30日後
30日後に覚えていれば、長期間記憶にとどめておくことが可能です。
国家試験を受験する仲間と問題を出し合う、人に教える
ある程度知識量が増えてきたら、国家試験を受験する予定の仲間と問題を出し合いましょう。
遊び感覚で問題を出し合うだけでも、「あのとき話した問題だ!」と記憶に残りやすくなります。
また、問題を出した後に人に解説することで、理解が深まります。
人間は人に教えられるようになって、はじめて理解ができたという状態になりますので、ここまでできると応用がきいた問題にも対応できるようになると思います。
まとめ
今回の記事では、管理栄養士国家試験へ向けての勉強法を解説しました。
勉強する範囲が多すぎて、途方に暮れている方もいるかもしれませんが、少しずつでも確実に準備を進めていけば、合格へ近づいていきますので、ぜひ頑張ってください(*^^*)
つらい勉強期間を乗り越えて、合格した時の喜びは何とも言えないですよ!
あなたが国家試験に合格をして、晴れやかな春を迎えられることを応援しています!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
