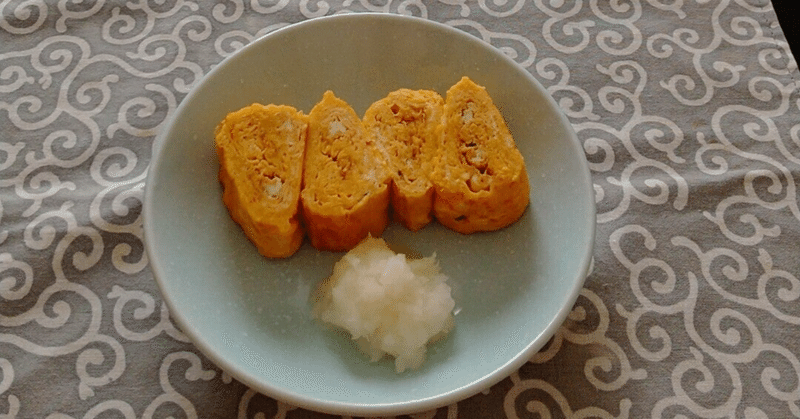
岩波書店『定本漱石全集』注解を校正する77 夏目漱石『それから』をどのくらい正確に読めるか⑤
プログラムの一部分の遂行
然しそれは代助が生れ落ちるや否や、この親爺が代助に向って作ったプログラムの一部分の遂行に過ぎないので、代助の心意の変移を見抜いた適宜の処置ではなかったのである。自分の教育が代助に及ぼした悪結果に至っては、今に至って全く気が付かずにいる。
むしろここは若い人たちの方がすんなりと頭に入ってくるところであろう。ここでいうプログラムとは演劇等の演目を記した紙の事でコンピューターのプログラムではない。しかしむしろ何か目的実行型のプログラムのように捉えた方が分かりやすい感じがする。それは漱石がプログラムという言葉を字義通りに使っているからだが妙に未来感がある。
こんなことも言いたくなる。こうしたプログラムという言葉の使い方、実物としてのプログラムではなくプログラムの性質を取り出し、順序通り進められていくことの意味として抽象的な形で使用したのはおそらく漱石が初めてであろう。
現代との意味の乖離という点にかんがみれば、このように極めて特殊な使われ方ではあるものの、一応コンピュータの存在しない時代のプログラムと云うものはこういうものだということも、これからは記録しておかねばならなくなるのではなかろうか。
古風な弓術撃剣の類
親爺は戦争に出たのを頗る自慢にする。稍もすると、御前などはまだ戦争をした事がないから、度胸が据らなくって不可んと一概にけなしてしまう。あたかも度胸が人間至上な能力であるかの如き言草である。代助はこれを聞かせられるたんびに厭な心持がする。胆力は命の遣り取りの劇しい、親爺の若い頃の様な野蛮時代にあってこそ、生存に必要な資格かも知れないが、文明の今日から云えば、古風な弓術撃剣の類と大差はない道具と、代助は心得ている。
代助の年齢は夏目漱石よりも十歳以上若く設定されているため、一世代若い感覚になる。庄司薫さんと薫くんのような関係か。夏目漱石は世代としては『三四郎』の広田萇に近く、まだ内戦が続いていた時代に青年期を過ごしていたことになる。つまりいつ皇軍兵士として戦争に参加するとも限らない時代を一応は体験していたということになる。
そして高浜虚子の記録を見て意外の感に打たれたのは、夏目漱石が弓の稽古をしていたことだ。平民階級に属しながら『坊っちゃん』では士族の意識を示すのも、案外本音に近いものがあったのかもしれない。
それは夏であつたのであらう、漱石氏の着てゐる衣物は白地の單衣であつたやうに思ふ。その單衣の片肌を脫いで、其下には薄いシヤツを着てゐた。さうして其左の手には弓を握つてゐた。漱石氏は振返つて私を見たので近づいて來意を通ずると、「あゝさうですか、一寸待つてください、今一本矢が殘つてゐるから、」とか何とか言つてその右の手にあつた矢を弓につがへて五六間先にある的をねらつて發矢と放つた。其時の姿勢から矢の當り具合など、美しく巧みなやうに私の眼に映つた。
何故漱石が弓の稽古をしていたのかは判然としない。ただ生存に必要な資格ではないにせよ、精神的には何かそういうものを求める所があったのだろう。
彼は地震が嫌いである
彼は地震が嫌いである。瞬間の動揺でも胸に波が打つ。あるときは書斎で凝っと坐っていて、何かの拍子に、ああ地震が遠くから寄せて来るなと感ずる事がある。すると、尻の下に敷いている坐蒲団も、畳も、乃至床板も明らかに震える様に思われる。彼はこれが自分の本来だと信じている。親爺の如きは、神経未熟の野人か、然らずんば己れを偽わる愚者としか代助には受け取れないのである。
地震が好きという人はいまいが、思い出してみれば谷崎潤一郎も大の地震ぎらいで、まるで予言者のように地震が恐いという話を何度も書いていて、ついに関東大震災にあうと、恐ろしいからと関西に逃げてしまう。お蔭で『卍』や『細雪』などの傑作も生まれた。
夏目漱石自身も地震が恐いようで、地震が起きた時自分だけ逃げだして、後で奥さんから叱られたという話もある。
ここではそんな地震ぎらい、臆病さまで代助と云うキャラクターの繊細さとして、「これが自分の本来だ」とまで言わせていることを見ておこう。臆病であることが本来であるとはまた独特な考えで、「豪胆≒古い時代のありかた」「臆病≒現代的なありかた」というやや極端な図式が見えるところ。
内容の多い時間を有する
「三十になって遊民として、のらくらしているのは、如何いかにも不体裁だな」
代助は決してのらくらしているとは思わない。ただ職業の為に汚されない内容の多い時間を有する、上等人種と自分を考えているだけである。親爺がこんな事を云うたびに、実は気の毒になる。親爺の幼稚な頭脳には、かく有意義に月日を利用しつつある結果が、自己の思想情操の上に、結晶して吹き出しているのが、全く映らないのである。
ここは代助が何をもってして「内容の多い時間」と言っているのか分からないところではなかろうか。音楽会や芝居に行くことだけということなら梅子も上等人種に属してしまう。ここまで書かれている部分では代助は大したことは何もしていない。むしろ「子供に調戯ったり、書生と五目並べをしたり、嫂と芝居の評をしたりして帰って来る」のであるから、傍から見ればぶらぶらしている暇人に見える。あるいは何か一つでもきりっとしたところが見えていない。
寺尾は懐から汚ない仮綴じの書物を出した。
「これを訳さなけりゃならないんだ」と云った。代助は依然として黙っていた。
「食うに困らないと思って、そう無精な顔をしなくっても好かろう。もう少し判然としてくれ。此方は生死の戦だ」と云って、寺尾は小形の本を、とんとんと椅子の角で二返敲いた。
「何時までに」
寺尾は、書物の頁ページをさらさらと繰って見せたが、断然たる調子で、
「二週間」と答えた後で、「どうでもこうでも、それまでに片付なけりゃ、食えないんだから仕方がない」と説明した。
「偉い勢だね」と代助は冷かした。
「だから、本郷からわざわざ遣って来たんだ。なに、金は借りなくても好い。――貸せば猶好いが――それより少し分らない所があるから、相談しようと思って」
「面倒だな。僕は今日は頭が悪くって、そんな事は遣っていられないよ。好いい加減に訳して置けば構わないじゃないか。どうせ原稿料は頁でくれるんだろう」
代助がいささかでも上等人種としての片鱗を見せるのはこの場面だけではなかろうか。友人が翻訳の助けを借りに来る。三十にもなって、つまり大学も卒業して何年も経っているのに、まだ相当の語学力を有しているという設定になるだろうか。この点はやはり人に頼まれて、書斎で日本の活花の歴史を調べる松本恒三に近く、二カ月以上も経っているのに、洋書の三分の二も読めない津田由雄とは遠い。
ただそれでも上等人種と威張るのには足りないだろう。ここは敢えて漱石が代助のまるで中身のない自惚れと高慢を書いているのかどうか判然としないところだ。
身体は丈夫だね
「身体は丈夫だね」
「二三年このかた風邪を引いた事もありません」
「頭も悪い方じゃないだろう。学校の成蹟も可なりだったんじゃないか」
「まあそうです」
ここで代助の体は丈夫なのだということが分かる。しかし『激読漱石』で石原千秋・小森陽一氏は、冒頭の心臓の鼓動を確かめる描写やこんな会話から、
「先生、今朝は心臓の具合はどうですか」
この間から代助の癖を知っているので、幾分か茶化した調子である。
「今日はまだ大丈夫だ」
「何だか明日にも危あやしくなりそうですな。どうも先生みた様に身体を気にしちゃ、――仕舞には本当の病気に取っ付かれるかも知れませんよ」
「もう病気ですよ」
代助は心臓疾患を抱えていたと読んでいなかっただろうか。ここには「本当の病気に取っ付かれるかも知れませんよ」と書かれており、代助が心臓を気にしていることを門野が覗き見をして知っていたということが書かれているだけだ。赤坂の待合のこともあり、心臓の負担から代助は性的不能者だとみることはできないと考えられる。
二三年このかた風邪を引いた事もありません
あるいは三千代が東京にいた時代は、風邪をひくこともあったかもしれない。
卒業すると、すぐ何処かへ行ったじゃないか
「それで遊んでいるのは勿体ない。あの何とか云ったね、そら御前の所へ善く話しに来た男があるだろう。己も一二度逢ったことがある」
「平岡ですか」
「そう平岡。あの人なぞは、あまり出来の可いい方じゃなかったそうだが、卒業すると、すぐ何処かへ行ったじゃないか」
「その代り失敗って、もう帰って来ました」
ここが漱石の分からないところだ。先に述べた多通り、「すると学校を出たての平岡でないから、先方に解らない、かつ都合のわるいことはなるべく云わない様にして置く」を、平岡には銀行以前に職歴があると読むとどうも矛盾するように思える。
学生時代から働いていたとしても「すると学校を出たての平岡でないから」という表現とは合わない。
可能性としてはここには面倒臭いので流した要素があるとして、「すぐにではありません。その前に一つ二つ仕事をしてから関西に行きました」とまでの内容が省略されたと見做すのはさすがに「書かれていないことを読む」誤読になりはすまいか。
まず「声は慥かに三年前分れた時そっくり」とあるので新橋の停車場で平岡を見送ったのは三年前ということになる。この時、平岡は三千代を連れて行ったはずだ。二十七歳で就職とはやや遅い感じもある。
ここは詰めて読んだところで何とも判断がしづらいところだ。
その昔藩の財政が疲弊して
その昔藩の財政が疲弊して、始末が付かなくなった時、整理の任に当った長井は、藩侯に縁故のある町人を二三人呼び集めて、刀を脱いでその前に頭を下げて、彼等に一時の融通を頼んだ事がある。
ここもよく分からないところだ。岩波は得に注を付けないが、そもそも藩とはどういうことか。
代助の父は長井得といって、御維新のとき、戦争に出た経験のある位な老人であるが、今でも至極達者に生きている。役人を已めてから、実業界に這入って、何かかにかしているうちに、自然と金が貯って、この十四五年来は大分の財産家になった。
まずこうあるので、徳川家の家臣で戊辰戦争に参加後、役人となり、実業界に転じて成功したかと思いきや、藩とあり、財政が疲弊とあるので、まずは地方出身者ということになる。ただ小倉とも米沢とも、いや、どの藩ともまず見当がつかない。
そして仮にこの『それから』が1909年、明治四十二年を舞台にして描かれているとすれば、つまり森田草平の『煤煙』が連載されている時空とずれがなく、代助が三十歳だと考えてみると、藩の財政が疲弊して、始末が付かなくなった時、整理の任に当った長井が親爺だとすると、親爺は四十二年前に最低でも成人していたと考えられ、現在では六十二歳以上だという理窟になる。それも藩の財政が疲弊したのが幕末だとしての話であり、二十歳そこそこで整理の任を任されたとしての話である。その両方に二年ほど幅を持たせると、もう親爺は六十六歳になる。当時としてはかなりの爺さんということになる。
あり得ない設定ではないが、ん? と思うところだ。
延金のまま出て来るんです
「御父さんは論語だの、王陽明だのという、金の延金を呑んでいらっしゃるから、そういう事を仰しゃるんでしょう」
「金の延金とは」
代助はしばらく黙っていたが、漸く、
「延金のまま出て来るんです」と云った。長井は、書物癖のある、偏屈な、世慣れない若輩のいいたがる不得要領の警句として、好奇心のあるにも拘かかわらず、取り合う事を敢てしなかった。
岩波はこの「金の延金を呑んで」に注解をつけて、
『論語』や王陽明の思想を絶体の規範として鵜呑みにしていることを皮肉ったもの。
と上品にまとめる。しかし「絶体の規範として」が何処から出て來るのかわからない。
代助に云わせると、親爺の考えは、万事中途半端に、或物を独り勝手に断定してから出立するんだから、毫も根本的の意義を有していない。しかのみならず、今利他本位でやってるかと思うと、何時の間にか利己本位に変っている。言葉だけは滾々として、勿体らしく出るが、要するに端倪すべからざる空談である。
代助は親爺の思想を信頼していない。延金のまま出て来るんです、とは未消化のまま、つまり延べ金が延べ金として、トウモロコシがトウモロコシとして出てくること、
東京に来たなぁって思います😁🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺#アサヒビール本社
— Beni (@Beni45053382) February 1, 2023
ちなみにこの形は、聖火台の炎🔥だそうです💩🤩 pic.twitter.com/bzhQId9rKH
つまり薫香ではなく「うんこ」ということではないのだろうか。
[余談]
夏目漱石・熊本最後の住まい 熊本市が取得へ #FNNプライムオンライン #テレビ熊本 https://t.co/tR2no07tpD
— FNNプライムオンライン (@FNN_News) February 3, 2023
うーん。
وظيفة الأحلام الأكثر شيوعًا لكل دولة، وفقًا لبيانات بحث Google. هل تتفق؟ pic.twitter.com/MuVsPdmjtw
— حول العالم (@OuWrd) February 3, 2023
スズメチャン♪
— ピピピ (@pi_pipi33) February 3, 2023
今日も1日お疲れ様でした
穏やかな夜をお過ごしください😊https://t.co/enf1gpNyx2 pic.twitter.com/jjCopxgRa6
空気銃を手にする統一教会信者たち。こうした経過を捜査当局は1960年代後半から把握していました。メルマガで紹介したのは「統一協会重点対象一覧表」です。日本で実射訓練をしていた証言もあります。 https://t.co/Asqw147snt pic.twitter.com/wqMvl1TI07
— 有田芳生 (@aritayoshifu) February 3, 2023
◉ ◉ pic.twitter.com/q8SyWiib2f
— cats being weird little guys (@weirdlilguys) February 2, 2023
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
