
DABADA SCAT

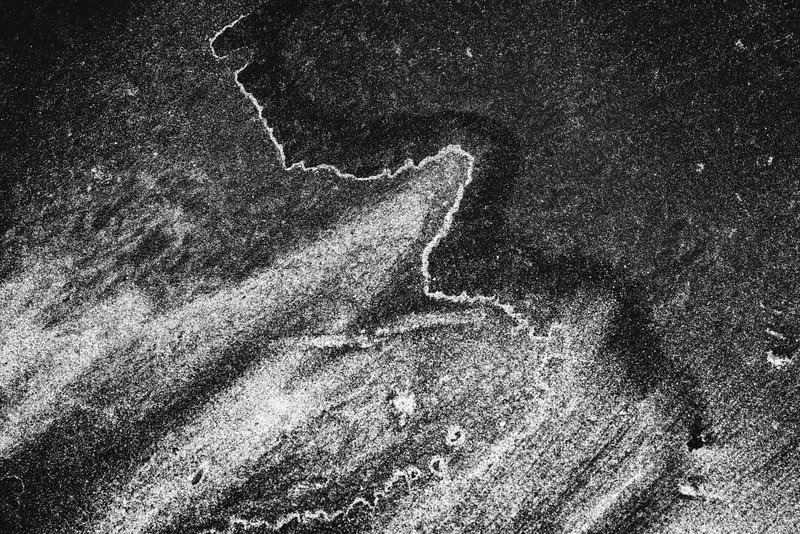










写真を撮っている人で、いわゆる、作家性を持っている人たちを羨ましいと思ってみたり、写真家に作家性なんてあるのか疑問に思ってみたり、僕の場合、人からどんな風にみられているのかは未だによくわからない。写真を撮っている身としてプロかアマチュアか聞かれることもあって、正直それもよくわからない。就職したという話をしたときに、プロじゃなくなったんだね。と言われたときは正直ちょっとムッとした気にもなったが、その人がそう言うならきっと僕は写真のプロフェッショナルではないのかもしれない。会社員かフリーランスかの話で言うなら、個人で仕事を請け負っていた時期もあるが、到底人並みの生活をしていたとは言えず、それがプロと言えるかという話にもなってくるのだが、ひとまず今は毎月給料をもらいながら写真を撮ってみたりしている。
医者や弁護士のように資格がない以上、人からプロといわれたら僕はプロだし、アマチュアだと言われたらアマチュアである。プロでやるならプロとしての自覚がなければ失礼という気もしつつ、それは人が決めることではないだろうか。写真はすでにある何かを記録するだけであって、それを日々生活の中に取り込んでしまっている僕自身も写真そのものも、まさに他力本願。ちなみに、あまり大きい声では言えないが、僕の写真術はきっと高くはない。こう思ってしまうのも、他人が作った手料理はよっぽどレシピが狂わない限り美味しいと感じるのと同じで、他人が撮った写真もよっぽど極端な撮り方をしていない限り、なんでもいいなと感じてしまうからかもしれない。
普段は自分の生活の延長の記録としての写真も撮っている。仕事として撮影を請け負うということもあって、仕事の写真と個人の作品としての写真を分けて考えがちになるが、仕事か作品かという棲み分けはもはや関係ないのかもしれない。お金をもらって人のために撮る写真は労働という意味で、日常の延長であって、日常を切り取ったものを作品とするのであれば、どちらも変わらないはずである。(写真が“作品”と呼べるのかどうかという話はここでは言及しないとして、便宜上、人から頼まれて撮影したもの以外を作品と呼ぶ。写真を撮るという行為そのものに暴力性を孕んでいるわけで、撮ったものを作品と呼ぶことすらおこがましいように思えてしまうので、写真を作品と呼ぶことに対する考察はまた気が向いたら。)作品も仕事も一緒だということを言いたいのではなく、当然、金銭が発生する以上はそれに伴う責任も発生するし、イメージを作り上げるための演出も避けられないが、演出をするということが、もはや写真を仕事にしている時点で、僕にとっては日常になるのかもしれない。
目の前の景色(被写体)と撮り手の関係の間に他者が介入すると、私、クライアント、(景色)被写体といった三者の関係が出来上がる。
【私】ー(関係性)ー【景色 / 被写体】⇒【写真】
【私】ー【依頼主(他者)】ー(関係性)ー【景色 / 被写体】⇒【写真】
いずれにせよ最終的に1枚、ないしは複数枚の写真のために自分がどう動くかということだ。自分の内面性が問われるかどうかという部分に着目すると、カメラを構える動機に他者が介入するかどうか、そこに自分の内面性をどれだけ反映できるのか、撮影をする姿勢やどこまで演出するのか、そして自分以外の他者(クライアントだけではなく、完成物が目に触れる範囲において不特定多数)の視点をどこまで気にするのかという違いはあるものの、撮った完成物に関して、仕事と作品の間に差はほとんどないと言えるのかもしれない。
そもそも個人の内面を写真に写し出すことは難しく、客観か主観という意味において個人の視点という主観性を強く押し出すことなら可能だ。喜怒哀楽といった撮り手の感情を写真で表現することはできない。(撮り手というのは、日本語には写真を撮る人のことを「カメラマン」、「フォトグラファー」、「写真家」と大きく3つの言葉で呼称される。海外の展示に行ったとき、ある人に日本でいうところの商業カメラマンはphotographer、写真家はphoto artistだと言われたことがある。バンドマンや音楽家をアーティストとひとくくりに呼んでしまうのは日本くらいかもしれない。彼らはmusicianである。ちなみに、camera manはテレビ局とかにいる動画のカメラマンのことを指すらしい。トルコだったか、ドバイだったか、中東らへんの自称photographerの方に教えてもらったことなので、本当かどうかわからない。ただ、妙に説得力があったことだけは覚えている。)あくまで撮り手が見る世界の一部を切り取ったもの。例えば、泣いている人の写真を撮って悲しさを表現したと言われても、写っている人の感情であって、それを撮り手に重ねるには「これは私の悲しさでもあります」と言ったような説明書きがないと成立しない上に、そんな説明書きを添えてしまった時点で、鑑賞者が読み取った新しい意味を否定してしまうという意味では駄作になってしまう可能性すらある。写真は記録と考えているが、ある物事の時間を凍結(保存)し、後々に残すためのものに、「作者」という主観性を強く出すためには、撮り手とその対象(風景/被写体)との関係性を明らかにすること。しかし、そのためには、写真は言葉に依存するしかない。目に見えないものは当然写真にも写らないからだ。ある人物の写真を撮ったとして、これが撮り手にとってどんな関係なのかは説明がない限りわからないし、他人である恋人を自分の親族として写すといったこともできるわけで、写真はどうとでもなりえるものだ。そして、この関係性というのは、人対人に限った話ではない。
例えば、写真を撮ろうと海外へ行ったところで、いわゆる写真家としての写真と、観光客としての写真に大差はない。この関係性というのを意識しない限り、極端な話、その国にカチコミに行く覚悟がなければきっといい写真は撮れない。日本人の写真家がアメリカへ行ったとしても、日本人が撮るアメリカの写真になり、アメリカ人が撮るアメリカの写真に近づくことは数年かけても難しい。どこをみても自分が育った環境とは違う景色に目がいってしまい、美しい景色を撮ったところで観光客が撮る写真と何も変わらないからだ。同じ町並みでも、日本人には見えないものがアメリカ人には見えているはずで、その逆も然り。灯台下暗しという言葉もあるように、外の人間にしか見えないものも存在する。見えないものを写真に写すことはできないと言ったが、ここでいう見えないものというのは、視点の違いという意味で、見えてはいるが、意識の中にはないものである。ロバート・フランクの「The Americans」、これはロバート・フランクがスイスから来た部外者としての視点で切り取ったアメリカの写真であるが、人対景色の関係性をこの作品が傑作と言われている理由の1つとして解説することができる。とはいえ、こんな一言で解説できるものではなく、当時のアメリカは第二次世界大戦後の繁栄と栄光の真っ只中で、部外者としてフランクの視点によって、黄金期とされていたアメリカの裏の部分、格差社会や戦後の倦怠感など、アメリカの実像を暴き出してしまったという点において、写真史の中でも重要な意義があるのだ。以前、NOTES Xでも書いたように、戦時中の報道写真やプロパガンダ的な写真から逸脱した作風、つまり、アメリカ人ではない部外者としてのフランクが切り取った風景に、これまでの客観性が重視されていたフォトドキュメンタリーというジャンルに主観性を持ち込んだという意味で大きな影響を与えた。
撮り手(人)と景色(風景)においても、関係性は重要だということ。関係性というと、私とあなた、私と友達、私と家族、私と恋人など連想しがちだが、人対人ではなく、静物であったとしても撮り手と対象となる景色との間にも当然、関係性が生じる。
こんな断定的な文体で書いていくのも多少気が引けるのだが、僕の性格上「〜かもしれない」「〜なんだろうなぁ」みたいにアバウトな感じで書き進めてしまうと、読みにくいし、あくまで僕が色んな人から聞いたこと、どこかで読んだちゃんとした理論の記憶から日記として書いているものだ。プロの執筆家がどんな過程で執筆しているのかなんて知ったことではないし、あくまで僕の勝手な想像として、映画評論なんかは劇場に座って観た一回の上映だけで、書いているのだとしたら、とんでもない記憶力の持ち主でない限り映画の全編を記憶することは難しいし、特定のシーンの描写をいくつも覚えることなんてほぼ不可能ではないだろうか。だから執筆家としての責任を果たせているのかもしれないが、失礼ながら想像と記憶を頼りに書いているのだと仮定して、ここに勝手に書いている日記も僕の記憶の中で改ざんされたものもあるかもしれないし、情報としての正確性は保証できないし、あくまで自分の頭の中を整理するためのものである。バルト曰く、テクストを読み解くことは快楽であって、作者の意図をあぶり出す行為ではない。(ちなみに、この一文だけ覚えているだけであって、小難しい哲学書みたいなものは読んだこともないし、彼の思想すべてを理解しているわけでもない。)撮ったものにいつまでも愛着を持っていては何も生まれない。悪く言えば自分の手は汚さず、他人にすべてを丸投げする。広く浅く手を出す自分にとって唯一長続きしていることが写真というのもなんとなく腑に落ちてしまう。
たくさん写真を見てほしいです。




