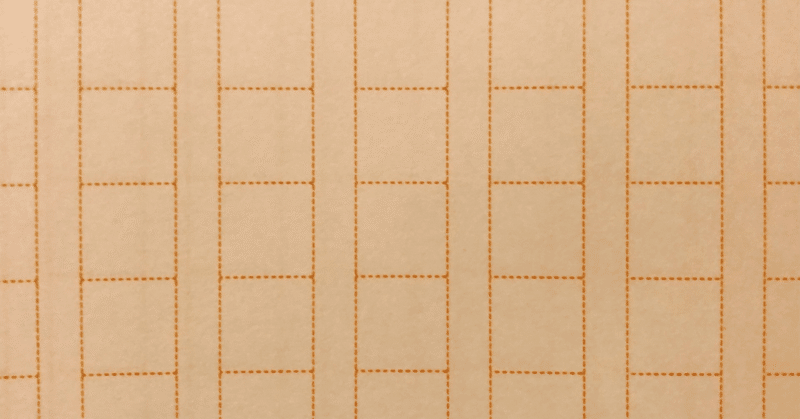
漆刷毛と伝統工芸(寄稿原文)
ある一般向けの冊子に漆刷毛と伝統工芸について寄稿させていただけることになりました。
しかし文字数制限のため伝えきることができなかったのが心残りです。
そこで、noteに全文を載せさせていただくことにしました。
ちょっと長いですが…お付き合いいただけたら嬉しいです🙇♂️
日本各地にはさまざまな伝統工芸や文化があります。そのひとつに漆芸・漆器産業があります。このものづくりで漆を塗る工程で使われる専用の刷毛を漆刷毛(うるしばけ)といい、この漆刷毛を作るのが私の仕事です。
漆刷毛はよくイメージされる刷毛とはちょっと違い、変わった構造をしています。形を例えるならば、ハイチュウです。長方形で、どこを切っても断面には毛が詰まっています。板状になった毛を四方からぐるりと桧板で囲ってあるのです。
使いはじめは少し手間がかかります。黒い毛先が見えますが、これはかたく固まっています。書道の筆なども使う前は固まっていますが、その比ではありません。カチコチです。もちろん、このままでは液体を塗ることなんてできません。どうするかというと…まず固まっている毛をハンマーで叩きほぐすのです。
けっこうガンガンと叩きます。毛をハンマーで叩くなんて、なんだか毛が切れてしまいそうですよね。でもうまくやれば、大丈夫なんです。
根本までしっかに叩きほぐします。毛を固めていた糊漆が粉状になってたくさん出てきますから、それをきれいに洗って完成。やっと使いはじめられます。
しかし使いはじめはまだ少し粉状のゴミが出たりするので、まず下塗りに使っていきます。使っていくうちに落ち着いてきて、毛先もいい感じになってきます。そしたらいよいよ上塗りに使えます。これを塗師さんは"刷毛を育てる"と表現したりするみたいです。私は刷毛を産み、塗師さんは刷毛を育てて使ってくれます。私はできるだけ素直で良い子になるようにと良い素材を吟味して産み、送り出しています。
何百何千と漆器を塗って、刷毛が育っていきます。するとゴミは出なくなってきますが、今度はだんだん毛先が摩耗して塗りづらくなってきます。毛先の寿命です。しかし、買い替える必要はありません。毛の根元でいったん切り落とし、ハイチュウのような断面から毛先をまた三角形に切り出して…と、繰り返し、持ち手が短くなるまで使うことができるのです。持ちにくくなってきたら後部に木をすげればまだ使えます。削ったりすげたりする使い方は鉛筆にも似ていますね。

かたく固まっていて、上から下まで通っている。

ところで、中の毛は一体何の毛を使っているでしょう?実は人間の髪の毛です!もちろん選りすぐりの良質で丈夫な髪の毛のみを使って作ります。そうです、漆は人間の髪の毛で塗られているのです。髪の毛は漆の粘度に対するコシがちょうど良いのです。
漆刷毛自体の歴史は古く、奈良時代の遺跡からもたくさんの、さまざまな姿をした漆刷毛が出土しています。以前この調査に同行させていただいたことがあります。出土した漆刷毛は、今の染色用の刷毛に似た形のものが多かったです。毛の部分は、人間や動物の毛を利用したようなものもあり、植物繊維のようなものもありました。柄は"木簡"を再利用して作ったようなものも見受けられました。これらについてはまだまだ調査の段階ですが、今後さらに面白いことが分かってきそうで興味深いです。

平城宮・京跡出土漆刷毛の構造調査より
http://hdl.handle.net/11177/7899
漆刷毛が今のハイチュウのような構造となって定着したのは江戸時代と言われています。永く使い続けることができ、しかも重要な毛の部分は、他の動物を傷めつけることなく入手しつづけることができる"人間の髪の毛"で作ることがこの頃主流となりました。素晴らしい文化に成長したと思います。人と漆の関係は縄文時代から脈々と続いてきた歴史がありますが、私はこの道具の存在を知ったとき、この道具の誕生によって漆と人との契りがさらに強く結ばれたように感じたのでした!
ちょっとスピリチュアルな思考すぎたかもしれませんね。すみません
漆器自体も、木や土といった身近な素材が組み合わさることでできています。そしてほとんどの作業が、人の手作業によって行われています。人間が自らの体を道具とし、自然の素材を使って作ってきた究極の超循環型生活用品…それが伝統工芸品なのです!うわースピリチュアル
しかし今、この手仕事を続けることがとても難しくなっています。道具や素材が手に入らなくなっているのです。さらにその道具を作るための道具や素材も手に入らなくなっています。職人も、どんどんいなくなっています…。
ひとつ例をあげます。漆刷毛に必要な良質な髪の毛は今や日本ではほとんど手に入りません。今の日本人の髪の毛は食生活やシャンプーなどの影響か、ふわふわでとても細く弱くなってしまっています。良い毛が手に入ったとしても、それらを仕分けする手が足りません。漆刷毛職人は私を含め全国に2件になってしまって、全く作業が追いつかないのです。弊工房では、中国の奥地の方々の髪の毛を、長さごとに仕分けされた状態で輸入して使っています。意外に思われるかもしれませんが、今や輸入人髪のほうが圧倒的に質が良いです。このようにして、伝統工芸はかろうじて形を保っているけれど、その中身はというとツギハギの借り物だらけというのが現実なのです。
しかし、漆刷毛がなくなったら何か困ることがあるでしょうか。塗師さんは漆器が塗れなくて困るかもしれません。でも一般の人々は漆刷毛が無くなっても、漆器が無くなっても、きっと困りませんね。気がつかないかもしれません。代わりになるものなら今の世の中いくらでもあるのですから。
しかし私は、将来の親子の会話を想像するのです。
お父さん:
昔は木という素材を削ってなんでも作っていたんだって。木は地面からどこにでも生えていたらしいよ。
化学塗料ができるまでは、漆という木の樹液を使っていたんだって。
化学繊維ができるまえには、漆を塗るための刷毛や筆には動物や人間の毛を使っていたらしいよ。
子供:
え!毛が生えた動物って何?それに、人間にも毛が生えていたの!?
ちょっと例えが極端すぎましたね。
でも、昔の人からしたら現代の人の会話もこんなふうに聞こえるのかもしれません。人知れず消えていった資源や文化は、きっとたくさんあるのです。そしておそらくこれからも…
昔から続いてきたものづくりや文化は、今はただの古くさい遺物やしきたり、もしくは高級な嗜好品やレトロないいかんじのもの、楽しい伝統行事として認識することが多いかもしれません。機能面はだんだんと手頃な素材や機械でできたものに置き換わっていきました。
便利なくらしのために、身の回りのものがどんどん早く、どんどん新しいものに置き換わっていくのは良いことです。しかし私は、伝統工芸や文化のもつ力も同じくらい重要になっていると感じています。伝統工芸や文化には、人が地に足をつけて生きていく方法が詰まっているからです。作ること、そして使うこと自体が、足元と、そして昔と今とをつないでいることを、私はこの仕事をしながらひしひしと感じるからです。
万物は諸行無常なのは分かっています。無くなることを止められないものもあります。でも将来、人々が道に迷ってしまったときに行き着く場所が宇宙のかなたではなく、この土地であってほしい。これ以上、この土地で生きていく知恵を無くしてしまわないように、私たち職人は資源と向き合い、そして伝えることを忘れず、これからもものづくりを続けていきます。
皆さんが漆器を使うとき、それを作った職人さんや使われた素材たち、そしてたまに道具のことなんかも思い出していただけたら嬉しいです。普段表からは見えない仕事だけれど、その存在をなんとなくでも覚えていていただけたら、きっと、突然消えたりすることはありませんから。
いつも使っている身の回りのものに、時々思いを馳せてみてください。あなたが次の世代にも受け継ぎたいものは、なんでしょうか。そのためにできることは、なんでしょうか。
と、偉そうなことを書いてきましたが、実際は私も日々のことに追われて、何かできているとは言い難いです。でも、現状を良くする動きを少しずつしていきたいです。頑張ります。この場を借りて、有言実行!
このたびは、漆刷毛と伝統工芸についてご紹介する機会をいただき、誠にありがとうございました。
2023年2月 刷毛や狐 内海志保
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
