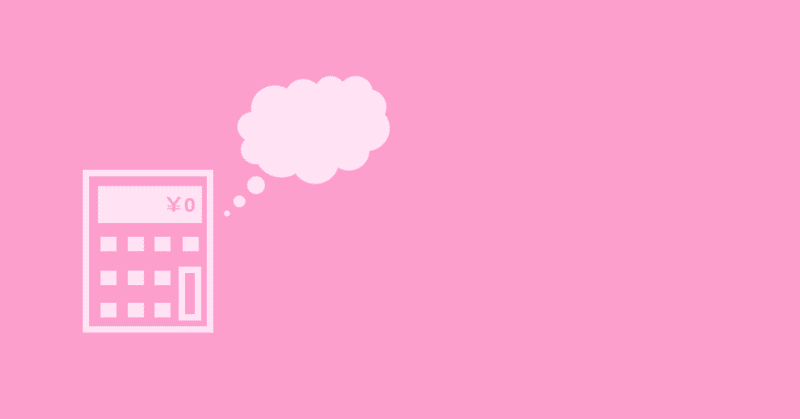
モノの価値そのものと、人が持つ価値
Yahoo!ニュースで中古CDの買取が終了するという記事を拝見いたしました。
遷移先 Yahoo!ニュース
音楽の聴取は、ライブ演奏、レコードから便利なCD,MDに移行し、サブスクリプションサービス、ライブ演奏、またレーコードが人気と様々な変遷を遂げています。
時代の背景もあり、演奏の価値そのものは変わりませんが、聴取する利便性、希少性の追求を繰り返していると感じます。
利便性を追求すると大量生産され、巷にあふれ手に取りやすくなりますが、徐々に希少性の追求、さらに利便性へ回帰となります。
そこで考えたいのが、モノの価値はだれが決めるのでしょうか。
大量生産にせよ、希少価値があるものにせよ、一定のマーケットがあるため、需要と供給から価格という数値が決定されます。
これだけものがあふれると、もうたくさんいらないよ というミニマリストも生まれ、マーケットがあり取引するものと、一定のマーケットがなくても個人が価値を感じて保有しているものと2つに分かれると思います。
マーケットがあるものは、金銭的な対価を得られますが、一定のマーケットはないが、個人が価値を感じているものについては、価値はつけられないはずです。
価値がつけられないということは、定量化できないため、無限大の価値を持つということにもなります。
数値で測定するか、心で測定するか
資本主義がすすみ、格差が拡大している世界であるといえますが、
価値を数値化したにほかならないと考えられます。
一方、価値を数値化していなかった時代の人はそれはそれで幸せだったのではないでしょうか。
数値化できないのに、幸せであるということは、個人の中に価値基準が備わっているからそれで満足である ということになります。
数値化を極大化することも必要でしょうが、ここは一つ自分の価値を信じてものや事を所有、体験するという価値磨きをしてみてはいかがでしょうか。
自分の決めた価値なので、それで十分という感覚がでてくると思います。
数値化という市場に対して、自分基準の価値を定めればいつまでも幸せを感じられる良い状態が続くと考えられます。
是非一度自分基準の価値で生きてみてはいかがでしょうか というお話でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
