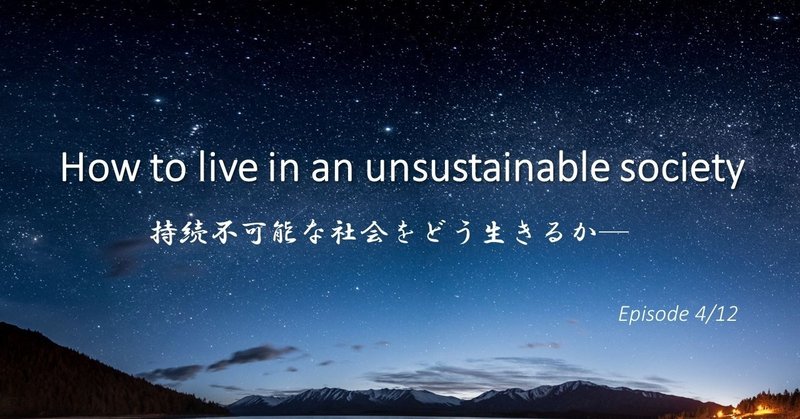
No.4|なぜ環境破壊に対する感じ方がこれほど冷淡になったのか?
前章で、"世界は自然の恩恵で回っているにも関わらず、それが危機に瀕している"ことを紹介した。しかし、自然保護の大切さをいくら力説されたとしても、どうしても違和感が拭えない方もいるだろう。自然破壊と言っても、まるで遠い月の国のお話のようで、頭では理解できたとしても腹落ちしない。その背景には何があるのだろうか?
①自然からの断絶
一つ目の理由は、私たちの生活の大部分が自然から断絶されてしまったことにより、自然との距離が離れてしまったことだ。
今では家から一歩も出なくても、あらゆるモノが配達されて快適に生活できる。またスーパーに買いに行けば大抵の食材が手に入る。けれどもそこに陳列されているのは"生命"ではなく、単なる"モノ"に過ぎない。

食品はきれいに加工されており、そこに"死"を感じる要素はどこにもない。それが元々生き物であり、どのように育ち、どのように屠殺され、どのように流通したのかを消費者が知ることはない。かつては、食べることを通じてつながっていた他の生物との関係性は断絶され、命を奪って生きるという罪悪感は希薄化されてしまった。ただ美味しさ、値段、安全性だけが広告によってことさら強調されている。
②報道のダイナミックさ
2つ目の理由は、テレビやニュースで描写される自然の光景があまりにダイナミックであることだ。過酷な報道競争は、演出をより過剰かつダイナミックに仕向けていき、受け手の感覚を麻痺させ始めている。いかに重大なニュースであったとしても、次第に飽きられてしまい放送されなくなる。ニュースはファストフードのように消化され、正しさよりも話題性や刺激性が求められている。それによって自然に対する見方が歪められ、自然に関する繊細な感受性が失われようとしている。

③自然欠乏障害
3つ目の理由は、日本では経済成長が優先され、都市における自然の整備はないがしろにされてきたことだ。都市にはマンションが建ち並び、庭のない住宅が少なくない。ビル群に囲まれた中、わずかに立てられた街路樹と、砂利で覆われた公園ばかりが存在する。身近に自然はなく、休日になると多くの人が郊外の行楽地へと詰めかける。けれども、そこにあるのは大自然が与える安らぎや静寂さとはほど遠い。人ごみの中を切り分けながら、束の間の非日常的を体験するばかりである。
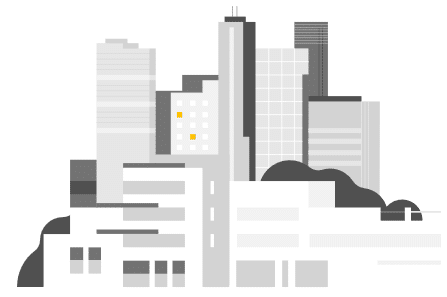
子供の感性が発達する時期に身近に自然を体験できないことは、脳の発達に大きな影響をもたらしてしまう。大人になってから絶対音感を身につけるのが極めて難しいように、然るべきタイミングを逃してしまったら、自然を感覚的に捉えることができなくなってしまう。
日本語には雨を表す言葉が400種類以上もある(引用元)。日本人には虫の「声」が聞こえ、外国人には雑音としか聞こえないという研究例もある(引用元)。そういった文化の継承が今途絶えようとしている。
こうしたことが原因で、私たちと自然との距離が随分と離れてしまった。自然の捉え方は理屈ではなく、感覚的なものだ。自然を"友"と見るか、"モノ"と見るかという捉え方には、埋められない大きな隔たりがある。
どちらが正解かは絶対的な答えは出せないのかもしれない。そう認識する人にとって、その認識こそが唯一無二の世界観だからだ。ただ、後者の生き方は、あまりに孤独な生き方のように感じてしまう。
何も知らなければ、世界はひどく退屈で、全部モノトーンに見えてしまう。けれども路傍の草や花の名前を知った時、虫や鳥の鳴き声が区別できるようになった時、世界はそっと色づき始める。一コマの世界にも無数の意味があふれていることに気がつき始める。
自然は子供に自立心や集中力、自己肯定感を育んでくれる。自然が豊かであるほど得られるものも大きかろう。ますます都市に住む子供が増える中、ついそんなことを心配してしまう。
機械は自然の代わりになりえない。自然なしでは人は生きられない。それにも関わらず、自然はますます破壊されていて、心理的な距離も開こうとしている。都市に人は"住める"けれど、その代償はあまりに高くついている。
(参考文献)「あなたの子どもには自然が足りない」(2006)
▼マガジン(全12話)
twitter:kiki@kiki_project
note:kiki(持続不可能な社会への警鐘者)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
