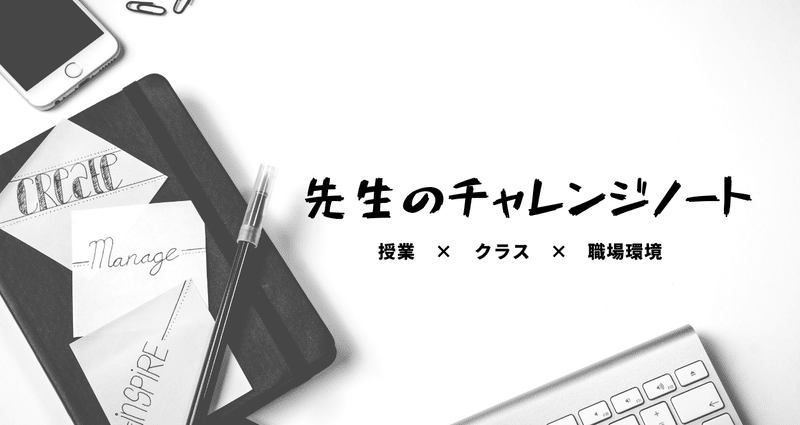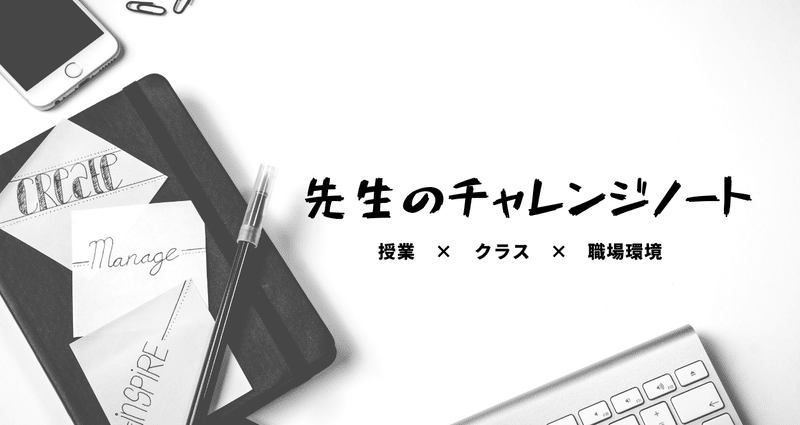教員が、学校教育について悩んでいること
最近、復職したら「仕事に対する課題感」が頭の中で再燃してきました。
モヤモヤが続く時は、まず「書き出す」という行動が大事!と休職中に学びましたので、早速実践です。
ということで今回は、わたしが仕事としている学校や教育について考えていることを書き出してみました。
読書感想文を生かし「ゼロ秒思考」でまとめたので抽象的なものもありますが、もし似たような気持ちの方がいたら嬉しいです。
(「ゼロ秒思考」のまとめはこちら)
一斉講義授業の限界を感じる○授業について来られない子ども、