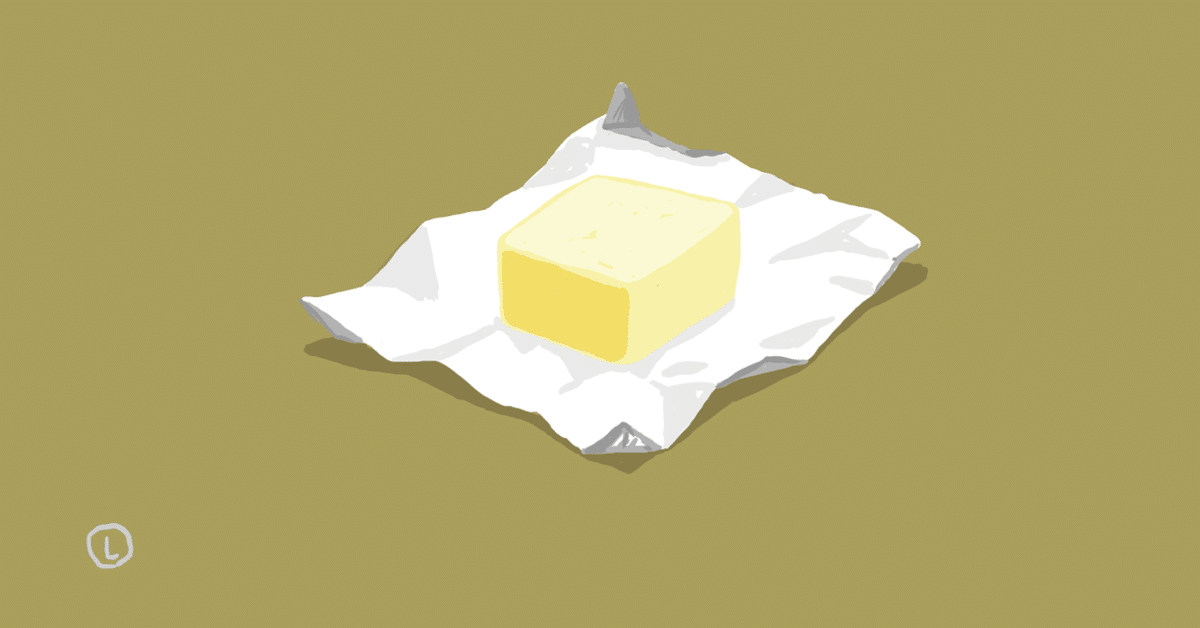
[ちょっとした物語]バターの香り
まだ昼前だというのに、腹が減ってきた。そんな時にキッチンを見回すと、たぶんあの人の残したパンケーキミックスを見つけた。
ああ、なんとも甘美な誘惑だろう。すぐさま、冷蔵庫の扉を開く。この黒い冷蔵庫の正反対にあるような牛乳を見つける。まだ半分はあるだろう。その揺れる体積を腕に感じながら取り出して、卵をひとつもう片方の手に取り、キッチンへ戻る。
ボウルにすぐさま、少しきしむような膨らみのある袋から、粉を入れ、牛乳と卵を入れて、かき混ぜる。ゆっくりとゆっくりと。その重みある攪拌は、僕の心も一緒に練るような、おだやかな気持ちにしてくれた。
フライパンに広げる頃には、なんだか腹も静かにそれを見守るように、落ち着きはじめていた。薄く油を塗った上に流し込んだ生地は、しばらくするとぷつぷつと熱が入っていく。その様を見ていたら、ふとバターがあったか気になり始めた。しかし、なぜだか冷蔵庫へ足を運ぶこともせず、ゆっくり膨らむそれを見守る。
「おい」
急な声におどろいた。声の方へ目をやると、一匹の猫が窓辺に居座り、こちらを見ている。なんだお前か。
「バターじゃないとおいしくにゃいだろ」
それは主観だ。あんたの完全な主観だ。しかし、その意見には同感だ。油を敷く時点で、なぜ僕はバターという選択肢を思いつけなかったのだろう。
「甘い匂いがするのに、バターの香りがないとはなんとも君は怠慢な人間だ」
おいおい、勘弁してくれよ。なにをもってそんな暴言を吐くのか。食べるのは僕だ。君ではない。表面はきれいな茶色になってきた。そろそろいい加減だ。
「でもさ、たまにはバターがなくてもいいかもにゃ」
黙ってくれないか。ほら、腹が声をあげてきた。白い皿に乗せると、たちまちいい香りが漂ってきた。もうがまんはいらない。早速食べてやろう。
「おいおい、本当にバターはでてこにゃいのかよ」
まだ君は窓辺でつぶやいている。フォークとナイフを両手に持ちながら、僕は最後に今一度、冷蔵庫の扉を開く。やっぱりない。さて、バターはないが、シロップはある。それでもういいではないか。そう思いながら、テーブルにつく。フォークとナイフを持ち、湯気がほのかに立ち上るその生地に目をやる。
「バター切れか、がっかりだ」
窓辺のやつは恨み節でそっぽを向いている。そもそもおまえにやる分はないぞ。そう心で思いながら、フォークを入れようとした。すると、部屋の扉が開いた。
「ただいま。あ、なんか甘い匂いがすると思ったら」
君が帰ってきた。なんとも間の悪い帰宅だ。
「バターなかったでしょ? 買ってきたよ」
窓辺を見ると、やつは奥の塀の上に移動していた。そしてにやりと微笑んで、軽やかに去っていった。まるで「救われたな」とでも言いたいかのように。
ため息とほほえみは、いつでも共存し、僕らは絶えず繰り返す。どうでもいいことでさえも、バターの香りのように誰かを惹きつけ、巻き込んでいくのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
