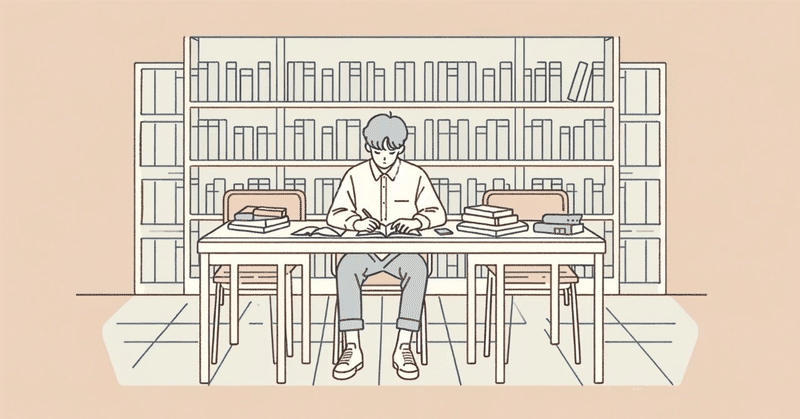
文章解説1 ユルスナール「とどめの一撃」 付帯情報の入れ方
(前略)エリック・フォン・ローモンは、ピサ駅の軽食堂で、自分をドイツに連れ戻してくれるはずの列車を待っていた。
「とどめの一撃」冒頭の文章です。
さらっと読むと情報量の多い文章だなーとしか思わないかもしれませんが、ここに、わりと使いやすくて効果的な描写のテクニックが潜んでいます。
それは、
自分をドイツに連れ戻してくれるはずの列車を待っていた。
というところ。
簡潔さを目指すなら、
エリック・フォン・ローモンは、ピサ駅の軽食堂で列車を待っていた。
でいいはずです。
こちらの方が読みやすいし、特に何かが不足している感じもしません。
ただ、もし書き手ができるだけ冒頭の早い段階で主人公がドイツ出身であることを読者に伝えたいと考えていたらどうでしょう?
ここに<主人公はドイツ出身>という情報を足さないといけなくなります。
そうすると、
・主人公は軽食堂で列車を待っている
・主人公はドイツ出身である
という情報を別々の文章で描写することになります。
そこで改めて元の文章を見てみましょう。
エリック・フォン・ローモンは、ピサ駅の軽食堂で、自分をドイツに連れ戻してくれるはずの列車を待っていた。
【列車】に【自分をドイツに連れ戻してくれるはずの】という付帯情報を挿入することで、主人公がドイツ出身であるということを伝えられます。
これが【連れて行ってくれる】だと、ドイツ出身だとは言い切れなくなります。
【連れ戻してくれる】と書くことで彼がドイツ出身であるという描写が成立します。
また【はず】にも意味があります。
本作は第一次世界大戦時のヨーロッパが舞台です。
本人も戦争帰りで負傷しています。
イタリアからドイツに列車で向かうことすら確実とは言えないはずです。
だから【はず】なのです。
もし
エリック・フォン・ローモンは、ピサ駅の軽食堂で、自分をドイツに連れ戻してくれる列車を待っていた。
としたら、それだけで世界観が早くも破綻してしまうことを作者は理解していたのでしょう。
たったこれだけの描写ですが、主人公の出身や、時代の空気感などなど、必要な情報が的確につまっていて、ほとほと感心させられます。
応用
ではこれを応用してみましょう。
例えば、主人公Aが東京から故郷の福岡に帰省するとします。
しかし、当日は台風が接近しており、運行に不安があるとしましょう。
Aは東京駅の喫茶店で、自分を福岡に連れ戻してくれるはずの新幹線を待っていた。
そのままユルスナールの文章を当てはめるだけで、
・Aの故郷は福岡
・これから故郷に帰省するらしい
・そこに何やら不穏な空気が漂っている
という情報を自然に読者に与えることができます。
ただ、読み手の理解力が必要ではありますが…
ダメな例
では、一見簡潔に見えて実はそうでもない文章にしてみましょう。
Aは東京駅の喫茶店で新幹線を待っていた。これから故郷の福岡に帰省するところだ。ただ、おりからの台風の予報が彼をやや不安にさせていた。
最初の文章を簡潔にしたことで、<福岡が故郷である><何か不穏な空気>をさらに足さないといけなくなり、結果全体で見るとちょっと説明的で不格好な文章になってしまっています。
なのでやはり【新幹線】というガジェットに対し、<福岡が故郷である><何か不穏な空気>という情報を足して表現した方が簡潔であると思えます。
文章を書く人は参考にしてみてください。
