慶應大学助教 木下衆先生インタビュー(前編・2)
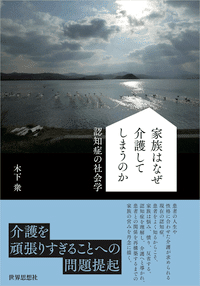
歴史的に制度の狭間に落ちていた認知症
杉本 私は1997年くらいに社会福祉士の資格を通信教育とスクーリングで取ったんです。そのときに一人で学び続けるのはなかなか大変だということで、福祉の現場で働いていた人たち数人と勉強会という形で一緒に学んで、その中に施設のソーシャルワーカーだった人がいたのですが、試験が終わった後で、おそらく仕事の斡旋の意味合いで施設を見学させていただいたことがあります。その時はまず最初に普通の施設を見学して、それから鍵を持たれて、そこは認知症のかたの専門棟みたいになっていて、施錠を解くとたくさんの人が入居していて、正直、生活の質から行くとかなりひどいというか、居住環境が悪い空間で結構びっくりしたんですよ。いわゆる精神病のような症状を持っている人も多そうで。そして最後にのちのちグループホームと言われる形で成立する新しい居宅介護施設のような広い普通の民家みたいなところに何人かの落ち着いた人が住われていて、そこでお茶をいただいて。かなりシュールな1日だったなあと思ったのが98年頭の冬でした。劣悪な処遇のところからすごく先進的なところまで一挙に見学させてもらった。その頃すでに介護保険が始まる話があったんですが、あれから20数年経ち、在宅介護のような形で中核にはケアマネージャーがいて、例えば私の訴えを受けて色々なサービスを繋いでくれている。そう考えるとやはり90年代くらいまで、まだ認知症の人たちの処遇というのは一般化されていなかったんだなという印象があります。
木下 それこそ大熊一夫さんとかが描かれていたような*『ルポ・老人病棟』とか、こういうところで描かれていた本当にその姿だろうなと思うんですよね。
杉本 はい。流石にそこまではひどくないかもしれませんが(苦笑)
木下 でも70年代当時の精神科病棟のイメージの悪さたるや、みたいな話があったりして、ただこれも教科書的な話ですけれども、一方でまた、老人病院しか預け先がないみたいなことはありました。まだ80年代から90年代にかけてですね。認知症の人といったら、大半が治らないわけですよね。その「治らない」病気を抱えた人は一体、どこでどうやって暮らしたら良いのか?ということがこの国の中でまだ道筋がついていなかった。治る病気である人は病院に行ってください。高齢者だったらご家庭で、みたいな話なんですけれども。でも治らない病気を抱えた高齢者が一体どこで暮らしたらいいのか。しかも当時は認知症というものの理解も「ただの呆けなんじゃないの?」みたいな状況でしたから、非常に曖昧な病を抱えてある種、制度の狭間に落ちていくようなものだったんですね。
私なども授業で80年代の写真と2010年代の介護の写真を並べて、80年代の写真とかだといわゆる身体拘束されてるみたいなのが典型なわけですね。それを出して、例えば2010年代なんかの写真だと読み聞かせのボランティアをやっている人の写真などを出したりすることがあるんです。おおむね似たような年格好のかたの写真なんですよね。その時にぼくがよく言うのは例えば片方の人が30年前にタイムトラベルしたら多分この人縛られているんだよね、と。片方の人が30年後にタイムトラベルしていたら、おんなじように生き生きとして、縛られずにいるかもしれないんだよね、って。何が違うんだろう?と言ったら、脳の断面はもしかしたら一緒かもしれない。でもあまりにも待遇が違う。何が違うんだろうというと、結局は社会のありかた、制度のありかたであるし、病いに関する知識なんだと。たぶん見学されたようなひどい状況というものは今は杉本さんの周りにはほとんど見られないと思います。
杉本 そうです。おそらくないですね。その意味ではすごい進歩ですね。ですから「認知症の人と家族の会」などの人たちが社会に向けて発信したこと、そういった一連の社会的な語りみたいなものが制度そのものをそれに見合った形に変えていったということはあるんでしょうね。
木下 そうですね。私はよく講義で紹介するんですけど、『認知症の人の歴史を学びませんか』(中央法規出版:2011)という、この本は非常に素晴らしい本だと思うんですが。訪問介護の先駆けになった宮崎和歌子さんという方が書かれた本です。この中でも当時の縛られていたような高齢者の扱いが、やっぱりこの時代の「あたりまえ」とされてしまっていたことに警鐘を鳴らされているわけですよね。それは「仕方ない」「これがあるべきケアなんだ」とされてきた。当たり前のものとされてきた。宮崎さんは到達点、といういい方もされていたんですけれども、私たちはこの20年くらいである種の到達点に至ったと思うんですね。
杉本 うん、うん。
木下 そこには先ほどおっしゃっていたような認知症を抱えた人や、認知症の家族の自助グループの発言もありましたし、専門職の運動もありました。さらに近年はいわゆる当事者の方がどんどん積極的に発言していくということもあったりする。それがある種の円環をなすというか、相互に影響しあう形で政策や自治体レベルのいろんなものを動かしていくということが起こってきたと思います。
トライ・アンド・エラーを試みるのが新しい認知症介護
木下 先ほど制度に関連した話を社会学の観点から申し上げたわけですけれども、制度面だけでなく、その認知症ケアに関する知識というか、「理念のあり方」ですね。それこそ身体拘束しなくてい良いんだ、あるいはこの人たちは思いが何か残っているんだと。例えば小澤さんの本の中にも出てきますけど、「物を盗ってしまう」ということ一つにも何かその人のライフヒストリーに根ざしている思いがあるかもしれない。そこを汲み取ってあげようと。例えば、ある人が何かたくさんのものをコレクションしていた。そのコレクションを奪われて施設に入ってしまったら、それが無くなってしまったという「喪失感」につながるかもしれない。仕事一筋に生きて来た人が仕事を奪われているとしたら、ものすごく不安に駆られるかもしれない。それが症状として現れているかもしれない。だからその人の「人生を読み込んでいこう」ということになっていくわけですね。で、それを踏まえてケアを提供すれば良い結果が生まれるかもしれないということ。例えばそれは杉本さんもそうだと思うんですけど、介護している側はいちいちお母さんの脳を計測しているわけではないと思うんですよね、当然ながら(笑)
杉本 はい。
木下 そうではなくて、その人の日常生活を観察し、その人の生きてきた今までの人生と照らし合わせつつ、ある種のストーリーを組み立てながらやってみる。場合によってはトライしてみたけど、エラーがあればまた修正を試みてということを繰り返していく。いろんな状況の中で、これがいいんじゃないかということをやってみて、エラーしたら修正してまたトライしてみたいなことを繰り返していく。そうやって手間をかけていくことで、認知症の人たちはその能力であるとか、その人らしさというものを発見できるんだということ。そういう理解が80年代以降起こってきて、特にこの20年くらいで定着したと言っていいと思うんです。その成果は80年代とかの細々とした草の根の運動があって、確実にそうやって社会は変わってきたことは認知症ケアの分野からは言えると思います。
杉本 当時は老人ボケと言われて、それは看ていた人に取ってみると徒手空拳の中で認知症の症状、例えば「物盗られ妄想」とか、「弄便(ろうべん)」とか、「徘徊(はいかい)」とか、苦労の連続の中で厳しく当たったり、きつく言わざるを得なかった。その時代から比べると、いろんな人が関わり、いろんな職種の人が手伝ってくれる中で、やっぱり家族が一手に引き受けなくなったことによって、いろんな意味で社会的問題としての認知症のネガティヴな印象というものは減ってきている感じがしますね。
それでも戸惑いは残る
木下 ただ一方でそうやって社会の問題として位置付けられてきていたり、進歩はしていっても、やっぱり「戸惑いは残る」というのは現実だと思うんですよね。僕自身が本の中で書きたかったのは結構そういうところであって。前後するんですけども、「社会学ってどういう学問ですか」という問いはいろんな答えかたがあるんですけども、僕自身は「社会規範を研究する学問です」という言い方をするようにしています。つまり法律でこうしなさいとか、制度でこうしなさいとか決まっているわけではないのに、何がこの社会ですべきものとされているか、誰が何に対してそうすべきとされているか。それを研究するのが社会学においては大きなテーマだろうと私自身は考えています。そう考えると介護という分野は「べき論」というか、規範に満ち満ちた世界だと思うんですよね。80年代だって別に「家族が介護しなさい」なんていう法律があったわけじゃない。でも例えば認知症の人を支える制度がない。病気を抱えた高齢者を支えるような制度がないことによって結局は「家族がすべきだろう」というふうに(家族が)利用されていく。今それに比べると例えば介護保険制度ができて社会の手も借りられるようになってきて、外部化し、専門職に委ねる。あるいは身体的ケアに関しては全部お任せしますということもやろうと思ったらやれる。にもかかわらず、杉本さんが冒頭おっしゃったと思うんですけど、やっぱり「戸惑い」が残ると思うんですよね。例えば80年代には認知症について知識がなく、暴言、弄便、徘徊なんかに対して、「コラ!」と叱りつけていた。それに比べて今の人も例えば認知症について学び、暴言や弄便や徘徊があるということを学んだからといって、じゃあ「コラ!」と言わないかというと、言っちゃうと思うんですよね。
杉本 本当ですね。
木下 勉強していても、症状に出会うと、「おかしい」と戸惑うわけです。家にいるのに「家に帰る」とか言ってどっか行っちゃうとか。そこでやっぱり「コラ!」って言ったり、場合によったら無理矢理にでも連れ戻したりといったことをやる。そうすると「いや、この人のやってること、背景には意味があって」ということは、学べば学ぶほど逆に家族が罪悪感を覚えることってあるわけですよね。「なんでこの人の思いに沿ってあげられないんだろう」と。ぼく、以前お話を伺うなかで、こう言った人がいたんです。お母さんが認知症でガスの火を使ってしまう。そこで母にわからないところにある元栓を閉めて火がつかないようにした。そのかたはすごく罪悪感を抱えておられて、要はお母さんの思いをちゃんと汲めなかったんじゃないかと。そのお母さんが火を使おうとすることには何か意味があったはずで、それを汲まずにいわば対処療法的に元栓を閉める、使えなくするということは、虐待じゃないかと思って悩むことがあると。そう話されたかたがいたんです。ある種いろんな知識を得て認知症の症状に対するメカニズムを得たら、罪悪感を覚えなくなるかというと、そんなことはない。罪悪感という言い方よりも、むしろ「戸惑い」。その表現がより適切かもしれません。確かに進歩したと思うんです。いろんな意味で認知症ケアに対する制度であれ、理念であれ。でもだからこそ、やっぱり悩むということがすごくあるんだろうなと思うんですね。
杉本 そこはやっぱり逆説的なんだと思うんです。知識を得て相手が変わり、学んで育ってお互いに成長するというポジティヴな関係性になれるのならいいんですが、やはり認知症の人たちはどうしても下り坂の人たちなわけですから。一方的に介護する側が学びを深めれば深めるほど、理性を保ちつつ相手の感情の深さの中にまで降りるというのはやはり理想的すぎて難しいですよ。そうすると当然のことながら自分はそこまでの理解はできないという限界があって、そこは自分の中で「ここまでしかできないんだ」というある種の諦めを持たないと、こちらの方も燃え尽きてしまう。そういうことはあると思うんですよね。ですから、僕はなるべくそう考えたいと思っているんです。ある種、共同の深みにハマってしまうと介護者になれなくなってしまうと思うので、家族はコーディネーター的にやるのが理想的なんだろうなと思うんですよ。感情レベルで一緒に降りようと思ったら、そこにどうしても入り込めない落差が生じてしまう。
木下 先ほどおっしゃっていた片方が学んでも認知症の人が学ぶわけじゃないというのはすごく大切なポイントというか、つまり例えばこっちがこれだけ勉強したんだからあなたも勉強してよになったら、それはもう介護でもなんでもないですよね。相手は言わば患っていて、いろんなことが低下していく。症状が軽度なかたはもちろん、重度のかたでも、進行していく恐怖であるとか、様々なことができなくなる恐怖は同様にあるだろう。ですから、ご本人が一番不安を抱えてかつ、苦しい状態にある。そういうふうに認識した時に周囲の人は学ぶんだけれども、こちら側が学んでも、その知識はそのまま何か反映できるのか?そこはすごくしんどいことですよね。ご家族もまた、本当にいろんなことを悩むというか。すごく辛いところだと思うんですよね。で、一方で「入り込めない落差」ということをおっしゃったと思うんですけども、家族と言ったって当然他人なわけじゃないですか。その親のことを全部知ってるわけじゃないし、本の中でも書きましたけど、何か働きかけようとすればするほど、「果たしてこの人のことを私は知っていたのだろうか?」みたいなことで悩まざるを得なくなる。この国は家族規範の強い国だとされますから、家族だったらなんでも知ってて当たり前でしょ?というような期待を持ってしまっていたりもする。「そんなことあるわけないよね」という限界に、この認知症という状態で“ドン“と直面せざるを得ない。
だから「この人は一体何に困っているんだろう?わからない」って。そこである種の落差を感じる時のしんどさ。それでもなお働きかけ続けないといけないしんどさみたいなものも、あるだろうなと思うんです。さっきおっしゃっていた割と今落ち着いているんだけれども、軽度から始まっていって、徐々に進行していってという話をされたと思うんですけども、でも例えば認知症が軽度の時に楽だったか?と言ったら全然そんなことはないと思うんですよね。
杉本 そうですね。本当です。
木下 家族会なんかでも軽度の時の方がかえって大変だったみたいなことはよく言われることがあって(笑)。要はご本人の身体はまだ動くし、口も達者だったりするし、ある種の自発的なコミュニケーションがたくさん取れたりする。そうするとかえって暴言であるとか、徘徊であるとか、いろんなことが出てきてしまって介護家族は困ってしまう。ターミナルケアをご自宅でやったという知り合いのかたもいるんですけども、その方がよく冗談めかして「いやあ、重度になったら楽だよ」って良く言ってたんですよ(笑)。でもそれはどういう文脈かというと、軽度でしんどいっていうのは、何か自分はダメなんじゃないかってお気持ちを持つ介護家族がいたりするからなんですよね。その時に「いやあ軽度の時の方がかえって大変なんだよ」って励ましていた。例えば介護認定とかしたら確かに軽いと出るかもしれない。でもだからといって家族や介護者の負担が軽いかと言ったら、全然そんなことはない。もちろん重度になったら楽かと言ったらそれも全然そんなことはないわけですが。ただ、そこの大変さのねじれというか、介護家族の抱える悩みの複雑さ。それが今起こっていることだと思います。介護の進歩は進歩だけれども、勉強しても結局戸惑わざるを得ないこと。そのことが介護には良く見られると思います。
(以下、後編に続く)
*『ルポ・老人病棟』-著者、大熊一夫はアル中患者になりすまして精神病院に潜入、『ルポ・精神病棟』を著し衝撃を与えた。その後老人問題に取り組み、1990年台前半、神奈川県内の“標準的”な老人病院を例に、老人病棟がいかにひどい状況にあるかに鋭いメスを入れた。福祉先進国、北欧諸国などと比べて日本の老人をとりまく環境がいかに大きく遅れているか、高齢化社会に入った日本の老人福祉の飛躍的向上を訴えた画期的なルポ。
よろしければサポートお願いします。サポート費はクリエイターの活動費として活用させていただきます!
