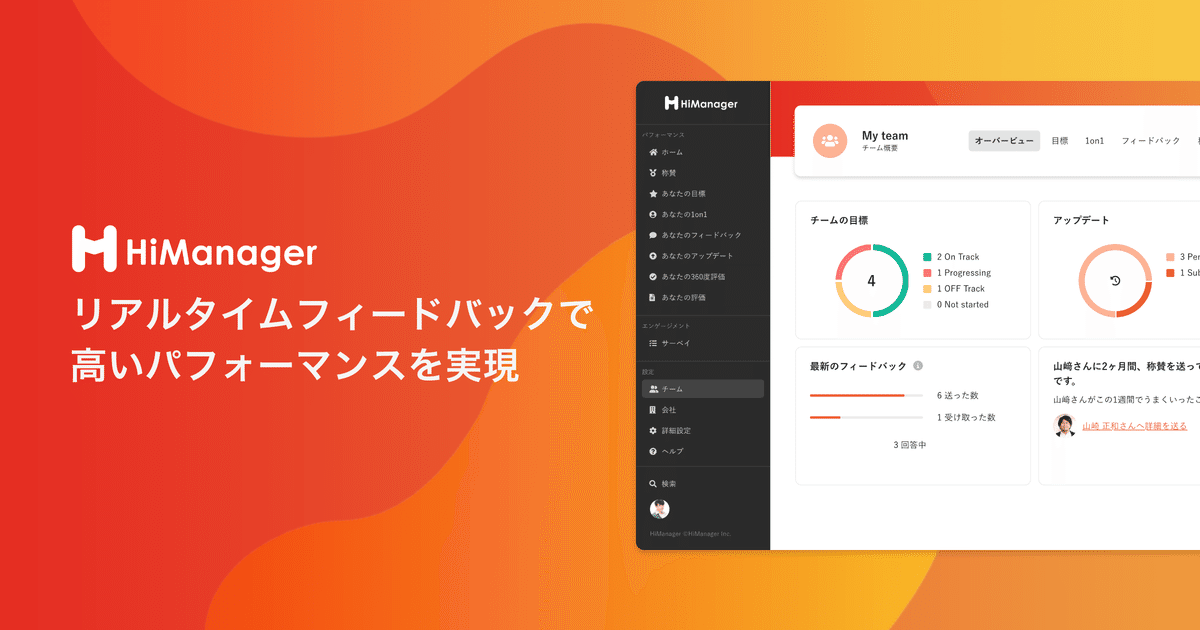人事部がデータを用いた戦略部門になるための取り組み
今回ご登壇頂いたのは、株式会社メルカリでHR OperationsのManagerを務めている岩田翔平さんです。
岩田さんは、前職のエン・ジャパン株式会社で転職サイトのプロダクトマネージャーを従事された後、株式会社メルカリに転職され、現在は人事システム導入やデータ活用強化をご担当されています。
今回は、岩田さんのご担当されているお仕事について、「データを用いた戦略部門の取り組み」をテーマにお話頂きます。
※本記事は、2021年10月14日に開催されたHR Millennial Lounge#13」のイベントレポートとなります。(テーマは「科学とデータが変えるHRとチームの未来」になります)
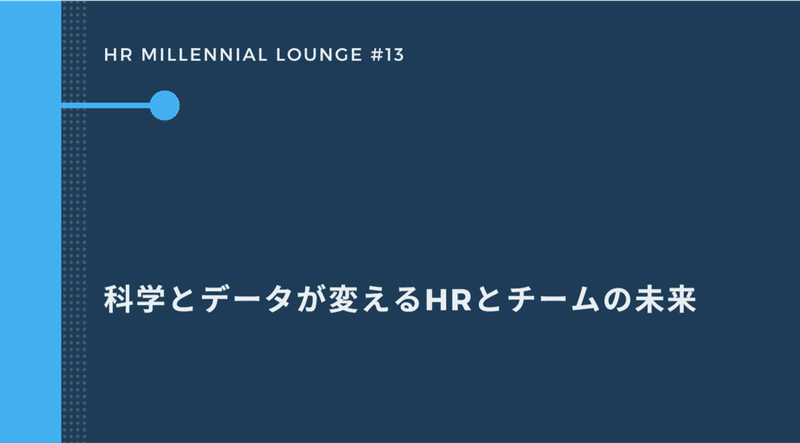
はじめに
メルカリで人事をしています岩田と申します。
前職はエン・ジャパン株式会社で転職サイトのプロダクトマネージャーを担当していました。
前職はプロダクトマネージャーを担当していたので、人事のスペシャリストというよりは、拡大する組織の中で派生する人事の横断的な課題を解決していくゼネラリスト的な役割を担ってきました。
メルカリがグローバルで成功していくためには、システム導入やデータ活用を強化していくことが必要ということで、HR Operationsというグループを組成しました。
本日は、「人事がデータを用いた戦略部門になるためには、どう取り組めばいいか?」という問いをテーマにお話したいと思います。
はじめに、人事データ活用が求められるようになった背景からお話していこうと思います。これ以外にもたくさんあるとは思うのですが、①株式市場からの健全なプレッシャー、②組織における多様性の拡大、③社内外問わないタレントの活用の必要性の3点が大きな背景であると思っています。

本背景から、これまでの経験則や正攻法では人事の取り組みがなかなか通用しない状況になってきている中で、様々なデータを活用した人事戦略の立案や実行が必要になってきています。
急速な組織拡大による変化で、データを基にした意思決定・コミュニケーションが不可欠に
本題に入る前に、弊社のことをお伝えしたほうが背景も含めて理解しやすいと思うので、弊社についてご紹介させて頂きます。
弊社は、「新たな価値を生み出す世界的なマーケットプレイスを創る」というミッションを掲げ、”グローバルでの成功”、”循環型社会の実現”を目指して日々取り組んでいます。
このミッションを達成するためのバリューとして、「Go Bold」、「All for One」、「Be a Pro」の3点を従業員は大切に活動しています。


次にHR領域において私たちの置かれている状況について、3点に絞って説明します。
1点目は急速な組織の拡大をしている点です。
ここ数年は前年の倍の人数へと急速に組織拡大を行っており、現在1700人以上の従業員がグローバルに存在します。

2点目は組織の多様性の高まりです。
冒頭で説明した人事データの活用が求められる背景としてもあったのですが、弊社でも多様性の高まりが進んでいます。現在40か国以上から社員が集まっており、東京オフィスのエンジニアリング組織の約半数が外国籍のメンバーという体制になっています。

3点目は、コミュニケーションにおいてハイコンテクストからローコンテクストへの変化です。
これは経営陣や人事が意図的に取り組みを進めているのですが、これまでハイコンテクストで通じていた部分も多様性の高まりによって、通じない部分も生じてくるので、多様性のあるメンバーがより理解を深めながら事業を進めていくために、ガイドラインやデータの活用に注力しながらローコンテクスト化を進めています。

上記3つを踏まえると、人事として求められる役割は今までと違ってきています。データを基にして意思決定とコミュニケーションを行うことや、従業員に納得感があるプロセスの設計が必要になってきています。

ステップの可視化でより効果的なデータ活用が可能に
以上のことを踏まえて、プロダクトやファイナンスの領域では当たり前であるデータ活用について、人事領域でどのように活用し進めていけばよいのかについてメルカリが取り組んでいる内容についてお話していきます。
弊社ではデータ活用に関して下図のステップを踏んでいく設計をしています。

下からプロセス構築⇒システム化⇒可視化と徐々にデータの活用のステップが上がっていくイメージです。
データ分析やデータ活用のお話をすると、ユーザー側からは機械学習、レコメンドなどを最初から求められることが多いと思います。
しかし、正しく効果的にデータ活用を実施するためには、まずプロセスをしっかり設計することや正しいデータが入力されるシステムを構築することが非常に重要です。
そのため、ステップを1つ1つを着実に踏んでいくことで高い成果を出せることを関係者全員に理解していただくために、ステップの可視化を大事にしています。
そしてこのステップは、下画像の3つに分解できます。

その中でも特にお話ししたい部分が➀見える化です。
なぜ➀見える化に注力してきたかというと、ドラッカーの「測定できないものはマネージできない」という言葉からきています。
何かの改善を進めようとしたとしても、そもそも今の状態を測定できていないとマネージできません。
そのため、「人事に関する情報を解像度高く測定できているのか」を問いかけながら、全体を俯瞰して捉え、計画を策定しています。
そういった中で、私たちがシステムやデータによって解像度を向上させていきたいと考えているのは「組織」「人材」「機会」の3領域になります。
「組織」に関しては、チームや従業員のコンディションがどういった状態にあり、どこに課題があるのかをサーベイを使って「見える化」をしています。
「人材」に関しては、従業員それぞれの経験やスキル、志向性などのデータを様々な形から取得して、「見える化」をしています。
「機会」に関しては、社内異動やメンタリング、研修プログラムなどのデータを集約し、従業員がより成長・活躍する機会を増やせるようなレコメンドをしていくことを考えて「見える化」を進めています。
機械学習やレコメンデーションをしようとした際に、データの整備がしっかりとされていないと正しいアクションをレコメンドできないため、プロセス構築やシステム化で情報を「見える化」することには注力する必要があります。
人事データ管理の「これまで」と「これから」
人事データ管理の「これまで」として実際にデータ活用を始めようとした際のデータ状況が下図となります。

本図の縦軸に人事データの種類、横軸に入社・職場環境等の社員の体験を記載しているのですが、様々な種類のデータベースが存在していたりスプレッドシートでデータ管理をしているものもあったりと、必要なデータをすぐに見つけることができない状況でした。
この事象は弊社だけでなく、恐らく急成長する組織では起こりうる、あるあるの事象ではないかと思います。
そういった状態から取り組みを進めてきた中で、現在は基幹システムを導入し、バラバラに点在していたデータをプラットフォームに集約することで、データの一元化を推進しています。
こういった仕組みを推進してきた成果の一例を紹介します。
これまではデータの可視化やレポーティングをする際に
「データを探す」⇒「データを集める」⇒「データの定義を合わせる」⇒「データを集計」⇒「データをレポートにまとめる」
といった工程を踏む必要がありました。
それが現在は、様々なデータの一元化が進んできたこともあり、上図のように様々な属性の情報をダッシュボードに集約することで、見たいデータをすぐに取り出せる状態を作り出せています。

他にも、X(Experience)データとO(Operational)データを掛け合わせることで新たな施策展開をしています。

例えば、私たちの会社ではエンゲージメントに最も相関がある項目は「成長機会」であると分かっているため、成長機会を強化するためにデータを基にさまざまな属性に向けた施策を展開しています。
従業員の体験をデータで管理し、従業員1人1人が最高のパフォーマンスを
私たちがデータを活用することで最終的に実現したいことは、「メンバー一人ひとりがバリューを発揮し、最高のパフォーマンスを出し続けられるよう、Employee Experience(従業員体験)をアップデートし続ける」ことです。
もちろんデータだけでは実現できないものであるため、他のHRの機能と一緒になって実現に向けて取り組んでいます。
具体的には、採用から退職まで従業員と様々な接点がある中で、「メルカリにおけるEmployee Experience(従業員体験)のあるべき姿」を掲げ、従業員の状態をチェックしながら、データを用いて多様な施策に取り組んでいます。

また、少し先の世界観になるのですが先程のデータの可視化からレコメンデーションへと段階を踏む中で、最終的には採用から退職までの接点の中でデータを用いたアクションレコメンドを従業員に提供していきたいと考えています。

下図にあるように、データ活用の高度化という点で前述したステップを踏んでいくことととデータ活用の領域の拡大とデータ分析の高度化を優先順位をつけながら進めている段階になります。

現在、「見える化」がかなり進んできていると実感しているので、今後は「洞察」と「促進」により注力して取り組みを進めることを考えています。

最後に
ご案内になりますが、弊社は今も積極的に採用募集していますので、ご興味持って頂けたら、是非ご応募いただけると嬉しいです。

本日はご清聴頂きありがとうございました。
・・・
ハイマネージャー
OKRや1on1、フィードバック、人事評価などハイブリッドワークのマネジメントに必要な機能が全て揃ったピープルマネジメント・プラットフォーム「HiManager」の提供、及びマネジメント・人事評価に関するコンサルティングを行っています。