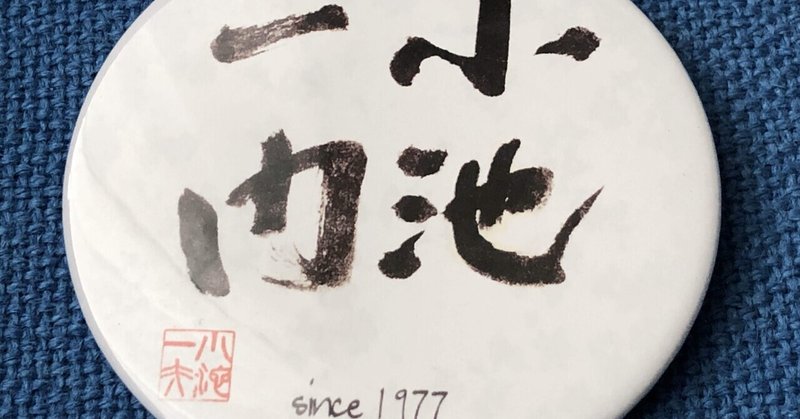
"キャラクターを起てろ!"劇画村塾第4期生 第3章〈3〉
<"都立大学漫画血風録"の始まり〜いつの間にか編集者さん達や漫画家さん達とのコネクションが加速度的に増えてゆく>
狩撫麻礼先輩&たなか亜希夫先輩コンビの『ルーズボイルド』は、残念ながら、何回か話を重ねたところで終わってしまった。(未だ単行本化もされていないはずで、なんとも勿体ない)
『ルーズボイルド』の担当編集者はHさんという人で、やはり我々と同じく都立大学の住人だった。 根っからの漫画編集者といった感じの、ちょっと口うるさいが、人懐っこい方だった。
このHさんとも、しょっちゅう、たなか先輩のアパートで顔を合わせることになった。
時には、行きつけのスナックに連れて行ってもらったり、自宅マンションまでお邪魔して、みんなで麻雀の真似事をやったりもした。(基本、自分は見学しているだけだったが)
そして、このHさんのおかげで、自分はもう一つ仕事にありつくことになる。
またしても麻雀漫画の原作だった。(繰り返しになるが、麻雀がロクにできもしないのに、だ)
Hさんが担当ではなく、Mさんという、もう定年退職間近の編集長兼担当者の方を紹介してくれたのだ。
新米原作者としては、Hさんのせっかくの厚意を無駄にするわけにはいかない。
すぐさま引き受けることにしたのはいいが、麻雀漫画の専門誌ではなかったため、闘牌を考えてくれる人がいなかった。
そこで思いついたのが、スタジオ・シップの販売部のOさんのことだ。
Oさんは仕事の虫で、自宅が遠いということもあって、よく本社の仮眠室に寝泊まりされていた。(本社には、漫画家さんやアシスタント諸氏のために、仮眠室があり、宿泊できるようになっていたのだ)
こちらも、風呂無しの安アパート暮らしだったので、たまにシャワーを借りたり、空いているデスクで原稿を書いて、そのまま仮眠させてもらうこともあった。
そのため、Oさんともよく顔を合わせる機会があった。
Oさんは、社長である小池一夫先生のことを、ものすごくリスペクトしていて、販売マンでもあるだけに、漫画にもひじょうに詳しかった。麻雀の腕もなかなかのものがあると、マネージャー諸氏からも聞いていた。
このOさんに、新しい麻雀劇画の闘牌シーンの考案をお願いすることにしたのである。
編集部から別途予算は出ないため、自分の安い原稿料の中から、労力に見合った手間賃をお支払いすることにした。
Oさんは、本当に雀の涙のような金額ながら、快諾してくれた。(思い返せば、副業になり、会社の規則に違反していたのかもしれないが、今さらながらOさんには感謝しかない)
かくして、『キャッシュハンター』にプラス、『ジローを見たか』なる麻雀漫画の原作も始まり、月一連載を二本持つことになった。
(編集長兼担当者のMさんからは、この後、さらに別の麻雀漫画の原作も依頼され、これまたOさんに闘牌シーンをお願いすることになった。が、こちらはほどなくして雑誌が休刊になり、Mさんも定年退職されてしまって、あまり記憶に残っていない。確か『ヒカルが走る』というタイトルだった記憶が……。『ジローを見たか』と同じく、単行本化はされず、漫画家さんとも直接お会いする機会がなかったこともあって、共に御名前も失念してしまっている。本当に申し訳ない限りです)
しかし、ほとんどといっていいほど麻雀には縁のなかった自分が、麻雀漫画の原作でそこそこ食えるようなってしまうとは、人生とは本当に不思議なものである。
そんなこんなで……。
Oさんとの打ち合わせのため、スタジオ・シップ本社に出向くことが多くなった。
当然のことながら、定時までOさんは仕事をされているため、終業時間後に、ということになる。
Oさんとの打ち合わせが終わる頃には、ちょうどマネージャー諸氏や事務局のSさんも仕事終わりや小池先生の原稿アップの待機時間中だったりして、一緒に飲み食いする機会も増えた。
自分も余力があって、呑みに行った後でも本社の社屋に戻って、原稿を書いたりしていた。シャワーもあれば、仮眠室もあって、冷暖房完備、アパートよりも快適だったということもある。
ちなみに、本社の社屋には”出る”と言う話もあったが、まったく霊感のない自分はついぞそういう経験をしたことはなかった。(Oさんは経験者だった)
幽霊よりも、小池先生の生霊のパワーのほうが明らかに強いという、もっぱらの噂でもあった。
確かにその通りだろうなと、小池先生のエネルギッシュな仕事振りを知っている身としては、妙に納得したものだった。
その頃のスタジオ・シップは、本社の横に、さらにもう一棟、大きな外人住宅を借り上げて、第二シップの社屋としていた。
Oさんは、たちまち、その第二シップの主のようになった。
打ち合わせがあるため、自分も出入りさせてもらい、Oさんや他の社員の方々と、夜を徹して漫画の話で盛り上がったりもした。
ここには、小池先生専用の執筆部屋もあって、ごくたまにだが、先生も顔を見せられることがあった。
「おまえ、何してるんだ?」
会社に自分がいることを怪訝に思った小池先生に訊かれた。
「は、は、はい。実は、Oさん達といろいろと漫画の話とかを……」
「ふうん。ま、若い連中は楽しくやるのが一番だ」
小池先生はあくまでも寛大だった。
(執筆部屋に置いてあった時計を、小池先生から「俺は使わないから、おまえにやるよ」と言われて、ありがたくいただいたこともある)
時期を同じくして……。
夏合宿で知り合った神戸劇画村塾第一期生の浜田芳朗氏(漫画家として活躍中の現・風狸けん氏)も、スタジオ・シップに出入りするようになっていた。
浜田氏は、小池先生が名作『I・餓男』の連載を再開された際、作画担当の松久鷹人先生のアシスタントとして、神戸より招聘上京していた。次いで、スタジオ・シップ所属だった神江里見先生のアシスタントを務めることになり、アパートのある街から通勤して来ていたのだ。
浜田氏とも親しく口をきくようになり、ここから、スタジオ・シップと契約していたアシスタントの人達との交流も始まった。
浜田氏と同じく神江里見先生のアシスタントだった近藤巧治氏(イラストレーターとしても活躍中の現・近藤こうじ氏)とも親しくなった。
全員そこそこ年齢が近いこともあって、色々と話が合うのが大きかった。
当時、トム・クルーズ主演で大ヒットした映画『ハスラー2』の影響で、プールバーが大流行していた。
まだ、カラオケボックスなどはほとんど見当たらず、もっぱらプールバーで玉突きをやったり、二十四時間の居酒屋やファミレスで朝まで語り合ったりした。
一方で、たなか亜希夫先輩や本沢たつや氏とも、スナックなどをハシゴすることが多くなった。
都立大学を根城とした、漫画と酒の日々が、始まったのだ。
(そういえば、気がついた時には、いつの間にか、劇画村塾の特別研修会も終わり、ちゃっかり卒塾証も手にしていた。卒塾時の記憶がまったくないのは、あまりにもドタバタしすぎていたせいかもしれない)
まさしく、あれよあれよという間にデビューが決まり、麻雀漫画の連載が始まり、ゆっくり考える間も何もなく、はからずも漫画原作者としての生活に入ってしまっていたのだった。
そして、さらにこの都立大学時代に、漫画原作者の自分としては決して忘れることのできない出会いがあった。
それは……。
劇画村塾とは直接関係はないのだが、先輩漫画家の土山しげる先生、猿渡哲也先生との出会いである。
〈続く〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
