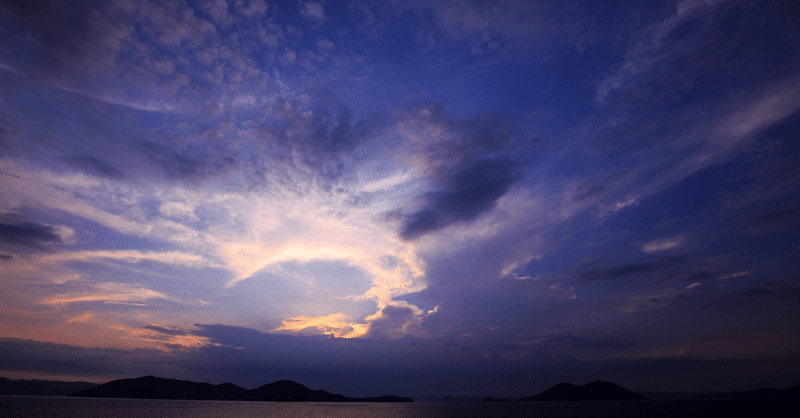
なぜ読めても書けないのか
自分自身で文章を書くのが苦手、と言われる大人は多いことです。苦手は苦手なのだから仕方ないのですが、それでは小学校からの学校教育、とくに国語というものは何だったのだろうと多少思うところがありました。
そう思っていたところ、昨日8月26日(土)の日本経済新聞29面の「言葉のちから 「書く」という営み」を読んで、少し目からウロコな思いになりました。この「言葉のちから」というのは批評家として多くの著作がある若松英輔さんの連載となります。
詳細な内容は、もしご興味があれば本記事をご覧頂ければと思います。ポイントとして、学校教育として求められていたのは「読解」であり、目にする言葉を忠実に理解することが求められるだけで、自分でさまざまなことを「解釈」して表現することが求められていたわけではない、ということです。そして「解釈」して表現することができないと、「書く」という営みにいたらない、というなのです。
若松さんが予備校に通っていた時の国語兼小論文の先生のことばが印象的です。「的確に正解を見つけられるようになっても文章を書けるようになるとは限らない。問題を解くことと、「書く」ことは地平を異にする」。そして、若松さんが予備校からの帰り道に古本屋で手に取った本の中で、フランスの詩人、哲学者が書かれていたのも印象的です。「書く、それは予見することである。」
本記事から考えると、既にあるものを読み、理解することと、それも踏まえてこれからのことを自分で考え、予見することは全く別のことなのです。後者のことができなければ、書くということには至らないのです。
こうした自分で考え、予見することまで学校教育で求めるのか、もし学校教育でないとすると、どのような場機会で学んでいくのかは大きなテーマです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
