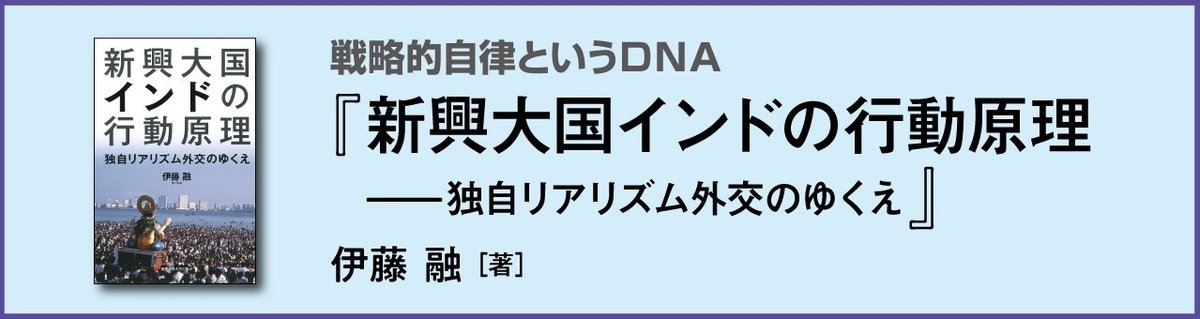【試し読み】『新興大国インドの行動原理』はじめに 公開
平均年齢27歳、中国とほぼ同じ人口を抱え、今後さらなる経済発展が期待される南アジアの大国インド。中国の台頭に伴い、国内でも新たな外交パートナーとしてインドに期待する向きは、年々強くなっているといえるでしょう。
しかしながら、インドは度々その理解を超えた外交行動で世界を惑わしてきました。ある時は「非暴力」「非同盟」の理念を掲げた第三世界の平和主義者。ある時は核実験を行い、パキスタンや中国とも国境戦争を厭わないリアリスト(2020年6月、ヒマラヤ山脈の国境をめぐってインドが中国と軍事衝突を起こし、1975年以来、実に45年ぶりに死者が出たというニュースが話題となりました)。そして現在は、かつてのロシアとの強固な関係から、西側諸国との連携にシフトしてきています。
果たして私たちが抱いている「インド」観は正しいのでしょうか。2020年9月中旬発売の『新興大国インドの行動原理――独自リアリズム外交のゆくえ 』では、インドが伝統的に受け継いできた「戦略」の文化をカギに、その国際関係を読み解いていきます。
この記事では、以下に本書「はじめに」の一部を公開していますので、ぜひご一読ください。
***
はじめに──「理解できない国」としてのインド
冷戦期を知るひとならば、「インドという国の国際社会におけるプレゼンスはかつてとは比べものにならないほど高まった」、という主張に異論を唱えることはあるまい。国際通貨基金(IMF)のデータにもとづくと、1980年のインドの国内総生産(GDP)は1894億ドルで、世界経済に占める割合は1.7パーセントにとどまっていた。ところがそれから40年近くたった2018年のGDPは2兆7187億ドルに達し、その割合も3.2パーセントにまで上昇した。いまやイギリス、フランスと肩を並べる経済力を誇る。当然ながら、世界のほとんどの国にとって、この新興大国との関係の重要性は、政治、経済、軍事のあらゆる領域で以前より増している。
インドへの渡航者数の変化をみてみよう。インド政府観光省の統計によれば、1980年には80万人にすぎなかった外国人入国者数は、2000年に265万人、そして2018年には1056万人に達した。急増する渡航需要に応えるため、首都デリーの玄関口、インディラ・ガンディー国際空港も大きな変貌を遂げた。思い起こせば、筆者が初めてインドを訪れた1992年、国際線ターミナル(ターミナル2)には搭乗口も免税店も数えるほどしかなく、中国に次ぐ人口大国の首都の空港とはとても呼べない代物であった。しかも空港を一歩出れば、牛が道をふさいでいた。しかし2010年には、78もの搭乗口を備えた巨大な国際線ターミナル(ターミナル3)が開業した。多くの乗降客の移動を支えるため、都心部への地下鉄も整備された。いまや世界中から多くのひとびとが、仕事や観光で日々インドに押し寄せている。
日本も例外ではない。インドを訪問した日本人は1980年の3万人から、2018年には23万6000人にまで激増した。かつては日本航空とエア・インディアが週数便ずつ往復するにすぎなかったが、いまや全日空も含めて毎日の就航となり、路線もムンバイやチェンナイ、ベンガルールなどの主要都市に拡大している。在留邦人数も1980年の838人から2018年には9838人にまで増えた(外務省「海外在留邦人数調査統計」)。2018年時点でインドに進出した日系企業は1441社、5102拠点を数える。中国や東南アジアに比べればまだまだ少ないとはいえ、日本人にとってもインドはかつてよりも身近な存在になりつつある。
民間以上に政府間関係の変化は如実である。1980年代から90年代の20年間で、日本の首相のインド訪問はわずか2回にすぎなかった。しかしいまや、日印双方の首相が毎年交互に訪問する関係が構築されている。首相だけではない。外務・防衛閣僚協議(2プラス2)をはじめとして、主要閣僚や政府高官も毎年のように往来する。アメリカとインドでつづけられてきたマラバール演習への海上自衛隊の参加など、共同演習を含む防衛交流も活発化した。もはや経済だけでなく、日本の外交・安全保障政策の柱の一つとしてインドが位置づけられていることは疑うべくもない。
注目すべきなのは、世界中の主要国・新興国が、同様に認識し、行動している点である。2010年後半のわずか半年のあいだに、国連安保理常任理事国五カ国の首脳が二国間会談のために立て続けにインドに足を運んだことは、象徴的な出来事であった(注1)。日本やアメリカだけでなく、中国やロシアも、インドを「戦略的パートナー」と位置づけて、自国との関係強化を二国間、多国間の枠組みで競っている。
しかし、このようにインドがいまや無視しえないパワーであるとしても、はたしてわれわれはどの程度この国のことを知っているのだろうか。たしかに、インドは日本人にとっても、昔から魅力の多い国だった。インド哲学やインド史、人類学の講座は日本国内の少なからぬ大学に設置されている。
しかし、社会科学分野、とりわけ政治学や国際政治学をディシプリンとする専任教員を、インドないし南アジアの「地域研究」担当者として採用している一般大学はみかけない(注2)。中国や東南アジアに比べて、南アジアについての知識の蓄積が立ち遅れてきたのは明らかである。
そのあらわれともいえるのが、1989年5月にインドが行った核実験と核保有宣言に対する日本国内の受け止め方であった。「唯一の被爆国」として、また核不拡散政策を主張する立場として、インドの行為に憤りを示したのは当然である。しかしこのときに同時にみられたのは、「なぜインドが?」という、驚きと失望であった。
核実験が突きつけたのは、われわれが抱いていた「インド」像とのギャップであった。それまで多くの日本人にとっての「インド」は、仏教発祥の地であり、「非暴力」理念を掲げ、それを実践することで植民地支配からの独立を勝ち取った崇高な国であった。独立後も、東西の冷戦体制のいずれに
も与することなく、「非同盟」を看板に、第三世界のリーダーとして平和外交を推進してきた。さらには、特定の国の核保有を正当化する核拡散防止条約(NPT)体制の欺瞞性を糾弾し、全面的な核軍縮・核廃絶を訴えてきた。まさに「インド」は、「反核・平和勢力」にとっては、尊敬すべきモデルにほかならなかった。だからこそ、核実験の衝撃は大きかった(注3)。
このイメージギャップの要因は、大きく二つに分けられよう。最初の要因はきわめて単純なものであり、われわれがこれまでインドの動向についてあまりにも無知・無関心だった、という点にある。じつはわれわれの抱いていた「インド」像からの逸脱は、なにも1998年に突然はじまったわけではない。それまでにパキスタンとは3度も全面戦争を戦っているし、中国とも国境戦争を経験している。そして1974年には「平和的核爆発」と称した最初の核実験を行っている。にもかかわらず、まだ国際的影響力も小さく、地理的にも遠いこの国への関心は広がらなかった。その結果、日本人の「インド」に対する一般的な認識に大きな変化は起こらなかったのである。
もう一つの要因は、より根源的な、国際政治の視座をめぐる問題である。インドが変わってしまったのではなく、そもそもわれわれの抱いていた「インド」像が間違っていたのではないか、という問いである。なるほどインドにおいて「非暴力」や「非同盟」が掲げられたのは事実である。しかしそれは、国際政治学(国際関係論)で従来いわれてきた、「理想主義(idealism)」としてとらえてよいのだろうか。同様に、核実験・核保有、そしてインドに対抗して同じく核保有したパキスタンへの度重なる強硬姿勢は、「現実主義(realism)」にもとづいた行動なのか。そもそも西洋の国際政治学を無批判に適用しているがゆえに、変容したようにみえるだけではないのか。本書の問題意識はまさにこの点にある。
他方で、近年の国際政治情勢を踏まえて、台頭するインドとの戦略的関係強化を主張する論調のなかにも、過度に単純化され、都合のいい「インド」像が散見される。日本でいえば、大国化とともに自己主張の度を強める中国を念頭に、同じ民主主義という価値を共有するインドと手を組むべきだといった主張である。インドも、自らと価値観が異なり、国境問題や海洋進出をめぐって対立関係にある中国には警戒感を抱いているにちがいない。それゆえ、日本やアメリカ、またオーストラリアと「インド太平洋」において協調するはずだ、いや同盟関係構築すら可能かもしれない、といった議論である。
こうした楽観論は、ほどなくすると裏切られる。2014年に就任したナレンドラ・モディ首相は、最初の域外訪問国として日本を選び、安倍晋三首相とのあいだで、日本との戦略的パートナーシップを「特別」なレベルに引き上げることに同意した。2017年には日米豪との戦略対話を10年ぶりに再開させるなど、インドは「インド太平洋」を唱える国々との協調に大きく舵を切ったかにみえた。しかし、翌2018年に入るとモディ首相は、中国の習近平国家主席、ロシアのプーチン大統領と相次いで「非公式首脳会談」を開いて連携をアピールした。さらには、「インド太平洋」は特定の国を対象にした同盟ではないという立場を国際舞台で明言した。こうした現実に直面するたびに日本では、インドはいったいなにを考えているのか、「理解できない国」だという認識が繰り返された。
インドが「普通の国」として振る舞おうとしない現状を嘆く声は、じつはインド人のなかからも聞かれる。とりわけ、国外で活躍するインド人研究者は辛辣だ。米国との同盟を明確に否定した2012年のインドの戦略文書『非同盟2・0』を、在インド米国大使の特別補佐を務めた経験ももつテリスは、「新しい革袋に古いワインを入れる」行為だと厳しく批判した。同様にアメリカで活躍する若手研究者のミラーは、世界的に影響力のある『フォーリン・アフェアーズ』誌に、インドは大国になることを志望しているというが、その割に明確な戦略もなく、グローバルな責任を引き受けようとしないと断じた。イギリスとインド両国で活躍する国際政治学者パントも、インドの政策決定者たちは、大国としての地位にはどんな役割が伴うものなのか認識できていないなどと、手厳しい。共通するのは、主要国の強い期待に応えようとせず、せっかくのチャンスをインド自身が逃しているのではないか、というもどかしさである。
今日のインドが「世界大国化」を図っているとしても、そこには本当の意味での「大戦略」はなく、目的も不明確なまま軍備調達を拡大し、場当たり的な外交に終始しているとの批判は内外で多い。インドの「戦略の不在」は、以前から指摘されてきた。これに対し、現在のインドの対外政策を、国力と環境が整うまで野心をあらわにしない、いわゆる韜光養晦(とうこうようかい)路線として、かつての中国になぞらえる見方もある。しかしそうだとすれば、まもなく人口で中国を、そして2030年代には経済力でもドイツや日本を上回るとみられるこの国は、そうなったときには中国のように、あるいは「普通の国」として、振る舞うようになるのであろうか。本書では、インドがなぜ「普通の国」として行動しないのかを考えてみることにしたい。
(注1)2010年代前半までの主要国のインド接近を扱ったものとしては、ホールの編集した研究が優れている。
Hall, Ian ed., [2014] The Engagement of India: Strategies and Responses, Georgetown University Press.
(注2)日本国際政治学会には地域研究の分科会として、アジアに関していえば、東アジア、東南アジア、中東が置かれているが、南アジアは存在しない。
(注3)たとえば、『朝日新聞』「天声人語」欄(1998年5月14日朝刊)、ならびに『毎日新聞』「社説」欄(1998年5月13日朝刊)を参照されたい。いずれも「非暴力」や「ガンジー」に言及して、インドの核実験はそこからの逸脱ととらえて批判している。
※こちらの試し読みでは読みやすさに配慮し、実際の本に掲載されている参照文献の記述を省略しております。
***
目次
はじめに 「理解できない国」としてのインド
第1章 理想主義から現実主義への転換か?
第2章 DNAとしての戦略文化
第3章 外交政策を制約する構造はなにか
第4章 インドのおもな対外関係――直面する課題
おわりに モディはインド外交を変えたのか?
あとがき
参照文献一覧
索引
#試し読み #国際情勢 #政治 #外交 #安全保障 #インド #慶應義塾大学出版会
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?