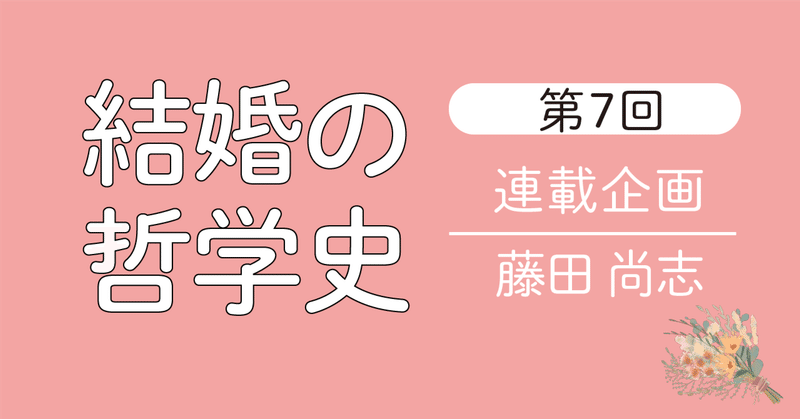
連載第7回:『結婚の哲学史』第2章フーリエ第1節フーリエの時代と生涯
結婚に賛成か反対か、性急に結論を下す前に、愛・ 性・家族の可能なさまざまなかたちを考える必要があるのではないか。昨今、結婚をめぐってさまざまな問題が生じ、多様な議論が展開されている現状について、哲学は何を語りうるのか――
九州産業大学で哲学を教える藤田先生による論考。今回からフーリエを扱います。
↓これまでの連載はこちらからご覧ください
***
ヘーゲルのフーリエ変換
ヘーゲルの次はフーリエである。もちろん、結婚の哲学史において問題となるのは、フーリエ変換(Fourier transform)で有名なフランスの数学者・物理学者ジョゼフ・フーリエ(Jean Baptiste Joseph Fourier, 1768-1830)ではなく、マルクス=エンゲルスによってユートピア社会主義者という烙印を押されてしまったシャルル・フーリエ(François Marie Charles Fourier, 1772-1837)のほうである。二人のフーリエについては、『レ・ミゼラブル』にこんな記述がある。第1部第3巻第1章「1817年のこと」の一節である。
科学アカデミーには後世の人々が忘れてしまった有名なフーリエ(Fourier célèbre)がいたが、どこかの屋根裏部屋には未来の人々が覚えているであろう無名のフーリエ(Fourier obscur)がいた。
ユゴーが1862年にこの大著を刊行した当時、数学者フーリエは本当に忘れ去られていたのか、1817年にもなお思想家フーリエは未だ無名であり続けたのか、真相究明は歴史家に任せよう。それにしても、ヘーゲルにある種の“変換”を施すとフーリエになると言いたいくらい、フーリエにはヘーゲル的な側面がある。実際、エンゲルスは『反デューリング論』で「フーリエには、社会の現状批判がある、真にフランス的で機知に富んだ(echt französisch-geistreiche)、それでいて深く透徹した(tief eindringende)批判が」と述べた後、こう続けている。
だが、フーリエがその最大の力量を発揮するのは、社会の歴史についての構想においてである。(…)フーリエは、同時代人ヘーゲルと同様の名人芸(Meisterschaft)で弁証法を使いこなす。同じ弁証法を用いながらフーリエは、人間が際限なく完全へと近づいていく能力を備えているという説に異を唱え、あらゆる歴史的段階には上昇期もあれば下降期もあると主張し、この観察を全人類の未来に適用する。(…)フーリエは人類の未来の衰退を歴史学に導入したのである。
エンゲルスは正しい。問題はただフーリエとヘーゲルが似ているということではなく、両者の弁証法がどのような“変換”の関係にあるのかを知ることだ。ヘーゲル『精神現象学』の刊行は1807年、フーリエ『四運動の理論』は1808年である。前者がゲーテの『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』のようなBildungsroman(自己形成小説・成長物語)的側面をもっていることはつとに指摘されるところであり、ヘーゲル弁証法が前章で見たように「止揚」(Aufhebung)を核とすることも揺るがないのだが、たしかに弁証法にはヘーゲル的でない仕方で、もっと豊かな可能性を見ることもできる。「同じ弁証法を用いながら」(mit gleicher Dialektik)、人類の歴史が挫折しながら前に進む際限のない上昇である必然性はどこにもないと主張することもできる。仮に上昇するとしても、まったく収束せず、無限に分岐した方向性に散開していくと主張することも。
セリー法則と弁証法(プルードン)
そもそもヘーゲルとフーリエの類似性を指摘したのは、エンゲルスだけではない。モーゼス・ヘスやカール・グリューンらヘーゲル左派の中に、フランス社会主義とドイツ哲学を並行的に捉え、サン=シモン≒シェリング、フーリエ≒ヘーゲル、プルードン≒フォイエルバッハと見る視座がすでにあり、マルクスもそれを踏襲している(『ドイツ・イデオロギー』第2巻第4篇)。そのプルードンは、1843年出版の著作『人類における秩序の創造について、あるいは政治組織の諸原理』において、すでにフーリエ的思考とヘーゲル哲学を交差させていた。
正確を期するなら、プルードンはヘーゲルとフーリエの並行性を指摘したのではない。フーリエについては、「セリーという普遍的な考えを最初に着想した」という点は高く評価しているものの(§214, p. 176)、全体的な評価はかなり微妙なものであると言わざるをえない。ただプルードンがフーリエ的思考のうちに、精神科学・政治科学を「真の」科学の水準に引き上げる革新的な何かを見出したことだけはたしかである。革新的な何か、それは「系列法則の特殊性」(§215, p. 177)である。1843年のプルードンにとって、科学はセリー的なものでなければならず、セリーを当該「科学」に適用することによって、それらは真の科学となる。
セリー法則を啓示した者(révélateur de la loi sérielle)はフーリエであった。他を寄せつけず、学問的訓練を受けず、孤独な天才であったが、深遠な道徳観、精妙で有機的な感受性、驚異的な予言者的本能を備えたフーリエは、分析することなく、純粋な直観によって、宇宙の至高の法則へと一気に飛躍した。彼はセリー理論(théorie sérielle)を知らなかった。
他のところでは例えば「方法の完全な欠如、ほぼ何の意味もない弁証法(dialectique à peu près nulle)、彼自身が発見したものに対する目を覆わんばかりの無知」(§453, p. 435)と述べるなど、著作全体ではかなり悪しざまに言っているという印象は拭えない。
ヘーゲルに関しても「想像力の及ぶ限り、自然と思想を三つの大きな系列に分類し、さらに三つずつ下位区分」する哲学者として「ふたたび三位一体のドグマを流行させた」が、それは「千ある見方のうちから選び出された一つの観点」にすぎないと切り捨てている(§210-211, p. 170-171)。むしろプルードンにとっては、アンペールの「四項分類」(classification quaternaire)ないし「四、四と分類していく体系」(§212, p. 173)のほうがヘーゲル的な「三項分類」(classification ternaire)に対する決定的な進歩なのである。
フーリエ的思考とヘーゲル哲学の交差という言葉で私たちが表現しようとしていたのはそうではなく、セリー主義と弁証法の根本連関である。プルードンは、「私たちの諸観念を構成し、解体する術」(§244, p. 201)である「系列的弁証法」を、より詳しく次のように規定している。
他のいかなる関係によっても結びつけることのできない諸項を、反省によって比較することから生み出される系列を「弁証法的系列」(série dialectique)と呼び、その用い方を教える特別な理論を「系列的弁証法」(dialectique sérielle)と呼ぶことにする。
プルードンの考える弁証法がそのようなものであるとして、彼が「ほぼ何の意味もない」と考えるフーリエ的弁証法とは、どのようなものであろうか。
ワルツか、マーチか
私たちは前章でヘーゲルの弁証法のリズムを論理的三拍子と呼んでいた。プルードンの指摘の中で、とりわけ興味深いのは、私たちならば「二拍子的」と呼ぶであろうものに対する注目である。ヘーゲル弁証法が三項系列であり、アンペールが四項系列であるのに対して、プルードンによれば、最小のセリーは二項系列から始まる。
可能な限り小さな系列は、少なくとも2つの単位を含む。テーゼとアンチテーゼ、交替、往復、反対、極端、極性、均衡である(…)。先に三項や四項のシステムについて語ったが、世界を際限のない二元論で説明することもできるだろう。哲学の原初形態の一つはそのようなものだったとすら思われる。
プルードンは明示的に二項系列をフーリエに帰したわけではないが、「セリー法則の啓示者」ではあっても「セリー理論を知らなかった」、本能で直観していたが、分析はしていなかったといった評価を見れば、そのように推測してもあながち外れてはいないだろう。後でも見るように、フーリエは軍隊の行進が好きで、街を行進しているのに出会うと、軍楽の響きに歩調を合わせながら、どこまでもその後について行ったという。
ただし、「二拍子 対 三拍子」というのはあくまでも分かりやすい比喩にすぎない。話をあまり単純化しすぎないように注意しよう。「算術マニア」(arithmomane)という自覚があるのだろうか、フーリエ自身も「システム構築者が陥りがちな、すべてを1つの数に結びつける排他的マニア」に警鐘を鳴らしている(Fourier 1851:341)。彼は3や4、7や12といった数を「神聖」と表現したかもしれないが、それらの数も「調和の基数であること以外の特権」は持っていなかった。フーリエの「系列」はあくまでも多様であり、人類という種の進化を記述し、人間社会の運動を表現する。系列とは位相、焦点、ピボット、両義性や移行を視野に収め、普遍的な運動の諸関係を規定する一般的な法則なのである。
広義のヘーゲル左派、マルクス主義の文脈の下流に位置しながら、独自の数学的感性でフーリエを高く評価していたのがレイモン・クノーである。ジャン・ヴァールが主催していた哲学雑誌『ドゥカリオン』(Deucalion. Cahiers de philosophie)には、アレント、カイヨワ、クロソウスキー、ジャンケレヴィッチ、バンヴェニスト、レヴィナスなど錚々たる顔ぶれが寄稿しているが、1955年に刊行されたその第5号に掲載された論文「ヘーゲル弁証法とフーリエの系列」で、クノーは、単純に見えるフーリエの「数学的社会主義」(マルクスの『ドイツ・イデオロギー』で批判されていたグリューンの表現)のうちに微妙な「重みづけ」を看取している。
正直なところ,フーリエは,1-2-1,1-3-3-1,1-4-6-4-1などのような純粋な二項分布を使うことはめったにない(ほとんどないように私には思える).彼は常に「重み付け」を行い、例えば上昇相は一般的に(ほとんど常に、私にはそう見える)下降相よりも「数」が多い。つまり、地球の歴史における2つの上昇期、遠地点と2つの下降期は、それぞれ(千年単位で)5 - 36 - 9 - 27 - 4(=81)となる。
フーリエ研究者の福島知己は、「このように微妙な偏差を導入しようとする傾向はフーリエの大きな特徴であり、単純数によって構成される均斉のとれた美を好むピタゴラス主義的な神秘主義者にはみられないものである」と指摘しているが(福島 2013:365注85)、私たちの文脈で言えば、正‐反‐合の論理的ワルツの三拍子で、論理学-自然哲学-精神哲学の体系で宇宙の全存在を包括するのではなく、「系列」(série)的マーチの二拍子で、ただしそこに微妙な「重みづけ」という偏差を加えることで無限に複雑な「群」を形成していくのがフーリエ的な弁証法だということになるだろう。これから私たちがその脱構築を見届けようとしているのは、家族‐市民社会-国家が形成する三位一体システムや、それらによる愛・性・家族の包摂をヘーゲルとは別様に“変換”しているフーリエ的思考である。
四つの林檎
さて、このイントロダクションの最後に、さまざまな解説などで触れられている有名なエピソードを紹介しつつ、フーリエ自身の思索と生涯をごく簡単に概観しておくことにしよう。フーリエによれば、人類の歴史の重要な転換点をしるしづけた四つのリンゴがある。第一の林檎は、アダムとイヴがかじった「禁断の果実」である。神は塵から作った〈人間〉をエデンの園に連れてゆき、どの木の実を食べてもいいが、中央の「善悪を知る木」の実だけは食べると死ぬ、と警告する。神は〈人間〉のあばら骨を取って〈女〉を作り、その妻とするが、〈女〉は蛇にそそのかされて「禁断の木の実」を食べ、夫にも与えた。こうして、二人はエデンの園から追放されてしまう。
第二の林檎は、ギリシア神話「パリスの審判」に登場する。不和と戦いの女神エリスがエギナ島の王ペレウスとテティスの結婚式に招かれなかったことに腹を立て、式場に「最も美しい者へ」と刻んだ黄金の林檎を投げ込んだ。名乗りをあげた三柱の女神――神々の王ゼウスの妻ヘラ、戦いと知恵の女神アテナ、愛と美の女神アフロディテ――の間にいさかいが起り、困惑したゼウスはトロイアの王子パリスに、その判定を委ねることにした。パリスを買収しようと、三女神はそれぞれ「富と権力」、「戦場での名誉」、「世界一の美女」を約束し、パリスはアフロディテに林檎を与えた。彼女は約束を果すべく、パリスをギリシャに案内し、スパルタ王メネラオスの妃ヘレネの姿を見せる。その美しさに魅入られたパリスは、ヘレネを誘惑して、トロイへ連れ帰った。そのため彼女の奪還をかけ、ギリシャとトロイアの間でトロイア戦争が起きることになった。これがオッフェンバッハのオペラ・ブッフ「美しきエレーヌ」(1864)の元になった神話である(ヘレネはフランス語で「エレーヌ」)。
第三は、林檎が木から落ちるのを見て「万有引力」を着想したという「ニュートンの林檎」である。「物が落ちる」という現象、地球上にある物体を地球が引っ張る力としての「重力」はすでに知られていた。ニュートンが画期的だったのは、この現象と太陽系の惑星の運行が同じ力に由来すると見抜き、その力を「万有引力」(universal gravitation)と名付けたことである。
そして第四の林檎が「フーリエの林檎」である。第一の林檎(アダムとイヴ)と第二の林檎(パリス)が、それらが引き起こした〈破滅〉によって有名だとすると、「フーリエの林檎」は、第三の林檎(ニュートン)同様、〈科学への貢献〉によって有名になるはずだ、とフーリエは言う。
私にとって一つの林檎が、ニュートンにとってと同様に、計画の指針となった。パリのレストラン『フェヴリエ』で、一緒に夕食をとった旅行者が、有名な林檎に14スウ支払った。私はと言えば、それと同じか、もっと上質の林檎が半リアール[一リアールは四分の一スウ]で買える地方から出てきたのだった。私は、気候のさほど変わらぬ地方の間でこれほど価格に違いがあるのに驚き、産業機構の中に根本的な無秩序があるのではないかと疑い始めた。そこから、産業的諸集団の系列の理論、したがってまた、ニュートンのやり残した宇宙運動の諸法則を私に発見させた諸研究が生まれたのだった。
二つの革命への憎しみ(1)産業革命:サン=シモンの〈生産〉とフーリエの〈流通〉
フーリエは、富裕な毛織物・香料商人の長男として生まれた。幼少の頃から激しく不正や抑圧を憎んでいたにもかかわらず、家業の商売上のことで正直であったために両親から罰せられた彼の生涯は、産業革命によって飛躍的に発展する〈商業〉への憎しみに貫かれることになる。1799年、フーリエは、商業の反社会性について、確信を深めるような出来事を経験する。マルセイユの食料品店で店員として働いていた彼は、主人の買い占めた米が価格の騰貴する前に腐ってしまったため、それを海中に捨てるよう命じられたのである。このエピソードは、同時代のもう一人の空想社会主義者サン=シモンが〈生産〉の問題をその思想形成の中心に置いたのに対して、フーリエが〈流通〉の問題をその思想形成の中心に置いたことを物語っている。
二つの革命への憎しみ(2)フランス革命
1793年、21歳のフーリエは、父の遺産を元手にリヨンに店をかまえ、米・綿花・砂糖などの商品取引に全財産を投入した。彼の注文した商品が到着したとき、反革命の拠点となっていたリヨンは、国民公会派の軍隊によって包囲されていた。貨物は反革命軍によって徴発され、自身も強制的に軍隊に編入された。やがてリヨンを占領した革命軍によって逮捕されると、今度は投獄の憂き目に遭った。釈放されてみると、財産はすっかり失われていた。こうして、フーリエは、商業に対してと同様、暴力や革命を徹底的に憎む気持ちを生涯持ち続けることになる。〈商業〉と〈革命〉――フーリエは文明社会の根本的矛盾を身をもって知り、それに対する批判の武器を探すことになる。
リヨン
フーリエは1800年から約十五年間、フランス第二の大都市リヨンに住み、ブローカーとしての仕事も安定し、そこで本格的な著作活動を開始する。1808年に始まる彼独自の思想の爆発、その基盤としてリヨンの都市的性格――絹織物工業で繁栄するリヨンの豊かさの中における住民の貧困――を無視することはできない。それまでの経験に加えて、商工業都市リヨンが抱えている経済的・社会的諸矛盾と労働者のミゼラブルな生活の中から、次第に独自の思想世界を構築していった。
猫と花
フーリエは生涯独身を通した。彼は猫と花を熱愛し、晩年には老少年あるいは老少女のような物腰を保っていた。色褪せてすりきれた服を着、薄暗い屋根裏部屋で、月日や季節の移り変わりにも気づかずに過ごした。軍隊が街を行進しているのに出会うと、軍楽の響きに歩調を合わせながら、どこまでもその後について行き、そして、何時間でも兵士たちの教練を眺めた。日常生活は過敏なほど綿密で、「今日は私の本の20/36を書き上げた」といった具合であった。晩年のフーリエは病気がちであったが孤独を選び、弟子の面会を拒否して、看取る人もなく死ぬ。遺体を発見したアパルトマンの門番によれば、フーリエは、フロックコートを着て、部屋を埋め尽くす花瓶の中で、猫に取り巻かれて、跪いて死んでいたという。
次回:3月15日(金)更新予定
↓これまでの連載はこちらからご覧ください
#結婚 #結婚の哲学史 #藤田尚志 #連載企画 #ニーチェ #ソクラテス #ヘーゲル #フーリエ #フロックコート #アレント #カイヨワ #クロソウスキー #ジャンケレヴィッチ #バンヴェニスト #レヴィナス #特別公開 #慶應義塾大学出版会 #Keioup
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
