
大森荘蔵著『時は流れず』(その1)
大森荘蔵著『時は流れず』(青土社)を読んでいるのだが、大森氏の見解が荒唐無稽に感じられるのは、大森氏の言語観によるものかな、と感じた。中途半端な経験論(本来、分析哲学と経験論とは相容れないものであると思う)とでも言おうか・・・
1.過去の知覚そのものを探しても見つけることができない事実に関しては、大森氏は自覚しているように思う。しかし、私たちが過去の出来事に確信を持ちうるのは、過去の出来事を指す命題(言葉)に対し、(とりあえず「現在の」としておく)知覚が現れるからではないのか? その事実を無視していないだろうか。
私たち(おそらく)は、過去の出来事として、味やら香りやら音やらを思い浮かべることができる。このあたり大森氏の記述と私たちの実際の経験が乖離しているのは、どう受け取れば良いのだろうか・・・?
ちなみに、西田は次のように述べている。
記憶においても、過去の意識が直に起ってくるのでもなく、従って過去を直覚するのでもない。過去と感ずるのも現在の感情である。抽象的概念といっても決して超経験的の者ではなく、やはり一種の現在意識である。(西田幾多郎『善の研究』岩波文庫、18ページ)
2.言葉の意味・命題の真偽が究極的に知覚的経験の有無で判断されることを否定しているために、トートロジー的説明になってしまっているように思える。
大森氏は「直覚的明証性という真実性」(大森氏、27ページ)について、次のように説明している。
「雪は白い」という命題が真であるのは雪が白い場合、またその場合に限ってである(if and only if ......)、という条件である。この奇妙な条件を理解するには、雪が白いか白くないかは馬鹿にでも直覚的にわかる、という直覚的明証性を回りくどく言っただけだと承知させすればよい。(大森氏、27ページ)
想起命題の場合はタルスキの心理条件の段階にとどまるべきだろう。つまり直覚的明証性を素直に呑み込んで、それ以上余計な手を加えないことである。(大森氏、28ページ)
・・・(タルスキがどう考えているかは別として)これは、言葉の意味が具体的知覚経験から離れてアプリオリに成立することを示しているのではない。そこに見えているものと「白い雪」という言葉とが繋がりあった、そこに見えているものを「白い」あるいは「雪」あるいは「白い雪」と(いやおうなしに)思った、その事実は否定しようもないこと、そして「そこにあるのは白い雪だ」という信念は、その時点においては「真理」なのだ、ということである。
「直覚的明証性を素直に呑み込んで、それ以上余計な手を加えない」とは、結局そういうことなのである。言葉と(知覚)経験とが繋がった事実、これはそれ以上説明できないが否定もできない明証性を有する事実なのだ。
繰り返すが、そう思ったことがその時点における(私にとっての)真理、言葉と経験とが(理由などわからないが)いやおうなしに繋がりあった、それが出発点であり、すべてはそこから始めるしかない、それが上記の「直覚的明証性」ということでもあるのだ。
その真理は、少し時間をおいて見直したら実際は雪ではなかったとか、他の人が見たら雪ではなかったとか、新たな見解が生じたときに塗り替えられる可能性を持つ。
一方、私が何度見ても、他の人が見ても同じように「雪だ」と思ったとすれば、その見解は客観性を持つものだと認めることができよう。しかし、その真理が客観性を持っていようが持っていなかろうが、結局のところ、私自身にとって真理というものはどこまでもプライベートなものなのである。知識が客観性を持ったら私自身の経験から離れていくわけではないのだ(このあたり哲学者の間で広く誤解されているように思える)。あくまで「雪」という言葉とそれに対応する知覚経験(具体的事物やら写真やら絵やら)であることに変わりはない。
いずれにせよ、その時点において、その命題に対応する何等かの知覚経験があること、それがその命題の意味であり命題の真偽を定めるものなのである。
そもそも「白い雪」と言葉だけあっても、そこに対応する何か(事象・経験)がなければどのようにして真偽を判断せよというのだろうか?
「言語的了解」(大森氏、47ページ)とはいったい何なのか? それらも究極的には知覚経験あっての了解なのである。顕微鏡で見た像も一つの知覚経験である。顕微鏡を見て実際に見えるからこそ血液の形が同定されるのである(大森氏、47ページに関係)。顕微鏡を覗いて何も見えなければ仮説が証明されることはない。このあたりの科学のプロセスが捻じ曲げられて理解されてしまっている。
3.実生活と実用との混同
以下の大森氏の説明だが、
普通人が他者についてあれこれ述べ考えるときの意味を模擬的に制作して、それに対して哲学者が提出するあれこれの難癖が的外れであることを示そうというもの(大森氏、12ページ)
・・・とある。普通というものの定義の問題はあるが(そして、模擬的という言葉も必要ないと思うが)、要するに奇怪な哲学者の理論というものに根拠がない、普通の人々(実のところ哲学者もそうだと思うのだが)は、そんな理論など関係なく他者を認識し、存在していると思い、時が流れると思っているのだ。その在り様を検証する必要があるのではないか、ということだと思う。
あくまで、私たちの実生活における経験を検証するのであって、それが「実用的」「実践的」かどうかは問うてはいない。
ヒュームも上記大森氏の見解と似たようなことを言っていたと思うが・・・いずれにせよ、私たちの日常的経験を検証していく、それが経験論であり、そこから乖離した抽象的な話をいくら続けたところで、結局そこには何の根拠も見いだせないのである。
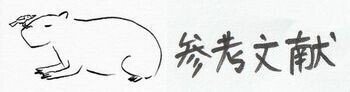
経験とは?経験論とは?
http://miya.aki.gs/miya/miya_report19.pdf
「実物ーコピー」という見解は「二元論」なのではなく、因果関係の問題(ブログ記事)
