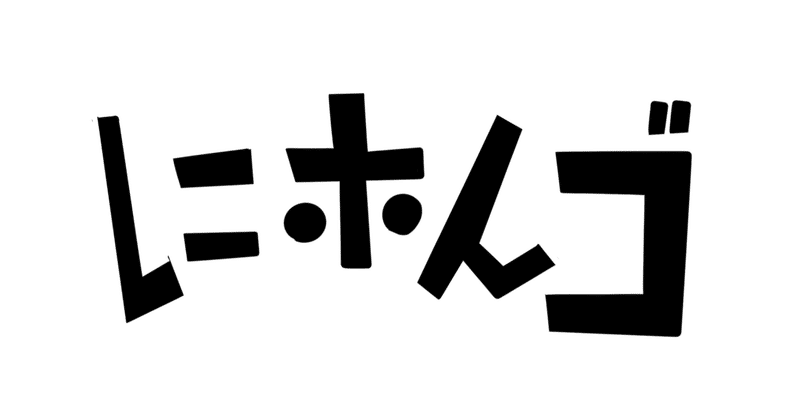
日本語ボランティアを始めてみた(オノマトペの種類)
2回目のボランティアに行ってきた。一週空いてしまったのは無念である。寒暖差に負けた。
それで、2回目のボランティアの報告である。
感想は、日本人より日本語に詳しいな、である。
主なボランティアの内容は、フリートークで変な日本語を直してほしい、とのことで、適当な話題探しからスタート。
相手はN1の資格持ち。普通に考えて「上手なのでは?」と思ったので、何で勉強してるの?と聞いてみた。そうしたら、返答は「知識はあるけど、能力がないから練習したい」とのこと。
「とくに、擬声語や擬態語が難しい」
と続けられて一瞬、思考が止まった。
擬音語は分かるけど、擬声語とか擬態語なんて日本語あったっけ?
慌ててスマホにお世話になる。
結論、擬声語擬態語という日本語はあった。
私より日本語に詳しくない?というか、意識して使ってないから難しいと言われても焦るな。
というわけで、改めて調べてみた。
擬音語などをオノマトペと呼ぶ。そのオノマトペは実は5種類に分類できる。
擬音語、擬声語、擬態語、擬容語、擬情語。オノマトペで一括りにしてたけど、正確には性格が違うらしい。
まず、擬声語。「わんわん」とか「こけこっこー」とか。次に擬音語。「ざあざあ」とか「がちゃん」とか。擬態語。「きらきら」「つるつる」とか。更に、擬容語。「うろうろ」とか「ふらり」とか。最後に擬情語。「いらいら」とか「うっとり」とか。
例を並べてみると、確かに性質が違うのが分かる。
日本語はオノマトペが多い言語である。資料によると韓国語の方が多いらしいが、言語的には多い方らしい。理由は、動詞の意味が基本的な意味しか持たず副詞で表現のバリエーションを増やすためらしい。
熟語の動詞になるとニュアンスが加わるけど、基本動詞はニュートラルな感じ。英語やフランス語を勉強していると動詞が沢山ありすぎて困るけど、日本語は動詞が少なくて困るわけだ。
となると、自然な日本語、上手な日本語にするためには副詞、オノマトペを使いこなせないといけない、ということか。
更にややこしいことに、同音異義のオノマトペが存在している。
例えば、「太鼓をどんどん叩く」と「日本語がどんどん上達する」といった感じである。
「どんどん」はまだ良い方で、「ごろごろ」なんてもっと凄い。
「猫がごろごろ喉を鳴らす」に「雷がごろごろ鳴る」、「目にゴミが入ってごろごろする」、「家でごろごろする」、「丸太がごろごろ転がる」…
日本語は同音異義語が多いとは聞くけど、そうか、オノマトペも同音異義があるのか…
こうして、一個賢くなった。次回は、日本語にまた詳しく成れそうな気がする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
