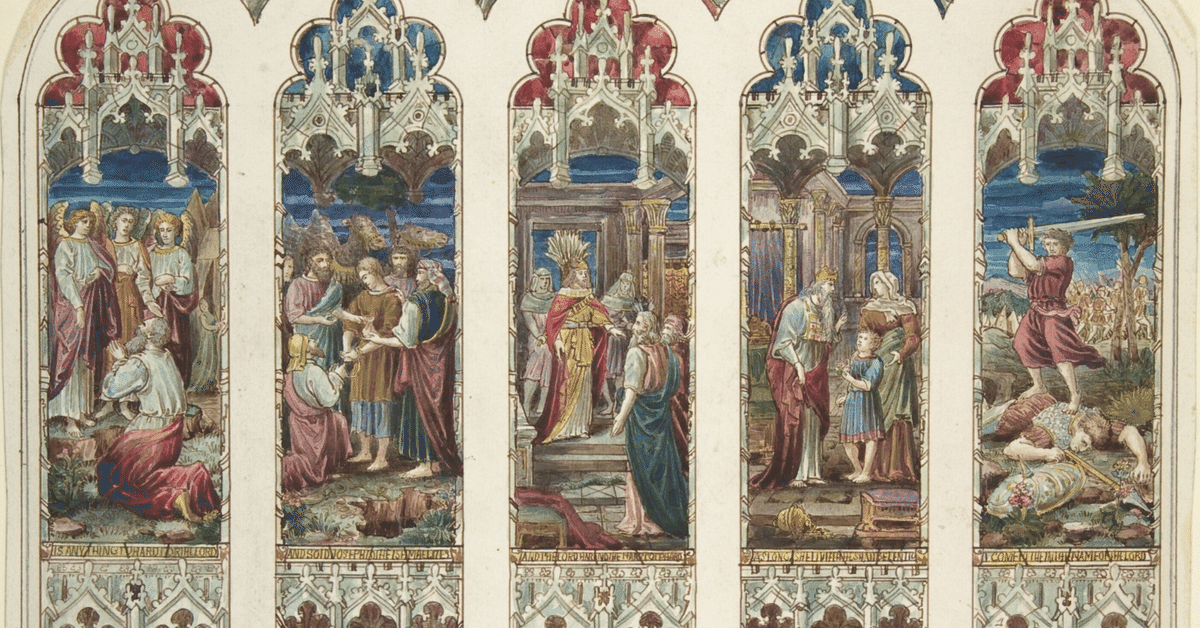
鋼鉄乙女のモン・サン=ミシェル戦闘記(61)
爆風がようやく収まったのは、数分が経ってからのことだった。
ビクリと身動ぎするたびに、少女の身体から土くれが落ちる。
動かないシュタイヤーを庇う体勢を崩さないまま顔をあげて、アミは瞳を見開いた。
まるで激しい空爆を受けたかのように、近くの家屋が全壊していた。
瓦礫と土と灰が、小山のように目の前に積み上がっていたのだ。
「ラ……ドム……?」
声は激しく掠れていた。
少年の姿はどこにも見えない。
助け出そうにも、この残骸のどこに埋まっているか見当もつかない。
「……気の毒ですが助かりはしませんよ」
《帝国の狼》の死を見届け、まるで呆けたようにガリル・ザウァーが呟く。
舞う土と埃に激しく咳込むその背中は、ひどく弱々しく見えた。
「ガリル・ザウァー、どうしてラドムを殺した……?」
「アーミーさん?」
汚れた顔を更に涙で濡らし、瞳を血走らせて睨みつけてくる少女から、ガリル・ザウァーは視線を逸らせた。
「気の毒なことをしました。《帝国の狼》のショットガンが彼を……」
「みんなを殺したことをバラされたくなくて、だからラドムの口を封じようと。そんなのひどいだろ。何でそんなこと……」
「アーミーさん!」
鋭い叱責が彼女の言を遮った。
「私の持っている銃はただの軽機関銃です。そんな威力はありません。あの子を殺したのはドイツ人です。考えたら分かる……」
しかしその言葉は、逆に少女によって阻まれる。
「たしかにその銃であの爆発は起こせない。でも、ピアノ線を撃ち切ることはできる。わたし、見えた。ガリル・ザウァーの銃がそこらの透明な線を撃って……」
奥歯を噛み締めるギリという音が響いた。
武器商人は硝煙漂わせるMG42の銃口を見下ろす。
第二七七歩兵部隊の上陸を見込んでこちら側の海岸線一帯に張り巡らせたピアノ線と、それに連動して爆発するブービートラップ。
「意外と目敏い……。何も考えないのが、貴女の良いところだったのにね」
──ああ、使えない腕で苦労して撃ったんですがね。
アミに聞こえないように小声で悪態をつくその姿に、善良な小動物の面影は残っていなかった。
「敵を殺すついでに、ラドムの口も封じたのか」
唐突に理不尽を感じて、アミは養父──少なくとも彼女にとってそれは事実だ──を睨みつける。
随所に張り巡らされた違和感という捩れが、一本の糸となる。
隠されていた真実が一気に描き出される感覚。
ガリル・ザウァーはずっと自分がドイツ人である事実を隠していた。
しかし《武器庫》の誰か──おそらくはユージン・ストナーとの連絡係であるロム・テクニカが、その秘密を知ってしまったのだろう。
ならばすぐに彼の母も知るところとなり、自分が追求を受けることになるのは目に見えている。
そうなる前に先手を打って彼等を殺した。
ガリル・ザウァーにとって、人生の目的がザクソニア・ロング=レンジの殺害という一個の事柄に集約される以上、《武器庫》の存在はすでに荷物になっていたのだ。
自身の片腕ともいうべきシュタイヤーと、盲目的に自分を信じるアミだけは戦力として残し、後はドイツ兵の仕業のように爆破した。
「ぜんぶ……全部話せ。ガリル・ザウァーがわたしの父親なのか!」
戯れにMG42の引金をひき、それがカチリという軽い音しか立てないことを確認してからガリル・ザウァーは弾丸の尽きた銃を放り捨てた。
ようやく己の右肩の異変に気付いたように、血液の溢れ出る箇所をハンカチで押さえる。
「全部話せと言われても……事実は単純です。アーミーさん、あなたとシュタイヤーは私の子。それだけです」
「シュタイヤーも? じゃあ……」
腕に抱えたままの男を見下ろす。
──あまり似てませんが兄妹ですよ。
人ごとのようにガリル・ザウァーは告げた。
──事実は単純です。
同じ台詞をもう一度繰り返す。話せと言うなら話しましょう、と。
「国籍について意識したことはありませんが、ええ、仰るとおりドイツ人ですよ。私は医者で、ドイツ軍の新兵器開発に関わっていました。開発中のその義手の実験のため、幼かった貴女の腕を切断したんです」
「怪我をしていたから仕方なくって言ってたじゃないか。実験のために……ガリル・ザウァーが、わたしの右腕を切断?」
「貴女は親孝行な子でしたよ。義手は順調に順応し、実験は成功をみせました。その二年後には左手も取り替える計画が持ち上がったんです。ところが切断手術の前日です。貴女の母親が、貴女とシュタイヤーを連れて国(ドイツ)を逃げ出した……」
あとは説明を受けるまでもない。
ガリル・ザウァーとともにそれを追ったのが目の前の死体──ザクソニア・ロング=レンジだったのだ。
全員生かして連れ帰る約束が、トラブルがあってアミとシュタイヤーの母はザクソニアに殺されたという。
憤ったガリル・ザウァーはシュタイヤーとアーミー、二人の子供を連れて難民のようにフランスへ逃げてきたのだ。
「妻を手にかけたこの男を殺し、ドイツ人すべてを殺し……あの国を滅ぼすために私は今まで……」
そこでガリル・ザウァーは娘の腕をつかんだ。
握られた手が血に染まっていることに、アミは嫌悪の叫びをあげる。
反射的に振り払った手を、拳の形に握り締めた。
「アーミーさん? 戦いはまだ終わってはいません。貴女は私を裏切ったりはしませんよね」
「さ、先に裏切ったのはガリル・ザウァーの方じゃないか」
握り締めた右拳がふるふると震える。
彼女の肩からも留め処なく赤の雫が零れ落ちていた。
幼かった自分が、父親によって腕を切断され実験材料にされたということ。
何年もの間、嘘を付かれ続けていたこと。
──そんなことは今更どうでもいい。
「その手は何ですか? 一時の怒りで私を殺しますか?」
「い、怒りじゃない」
どんなに恨みが蓄積しようとも、彼女が自分に手をあげることはない。
そう確信しているかのように、ガリル・ザウァーは落ち着き払っていた。
「怒りなんかじゃない……!」
血を吐く叫びは目の前の男には届いていないように感じられる。
アミは思う。
自分のことはどうでもいい。
ただ、シュタイヤーを見捨てたこと。
《武器庫》の仲間たちを殺したこと。
関係ないラドムに銃口を向けたこと。
それが許せない。
──いや、そんなことだって、どうでもいいんだ。
余計な力が右手から抜ける。
拳の震えが止まったことを少女は自覚した。
目の前にいるガリル・ザウァーをまっすぐ見つめる。
父親である男と絡み合った視線を逸らせることなく、彼女は右腕を突き出した。
「わたしがこうするのは、ガリル・ザウァー……あなたの憎しみを終わらせるためだ」
右拳が肉を裂き、心臓を潰す。
その弾力と衝撃を全身に覚えて、少女はその場に倒れ伏した。
──ぴしゃり。
湿った音をあげて自らの血だまりに倒れ込むガリル・ザウァー。
その気配を隣りに感じて、アミは右手を伸ばす。
彼が絶命したのは分かった。
血塗れの手で触れた父の頬。
己の腕──その金属の冷たさがガリル・ザウァーの身体を凍らせていくようで、彼女は慌てて手を除ける。
「せめて仰向けに倒れたらよかった……」
そうしたら空を見ながら死ねるのに。
心は死んでしまった。
もう動く力も残ってはいない。
地面を舐めるような体勢で、このまま死んでいくのは少々不満だったが、それも仕方ないのだろう。
何故なら自分は沢山の人を殺してきたから。
そのくせ大切な人ですら守れなかったから。
だから救いなんて、訪れるはずがない。
涙が地面を濡らした。
全身の痺れを自覚する。
──このまま、早く死んじゃいたい……。
そう思った瞬間、彼女の視界は輝く白に染まった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
