
業平 高樹のぶ子氏著 他
三連休は雨、雨が止んだかと思うと強風で自転車で外を走れない日々でした。
しかし、そんな休日は読書と珈琲日和でもあります。
何冊か読んだ中でご紹介するのが高樹のぶ子氏著の「業平」。在原業平を主人公とした小説です。読んでいる間、そして読後も大らかで優雅な心地に浸れる名著でした。
日本人であれば在原業平という名は歴史に興味がなくて詳しくは知らなくても聞いたことはある名前でしょう。そして在原業平の名前すら知らなくても、次の百人一首の歌の初句はご存じなのではないでしょうか。
ちはやぶる 神世もき聞かず 竜田川 からくれなゐに 水くゝるとは
映画のタイトルにもなっていましたね。
私は、子供の頃から平家物語が好きで、保元平治の乱から承久の乱に至る時代に関する本はたくさん読んでいたのですが、正直申しますと在原業平とその時代についてはあまり関心がありませんでした。少し前の時代の人としては空海は、その戦略的思考と天才、墨跡に惹かれて信仰の対象としてではなく人物として尊敬していますし(年末の帰郷時は毎年、九度山から奥の院まで散策します。)、最澄との関係、また嵯峨帝までがかろうじて関心の対象でした。
そんな中、今年に入ってA&Yというpodcastの中でAsami氏がお薦めのコミックとして紹介された灰原薬氏の「応天の門」にはまってしまったのです。
主人公は菅公 菅原道真ですが、その歳の離れた友人(?)として在原業平が何とも憎めない魅力的な人物として描かれています。もちろん、小説にせよコミックにせよ伝記ものは主人公とその周辺の人物を魅力的に描くもの、実像からはかけ離れているかもしれないのですが、興味を持って欠落していた桓武帝以降の平城帝、嵯峨帝、薬子の変から応天門の変、菅原道真の太宰府左遷までの期間の歴史を調べてみました。これが不謹慎かもしれませんが面白い。
この時代には富士五湖、樹海が生まれるきっかけとなった富士山噴火も起こっているのですよね。
在原業平が平城帝の嫡子で廃太子された阿保親王の子であることもこの過程でようやく知りました。
「業平」では、そんな生い立ちや多く残されている歌を素材として、えも言われぬ韻を踏んだ魅力的な文体で描かれています。
今の京都にはこの時代の建物は何一つ残っていません。市内で一番古い建物が確か山科にある醍醐寺五重塔ですしね。しかし、ワクチンを打って落ち着いたら、十輪寺や奈良の不退寺などゆかりの地を歩いてみたいと思います。
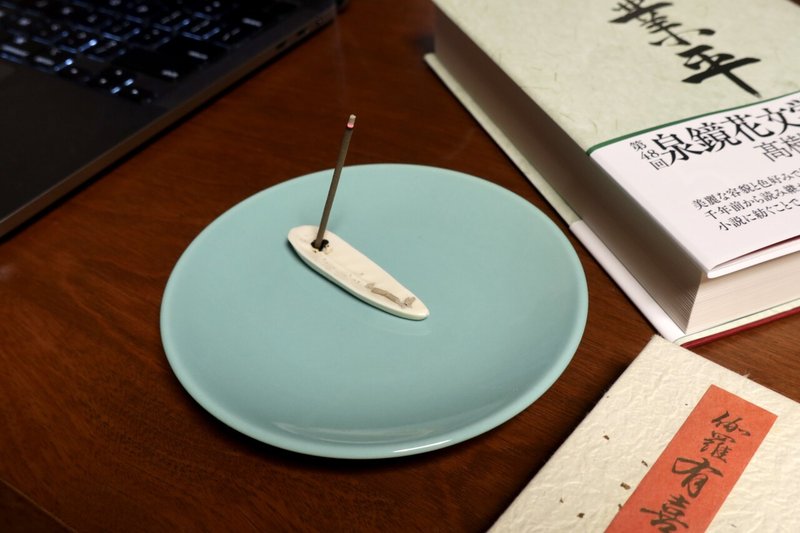
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
