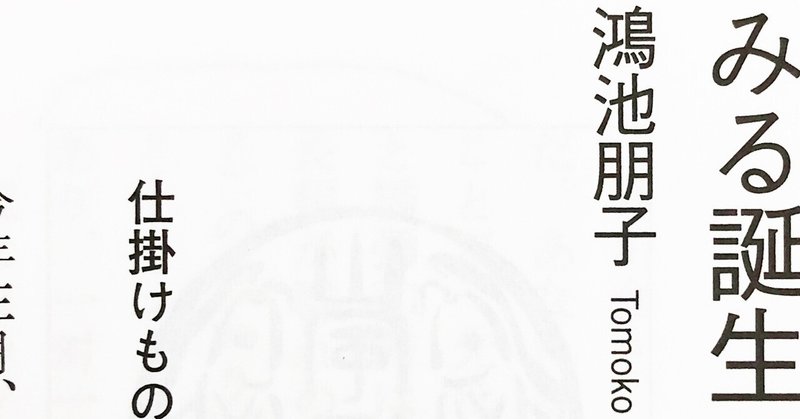
手でみるー鴻池朋子「みる誕生」を読んでみた
私はアートとは縁遠い生活を送ってきていまして、現代アートが何をしているのか、ほとんどわかっていません。
そんな私が一人の現代アーティストの文章と出会いました。
その文章は、定期購読している雑誌にたまたま掲載されていました。
こういう偶然があるから雑誌はやめられません。
出会ったのは鴻池朋子の「みる誕生」。
雑誌『ゲンロン13』(2022年10月)に掲載されていました。
読むと、アーティストが何をやろうとしているのか、ちょっとだけわかったような気がしました。
それは、純文学作家のやろうとしていることと似ている感じがしました。
今回はこの「感じ」を記事にしたいと思います。
動線をみる
…展覧会で一番に時間をかけてきたことといえば、それは「動線」。展覧会とは、外から何かがやって来て、中を通って、そしてまたでて行くこと。…そのルートは建物の入り口から、最寄りの駅から、もっと遡れば何かが家をでるときから、眼に映っている機能的に構造化されたものとは違うインフラをデザインする。動物が川に水を飲みに来られるように。
いくらアートに縁遠い私でも美術館にはたぶん20回くらい行ってます。
特に知識もないのに行ったのは…アートがわかるとカッコいいんじゃないかと思っていた時期があったような気が…(恥
しかし、動線、一度も気にしたことありませんでした。
ポイントは現実とフィクションの境界をどうつくるか、
機能的に構造化されたものとは違うインフラをどうつくるか。
まず現実とフィクションの境界について考えます。
純文学作家はどう言っているか。
「コンサートに行くんだ」と思って家を出て電車に乗ったときには、まだ他の人たちと同じ顔をしている。しかし、すでに「コンサートに行く」という特殊な時間は始まってもいる。…コンサート会場に近づくと、自分と同じ足取りの人がいっぱいいて、ダフ屋もあちこちに立っている。そして、いよいよチケットを渡して会場に入り…という一連の流れがあるから、会場の照明が落ちた瞬間に…それまでの流れがあるからみんなが反応する。…現実からフィクションに入っていくという意識をそれぞれの人で持つようにしてほしい。「はい、小説です」と言って差し出せば、誰もがそのまま素直な読者になってくれるわけではない。
現実からフィクションへどのように誘うか。これについては今回召喚したアーティストも純文学作家も具体的な方法を明らかにしていません。しかし重要なのは間違いなさそうです。
そいえば落語のマクラも同じような目的だったような気が。(ちなみに落語の知識もほとんどありません。)
アートも純文学も人間の認知に関わっていると思うのですが、そうすると現実と虚構の境界は彼らの取り組みのど真ん中なのでしょう。
つづいて機能的に構造化されたものとは違うインフラについてです。
文学では機能的に構造化されたものといえばストーリーではないでしょうか。
人がストーリーの展開を面白いと感じられる理由は、展開が予測の範囲だからだ。その枠をこえた本当の予測不可能な展開だと、感想以前の「???」しか出てこず、面白いどころか、「意外だ」と感心することすらできなくなる。
保坂は例を挙げています。
野球は何が起こるかわからないというけれど、マウンド上でマグロをさばきはじめたりはしないといいます。
つまり予測の範囲内のことしか起きえない。
そしてどうやら文学の、小説の本質らしきものについて語ります。
…小説も同じことで、読者が日常使っている言葉や美意識と完全に重なり合わないものを積み重ねていく、そのプロセスの中にしか答えはない。
つまり読者の今までの認知とはズレているものを提示すること。提示しつづけること。
私(保坂)にとって「面白い小説」とは、最初の一行を読んだら、次の行も読みたくなり、その行を読んだらまた次の行も読みたくなり…という風につながっていって、気がついたときには最後の行まで読んでいたーそんな小説のことだ。
どうもストーリーを重要視していないようなのです。
保坂の「面白い小説」とは認知のズレを表現しているもののこと。
これがアートにも言えるのだとすれば、私のような鑑賞者の心得は次のようなことになるでしょうか。
まず会場に入る瞬間に集中すること。現実との境界に感覚を研ぎ澄ますこと。そしてわからないこと、違和感のあることを感じること。たぶんそれがサイン。
そして、わからないことと、違和感のあることを感じることは、入る瞬間だけでなく、鑑賞全体について継続すること。
しかし、それだけでは不安です。結局、よくわからないという結果になりそうなきが気がします。
もう少しヒントがないか探します。
二重にみる
鴻池は展示会場に作品を設置しようとしている日に、奇妙な経験をしています。
実際に自分がいる美術館の展示室と等身大の自分、つまり網膜が光を感知し実際に眼に映っている画像と、さらに模型の中から模型内を見回しているもう一つの別の画像…が同時に見えている、起こっているのだ。…奇妙すぎる。けれど、これは何かとっても大切な、小さな、今にも消え入りそうなことだったので、私が驚きすぎてそのささやかなものが逃げていってしまわないよう、気持ちを呑み込んで静かに息を整えた。…
眼では見ていない。光の明暗ではない。光を必要としていない者たちが見て、診て、看て、観て、視ているビジョン。私の「見る」は眼だけではない!
現実を二重にみているようです。一つは常識的な見る、視る。もう一つは非常識的なミる?
では純文学者はどう言っているか。今度は別の小説家を引用します。
わたしは、さっき、この部屋の電気を消しました。部屋は完全に闇に包まれています。
わたしは、時々、こうやって闇の中に座り、何時間も過ごすのです。
最初のうちは、なにも見えない。…
目を見開いてもなにも見えない。
耳をすましても、なにも聴こえない。
実は、これこそ、ものを考えるのに、いちばん適したやり方なのです。そう、これはヘレン(・ケラー)が長い間住んでいた世界、小説を書くために一度は住まなければならない世界でもあるのです。…
あなたが最初にやらなければならないのは、知識をぜんぶ、いったん、忘れてしまうことです。なぜなら、あなたは感受性をとぎすまし、こうやって、暗闇の中で目を見開き、沈黙の中で耳をすまさなければ、小説をつかまえることができないからです。…
し、静かに。そんなに騒いでいては、あなたの小説が、通りすぎていってしまうではありませんか。
鴻池も高橋も対象のとらえかたがそっくりです。
目と耳以外の感覚をとぎすまさなければならない。鴻池は引用とは別の箇所で「美術館では視覚と聴覚をコントロールしやすい」(127P)とコメントしています。そして、鴻池も高橋も騒ぎすぎては逃げていくと同じような表現をしています。
視覚と聴覚はすぐに他の感覚を排除できるほど強力なのですね。
ではどうやって目と耳以外の感覚をとぎすますのか。暗闇にいれば何とかなるのでしょうか。
(…いったいなにを書けばいいのかを)徹底して考えてみる。考えて、考えて、どうしようもなくなったら、まったく別の角度で考えてみる…世界を、まったくちがうように見る、あるいは、世界が、まったくちがうように見えるまで、待つ…簡単にいうなら、他の人とはちがった目で見る、ということです。そして、それは、徹底して見る、ということでもあるのです。なぜなら、ふつうの人たちは、ふだん、なにかを、ただぼんやりと見るだけで、ほんとうはなにか、とか、そこにはなにがつまっているのか、とか考えたりはしないからです。
暗闇で徹底して見る、別の角度で考えてみる、あるいはまったくちがうように見えるまで待つ。
暗闇で見る?
どういうことでしょうか。
手でみる
そういえば20世紀を代表する哲学者の一人、ジャック・デリダも目と耳の間の空間について哲学したのでした。
目と耳以外の空間には、未開拓の豊穣な世界が広がっているのかもしれません。
鴻池は、手でみることによって豊穣な世界をつかまえようとしているようです。
手は光を経由しないルートを持っている。全体などなく、指が触れたところから、少しずつ端っこからこの世界は形になっていく。ゆっくりと、手は恐る恐るあたりの気配を確かめながら、舞うように探りながら、ともに果てしなく迷う時間を歩いて世界を形にしていく。
そろそろ眼は手の力を借りながら、その絶大なる特権を他の感覚器官と交換、分配し合うときに来ているように思う。…様々な感覚が、光を経由するだけではない小径を通って協力してくれたら、その地上の物たちが持っている根源的な暴力はいかようにも、喜びにさえも変換できる。
手でみる、肌でみる、鼻で、口で、舌で、全身でみる。
なるほど。まずは鼻でみるのが無難でしょうか。とりあえず接触がないので。次に肌または手からみるのが良さそうです。でもちょっとだけ危険そうです。
そして舌。かなり勇気が必要な気が…。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
