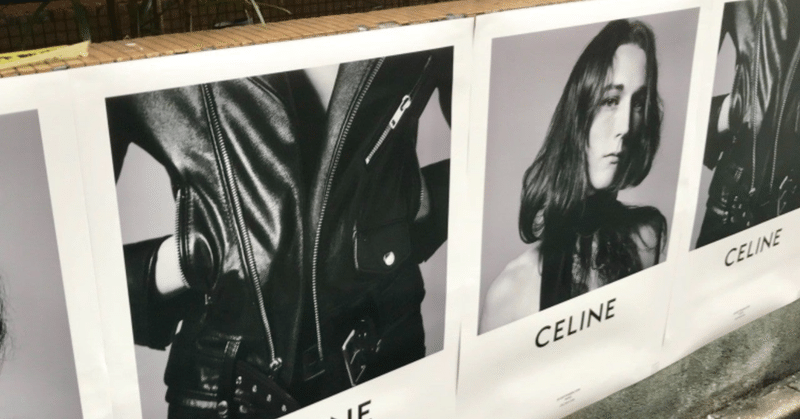
コマ割りが視線誘導のためにあるというワケ
マンガに必須のコマ割りというものの機能は、ひとえに視線誘導にある。ただ1つのイラストではない動きを伝える「漫画」という表現方法において、複数の「コマ」は最適である。だが、コマはただ置いてあれば良いというわけではなく、即ちそれは単なる区切りではなく、どのように動きを見て行ってほしいのかを示す道具なのだ。
技法・手法と言っても良い。それだけ、漫画におけるコマ割りはなんとなくではない、理論的に実現されるものだ。読者がどのようなテンポで漫画を読むのかを決める。それをまさに視線誘導と言う。
より詳しく言うならば、誘導とは読者がどこを見始めて、どこを見終わって次のページに行くのかをデザインするということである。もちろんそのためには、物語的な展開(起伏)と、視線移動が中断するタイミング(ページなどの区切り)が決められていなければならない。
そういったルール、枠組みそれぞれの中で、コマ割りはなされていくものである。たとえば、もっとも注目させたいイラストがあればそれは大ゴマに配置されるだろう。あるいは時間経過が表される場合、コマが細切れになったような表現がよく使われる。
これらのコマがどうして、そういった形や大きさになっているのかといえば、物語的にしっかりと読者に印象付けたい部分と、そうではなく流れでスルスルと読み進めてもらいたい部分、加えて、見るのをやめてページを捲ったりスクロールしたりする部分というのが、きちんと定まっているからである。
それらは総称してテンポ感と言って良い。しかし、単にテンポ感が良いという意味でのそれではない。同じ大きさのコマが並んでいるのだって、テンポ良く読んでいけるはずだ。でもそれをしない理由は、注意を集め、もしくはそらすことができるからである。
これが物語的な緩急とマッチすることによって、まさに漫画表現として完成される。
そういう技法として培われてきた1つの結果が、漫画におけるコマ割りという名の視線誘導である。
※このテーマに関する、ご意見・ご感想はなんなりとどうぞ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
