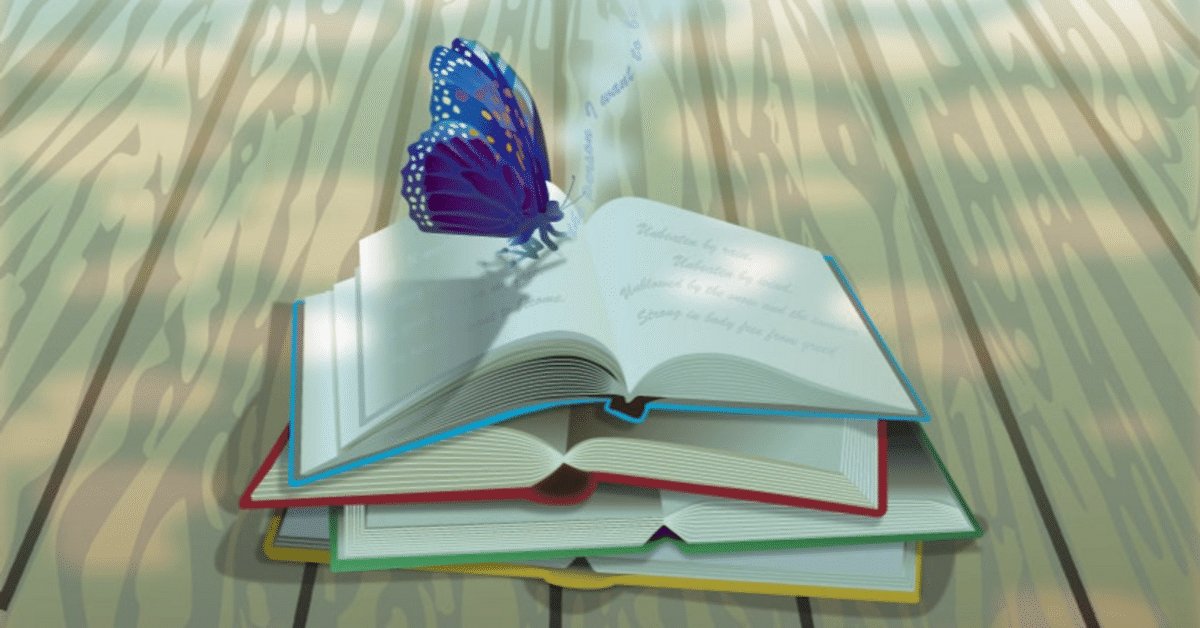
結素理論:システムにおける結素
はじめに
昔の事を記事に書く機会がありました(参照記事1)。その中で、私の昔からのポリシーの1つ「最小の努力で最大の成果を得る」の事を書いた時に、ふと、これがシンプルさを生み出す要因になると気が付きました。そこに着想を得て、結素(ゆうそ)/Simulという用語を定義して、それを軸にした考え方を整理していこうとしています(参照記事2)。
結素(ゆうそ)は、1つのものや事象で2つ以上の利点がある、というものです。簡単に言えば、一石二鳥、一粒で二度おいしい、そういうものです。
結素に着目すると、それがシンプル化に大きく貢献することが分かります。例えば、1つの道具で1個の機能しかなければ、10個の機能を実現するために10個の道具を用意しないといけません。けれども1つの道具で2個の機能があれば、10個の機能を実現するのに5個の道具で済みます。結素がシンプルを生み出しています。
この記事では、システムを対象に、結素が果たす役割や特性を書き下していきます。
システムにおける結素の直接の効果
結素は、システムに対して以下の直接的な効果を持ちます。
1. 効率性:結素は1つのものや事象で複数の機能や価値をもたらしますので、エネルギーやリソースの使用を効率化します。
2. ロバスト性:結素は1つのものや事象で複数の機能や性質をもたらすため、要素が多くあるシステムよりも壊れにくくなります。また、環境の変化や、自分自身の変化に対して、適用できる可能性が高くなります。このように、結素はシステムにロバスト性を与えます。
3. 交換性:要素が少なくて済むため、システムを別の場所に移動させることが容易になります。これは少ないエネルギーで済むという点の他に、移動中にシステムが壊れにくいという事も意味します。
4. 生産性:要素が少ないため、再生産したり、複製したりする際にも有利です。このため、システムの増殖に有利です。
また、結素の中には、システムにとって特別な効果を持つ結素があります。それは、複雑に進化し発展したシステムの機能を生かしたまま、一定の秩序をもたらしてシステムの拡張性を確保するという2つの利点を実現する結素です。
一般的にこうした結素は、システムに仕切りを設けるようなものです。仕切りの内側に複雑な機能を内包しつつ、仕切りの外の環境とはシンプルな規則でやり取りすることを可能にする。このような結素が出現すると、システムはそれまでの機能を活かしたまま、新たな進化や発展を推し進めることができるようになります。
自然システムの発達段階における結素
自然界における結素の役割
自然界の生み出したシステムとして、生命誕生以前の有機物の化学進化システム、生物、知能などがあります。これらの進化と発展において、結素は本質的な役割を果たします。
自然界は、揺らぎやランダム性を持ち、空間と時間の広さを使って、要素の様々な組合せを試行することができます。
この試行の中で、結素が発揮される組み合わせにあたると、効率性とロバスト性を持つ要素が生まれます。通常の自然現象は、時間と共にエントロピーを増加させていく傾向にあります。一方、結素が発揮される組み合わせができると、その周囲はエントロピーが下がります。その一方で、エネルギー効率は改善します。これにより、段階的に新しい組み合わせで新しい結素が見つかっていきます。
このように、結素を中心としたシステムは、周囲の環境からエネルギーや要素を取り込み、エントロピーを下げながら自然に「落下」していきます。この「落下」が繰り返されることで、結素を中心としたシステムは進化します。そして空間内の複数のシステム同士も結素によって多角的に結びつき、総体として発展していきます。
また、システムが進化し、総体として発展することで、多様化して複雑なものになっていきます。結素はシンプル化の効果がありますが、それでも結素が多角的に組み合わさっていけば複雑さが増大します。そうしてシステムの総体が成熟すると、それ以上の進化や発展が難しくなります。
しかし、結素の中には、機能を維持したまま、拡張性を高くする、という2つの性質を持つものも存在します。これは通常、複雑で高度な機能を持った要素の凝集部分と、周囲との間に仕切りを設ける形で実現される結素です。その結素には、単に閉じ込めるだけでなく、必要なエネルギーや要素の交換はできる仕掛けも必要です。これによりシステムの内側の機能も維持しながら、総体としての機能も維持されます。
このような特別な結素が現れると、システムおよびその総体は、内側に複雑で多様な機能を維持しながら、仕切りの外側から見るとシンプルさを取り戻します。そしてシンプルさを取り戻したことで、システムおよびその総体は、エントロピーを下げる方向へと再び勢い良く「落下」していきます。
知覚と結素の関係
生物は外界を知覚して反応する能力を持っています。
外界からのある刺激を受けたら、どのような反応をするかは、基本的には遺伝子に本能として刻まれています。Aという刺激があった時に、そのAの方に近づくという反応をする種と、Aから遠ざかるという反応をする種で、生存能力が高い方が生き残り、低い方は消えていくことになります。この刺激に対する反応が、遺伝子に刻まれるわけです。
この過程についても、知性がなくても実現できます。刺激に対する反応は遺伝子の変異でランダムに生成され、自然淘汰により適した遺伝子だけが残りやすくなります。
ここでもし、Aという刺激に対して遠ざかることが生存のためには正解だとして、その時に可能な限りエネルギーを使用しないような遠ざかり方が出来れば、より生存には有利でしょう。この反応の仕方は、Aという刺激がもたらすリスクから遠ざかりつつ、ついでにエネルギーも温存できるという2つの価値を持ちます。
そうです、これが生物の知覚と反応における結素です。この結素は、遺伝子に刻まれて子孫に継承されていきます。
学習と結素の関係
生物が知覚に対して反応するやり方を変えるのは、遺伝子の作用だけではありません。高度な生物は学習することもできます。
学習も同じように、知覚に対する反応の仕方の中で、最も自身の生存に有利な反応の中から結素を見つけていく過程です。高度な学習ができる生物は、多様かつ多数の刺激に対して様々に反応し、その中で結素を見つけて身に着けていきます。
この時、単にランダムに反応を変化させてその中からたまたま見つかった結素を見つけているのかもしれません。あるいは、結素を見つけやすくし、記憶に残しやすくし、反応として採用する割合を高くしたりするような何らかのメカニズムがあるかもしれません。そのような仕掛けがあれば、素早く効果的な学習が実現でき、生存に有利に働くでしょう。
意識と結素の関係
人間は、意識的に結素を組み合わせて、表現や道具を設計(デザイン)します。人間の脳は、結素を処理するのに適しているのです。
人間の脳は、結素を発見して抽象化することができます。そしてその結素を同じ分野の別の個所に転用したり、別の分野に応用できる能力を持っています。人間は結素を見つけ、加工し、適用する事で、様々なことを効率化しつつ、創造性豊かに様々なものを作り上げています。
人間が結素を操るこの能力は、自然界や人間以前の生物には存在しなかった能力です。この能力は、継承や学習よりももっと素早く深く新しい結素を作り上げます。
また、人間の意識は、一見関連性のない分野同士で結素を交換することを可能にします。これにより結素は時間や空間だけでなく、分野やスケールを超えて多義的に存在することになります。また、人間の意識によって複製されることで、結素はその存在範囲を広げることができる、とも言えます。
結素の分類
形式的結素と不定形の結素
結素には形式的結素と不定形の結素があります。それぞれ以下の特徴を持ちます。
形式的結素:
しっかりとした形や構造がある。
形式的結素同士を組み合わせて新しい結素を作ることが容易にできる。
言葉や図表で表現できる。このため他者と交換が容易にできる。
不定形結素:
形や構造があいまい。確率的であったり形状や構造に可変性がある。
組み合わせて新しい結素を作ることは難しい。形や構造の維持の度合いによる。
言葉や図表で表現することは難しい。このため他者から直接獲得することは難しく、経験的に把握する事しかできない。
普遍的結素と局所的結素
結素には普遍的なものと、局所的なものがある。おそらく絶対的な普遍性はないため、普遍的といっても完全な普遍性までは求めていません。
普遍性の高い結素は、様々な場所や時間、分野で登場します。このため意識にとって発見が容易であるという特性があります。そして、意識によって別の個所や別の分野に複製可能です。こうした面から普遍的な結素は、高い増殖性を持つとも言えます。
一方、局所的な結素は、特定の分野の特定の個所でのみで存在したり、いくつかの限定された範囲でのみに存在したりします。普遍性を持たないという事は、複製や増殖が出来ないため希少性があります。かつ、失われると二度と取り戻せないという意味でも、特別な価値を持ちます。
シンプルな結素と複雑な結素
形式的でも不定形でも、普遍的でも局所的でも、結素にはシンプルなものから複雑なものまであります。
シンプルな結素は、複雑な結素と比べて、他の結素と結合しやすいという特性があります。複雑化すると、それだけ他の結素と組み合わせた時に副作用が出やすくなり、結合が難しくなります。
意識における結素の分類の意味
自然科学分野における結素は、概ね形式的かつ普遍的な結素を扱います。そして、シンプルな結素から基本原理や法則、定理や公理を導いて、できるだけ少ない結素で多くを理解しようとします。
また、工学の分野では、これらの形式的かつ普遍的な結素を組み合わせて、様々な道具や構造物やシステムを設計します。よく言われるように、自然界の観察から得られた結素を、全く異なる分野の設計に持ち込むこともあります。
こうして結素を組み合わせて設計することで、多機能でありつつ使い勝手やメンテナンス性に優れ、それでいて製造が容易で低コストで効率が良いようなものを作り出すことができます。かつ、とても一人だけでは作り上げることのできないような大規模なシステムまでも、大人数で分業して設計する事すら可能にします。
形式的かつ普遍的な結素を扱うからこそ、こうしたことができるのです。
一方で、人文科学の分野では、不定形かつ局所的な結素を扱います。文化的なものはその地域の人にとってはとても価値がありますが、別の文化圏の人には全くその価値が理解できないという事があります。また、人間の心や感性に訴える芸術作品も、人によって共鳴度が大きく変わります。
そして、文化や芸術は、その表現を複製することは容易ですし、様式を真似ることもできますが、その真価を発揮して人を豊かな気持ちにしたり人の心を震わせるのは、「本物」にしかできません。不定形の結素の本質は、いくら表現や様式を真似しても、複製することはできないのです。
このため、複製ではなく体得するよりほかありません。例えば、ピアノの曲の練習において、そこにある神髄のようなものを身に着けるということを強く意識しながら練習した人と、単になめらかに上手に弾くことを目指して練習した人を想像してみて下さい。最終的にその曲の演奏の上手さにはそれほど変わりはないかもしれません。しかし、本質的な結素を獲得できるかどうかという点で、前者の方が、より人を感動させるメロディーを奏でられるようになっているのではないかと思います。
さらに、社会科学の分野において、社会の中での結素は、常に形式的結素と不定形の結素の両面が存在することを示唆します。同様に、普遍的結素と局所的結素の両方が入り交じっていることも認めています。例えば経済の分野であれば、形式的な形で価値の交換が行われることを認める一方、不確実性や外部不経済のような不定形の要因の考慮が行われます。また、経済主体は合理的な行動をとるという普遍性を持たせつつ、その主体の選好は多様性を持つという形で局所性も認めています。
この他、法律や組織経営のような分野でも、こうした異なる分類の結素が同居していることを前提にしていることが分かるでしょう。これは社会を構成している個人が、本質的には複製も代替もできない不定形で局所的な結素の凝集体でありつつも、社会化により一定の形式的で普遍的な結素を学習してその内側の凝集体を隠蔽したカプセルでもあるためです。
さいごに
結素(ゆうそ、Simul)のフレームワークで掘り下げていくと、この記事に記載したように、様々な事象を新しい視点でありつつも、鮮明に分析することができます。
結素の重要性に気が付いたのは、ほんの二日前です。しかし、参照記事2の末尾に記載した通り、このアイデアは新しい知の地平線を切り開いていける力を感じます。また、長くなるためこの記事では書き出せませんでしたが、結素で説明できることはまだあります。次回の記事では、結素を見つけて活用する脳の仕組みについて、記載しようと考えています。
参照記事一覧
参照記事1
参照記事2
サポートも大変ありがたいですし、コメントや引用、ツイッターでのリポストをいただくことでも、大変励みになります。よろしくおねがいします!
