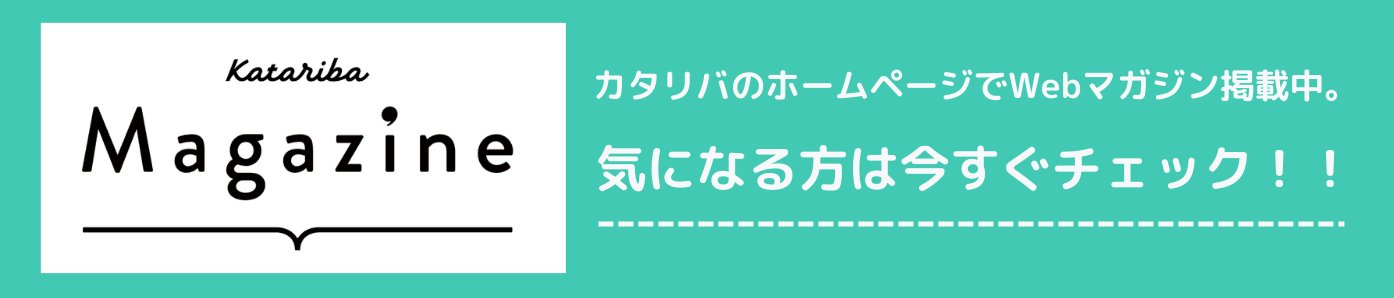「『ねばならない』がないところ。」学校でも家庭でもない、中高生のための"サードプレイス"
はじめまして、カタリバで b-lab(文京区青少年プラザ)の運営に携わっている横田です。(カタリバはニックネームで呼び合う文化なのですが、ぼくは「よこしん」とよばれています)
「現場で10代の居場所づくりに関わりたい」と新聞記者を退職して1年半。これまでb-labで、学問やスポーツ、音楽を通した関係づくりや、最前線で中高生と関わる学生ボランティアの育成などに関わってきました。
b-labは、日本を代表する「ユースセンター」のひとつ。この言葉は耳慣れない方も多いと思いますが、中高生(ユース)にとっての、家庭でも学校でもない自由な第3の居場所(サードプレイス)であり、活躍の舞台です。現在は、そうした「ユースセンター」と呼ばれる場所を全国に広めようと、国内のユースセンター同士で連携してその価値や魅力を発信する動きも始まっています。
この記事では、3月に開催したオンラインイベントで中高生やスタッフが語ってくれた言葉から、「ユースセンター」という居場所の価値について考えたことを書いてみたいと思います。
「#ユースセンターがある生活」3月に中高生と価値発信イベントを開催
2022年3月21日、b-labは兵庫県尼崎市の尼崎市立ユース交流センター(運営:尼崎ユースコンソーシアム)との共同イベント「#ユースセンターがある生活」を開催しました。

コロナ禍でオンラインイベントの文化がずいぶん拡がりましたが、500km離れた2拠点から、職員や中高生が一堂に会し、ユースセンターで得られる体験について語り合えるのも、オンラインならではですね。
まずはふたつの施設の館長が、それぞれ施設の概要を紹介。館内を歩いて中継しながら、どんな場作りをしているのか、現場の実際の様子をオンラインツアー形式で伝えました。
施設を紹介する2人の言葉に共通していたのは、「やってみたいをやってみる場所」ということ。「中高生スタッフ」「ユース運営委員会」といった、中高生自身が大人と共に悩み、議論しながら場所を作っていく仕組みも明かされました。

「ここでは全く否定されない」中高生が見たユースセンターの価値
このイベントの目玉は、施設を利用する中高生たちが職員と意見を交わしたディスカッション。普段は利用者、ときには運営側として、スケボーや謎解き、イラストなどそれぞれの得意分野で活躍している中高生たちがスピーカーとして登壇しました。
「ユースセンターの価値は?」
この直球な問いに対して、まずb-lab副館長でユースワークに定評のあるスタッフあっくんは、「『ねばならない』がないところ」と即答。
それにつづけて、b-labを利用する高校生のひびきちゃんは、「ここでは全く否定されない。スタッフに相談しても、解決方法じゃなくて選択肢をくれる。そして、色んな考えを持ったスタッフがいる」と語ってくれました。
ほかにも、
(イベント企画時に)どうやったら人を楽しませられるかを意識するようになった(b-lab利用者ふうちゃん)
たくさんの人と話す中で、考え方の違いを理解できた(b-lab利用者たいようくん)
ユースに来てからは、失敗も良い経験だからどんどんチャレンジしようって思えた(尼崎ユース交流センター利用者かりんちゃん)
など、利用者の中高生たちも自分の視点から、ユースセンターで過ごした時間を振り返り、価値を言葉にしてくれました。

"ねばならない"をとっぱらえる場所
普段は学校で、校則や勉強、部活など「規範(=ねばならない)」の中で生活しながら社会性を身につけていく中高生たち。
その「ねばならない」を一回とっぱらって、「何をやっても良いし、何もやらなくても良い場所」がユースセンターです。学校などの同質性の高いコミュニティから抜け出して、普段は出会わないような大人や他校の子たちと出会いながら、自分らしくのびのびと過ごしたり、新しいことに挑戦したり、「他者との交流を通して、自分の世界が拡張され、豊かになる」ということが、ここでは日常的に起こっていたんだなと、中高生の声から再認識させられました。
イベント終了時には、次回のイベント「#ユースセンターがある生活」は5月に開催すると予告されると、参加してくれていた高校生から「このイベントの企画に関わりたい」と嬉しい表明も。

「ユースセンターが、学校と同じくらい当たり前になる社会を」
この言葉は、b-lab館長、よねさんの口癖です。でも、国内の同種施設は数えるほどしかなく、ユースセンターという言葉はまだ私たちにとって身近ではありません。
それでも、中高生自身が魅力を語ってくれた今回のこのイベントに、1スタッフとして、なんだか背筋が伸びたような気がしました。若者の場所なんだから、若者が語ればいい。そして、新たな若者を巻き込んでいく。当事者である彼・彼女たちとともに考え続けることが大切なんだなと。そして、ユースセンターが当たり前な世の中を実現したいと、改めて感じました。
これからもb-labで働くひとりとして、「ユースセンター」についてさまざまな視点をお届けしていこうと思います。ぜひみなさんも、この居場所の存在を、心のどこかで覚えていただけたらうれしいです。
(TEXT:横田伸治)
文京区青少年プラザb-lab(ビーラボ)は、東京都文京区からの委託をうけ、カタリバが2015年から運営している中高生のための放課後施設です。
▼取り組み紹介
▼中高生向けb-lab公式サイト