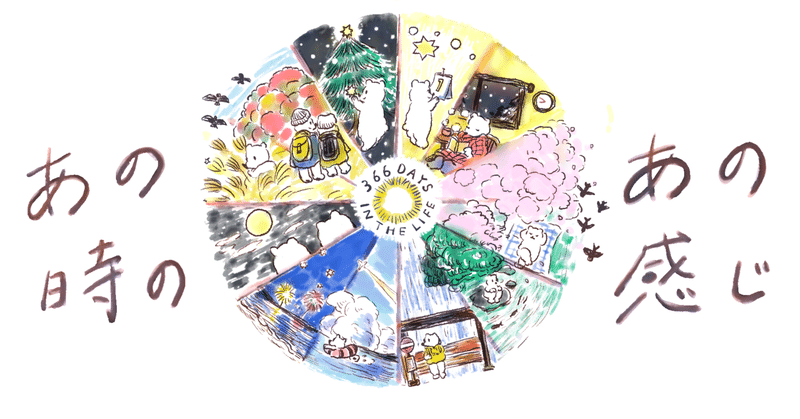
初日の出を見逃した正月、海に夕日を見にいくときのあの感じ|安達茉莉子
年の暮れ、世間は一斉にお正月に向けて進んでいく。大掃除、お正月の準備に年越しそばにと、まるで滝に向かって川の水が流れこんでいくような怒涛の勢いで、追い立てられる感じが苦手という人も少なくないだろう。一人暮らしで年末も帰省しない気楽な私としては、流れの隅っこの岩陰でひっそり息づいている小魚のように、同じ川にいながらもそうした奔流とは距離を置いている。小魚は結構、この首都圏のお正月の雰囲気が好きだった。
大晦日から元日にかけて、夜間も電車が動くのを知ったのは、30歳を過ぎてからのことだった。大学進学を機に上京して以来、正月は毎年実家に帰省するか、そもそも日本にいなかったりしたので、まったく知らなかった。一年のうち一夜だけ、終電がない夜がある。半信半疑だったが、電車は本当に動いていた。初めて夜に都内の神社で初詣をしたその時は、まるで世界の秘密を知らされたように興奮した。暗闇の中、篝火や灯籠の炎の揺らぎを見ながら上野公園の不忍池のほとりを歩く。大晦日の夜から正月の間だけ開くゲートのようで面白かった。
横浜市内に引っ越してきてから、二度目の大晦日と正月を迎えた。近所の蕎麦屋で買ったお蕎麦も食べて、一年をしまう準備はできている。今夜、電車は夜通し動いているのを知っていて、一年の間で一夜だけ出現する特別列車に乗りたい気もむらりとする。今頃、鎌倉の鶴岡八幡宮での年越しに向かって、粛々と人が集まっている頃だろうか。暗闇の篝火の中、参道に人が満ちる音を想像する。その中にひとり厚着して混じるのも良いかもしれない。真夜中の混雑した初詣を見てみたいし、寒さに震えながら、振る舞われる甘酒をいただくのもいいかもしれない。その後、初日の出を見に行ってもいいかもしれないと心惹かれたりもする。そんな、ありえるかもしれないささやかな冒険の分岐を静かに閉じながら、布団に潜りこむ。洗っておいたふかふかの毛布。新年くらいはと片付けた部屋が、ベッドテーブルに置いたランプの光に薄明るく照らされる。明かりを消して、ゆっくり眠りに落ちていく。私はこれがいい。私は私のペースを保つことが今一番幸福なことだから。
初日の出は布団の中で迎えた。起きたらとっくに朝が来ていた。起き上がり、台所で支度をする。お節は今年も作りそびれてしまったが、餅さえ食べられたら正月気分としては満たされる。大晦日に煮た小豆をお汁粉用に温めて、その傍ら、記憶を頼りにお雑煮を作る。濃いめに出汁をひき、鶏肉を下拵えして、にんじんを花の形に切り、餅を焼く。祖母はどうしていたか、母はどうしていたか。この瞬間は、実家で過ごした正月に記憶でつながる時間でもある。近くに住む人にもらった柚子の皮を細く切る。実家で過ごしていた頃の日々と、現在の日々が、椀の中でひとつに混じる。
坂を降りたり登ったりして、見晴らしいの良い高台にある近所の神社に初詣に出かけると、鳥居をはみ出して人が列を作っていた。この辺りにはこんなにも人が住んでいるのかと、毎年律儀に驚く感じが好きだったりする。
鳥居を越えて参道に並ぶと、とてもよく晴れていた。東京、千葉、横浜と住んだけれど、不思議といつも、決まったように元日は澄み渡るように晴れている気がする。まだ黄色い葉が残るイチョウの木や、お社にはためく白い紙、その向こうにある晴れた横浜の空を眺めながら並んでいると、私の後ろにいた家族連れの3人が話をしていた。おばあさんと、おそらくはその娘さんと、お孫さん。おばあさんが言った。
「なんだかおじいさんを思い出すねえ。帰ってくるといつも足が冷たくなっていた」
見ると、法被を来た近所の人たちが、神社の手伝いをしていた。“おじいさん”もまた、そのようにして法被を着て、正月の出事に駆り出されていたのだろうか。足が冷たくなるまで。
同じ土地に住んでいる、知らない人たち。誰かの記憶が混じる。私の順番が来て、賽銭を入れて、手を合わせた。ここに住むことができて幸せです。そう自然と出てきた。この場所に住むことができて毎日幸せです。あけましておめでとうございます。
お詣りをすませた後もまだ日は高く、晴れ渡っていて、なんだかこのまま家に帰るよりも、どこか開けた明るい場所に出たくなった。海を見に行こうと思い立ち、電車に乗り最初に鎌倉に向かう。鶴岡八幡宮の参拝の列に並んだ。昨日の夜に、一瞬だけ夢見た夜の初詣を昼間にやるのも悪くない。寒さに震えながら甘酒を飲むときのあの感じ、をできるかと思ったが、参道に並んでいる1時間半くらいの間は、陽に照らされてむしろ暑いくらいだった。甘酒は見つけられなかったが、お詣りしたあと、参道にある屋台で箸巻きを買って食べた。正月から粉物。何を食べるか食べないか、知らずに縛られがちな正月気分の中で食べる、焼けた少し焦げたソースと熱々のお好み焼きの生地がおいしかった。
少し陽は翳ってきていたが、日没の海にはまだ間に合う。初日の出は見逃したから、夕日を見るのもまた一興。少し歩けばすぐ由比ヶ浜だが、葉山の方にある馴染みの森戸海岸に行くことにして、電車でひとつ隣の逗子駅まで行った。バスに乗ると、逗子に住む友達から連絡があり、今から初詣に行って、夕日を見にいくところだという。
道はひどく混雑していたので、夕日に間に合うといいなと思いながら、森戸海岸に立った。こじんまりとして砂の粒が大きい浜辺に立つと、夕日に照らされて真っ青に輝く海と、その向こうにぼんやりと富士山、伊豆半島が見える。
乾燥しきった冬の空気の中に、潮風の湿気を感じる。それは春の空気に少し似ていた。これから一度寒くなるが、だけどだんだん空気も緩んでいくだろう。生温かい雨が何度か降って、空気に水気が増えていき、それを繰り返して気温自体も上がっていく。歩く足元から、芽吹くような春の気配を感じる頃には、今履いているブーツもしまって、防寒のレイヤーも一枚減って、気づけば季節は移り変わっているだろう。だけど今は、この乾いた透明な空気の中で、鼻先を冷たくしながら風に吹かれているのが気持ちいい。
森戸海岸は、いつものように、夕日を見に集まってきた人達で賑わっていた。それでも混雑というほどでもなく、皆それぞれ海の先に沈んでいく夕日を見ている。明るく照らされて、晴れやかな、知らない人たちの顔を振り返って眺める。友達が私を見つけて手を振った。ちょうど夕日が沈む前の瞬間だった。
「沈んだあとが綺麗なんだよね」
そう話しながらしばらく沈んだ後の海を眺め、車で一緒に逗子駅まで送ってもらい、なんとなく去りがたく、開いていたスターバックスに入って一緒に熱いコーヒーを飲んだ。店内は結構混んでいる。すべて完璧な元日だった。

連載『あの時のあの感じ』について
今、私たちは、生きています。けれど、今を生きている私たちには、自由な「時間」が十分になかったり、過ぎていく時間の中にある大切な「一瞬」を感じる余裕がなかったりすることがあります。生きているのに生きた心地がしない——。どうしたら私たちは、「生きている感じ」を取り戻せるのでしょうか。本連載ではこの問いに対し、あまりにもささやかなで、くだらないとさえ思えるかもしれない、けれども「生きている感じ」を確かに得られた瞬間をただ積み重ねることを通じて、迫っていきたいと思います。#thefeelingwhen #TFW
著者:安達茉莉子(あだち・まりこ)
作家、文筆家。大分県日田市出身。東京外国語大学英語専攻卒業、サセックス大学開発学研究所開発学修士課程修了。政府機関での勤務、限界集落での生活、留学など様々な組織や場所での経験を経て、言葉と絵による作品発表・エッセイ執筆を行う。著書に『毛布 - あなたをくるんでくれるもの』(玄光社)、『私の生活改善運動 THIS IS MY LIFE』(三輪舎)、『臆病者の自転車生活』(亜紀書房)、『世界に放りこまれた』(twililight)ほか。
