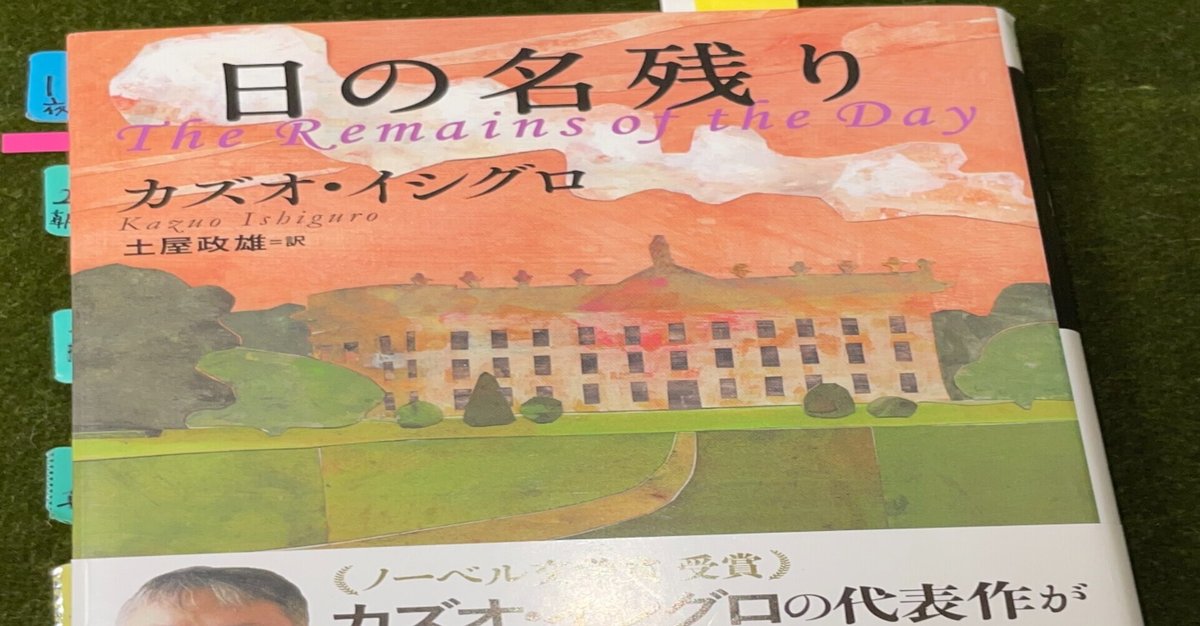
狂信と純真、もしくは東京五輪とノスタルジー。
「日の名残り」カズオ・イシグロ著:早川epi文庫
余談だが、先日7月22日、東京五輪開会式の演出家の一人である小林賢太郎氏の過去におけるユダヤ人ホロコースト揶揄問題があったとき、ちょうど偶々、本書のあるくだりを読んでいた途中だった。
主人公の執事スティーヴンスが仕える貴族、ダーリントン卿が第二次世界大戦前に反ユダヤ主義に傾倒していき、邸内で勤勉に働く若い女中二人を、ユダヤ人であるという理由で強制解雇する場面がある。もし本国へ送り返されたとしたら、命さえ危険な時期であるのにだ。欧州の小説を読んでいると、どこかでナチスの問題が俎上に乗るときが多々ある。私たち日本人の欧州に対する歴史認識の低さを思い、そのニュースに気が滅入ったのだった。
小説に話を戻すと、物語は1956年の夏、雇主から夏の休暇を貰った老執事スティーヴンスが、昔共に働いた女中頭に会うためにイギリス西部を旅する、というのが大まかな話。その旅のなかでかつて栄華を放っていた邸宅での日々を回想しながら、物語は過去へ遡上していく。いわば、地理的な旅をしながら、時間的な旅(主に第一次世界大戦後から第二次世界大戦前まで)の記憶を回想していく。時間と空間を縦横無断に駆け巡る本書の設定は、小説の醍醐味に溢れている。
本書で特筆すべきは、スティーヴンスのいかにも英国らしい、執事という職業に対するプロフェッショナルさにある。父親が亡くなろうとも、長年密かに思いを寄せる女中頭に去られても、仕事優先、仕える主のために命を懸けるほどの献身ぶり。その忠誠心はまるで侍みたいだ。英国的であることと日本的であることは、イシグロの小説においては限りなく近い。映画ではアンソニー・ホプキンスとエマ・トンプソンが演じていたが、途中からその不器用さが…スティーヴンスが高倉健に、女中頭のミス・ケントンが倍賞千恵子に見えたり。
そして、大戦後はナチスへ肩入れしたダーリントン卿は、その政治手腕が愚行とみなされ世間から厳しく弾圧されていく。そこに狂信的とさえ見えるほどに卿に忠心してきたスティーヴンスも立場が辛いものとなる。ただ、自分が命を懸けてきた信念を今更曲げられないのが人間か。過去の偏狭な価値観にしがみつき続けるスティーヴンス。ある意味では、狂信的であるということは恐ろしいもの。と、言いつつ思うのが(どうしても時期的なものだけに…)ここ最近のおけるコロナ対応と東京五輪に追われる菅内閣。世間や科学者から何を言われようが、自らの思いだけでつっぱしる、あの怖さ。世間から過去のインパール作戦の再来のようと言われようが、止められない。あるとき総理が、五輪の意義を問われて、自身の高校生の頃に見た57年前の五輪の感動の思い出を語った場違いさを思い出したい。1964年のノスタルジーのためにパンデミック禍の五輪があるのだろうか。その価値観は、スティーヴンスと同じで、ある種、かつての栄華への妄信とさえ思えるものだ。過去の英霊を引きずるかのような価値観の危うさを、今考えたいとさえ思う。
ただ、最後は旅路の果てに辿り着いた海辺の町でのスティーヴンスが、切ない。ただただ残るものは虚しさだけなのか。海を見て男泣きする老執事の人生の晩年を思い、涙した。この文庫の解説で丸山才一氏もこのシーンを絶賛していた。年老いた男が、過去を想い、哀れ深く泣く。彼ははただ、命を懸けてまで主人へ従僕をしてきただけだった。狂信的ではあるが、見方を変えるとこんなに純真さをもった人間もいないだろう。と、将又思い出したのが、イシグロの最新刊『クララとお日さま』におけるクララだった。主人の為にただただ、太陽へ祈りを捧げるクララの宗教的なまでの純真さが、海を見て泣く老執事に重なってしょうがない。
普遍的な人間のまた、人生の哀しみのアレゴリーとしての、"日の名残り”。哀れさと深さに、狂信と純真のあわいに心揺さぶられる。訳は土屋政雄、名訳である。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
