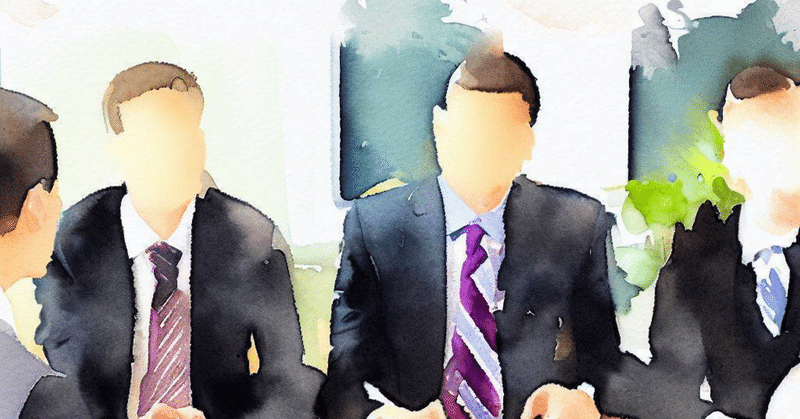
【短編】ある面接の思い出
ハローワークに通って仕事を探しながら、失業給付金を受けてとっていたときの話である。
履歴書を何十社と送り続けても、決まって不採用通知「一層のご活躍をお祈り申し上げます」と共に送り返されてくる。悲観的になって、正社員はもう諦めようか、そもそも自分は社会に必要とされていないのではないか、などと考えて落ち込んでいると、そのうちの一社から、とにかく面接に来いと直接電話があった。
久しぶりにスーツに袖を通すどころの話ではなかった。最後に髪に櫛を通したのがいつのことだか覚えていない。数ヶ月間、職安とアパートの往復ぐらいしか出歩くこともなく、鏡に映った蓬髪、無精髭の己の姿は、かなり浮世離れしていて、自分でも電車でこんな人に隣りに座られたらちょっと嫌だなあと思うほどだった。
シャワーを浴び、髪を切りに行ってスッキリし、クリーニングに出したスーツを受け取ると、徐々に社会復帰しているような気がしてきたものだ。
目当ての会社は、都心の繁華街の裏通りにあった。薄汚れた昭和の雑居ビルの5階、エレベーターが故障中で、トボトボと暗いリノリウムの階段を上ると、「阿久理商事」と看板が出ている。「失礼しまあす!」と自分でも素っ頓狂に思えるぐらい声を張り上げ(ハッスルしすぎ)扉を開けて、あっと息を呑んだ。思わず「失礼しました」と一礼して、退出しそうになったほどである。
エントランスも受付もなく、扉は事務室に直結していた。扉を開ければ、そこはもう事務室だった。そして、そこで仕事する制服姿のOLたちが(横6×縦6の36人ぐらい?)が一斉に端末から顔を上げて、挨拶するわけでもなく、笑顔を見せるわけでもなく、きっとこちらを凝視する。
それが、なんというか、揃いも揃って、失敗した福笑いみたいな顔をしていた。いや、福笑いというのは、目・鼻・口のパーツ自体は同じで位置が異なるだけだから、正確な比喩ではないだろう。それぞれのパーツの位置のバランスの悪さだけが問題ではなく、パーツそのもののサイズや形こそが異様であったのだ。
いや、人の容姿をあげつらうというのは、下品なことだとわかっている。下品どころか、卑劣であろう。それはもう、ハッキリと良くないことだ、最低の行為だ。そもそも己が、人様の顔のことをアレコレ難癖つけられるような立派な面相の持ち主ではないことも重々承知している。
しかし、である。これは一体何なんだ。クラスに一人いるかいないか、どころか学年に一人いるかいないかレベルの醜女をここまで揃えると、もはや壮観である。明らかに顔で選んでる。彼女たちはある明確な基準で採用され、ここに集められ、並べられ、展示されているのではないか。一体全体、何のために。モダンアートのインスタレーションか?
別に神社仏閣にとりわけ興味があるわけではないが、昔旅先で見た五百羅漢像を思い出す。雨ざらしの苔むした石像たちは、一体とて同じ顔はなく、獅子鼻・ワシ鼻・団子鼻、やたら目が細かったり、ギョロ目だったり、福耳だったり、顎が突き出ていたり、額が秀でていたり、頬がこけていたり、垂れ下がっていたり、口がひん曲がっていたり、耳元まで裂けていたり、皆思い思いのポーズをとり、カリカチュアだからグロテスクである一方、どこかユーモラスでもあった。三十と五百では桁が違うが、五百羅漢だって実際に五百体あるわけではないし、右手と左手の指の合計以上が「たくさん」なら、三十も五百もたくさんである。この会社の年齢不詳のOLたちは、記憶の中の阿羅漢の集団にとても似ていた。
奥の窓際で一人の男がゆらりと立ち上がった。普通は上司と対面、もしくは横になるようにデスクを配置するかと思うのだが、なぜか彼女たちは窓側に背を向け、入り口に顔を向けているのだった。つまり上司はずらりと並んだ部下の後ろ姿に向かって腰かけていたわけである。
福笑いからの連想でも何でもなく、男はひょっとこみたいな顔をしていて、遠くからはお面を被っているように見えた。今にも腰を突き出し背を曲げ、手のひらをかざして馬鹿踊りでも舞い出しそうで、これはこれで、なんだか目が離せない。
「面接の方?」顔に似合わず朗々と響く美声であった。
「はい! よろしくお願いします!」
なんかえらい所に来てしまった、無事に帰れるだろうかと心臓が早鐘のよう打つ。応接室に通され一人になって、冷静に考えてみると、書類選考を通ったのは履歴書に貼った写真のせいではないかと思われた。あの顔写真が、この会社の基準にぴったり合致していた、つまり己が醜男だから、面接に呼ばれたのではないか。しかし、美男美女を選ぶならわからないでもないけど、どういうわけで不器量な人ばかり採用するのか、社長がゲテモノ趣味なのか、あるいは社長夫人が相当嫉妬深いのか。いずれにせよ、男の容姿は関係ないはずだが。
と、そんなことが気になり出すと、ひょっとこが入ってきて(渡された名刺の肩書きは部長だった)、履歴書を広げて色々と質問し始めても、気持ちの切り替えがうまくできずに、せっかくの面接だというのに生返事になってしまった。頭の中で渦巻く様々な疑問が、堰を切って流れ出すことを止めようと必死であったのだ。
ノックの音に我に返ると、年相応に肥えて、化粧の厚いグレイヘアの女性が目の前に立っていた。「社長!」と、ひょっとこが慌てて席を立ったので、つられて立ち上がろうとするのを手で制して、彼女は革張りのソファにかけた。直視するのが憚られたからチラ見すると、まことに平々凡々とした容姿で、なんだか裏切られたような気がするのだから不思議なものだ。
「どうぞ続けてください」
自己紹介もせずに、社長と呼ばれた初老の女性は、黙ってただじーっとこちらの顔を見つめてくる。視線をそちらへ向けずともわかる、品定めされているのだ、顔面を。赤くなった顔をうつむけていると、汗が滲み出してきて膝に置いた手にポタリと滴る。この会社には、男性が部長しかいないのか、それとも他の者は外回りでもしているのか。沈黙が訪れると、隣の事務室からひっきりなしにキーボードを叩く音が聞こえてくる、およそ30人分だけど、五百羅漢像がパソコンに向かっている図が脳裏に浮かぶのだ。
「それでは」と、キリの良いところで女社長が言った。「何か質問がありますか? 何でも答えますから、遠慮なく仰ってください」
そしてまた、こちらをじっーと値踏みするかのように見つめるのである。その瞳は、あなたの考えていること、あなたの抱いている疑問は、みんなお見通しよと語っていた、さあ訊くなら訊くが良い、もしそうする勇気があるのなら。
「はあ」
訊けなかった、どうしても質問することができなかった。非礼を避けたというより、想像できないような非常識な返答が恐ろしかったのだ……。
それから二、三日経ってから電話がかかってきて、それはひょっとこの美声であったのだが、ぜひうちに来てほしいとのことだった。もちろん、正社員の座は喉から手が出るほど欲しかったけれど、申し訳ないが他に決まったと嘘をついて即座に断った。
もし、あそこに就職していたら、今頃どんな人生を送っていただろう、時折りそんなことを思うのである。それは、怖いもの見たさの感覚に似ているかもしれない。そう、もう一度訪ねていって、あの体験が悪夢や幻ではなく、阿久理商事がたしかに存在していることを確かめたいと考えているのだ。
(了)
【関連作】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
