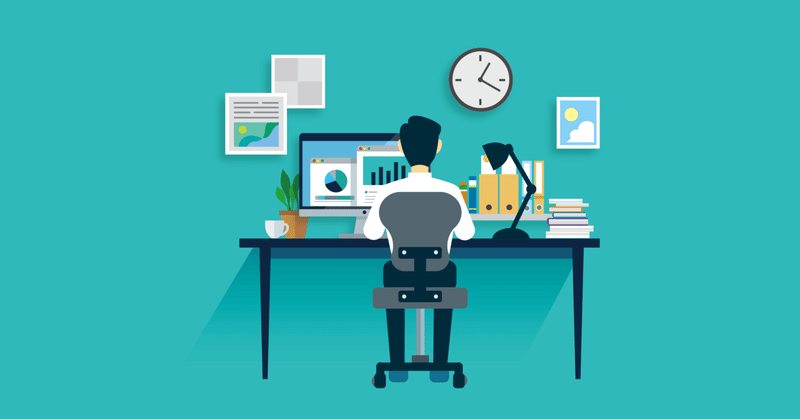
【掌編】美人考
そういえば近頃、ベンチャー企業という言葉を聞かなくなったような気がする。これは自分が、日本最大のビジネス街の(近くにある)インテリジェント(っぽく見えなくもない)ビルにあった、(自称)ベンチャー企業で働いていた時の話。社長ですら三十代前半、とにかく社員は皆若かった、自分以外は……。
誰でも知ってる日本最大の事務機器メーカーからリースしている複合機がまたしても壊れて、皆は顔を見合わせた。
前回修理を頼んだとき、やって来た人がドレッドヘアに真っ黒に日焼けしたサーファーみたいな(偏見です)青年で、まるでカスタマーエンジニアっぽくなく(偏見です)、なんだかそれがおかしくてしょうがなかった。ジロジロと視線が注がれる。一連の作業を終えて彼が出てゆくと、堪えかねたように女子社員が「ほんとうに真っ黒ね!」と頓狂な声を上げたので、フロア中が爆笑の渦に巻き込まれたことを思い出したのである。
「またあのサーファーが来るのかなあ?」
「ああ、あのドレッドヘア!」
「そうそう真っ黒な人!」
違った。その代わりに凄い美女がやって来た。メンテの人が子会社か委託先か、どこから派遣されてくるのか知らないけれど、なんて個性的な面々を取り揃えているのだろうと思わず感心してしまう。
いや、とにかく飛び切りの美人であった。かつて見たことのない、非現実的な、つまり虚構的な、映画のスクリーンにでも相応しいような美しさである。
あの恐ろしいほどの美しさをどのような形容詞や比喩で表現可能か、今あれこれ頭を悩ましてみる。芸能人の誰それに似ているなどと言っても無駄だ。しかし、私たちはどういうわけか、美のスタンダードというものを生まれつき持っているわけであって、そこにピッタリと当てはまる、当てはまり過ぎる風貌というものが現実に存在し得れば、それはもはやグロテスクとさえ言えるのだった。
病気や怪我のために顔に痣や傷が残って、好奇の視線に晒される人たちと、ある意味似ていると思った。
男たちは皆、息を呑んで彼女を凝視する。失礼にならない程度に、と本人は思っているのだろうが、一旦見てしまうともはやどうやっても視線は逸らせない。オフィスは異様な雰囲気に包まれた。
それにしても、一体なんだって彼女はこんな仕事をしているのか、もっと輝ける舞台があるはずではないのか。あるいは、モデルになるには身長が足りず、アイドルになるには決定的に愛嬌が欠けており、女優になるには喜怒哀楽の表情が乏し過ぎる。そもそもスポットライトなど浴びたくない質ということもありえる。全く無表情で、見られるままになって、じっと耐えている風には見えないけれど、視線を跳ね返すような気の強さも感じられない。とうに見られることに無感覚になっているのかもしれなかった。
彼女の美貌は日常生活には相応しくないスペックであり、当たり前に生きてゆく上での障害であったとしたら。
彼女が仕事を終えて立ち去ったとき、誰も笑いはしなかった。ただ男たちはふっと我に返り、黙って視線をやり取りし、重々しくうなずき合ってそそくさと業務に戻り、それから少しずつオフィスは日常を取り戻したのである。本当のところ、彼らが何を考え、どう感じたかは自分にはわからないし、興味もない。ただ張りつめたような孤独を想っていた。
(了)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
