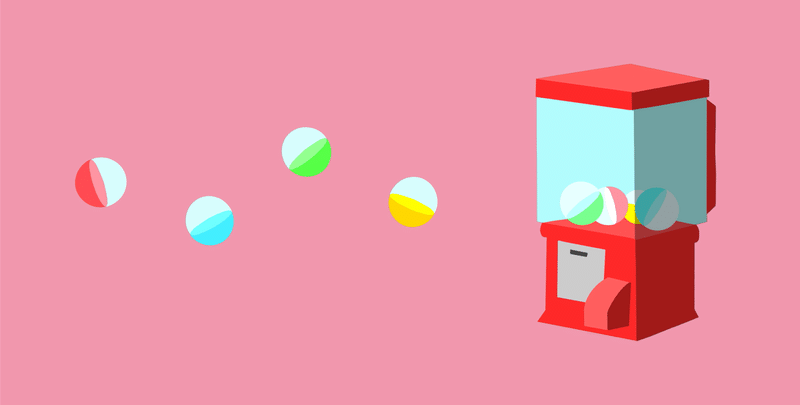
資本主義社会から生まれた玩具
YouTubeチャンネル登録者数8万人超えのサッカー系YouTuberの谷田部真之助という方がいらっしゃるのですが、僕は、彼が運営するジュニアサッカースクールの、大阪市会場の担当コーチとして、2019年10月から先月まで活動させていただいた。
(僕自身が動画に出演したり撮影現場に居合わせたり動画編集したりしたことはない。僕が関わったのはスクールの活動のみ。)
細かいことを言うと、運営者である谷田部さんは、いわゆる「YouTuber」ではなく、元々「サッカー家庭教師」という分野を開拓して人気を博した人で、数年前にYouTube活動を始めたことによって人気が加速したという感じである。
ちなみに僕は彼のファンとかではなく、たまたまサッカーコーチの求人を見つけて彼のスクールに辿り着いたという感じだ。
そんな彼のもとで、ジュニア年代のサッカーコーチというお仕事をさせていただいていたのだが、先日サッカースクールの参加人数が減ってきたこともあり、急遽「廃校」となった。
今回は、2019年10月から2022年1月までの16カ月間スクールコーチとして活動させていただいた中で感じたことなどを綴っていこうとおもう。
結論、めちゃくちゃ楽しかった
なんといっても楽しかった。「楽しいかどうか」は、仕事をするうえで、教育に携わるうえで、スポーツをするうえで、そして生きるうえで、最も大切なことだと思って生きているのだが、まず16カ月間これを継続してクリアできていた。素晴らしいことだとおもう。
サッカースクールの内容自体は、小学生たちが毎週同じ曜日の同じ時間に集まって、1時間フットサルコートでミニゲームを行うという単純なもの。いわゆる「ストリートサッカー」をイメージしたものだと言えるだろう。
大阪市会場の担当は、僕ともう1人コーチがいて、基本的に2人体制でやっていた。選手たちの送り迎えをしていたパピー(父親)たちのうち1〜3人が、スクール生や僕らコーチと混ざって、みんなで一緒にサッカーを楽しんでいた。運営者である谷田部さんも、月に1回、大阪まで来て一緒にゲームに参加していた。
僕自身は元々サッカーを10年以上していたものの、もともとサッカーコーチの経験はなかった。それにも関わらず、大阪市会場の担当コーチとして採用され、一般的なアルバイトの3倍くらいの給料(厳密には報酬)を受け取りながら、楽しく仕事ができた。なかなかの幸運だとおもう。
気になったこと
当然のことだが、0から100まで全てが「楽しいこと」で埋め尽くされていたわけではない。
練習会の雰囲気が悪くなったりとか、怪我人が出たりとか、コーチである僕自身が怪我をしたりとか、そういうこともあった。そういった問題はどこのスクールやチームにも存在するものだろう。
また、そういった細かい問題とは別に、スクールにはいくつかの構造的問題もあった。そして、それら問題を認識してからは、「このスクールはそんなに長く続かないだろうなぁ」「廃校になるのも時間の問題だなぁ」と思っていた。
ここでは、(運営的に採算が取れるかどうかというところは一旦横に置いといて、)2つの気になっていた点について振り返っていきたいとおもう。
①サッカーやりすぎ問題
僕は常々おもっていた。スクール生のみんな、練習会に来てくれるのは嬉しいんだけど、サッカーやり過ぎなんじゃないか、と。
僕らがやっていたスクールは、どこかのチームに所属せずにスクールと自主的な練習や遊びだけでサッカーをしている選手にとっては、すごく良い環境だったとおもう。
以前スクールに来ていた選手のうちの1人は、どこのチームにも所属しておらず、サッカーをするのはスクールの練習会と自主練だけだったようだ。そのため、サッカーに対して常に前のめりだったので、何かを教えることもなく勝手にどんどん上手くなっていった。

一方、気になるのは、普段チームに所属して平日も土日もサッカー漬けの日々を送っている選手たちだ。
スクールに来てくれていた選手たちのうち大半がどこかしらのチームに所属していたのだが、練習会に来た時点で既にヘトヘトだという選手が毎回のようにいた。
もちろん、心も体も丈夫で、所属しているチームの活動だけでは足らず、サッカーに飢えているような選手も少なからずいたので、チームに所属している選手のうち全員が「サッカーやりすぎ」だとは思わない。
しかし、明らかに身体や心が悲鳴をあげている選手がパピーの運転する車に乗せられて練習会にやってくる姿を見ると、「所属チームの活動だけで充分ではないだろうか?」と思うことが多々あった。
特に僕らがやっていたようなスクールはゲーム形式で進行するだけなので、もしサッカーに飢えているのであれば、近所の公園とか場所を見つけて友達同士でサッカーをすればいいんじゃないのか、と思うこともあった。
南野拓実や遠藤航が通っていたクーバーサッカースクールのようにテクニックを教えるスクールをやっているのならば、話は変わってくるが、、、
あと、一部のスクール生が所属しているジュニアサッカーチームで、「土日は二部練習を行うときもある」という話も耳にした。
二部練習?令和の今の時代に?ジュニア年代で?それ、チーム内で効果検証されてるの?
聞くところによると、そのチームは1回あたりの練習時間も長いらしい。3時間とか。それもチーム内で効果検証されてるの?
そして、そんなチームに所属しているにも関わらず、さらに別のスクールにも通って「掛け持ちをする」という選択をする選手や保護者がいることにはかなり驚いた。
②保護者の過剰干渉、大人のエゴ
もうひとつ気になっていたのが、保護者たちの選手への関わり方だ。
僕らがやっていたスクールは、スクール生の家庭から毎月それなりに高い料金を支払ってもらうことで運営されていた。
スクールの練習会は、公共施設などを使うのではなく、1時間につき1万円以上もかかる人工芝のフットサルコートをレンタルして行われていた。それなりに高い金額設定でないと回らないというのは実情ではあった。
それでもスクールが16ヶ月間も運営され続けていたのは、運営者である谷田部さんのブランド力のおかげだろう。
2019年9月に行われたスクールの体験会では、体験会終了後、彼のファンがサインを求めて彼の周りに集まった結果、サイン会と写真撮影会が始まった。
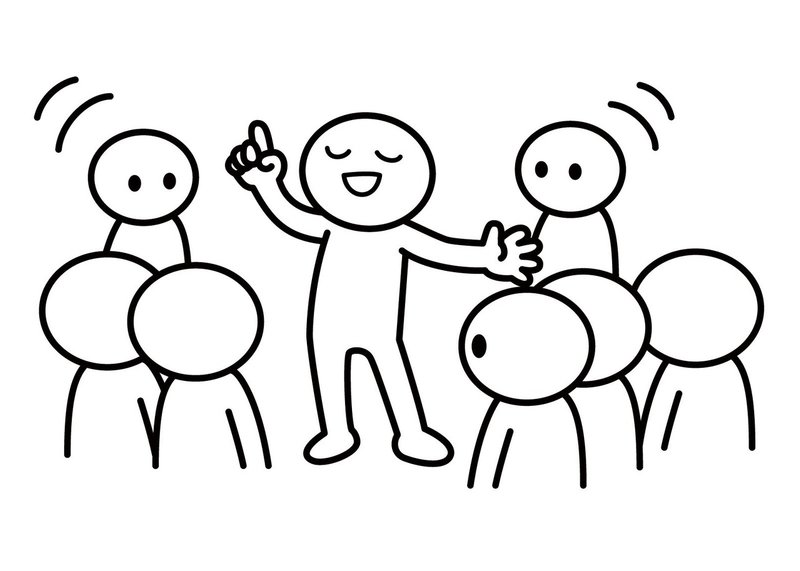
彼のファンではなかった僕にとって、その光景は異常に見えた。しかし、その彼の魅力がブランドと化してスクール運営に繋がっていた。
僕はその光景をみて、「資本主義すげ〜」という具の重力に耐えられないピザ生地のように薄っぺらい感想を持った。
そんな感じで、スクールはブランドによって支えられていた。その結果、スクールに来てくれる選手というのは限られてくる。
来てくれるのは、経済的に裕福な家庭の選手だ。しかもクルマでの送り迎えが必要なので、保護者さんに時間的余裕のある家庭の選手に限られる。
そして、そういった余ったお金と時間を子どものために費やしたい家庭の選手となると、必然的に親子がベッタリ引っ付いている家庭にいる選手ばかりとなってしまう。
(繰り返しになるが、全員ではない。あくまでそういう傾向が見られたという話。)
親子がベッタリ引っ付くことが良いとか悪いとかは分からない。しかし、その結果、生まれてしまった問題がある。
それは、「余計なことをしてしまう大人」が誕生してしまうという問題だ。
「もっと走れよ」「なんで早くシュートを打たないんだ」「遅い遅い遅い!!!」そんな声がコーチの口からではなく保護者の口からコート全体に響き渡るということが度々あった。
もはや地獄である。サッカーというスポーツは、選手本人の「認知」というものが重要になってくるものなのだが、大人の余計な掛け声によって大切な認知に大きな邪魔が入りこんでしまう。
しかも、そういった掛け声をしてしまうのは、決まってサッカーの経験がないパピーである。しんどい、しんどい。
(何度も繰り返すが、これはその場にいる大人全員のことではない。あくまで傾向の話をしている。)
どこまでいっても結局資本主義
ここまで述べてきたとおり、スクールの活動には構造的問題があり、特にスクールの存在意義は感じられなかった。
もちろん廃校になったことで選手たちに会えないのは寂しいし、選手たちが今後どう育っていくのかを見届けられないのは惜しい気がする。
しかし、スクールの立て直しに可能性があったとしても、そこに力を注ぎたいとは思えなかった。何かしらの対策をしたり工夫をしたりすれば、スクールの"延命"もできただろう。けれども、それならばさっさと活動終了した方がいいと思っていた。
結局ぼくがスクールのコーチをやり続けていたのは、「じぶんが楽しむため」「お金という報酬を貰うため」だった。「スクール運営を成功させて日本サッカーを変えたい」とか、「スクール生からプロを輩出したい」とか、そんな気持ちは1ミリもなかった。ただただ、じぶんとお金のためだった。
とはいえ、選手や保護者たちと喋ったりサッカーをしたりすること自体はめちゃくちゃ楽しかった。そして、結果的に金銭的報酬が貰えた。僕にとってはそれだけで十分だった。
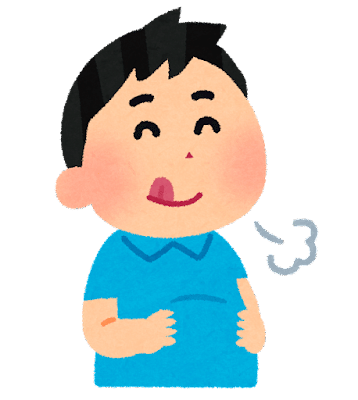
もし、僕が、サッカーコーチとしての職業的倫理観を持ち合わせている人であれば、もしくは"道徳を履修している人"であれば、「①サッカーやりすぎ問題」や「②保護者の過剰干渉、大人のエゴ」について何かしらの行動をしていたであろう。
しかし、僕はそういった職業倫理も道徳心も持ち合わせていなかった。とにかく「楽しければいいや」「結果的に報酬が貰えたらいいや」という感じだった。
つまり、僕らが活動していたスクールというのは、僕にとっては、資本主義社会から生まれた玩具だったのである。
利益が出ることを目指して運営がスタートし、資本主義ゲームでそれなりに勝っている家庭がそこに参加し、僕のようなプー太郎が報酬というおこぼれを頂く。
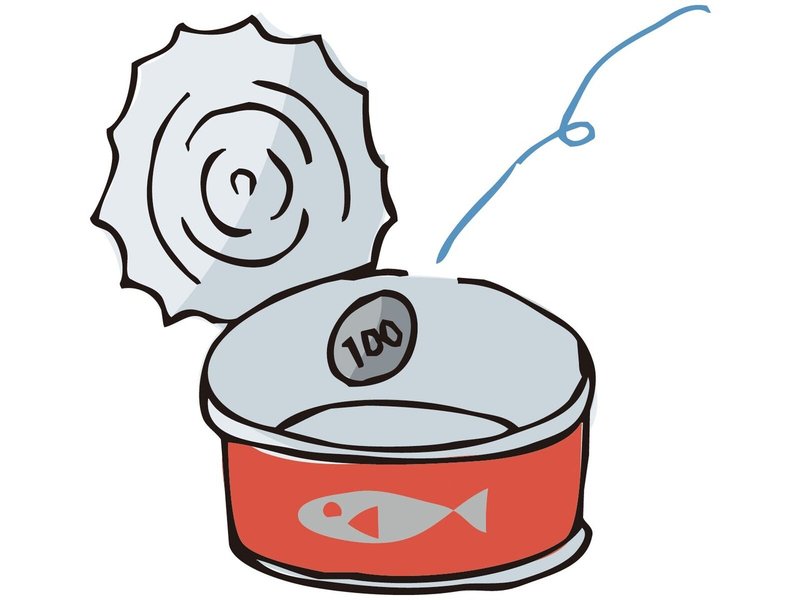
活動自体は楽しかった。だからこそあまり言いたくないが、スクールの存在意義は資本主義によって支えられていた。これが現実である。
おわり。
(こちらの記事に何かを批判したいとか何かを変えたいとかそういう意図はありません。感じたことをそのまま書いた長めの日記です。)
里芋です。
