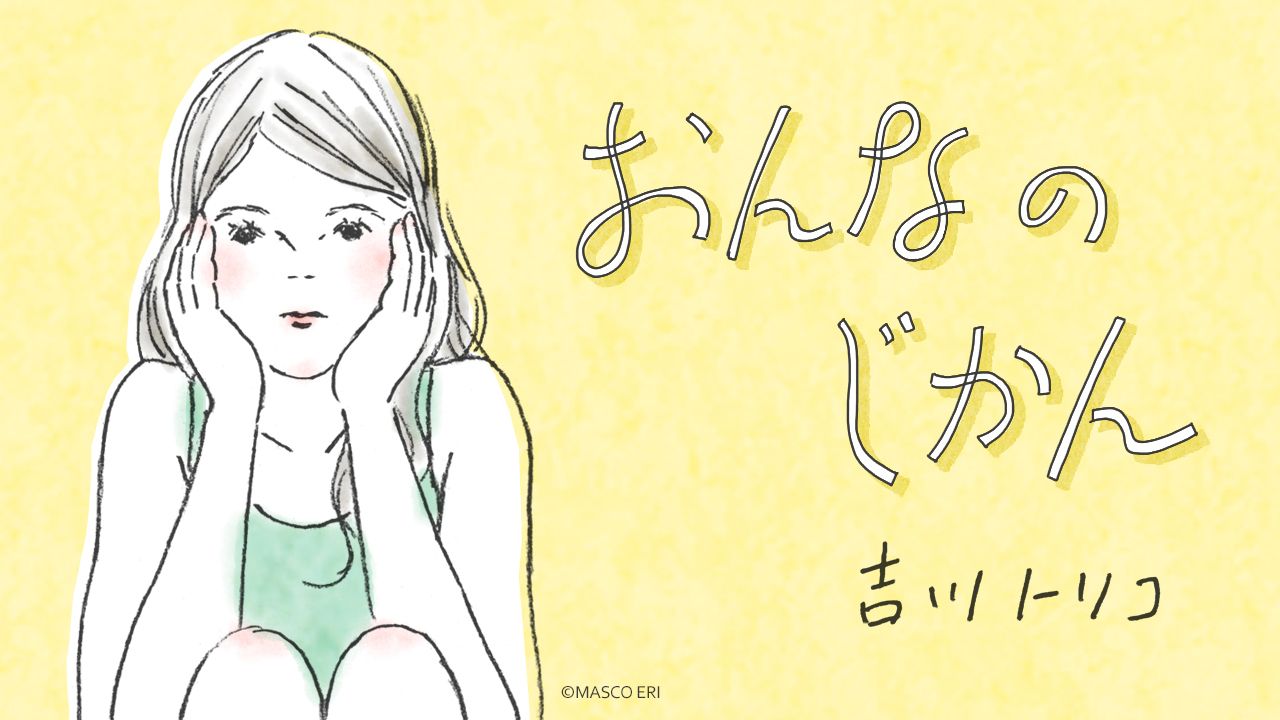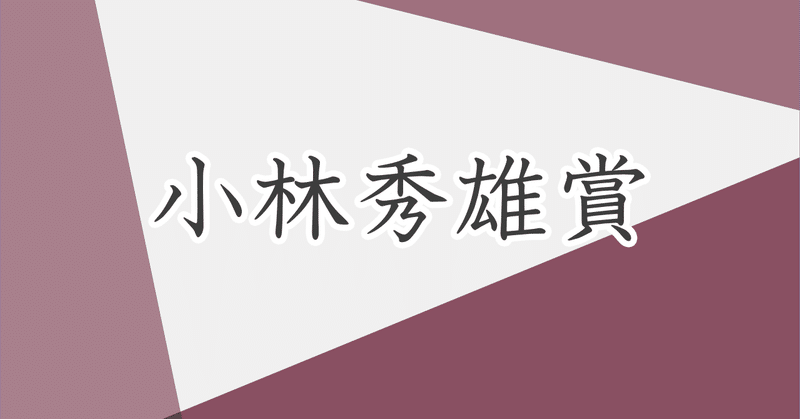
第20回小林秀雄賞は岡田暁生さん『音楽の危機』に(No. 927)
考える人 メールマガジン
2021年9月2日号(No. 927)
第20回小林秀雄賞は岡田暁生さん『音楽の危機』に
8月26日午後、一般財団法人 新潮文芸振興会の主催による「小林秀雄賞」選考会がオークラ東京にておこなわれ、第20回小林秀雄賞は岡田暁生さん『音楽の危機 《第九》が歌えなくなった日 』(2020年9月刊行、中央公論新社)に決定いたしました。
過去の小林秀雄賞受賞作品ならびに受賞者インタビューは、こちらをご覧ください。
磯野真穂×與那覇潤「コロナ禍に人文学は役に立つのか?」
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、1回目の緊急事態宣言が出されてから1年4か月あまり。理系の専門家が主導するコロナ対策の裏で、見過ごされている問題はないのか。人文学の視点から何か提言できることはないのか。人類学者の磯野真穂さんと、(元)歴史学者の與那覇潤さんが話し合いました。
第1回 パチンコと居酒屋と「共感格差」
第2回 「いのちの現場」はどこにあるのか
ブレイディみかこ×ヤマザキマリ「パンク母ちゃん」
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー2 』の発売が9月16日に決まったブレイディみかこさんと、ヤマザキマリさんとの対談「パンク母ちゃん」、noteで好評配信中!
「考える人」で冒頭の立ち読みができます。
1. パンクな母ちゃんとクレバーな息子たち
2. 詩人と本気で恋をした
3. 私たち一生「グリーン」
アクセスランキング
■第1位 磯野真穂×與那覇潤「コロナ禍に人文学は役に立つのか?」
第1回 パチンコと居酒屋と「共感格差」
■第2位 早花まこ「私、元タカラジェンヌです。」
第4回 鳳真由(前篇) 宝塚から医療大学へ――どうやったら自分なりに理解できるか、いつも考えている
■第3位 吉川トリコ「おんなのじかん」
15.流産あるあるすごく言いたい
最新記事一覧
■小谷みどり「没イチ、カンボジアでパン屋はじめます!」(8/27)
24. われらオオサカベーカリー の「日本風菓子パン」納入奮闘記
小谷さんがカンボジアで開いたベーカリー宛てに、「日本の菓子パン」を置きたいとカフェから注文が! でも「日本の菓子パン」ってどんな特徴があるのでしょう?
■ジェーン・スー「マイ・フェア・ダディ! 介護未満の父に娘ができること」(9/1)
11.心と体重をすり減らし
ジェーンさんのカンペキな父上支援計画と実行により、順調に見えていた生活に翳りが。どんどんお父様の体重が減ってしまっているのだ。さらに、2回目のワクチン接種を渋り出したうえに、新しい家政婦さんに文句をつけ始め……ジェーンさんの堪忍袋が破裂寸前!
「考える人」と私(27) 金寿煥
創刊から7号目の「考える人」2004年冬号の特集は、「大人のための読書案内」。“plain living & high thinking”というスローガンを掲げる「考える人」としては、満を持しての読書特集です。
雑誌として「読書特集」は定番のものですが、だからこそ〝切り口〟が問われます。あらためて同特集を繙いてみると、「2004年」という時代がひとつのキーになっているように思います。
同年4月には、ソニーの電子書籍リーダー「LIBRIe」が発売。それに合わせるようにして各出版社が電子書籍のコンテンツを準備し始め、これで一気に電子化の波が来るぞと、出版界全体がにわかに騒がしくなったことを覚えています。実際は、その17年後となる現在でこそその需要は高まっていますが、当初予測されていたほど電子化は加速せず、紙の本がしぶとく生き残っているのが現状でしょう。
特集「大人のための読書案内」のリードにも、「本の中身はデータと呼ばれたりコンテンツと呼ばれたりするようになった。インターネットで検索すれば北海道や九州の古書店から本を取り寄せることも可能になった。ウォークマンのような本がまもなく出来るとも聞いた」とあるように、そうした読書環境をめぐる〝変化の風〟を感じつつ、「変わるもの。変わらないもの」をそれぞれレポートしていこう、という意図が示されています。
「変わらないもの」代表としては、装幀家の金田理恵さんによる「函入クロス装の本をたずねて 静かな本」。昭和の時代までは多く作られていた函入りの書籍ですが、「出版不況」という声が囁かれ始めた頃から、そのコスト面も考慮され、徐々に少なくなっていきます。金田さんも、愛読していた洲之内徹『気まぐれ美術館』シリーズが、途中から函入りでなくなったことを嘆いています。いわく、「白い函は、美術館の、白いけれどもやわらかく緊張した空間を思わせる。ところが、初めて新刊を待ちうける側に立った私の前に現れたのは、函をとられて剥き出しにされた、とも見える白いカバー装に姿を変えた単行本だった。そのときの落胆は忘れられない」。金田さんは製本所や紙器所を訪ね、職人さんが手仕事で美しい本を作り上げる過程を取材しています。いわばマテリアルとしての本の魅力を伝えるレポートです。
「変わるもの」代表は、ライターの永江朗さんによる「ネット古書店利用術!」。古本の流通がネットの普及によって大きく変わり始めている――そのことに焦点をあてたルポです。すでに通販サイトとしてアマゾンは日本にも上陸していましたが(日本国内でのサービス開始は2000年11月1日)、古書の取り扱いについては、まだまだ現在のような規模ではありませんでした。そこでネット古書店のパイオニアである東京・町田「高原書店」や、ライターの野崎正幸さんが個人で経営するネット古書店「文雅新泉堂」を訪ね、話を聞いています。ある意味で、まだ牧歌的かつ群雄割拠的だったネット古書店をめぐる当時の状況を詳しくレポートしています(私が編集を担当したのは、この永江さんのルポでした)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■note
https://note.com/kangaerus
■Twitter
https://twitter.com/KangaeruS
■Facebook
https://www.facebook.com/Kangaeruhito/
Copyright (c) 2020 SHINCHOSHA All Rights Reserved.
発行 (株)新潮社 〒162-8711 東京都新宿区矢来町71
新潮社ホームページURL https://www.shinchosha.co.jp/
メールマガジンの登録・退会
https://www.shinchosha.co.jp/mailmag/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
もしサポートしてくださったら、編集部のおやつ代として大切に使わせていただきます!