
教科書の短歌① くれなゐの二尺伸びたる薔薇の芽の針やはらかに春雨のふる 正岡子規
光村図書中学国語2年に載っている短歌作品。
五七五七七の短歌が中学校の国語の教科書に載っている。ずーっと昔の「万葉集」や「百人一首」の短歌も教科書にあるが、明治以降の作品も載っている。「明治は遠くなりにけり」なのに、いまだに明治のものも残り、中学生が授業で学んでいる。
時代を超えた短歌を知り、日本語の教材として覚えてしまおう。
中学校の国語の教科書に載っている「短歌」を3回にわけて紹介する。
くれなゐの二尺伸びたる薔薇の芽の針やはらかに春雨のふる 正岡子規
赤く二尺ほど伸びたバラのまだやわらかな針に、やわらかな春雨が降っている。
現代短歌のもとを作った明治時代の歌人、正岡子規(まさおかしき1867~1902)。「歌よみに与ふる書」を書き、「写生」をとなえた。見たまま、思ったまま表現せよという。この歌はまさにそれ。絵に描こうとするとイメージが浮かんでくる。実際に描いてみよう。
紅(くれない)に赤く伸びた新芽。バラの新芽は赤い色で伸びる。それが2尺(約60㎝)ばかり伸びている。けっこう長く伸びている。
バラだけではない。いろんな木々が、初夏の紫外線にやられないように、葉を赤くしていることが多い。生徒に初夏の庭や街路樹を観察させれば、自然と接する機会の少ない中学生の発展学習ともなる。窓から外を見るだけで、学校には木がたくさん植えてあるので、赤い芽のある木も見られるかも(クスノキなど、けっこう赤くなる木は多い)。
バラは新芽だからまだトゲ(針)も柔らかい。そこに柔らかい春雨が降っている。春雨は、「春雨じゃ。濡れて行こう」(新国劇「月形半平太」のセリフ)といわれ、濡れても大丈夫な柔らかい雨のイメージがあるが、今は集中豪雨がしょっちゅうなので、春でも激しい雨が降っているかもしれない。今の子どもたちは柔らかな春雨をイメージしにくいかもわからない。
この歌では、「やはらか」(柔らか)は「薔薇の芽の針」(針)と「春雨」の両方にかかっている。「針がやわらかい」と「やわらかな春雨」。
短歌は万葉の昔から日本にあったが、「新古今和歌集」や「百人一首」(共に鎌倉時代)以降、短歌はすたれていった。一部の人の趣味の世界となっていた。それを、今のように短歌をつくる人がたくさんいるようにしたのが正岡子規(俳句も刷新した)。
彼の代表作は暗記して覚えてしまいたい。
いちはつの花咲きいでて我が目には今年ばかりの春 行かんとす 正岡子規
春の終わりを告げるイチハツの花(アヤメ科、初夏に咲く=夏の季語)が咲いて、病床の私には今年が最後となるだろう春が終わろうとしている。
実際は翌年も春を迎えたが、正岡子規は秋に亡くなっている。
瓶にさす藤の花ぶさみじかければ たたみの上に とどかざりけり 正岡子規
カメに挿してあるフジの花が短いので、畳まで届いていない。そんな観察ができるのも、ずっと病床の布団の中にいるから。小さなことにも目がいってしまう。
こういう有名な歌も覚えたい。
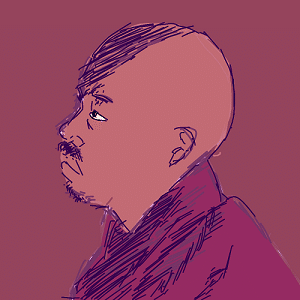
夏のかぜ山よりきたり三百の牧の若馬耳ふかれたり 与謝野晶子
夏の風が山から吹いてきて、草を食べている若い馬たちの耳にあたっている。雄大な自然の中にいる馬の群れ。その中の若い馬たち。300頭いるわけではなく、たくさんいるという意味。
作者、与謝野晶子(よさのあきこ1878~1942)は、ちょうど子育て真っ最中の頃の歌。
海恋し潮の遠鳴りかぞへては少女となりし父母の家 与謝野晶子
海が恋しいなあ。波の遠鳴りの音を数えながら少女となった故郷の父母の家よ。
「海恋し。」と五七五七七の最初の五で「。」がくる初句切れ。
潮の遠鳴りは、ドドドーッと遠くから聞こえる波の音。その音を聞き、「ひとーつ、ふたーつ……」と数えながら育った父母の家よ。体言止めになる(「家」という名詞で終わる)。海と父母が結びついて思い出される。故郷をなつかしむ「望郷の歌」。こういう言葉が高校入試によく出る。ぜひとも暗記して覚えたい。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
