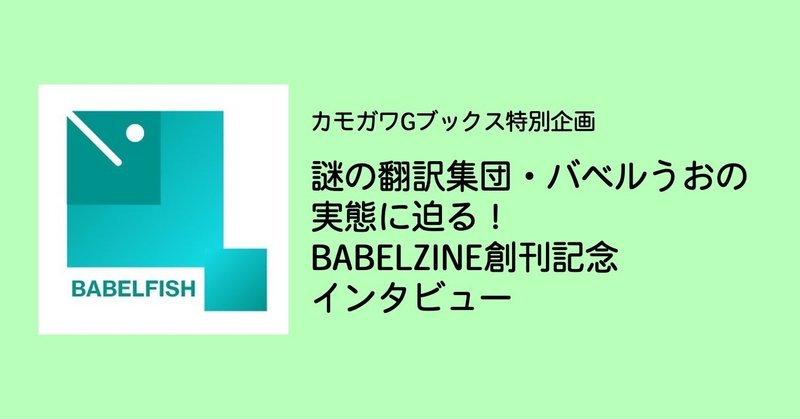
謎の翻訳集団・バベルうおの実態に迫る!BABELZINE創刊記念インタビュー
2020年代の翻訳小説を切り開いていきたい――
そんな力強い言葉とともに、今年の元旦、ある団体のTwitterアカウントが開設された。その言葉を裏切ることなく、当該アカウント上では次々と海外の未邦訳作品が紹介されていった。
そしてついに、今年6月には、紹介されてきた未邦訳短編をもとに自ら編訳した翻訳小説同人誌『BABELZINE』Vol.1を創刊した――その団体とは、謎の翻訳集団・バベルうお(@Babel_Uo)。
彼らは一体何者なのか。そして、彼らの精力的な活動はどのような意識に支えられているのか。
今回は初となるインタビューを通して、謎多き"バベルうお"の生態に迫った。
○8匹のバベルうおと設立経緯について
――本日はインタビューをお引き受けいただきありがとうございます。カモガワGブックスの鯨井です。何卒よろしくお願いします。
さて、バベルうおさんといえば、今年の元旦に突如としてTwitterアカウントを開設され、先日は翻訳同人誌・BABELZINEを創刊されるなど、海外の未邦訳作品の紹介を精力的に行われていますよね。
そこで、みな気になっていることだとは思うのですが……一体何者なんですか!?
未邦訳作品の紹介・翻訳なんて、なかなかすぐにはできないですよね。どういった方が所属されているのか、お話できる範囲でお聞かせ願えますか。
バベルうお いま、バベルうおは8匹います。
このうち翻訳しているのは7匹で、残る1匹は組版や校正を担っています。
なお『BABELZINE』vol.1 のための翻訳作業には、クラブ外からさらにもう1匹が参加しました。
他の団体との関連という面では、2010年代後半ごろに京大SF研あるいは東大SF研に在籍していた個体(インカレ含む。現役会員もいる)によって構成されています。
学生と社会人がともに在籍しており、年齢でいうと、構成員の全員が2020年現在20代です。
メンバーの居住地などはバラバラですが、おもしろい小説をどんどん読み、どんどん翻訳することで、2020年代の日本における海外小説受容(特に、SF、ファンタジー、ホラーなどのジャンルフィクションと主流文学のはざまを行き来する膨大な作品群の受容)を盛り上げたいというモチベーションを共有しています。
🐟 <語尾は「うお」にしたほうがいいウオか?
――なるほど。皆さんお若い方々なんですね。「うお」は……どっちでも大丈夫です。
そういえば、どうして「バベルうお」なんですか?
名前の由来も含めて、設立経緯などお聞かせ願えればと思います。
バベルうお それは秘密です。フフフ
――かわされましたねえ。でも皆さん、英語で小説を読み始めるきっかけになった出来事はあったかと思うんですよね。それは何だったんでしょう?
バベルうお 直接のきっかけについては、個々魚バラバラなので難しいですが、みんな面白い現代小説が英語圏にたくさんあり、しかしなかなか日本語に翻訳されないというフラストレーションを共有しているんじゃないかと思います。
その一つのきっかけとして特筆すべきなのは、2016年~2019年の京都SFフェスティバル(注)の合宿企画で、SFレビュアーの橋本輝幸さんが行ってきた英語ウェブジン(オンライン雑誌)の紹介です。
ウェブジンには無料で読める英語のおもしろい短篇がたくさん公開されているという情報は、企画を聞いていた学部生や院生たちを奮い立たせました。
(注・毎年秋に開催されるSFコンベンション。略称は京フェス。京都大学SF・幻想文学研究会のメンバーを軸として運営されている。主に作家や評論家などのゲストを招いて講演・インタビュー等を行う昼の本会企画と、夜に旅館で行う合宿企画の二部構成が通例。公式サイト)
――確かに、海外小説の翻訳の機会は減ってきている気がします。特に短編SFは、SFマガジンの隔月化以降、訳される機会がめっきり減りましたね。
きっかけとしては、橋本さんの活動が共通して大きかったと。無料というのも、学生にとっては大きいですよね。
○ウェブジン、アンソロジー、推薦リスト……未邦訳作品の泳ぎ方
――次に、紹介・翻訳する短編の選び方なのですが、数多ある作品の中から、どのようにして"発掘"されているのでしょう? また、特にチェックしておられるウェブサイト(ウェブジンや感想サイトなど)があれば教えてください。
バベルうお 選び方は構成魚によってバラバラです。各人お気に入りのレビュアーなどを参考に、おもしろそうな小説をつまみ食いしています。
構成員たちがよくチェックするウェブ媒体はTor.com、Clarkesworld、Lightspeed、The New Yorker、Fireside、Strange Horizons、Uncanny などです。
それから、橋本さんが運営されているRikka ZineのTwitterアカウントの投稿はよくチェックしています。最新の海外文芸事情を発信しつづけられていて、とても参考になります。
また、ローカス誌をはじめとする各媒体の推薦リストや、さまざまな賞のノミネートリストも参考にしています。
(※2019年度版のローカス誌推薦リスト:https://locusmag.com/2020/02/2019-locus-recommended-reading-list/)
長編に比べて短編はハードルが低いので、そういった短くて無料公開されているものを多く読むことで、おもしろい小説を探している構成員が多いんじゃないでしょうか。
一方で、無料のウェブジンに限らず、書籍として販売されているアンソロジーや長編作品を渉猟している構成員もいます。通販の発達や電子書籍の登場により、原書の入手は比較的簡単になっており、価格も国内の出版物と比べて高くはありません。
ウェブジンなどが提供している朗読の音源(一部はポッドキャストアプリで手軽に聴取できます)を聴くのを試していた構成員もいるのですが、こちらは現状ではあまりうまくいっていないようです。
まだまだ方法については模索中でもあります。
――なるほど。この辺り、バベルうおさんの活動に触発されて、自分でも未邦訳で面白い作品を探してみよう! と思われている方にとっては、大いに参考になるのではないでしょうか。訳されたものを読むばかりの側からすると、大変頭の下がる思いですが……。
○実際の翻訳作業と許諾の取り方
――では、未訳作品でおもしろいものを見つけ出したあと、実際に行われる翻訳作業についてお聞きしたいのですが……集団内でどのように翻訳を進めていらっしゃるのでしょう?
バベルうお 個人で頭から終わりまで訳したあと、翻訳メンバーが原文にまで立ち返って訳文を精読します。
気になった点や、誤読ではないかと思われる箇所は、Googleドキュメントのコメント機能を利用して指摘し、相互に意見交換しています。
日本語として違和感があったり、原文と意味が食い違っている箇所については妥協なく指摘を加え合って修正を重ねたので、『BABELZINE』Vol.1 の翻訳の精度はアマチュア翻訳としてはかなり高くなったのではないでしょうか。
また、翻訳の方法とはまたちょっとズレますが、毎週末に翻訳ゼミを開いています。会員が気になった短編小説について、その小説内の同じ部分を個々魚で翻訳し、翻訳文を比べて意見交流をするゼミです。このゼミによって構成魚たちの能力を底上げしています。
また、この翻訳ゼミのなかで他のメンバーから評判がよかったものを今回の『BABELZINE』Vol.1 にも載せているので、他魚の訳を参考にできた短編もあります。
――訳をすり合わせてブラッシュアップして、なおかつそれぞれの翻訳スキルの向上も図っていらっしゃるわけですね。志が高い……。
すり合わせの作業も含めると、相当な手間が掛かっているように思えるのですが、今回の『BABELZINE』Vol.1 には具体的にどれくらい時間がかかっているのでしょうか?
バベルうお 翻訳作業自体は1か月程度、その後のチェックや改稿でさらに1〜3か月程度でしょうか? 当たり前のことではありますが、訳した本数が多い構成魚ほど時間がかかっています。
――元々は5月の文学フリマ東京で刊行される予定だったんですよね。カモガワGブックスの新刊も、それに合わせて同じブースに置かせて頂く予定でした。ですが、昨今の情勢を受けて文学フリマが中止になってしまって……。それに伴って『BABELZINE』の刊行も1ヶ月ほど後になりましたが、その期間はブラッシュアップに伴う改稿をされていた、ということでしょうか。
バベルうお 『BABELZINE』の刊行がもともとの文フリよりも遅れたのは、ブラッシュアップに使ったのもそうですが、人間明確な締め切りがなくなると怠けるというのが大きいですね(笑)
――ん? 人間……?
それはさておき、翻訳の頒布許諾に関してはいかがでしたか。翻訳に縁遠い人間には全然想像のつかない過程なのですが、やはり相当難航されたのではないでしょうか?
バベルうお 翻訳の許諾については、作者本人にメールで直接問い合わせました。結果的に許諾が取れず惜しくも載せられなかった作品も多くありますが、快諾してくれた作家の方も多く、『BABELZINE』の創刊号に11編もの短編を載せることができました。
たとえば、メンバーの白川は5編交渉して1編載せられたくらいの打率ですね。もっと打率が良かった魚もいますが。
――5編に1編はかなり大変ですね……。見えないところでの努力が偲ばれます。
○今後の展望――2020年代の翻訳小説を切り開くために
――最後に、今後の展望についてお聞かせ下さい。
バベルうお 第一の指針は、『BABELZINE』を継続して作り、頒布することで、最新の海外小説を日本語で読める豊かな土壌を形成することです。
Vol.1では権利交渉、翻訳のブラッシュアップ、印刷所への入稿と、何もかもが手探りの状態からのスタートでしたが、ここで得た経験をうまく生かして、安定的に号を重ねていければと思っています。
第二の指針は、英語圏のおもしろい未訳小説をたくさん紹介し、英文小説を読む文化をもっともっと多くの日本語読者に広げることです。やっぱり「ガイブンはハードルが高い」と思われている方は多いと思うので、できるだけこのハードルを下げていきたいと考えています。
それから、これまでTwitterでの未訳作品紹介をメインに行ってきましたが、徐々にnoteでまとまった記事を公開していきたいと考えています。ぜひわれわれのアカウントをフォローして、今後の活動にご注目ください。
――素晴らしい取り組みだと思います……! これからもぜひ、2020年代の翻訳小説を切り開いていっていただきたいです。
BABELZINE創刊の言葉で引かれていた「言語を越えて複数の荒れ地を出会わせる営み」の実現に向けて頑張ってください! 本日はありがとうございました。
(2020年6月某日)
※このインタビューは、9月刊行予定のカモガワGブックスVol.2 英米文学特集にも掲載予定です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
