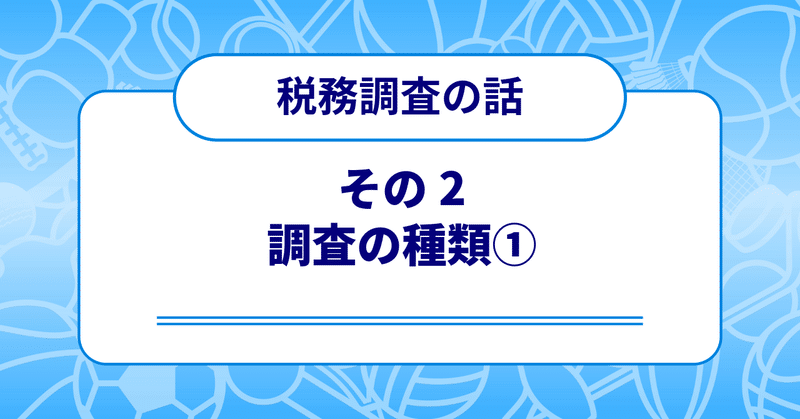
税務調査の話 その2 〜調査の種類①〜
元国税職員による税務調査のあれこれ。第2回は、調査の種類を整理します。
前回の記事
強制力による分類
意外に思われるかもしれませんが、税務調査には、理由もなく拒否できるという意味での純粋な任意調査はありません。全て強制力を伴います。
間接強制調査
国税通則法第74条の2等に規定される質問検査権の行使による調査で、ほとんどの税務調査はこちらです。詳しく知りたい方は↓を参照
一般的には任意調査と呼ばれますが、同法第128条第2号により、調査を忌避した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。これを受忍義務といいます。
ごく稀に調査を妨害したり質問に答えなかったりする納税者がいますが、この受忍義務を説明して調査に応じるよう説得することになります。
直接強制調査
国税犯則取締法による刑事事件の立件を目指した直接的な強制力を伴う調査です。妨害行為に対しては、強制力をもって排除することができます。
例えば、納税者が玄関や金庫の鍵を開けない場合、錠前を破壊して捜索を行うことができます。また、一般的には、証拠隠滅防止のため、調査着手時に行動の静止を求められます。
こちらの調査は、国税局査察部の所掌となり、税務署が行うことはありません。昔はマルサという隠語が使われていましたが、映画でこの言葉が有名になったため、職員は査察部の所在するフロアでもって、"○階"と呼ぶことが多いです。
予告の有無による分類
上記の犯則調査は当然無予告です。こちらでは、一般的な税務調査を想定しています。
数年前の国税通則法の改正により、原則として税務調査は予告をしてから行うこととされましたが、必要性が高い場合には無予告で調査を行います。
最近ではキャッシュレス決済も増えてきましたが、現金で代金を支払う飲食店もまだまだ多いです。現金決済の場合、記録が残らないことも多く、現金そのものを隠してしまえば売上を少なく見せる脱税(売上除外といいます。)ができてしまうので、飲食店の調査の多くは無予告で実施します。
内観調査・外観調査
こちらは、税務調査着手前の準備的な調査で、無予告調査の着手前に実施されることが多いです。
内観調査
主に一般消費者向けの店舗を対象に実施します。飲食店が多いですね。飲食店を例にすると、調査官が実際に客として入店し、お客さんの数をカウントしたり、メニューから概ねの客単価を想定したりして、1日の売上を推計します。これと帳簿上の売上を対比して売上除外の有無の心証を得ます。
風俗店でもこの手法がよく使われます。筆者もあまり気が進みませんでしたが、キャバクラや個室ビデオ店の内観調査を実施したことがあります。直接的なジャンルに当たらなくて良かったです(笑)
ちなみに内観調査の費用は公費で支弁しますので、喜んで行きたがる人も中にはいます。
若手の女性事務官に向かって「お前この店の面接受けて来い」とか今ではあり得ないパワハラ・セクハラも見聞きしましたね。ひどい職場です…した。
なお、「お客さんの入りからすると売上が少ないですねぇ」と言っただけで「すいませんでした!」とは通常なりませんので、コスパが高い方法かというとなんとも言えません。
また、古典的な手法として、前日夜に番号を控えた1万円札を使用し、調査当日の朝にその1万円札の存在を確認するということもあります。1万円札はお釣りとして出ることはないので、銀行が開く前にその1万円札がなければ隠したことになるからです。
外観調査
店舗の外観を見て回り、調査着手時の逃走ルートの見落としがないかを確認したり、社長の自宅を見て役員報酬の金額との対比で不自然に豪奢でないか確認したりします。脱税して捻出した資金で自宅や高級車を購入している場合もあるからです。大抵は空振りですが…
調査の着手は代表権のある社長に宣言しなければならないので、社長の行動パターンを把握することも重要です。店舗に入ってみたものの社長がおらず、調査着手を察知した社長に証拠隠滅を図られるなんてこともあります。社長が自宅にいることが多い場合、店舗と自宅に同時に調査に入ることになります。調査官同士で「着手5分前、準備完了」「社長と接触成功!ただいま交渉中」なんて緊迫したやり取りをします。
おわりに
少し長くなってしまいましたので、今回はここまで。このほかにも財務分析に基づく準備調査や銀行調査などなどありますので、次回もお楽しみに!
次の記事
お仕事のご依頼はこちらまで
最後までお読みいただきありがとうございます😊少しでもお役に立ったらスキ(❤️)していただけると嬉しいです。note会員でなくても押せます。
