
ことばを探求し続ける人
安部広太郎さんをこのように表現したら失礼にあたるだろうか。
この度、安部広太郎さんの『コピーライターじゃなくても知っておきたい心をつかむ超言葉術』を拝読した。
幼い頃から本を読んで育ち、言葉に興味があり、ひすいこたろうさんというコピーライターさんの本を中学生の時に読んで以来、"コピーライター"という職業に興味があり、更に、大学でフリーペーパーサークルに所属し、その記事を書いている身として、買わない・読まないという選択肢はなかった。
「はじめに」の「I LOVE YOUの訳し方」で、まず引き込まれた。かの文豪が「月が綺麗ですね」と訳したのは有名な話。それを自分に落とし込むという作業。これが最初の関門なのか。私がどう訳したかは後述するとして、特に印象に残った点を記してみたいと思う。
①第7章「企画書はラブレターだ」から「あなたはあなたになる」より
ここを読んでいるときに、ふと、かつて取り組んでいたビブリオバトルが思い出された。
ビブリオバトルとは、「本を通して人を知り、人を通して本を知る」というコンセプトのもと、行われている知的評本合戦である。下記のリンクはビブリオバトル公式サイトである。
引用先:知的書評合戦ビブリオバトル公式サイト
本が大好きな人たちが「この本こそは!」という本を持ちより、5分間で本を紹介する。聞き手は、紹介された本のうち、「最も読んでみたいと思った"本"」に投票する。本について語った人にではなく、あくまで、紹介された本に投票するのだ。ここがこのバトルの面白いところだと思う。
私は高校時代にこのバトルの県予選に参加した。相棒は、河村元気さんの『世界から猫が消えたなら』。
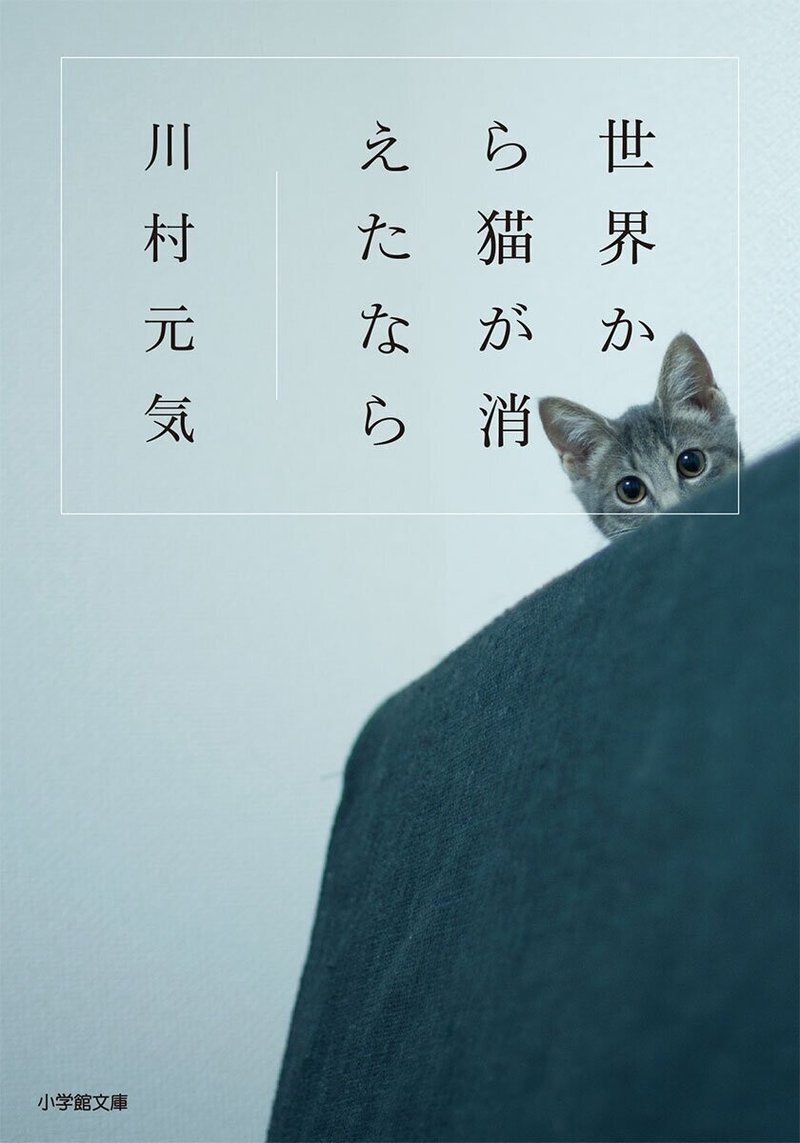
余命宣告をされた青年の前に、悪魔が現れ、「この世界からモノを消す代わりに、貴方は1日長く生きられる」と告げられる。彼は悪魔に言われた通り、モノを消していくが、その世界で見たのはーーー。
結果は予選敗退であったが、大勢の前で好きな本を5分間語りきるというのはとても貴重な経験をしたと思う。
私がビブリオバトルを思い出したのは、恐らく、文章の中に出てくる、「企画書を通して自分を知ってもらう」という言葉からだと思う。企画書は、企業へのラブレターであるし、ビブリオバトルは、作家への、そして本へのラブレターであるのだと思う。
何かを好きであるという気持ち、その好きなものを伝えたいという気持ちは、どんな分野・業界を問わず共通しているものなのだろうという気づきを得られた。その思いが評価されようとされなかろうと、その思い、何かを熱烈に好きになり、その素晴らしさを伝えたいと思えただけで、それは財産になるし、生きていてよかったと思える。
②第4章「感動屋になろう」から「つくり方から企画する」より
ここでは、阿部広太郎さんがシンガーソングライターの向井太一さんとの共作詞に挑んだときの体験が綴られている。
すでにメロディーがある「曲先」の状態であり、向井さんが考えた歌詞もある状態での作詞。阿部さんは今までともに企画を勉強してきた企画生たちのことを考えていた。
そしてできたのが次の『FLY』という楽曲である。
引用先:向井太一/FLY(Official Music Video)/YouTube
文章中にこのurlを見つけ、YouTubeで音楽を聴き、向井さんの高音の澄んだ歌声と力強く背中を押してくれる歌詞に聞き惚れていたのだが、「THE FIRSTから来ました!」というコメントを見つけ、首を傾げた。
THE FIRSTとは、SKY-HI率いるBMSGが主催したボーイズグループ発掘オーディションである。一次審査(書類選考)、二次審査(各地開催)、三次審査(歌唱・グループ審査)、合宿審査、最終審査とあったのだが、私は合宿審査から追いかけていた。そのTHE FIRSTとこの楽曲の関連が見えずにいたのだが、二次審査でこの曲を歌った方がいらっしゃったのだ。彼も高音を使いこなし、のびやかに歌っていてとても魅力的であった。
このように、「言葉」が好きな私がこの本に出会い、この本から新しい音楽に出会い、その楽曲が私の好きな「THE FIRST」に繋がっていた。この偶然にとても驚いた。と同時に、「好きなものは繋がるのだなぁ」という妙な納得感に包まれた。
最後に、私の「I LOVE YOUの訳し方」を記してみたいと思う。
文章を通して、安部広太郎さんから「今、どう訳しますか?」と問われ、私は「愛する」ってどういうことだろうか、というところから考え始めた。
まず思い浮かんだのは、「愛の反対は憎しみではなく無関心」という言葉だった。つまり、愛とは、関心を寄せること。誰かに興味を持ち、誰かと繋がろうとすることだと思った。
浅田悠介さんという方が書いた、『宇宙が終わるまでに恋をしたい』という本の中で出てくる、(ベニコさんがとにかくとてもかっこいいのだか、それはまた別に紹介してみたいと思う。)その中で、他人に興味を持つための方法として、「ブリッジ」という技術が紹介されている。これは、他人という宇宙を知るためにすることであり、これこそが愛への第一歩ではないかと思う。
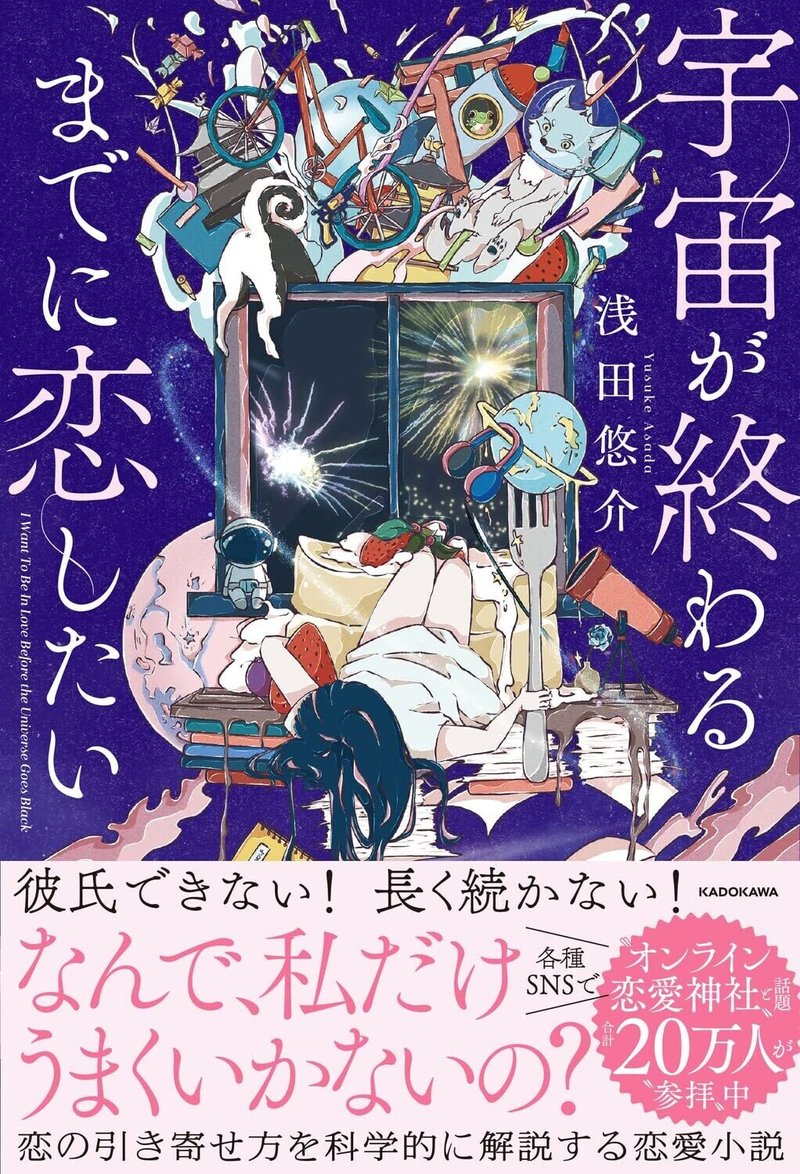
だから、今の私の「I LOVE YOU」の訳し方は、「お茶しません?」である。
どういうことか。私にとっての関心の向け方とは、「一緒に美味しいものを食べながら誰かと話をすること」、そして、そのために「誰かを誘うとすること」が愛への第一歩ではないかと考える。
愛するとは、本当に広い意味がある。だから、今回は、誰かに興味を持つこと、そのことからもうその人への「I LOVE YOU」を伝えることになるのではないかと考えた。
また、この言葉を見つけたとき、思い浮かんだのは、「長年連れ添った老夫婦が寄り添ってお茶を飲んでいる」様子であった。あなたは、「一緒にお茶を飲もう」を読んで、どんな場面を思い浮かべただろうか。
これから、私の「I LOVE YOU」の訳し方は変わっていくと思う。だから常に考え続けたい。誰かを愛するとはどういうことなのか。言葉とはどういうものか。
この本を読んで、言葉への熱意、仕事への熱意を改めて考えることができた。そして、一つ一つのことを真摯に向き合うことの大切さを再認識できた。
僭越ながら、この文章をもって、私から安部広太郎さんへのラブレター(読書感想文)としたいと思う。最後になるが、この本に関わるすべての方、そして、ここまでこの文章を読んでくださったあなたへ、感謝を込めて。ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
