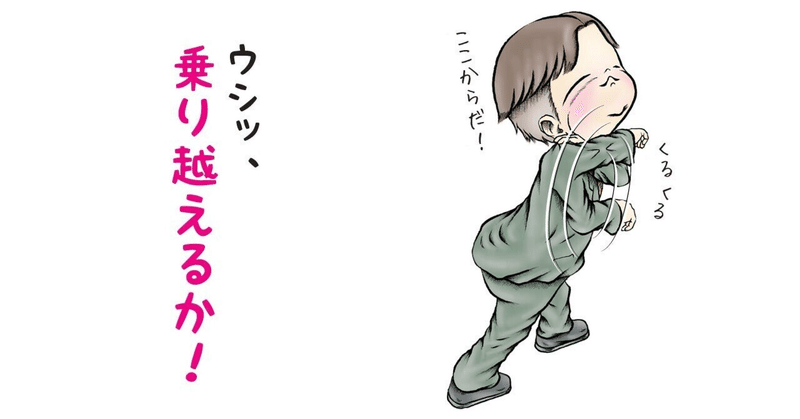
Giver、Taker、Macher
最近出会った考え方に、このような考え方がありました。
かくいう私は、上記のテスト結果に従えば、恐らくマッチャー。ただ、完全なマッチャーではなく、割とギバー寄りのマッチャーだと感じています。
noteでは楽しいだけでなく、嫌な思いも何度か経験してきました。
先日、ある方との会話で「優しい人ほど、人間関係に苦労している印象がある」という会話がありました。
実際に、私の周辺でもそういうタイプは多いです。ただ、ワタシ自身は闘争心をむき出しにすることは滅多にないため、「giverタイプ」に見られ、結果として利用しやすい人物と踏まれる傾向はあったのかもしれません。
GiverタイプはTakerの標的にされやすい?
そう捉えると、何となく、ワタシがトラブルに巻き込まれるパターンも見えてくる。
個人的には、会話の端々で「○○してやっている」など、見下したモノ言いをしている人は、やはり要注意人物。
私を一方的に「giver」だと思い込んでいたとしても、それは完全に先方の都合。そして、私は「giver」の要素が強めかもしれませんが、本質は恐らくマッチャー。
また、ビジネスの世界では「giverが成功しやすい」と言われていますが、実際には、「Macher」の方の割合が多いのですよね。
誰もが成功者になれるわけでないのは、数字上明らかです。では、どうやって幸せになるか。
一例として、マッチングの相手から「どのようなgiveを受けたか」。それを意識するのも大切なのではないでしょうか。
何も財物に限った話ではなく、例えば、noteであれば「素敵な作品を提供していただいて、ありがとうございます」の気持ちも大切、ということです。
それは、きっと自分自身を肯定することにもつながってくるから。
取られるのはモノやお金だけではない
そして、物凄く共感した……というのでしょうか。「薄々気づいていたけれど、やはりそうだったのですね」と感じたのが、こちらの記事でした。
やたらとネガティブな意見や、「強い意見を言える自分」に酔っているのではないか?と感じる人っていませんか?
私自身も、「ああ、この人は自分が認められたい承認欲求を満たすために、他の人を利用しようとしているのだな」と感じる人に、何人も出会ってきています。
特に、印象深いのは以下の段落でしょうか。
我が国においては、「実るほど頭を垂れる稲穂かな」という言葉がある通り、成功者ほど謙虚であるスタンスが好まれ、過度に自分の優位性を誇る姿は下品と見る人は少なくない。それでもめげずに自分のPRがすぎると、「特定班」と呼ばれる一派に恥ずべき過去を掘られ、一気に称賛から批判へと流れが逆転するという光景はこれまでに何度も見てきた。
先に示したTakerが得ようとするのは、必ずしも金銭などの財物に限りません。
相手方の関心や愛情を買おうとするのも、立派なTakerの行為の一つ。ときには、人脈や信用すら奪い取られることもあります。
まあ、多くの人、すなわちマッチャーやgiverからすれば、「お付き合い」の範囲内で穏便に済まされますし、「お互い様」と感じる部分もある。だからこそ、多くの人は「面倒そうだな」と感じたら、そっと離れていくのですよね。
ですが、本当に自己中タイプのTakerの場合は、全ての世界をゼロサムゲームと捉える傾向がありますし、何よりも、付き合っていて非常に疲れます。
先の研究によれば、全体の中の19%がtakerだというデータが出ていますから、確率論で言えば、約5人に1人がtakerタイプということになります。
これを多いと見るか、少ないと見るか。
捉え方は人それぞれでしょうけれど、私の場合も、お付き合いしてきた人々のトータル数で言えば、あながち的外れでもないのかな~と感じます。
承認欲求は、多くの人が多少なりとは持っているもの。ですが、アゴラの記事でも示唆されているように、それが他人に向けられ、時には行き過ぎてしまうことが問題なのです。
Giverならでの喜びも大切にして欲しい
私も多少なりとは承認欲求も持っています。もっとも、それは自分自身との対峙の仕方の問題であり、本来は、敵対的に他人に向けるべきものではありません。
少し嫌らしい話になりますが(苦笑)、いわゆる「フォロー返し」も「スキ返し」も、大体は「返報性の法則」の一言で、心理的な説明はできてしまうのですよね。
ですが、それを盾にいちいち噛みついていたら、疲れませんか?
自分自身を他者と比較することはあまりないですが、憧れることはある。ですが、結局「その人の完全コピー」になれるわけではないのですよね。育ちも環境も、100人いれば100通りの人生があるのですから。
そしてTakerが満たされることがないのは、人が離れていく原因が理解できず、ますます負のスパイラルを招いているからなのかもしれません。
MacherやGiverの人々がそれに付き合わなければならない必要性や義務は、ないと思うのです。
「最近、周りから嫌われているかも」。
仮に、そのように感じたのならば、
相手を利用するために、関心をひこうとしていないか
相手の時間と感情を浪費させていないか
それを意識するだけでも、かなり状況は変わってくると思うのですけれどね……。
少しばかり強めの意見に遭遇しまくって疲弊していた反面、多くの仲間の「楽しい」空気、そして各種の企画などを通じて新しい出会いに何度も救われた。そんなジェットコースターのような感情を味わった、今年の春でした。
©k_maru027.2022
これまで数々のサポートをいただきまして、誠にありがとうございます。 いただきましたサポートは、書籍購入及び地元での取材費に充てさせていただいております。 皆様のご厚情に感謝するとともに、さらに精進していく所存でございます。
