
インターネットアートとは何か
人間の知覚が形成される方式――知覚のメディア――は、単に自然の制約だけでなく、歴史の制約も受ける。
コミュニケーション自体は実態でないので知覚対象たり得ないが、芸術がこの不可能を補完する。
はじめに
本日2020年8月18日から、東京都写真美術館で「エキソニモ UN-DEAD-LINK インターネットアートへの再接続」展が始まった。インターネットアートの先駆者であるエキソニモの初期から現在に至る活動をすべて追うことができる、歴史的な展覧会である。2017年頃から準備を進めてきたが、コロナ禍により通常の展示が叶わない中、インターネット会場とリアル会場の2部制という形で行われることとなった。
アート・ユニット「エキソニモ」初の大規模回顧展、東京都写真美術館で - リアルとオンラインの接続 - https://t.co/BsDUTRwtOy pic.twitter.com/BPqMjP5x01
— Fashion Press (@fashionpressnet) August 15, 2020
遡ること8年前の2012年2月28日、私はNTT ICC(インターコミュニケーション・センター)で行われていた展覧会「インターネット アート これから――ポスト・インターネットのリアリティ」展に足を運んでいた。
会場内では、Webを通じて日々アップデートされる作品、Web上に存在する膨大なデータを利用した作品、匿名性と自己同一性というインターネット文化の特徴を捉えた絵画など、通常のギャラリーでは展示し得ない多種多様な芸術作品が存在感を放っていた。それらは私に「インターネット」と「アート」の関連を考えるきっかけを与えてくれた。

そもそも「インターネットアート」とは何だろうか。
美術評論家の暮沢剛巳が「未来派からメディア・アートまで 芸術と科学の同床異夢」(2005)で定義したところによると、「コンピュータ空間内に構築されるアート作品の総称」であり、「その範囲はきわめて広いが、ネット特有の環境を利したアート作品」となる。続けて彼は「1997年以降はRealplayer8などのプラグインが普及、さらに遠近感に富む表現が可能になり、ネットアートはわずか10年のうちに百花繚乱の観を呈するようになった」とも述べている。
またGRANDBASE inc.代表の栗田洋介の定義によると、「インターネット特有の要素をテーマにしたアート作品」であり、「Webブラウザ自体であったり、ソースコードであったり、ハッキング文化的なものであったり、ネットに潜む事象を新たな解釈で捉えて、提示している作品たち」を指すものである。それはブログ・BBSなどの個人サイトや、既存のアート作品をそのままWeb上で閲覧可能にする活動とは区別する必要がある。
暮沢も「範囲はきわめて広いが」と留保しているとおり、インターネットアートというジャンルを正確に定義することは難しい。そこでまずは、1990年代にインターネットアートが成立するに至った背景を、1960年代から現在までの美術史的・技術史的観点から順に確認していきたい。
インターネットアート前史
インターネットアートは、その源をコンピュータアート(制作や展示にコンピュータを用いる現代アートのジャンル)に発する。初期のコンピュータアートは、技術者がコンピュータの可能性を拡張するために試みたテクノロジー・オリエンテッドなものだった。
記録に残る最初のコンピュータアートは、ベン・F・ラポスキー(1914–2000)の「オシロン」(1952)であるとされる。リサージュ曲線と呼ばれる数学的形体をコンピュータに出力させたもので、細胞分裂のような神秘的な曲線美をそこにみることができる。

このような表現は 「オートマチック・ドローイング」と呼ばれたが、関数や方程式をコンピュータに高速で処理させてその結果を出力したりするだけでは、アートのジャンルとして定着するほどの力は持たなかった。この時代のコンピュータアートは、ベル電話研究所や大学でコンピュータを専門に扱うエンジニアによる幾何学的パターンの作品が大半を占めていた。
有名なものとして、ケネス・C・ノールトン(1931-)とレオン・D・ハーモン(1922-1982)による「コンピュータ・ヌード」(1967)がある。人物写真をコンピュータに取り込み、濃淡の階調を自動的にデジタルな記号に置き換えて出力したものである。ニューヨーク・タイムズ紙に掲載されたことで、コンピュータアートが広く公開された最初期の例となった。

コンピュータアートの流れが大きく変わる歴史的な展覧会が、1968年にロンドンのICA(Institute of Contemporary Arts)で開催された「サイバネティック・セレンディピティ」展である。展覧会の副題に「コンピュータと諸芸術」とあるとおり、コンピュータにまつわるさまざまなアートを集めた初の国際展覧会であった。
図形やペインティングといった視覚芸術だけでなく、作曲や自動演奏、コンピュータと融合させたダンス・パフォーマンス、実験文学、キネティック・アート(動く彫刻)、CADシステムによる芸術作品などが一堂に会した。ICAディレクターのヤッシャ・ラインハート(1933-)によって企画され、その後米国に巡回して計4万人もの来場者を記録した。
マーク・アドリアン(1930-)によるテクストを分析・処理して自動出力させる「コンピュータ・ポエム」も展示された。世界初のコンピュータによる詩であり、現在の言語処理技術の先駆けである。
ウィリアム・フェッター(1928-2002)は大型コンピュータを駆使して3Dモデリングや流体力学のシミュレーションを行い、グラフィック・デザインに革命をもたらした。フェッターはボーイング社のエンジニアでもあり、「ボーイング737」の設計者として航空史に名を残している。

日本からは東京大学工学部と多摩美術大学の学生を中心に結成された制作グループ、CTG(コンピュータ・テクニック・グループ)が出品した。彼らの代名詞的存在である「Monroe in the net」(1968)は、パターン認識技術を使って格子状のグリッドをわずかに歪めることで、遠くから眺めるとマリリン・モンローの顔が浮かび上がってくるものである。

1970年代に入るとCG(コンピュータ・グラフィクス)技術が進歩し、エンジニアにとどまらずアーティストの関心を大いに惹くようになった。1980 年代には一般の鑑賞に耐えうる高度なCG表現技術が発達し、TVコマーシャルを中心にCGブームが巻き起こった。自由な視点から斬新でダイナミックな映像が作られるようになり、色を混ぜると暗くなる(減算混合)ことがないため、輝度の高い色を使った視覚体験を提供できるようになった。
1982年にSIGGRAPH(アメリカ・コンピュータ学会におけるCGを扱う分科会)で開催された第一回アート・ショウは、タイルやタペストリー、工業用グラフィック・デザインや照明器具など、広範囲なコンピュータアートが集う場となった。従来のコンピュータアートが、新しいテクノロジーの体験とそれを通しての造形をそのまま芸術表現にしていたのに対し、このアート・ショウでは、機械が提供するインタラクティヴな交流、時間・空間を巻き込んだ人間の意識の拡大がテーマとなっていた。
1980年代以降のコンピュータアートのキーワードはこの「インタラクティヴ性」、すなわち「作品と鑑賞者との”相互作用”によって芸術表現が成立する」ことであり、絵画や彫刻といった既存の芸術形式には見られない大きな特徴となった。
外部環境の光・音・動き・温度を捉えて反応する高精細なセンサー技術が発達し、またそれらの情報を基に作動するフィードバック機構の技術も上がっていった。人間の五感に近いセンサーだけでなく、 超音波や赤外線、無接触のオプティカルセンサーなど、人間が感知できない技術も次々と開発され、魔術のような体験が身近なものとなった。
このような潮流は1990年代に至っても変わらず、VRやARといった技術をアートに取り入れ、未だかつて体験したことのない芸術表現が旺盛に試みられている。
1990年代半ばにはインターネットという新技術の商用利用が開始され、双方向性を特徴とする新たなメディアが登場した。この流れを受けて現れたのが「究極のインタラクティヴ性」を有するアート、インターネットアートである。
インターネットアートの代表的作家
インターネットアートの代表的作家紹介するにあたり、まず何と言っても最初に挙げなければいけないのがJodiである。
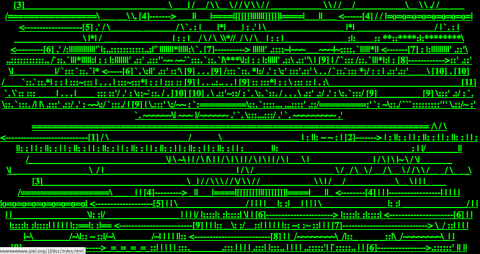
Jodiはオランダ人Joan Heemskerk(1968-)とベルギー人Dirk Paesmans(1965-)の2人組ユニット。1990年代中頃から活動を始め、現在でも不定期に活動を続けており、未だにその活動に関して議論が交わされ続ける特異な存在である。
初期の作品はWeb上にのみ存在する。そこにアクセスした途端、まるでコンピュータがクラッシュしたかのようなカラフルな画面が現れるというものである。これだけ聞くといわゆる「ブラウザクラッシャー」であるが、"誕生したばかりの新しいメディア"を通して"特権的なアーティスト"(当時は現在のように誰もがプログラミングできるわけではなかった)が"誰も見たことのない視聴覚体験"を提供する、という点で、まさにメディアアートの特性を備えている。
白井雅人は「メディアアートの諸相」(2008)の中で、彼らの活動を「Webやそこで使われるHTMLコードを脱構築(デコンストラクション)するような作品」と評している。ネットの文法を用いながらその文法自体の危うさを暴くという点では、まさにポストモダニズム的な野心が垣間見えると言える。
同じくインターネット黎明期の代表的アーティストとして、英国のヒース・バンティング(1966-)が挙げられる。

彼の初期の作品で今でも高く評価されているのが「Kings X Phone in」(1994)である。日時を指定してロンドンのキングス・クロス駅にある公衆電話に世界中から電話をかけるようインターネットで呼びかけるという作品だ。受動と能動を逆転させる可能性を秘め、近年「フラッシュ・モブ」として定着した現象の一種の原型を見ることができる。
もうひとつの初期作品として「_readme.html (Own, Be Owned or Remain Invisible) 」(2006) が挙げられる。デイリー・テレグラフ紙に評論家ジェームズ・フリントが書いた批評記事をインターネット上にそのまま載せ、その記事の一単語一単語にその単語のリンクを貼る(たとえば「This year」というそれぞれの語に「www.this.com」「www.year.com」を貼る)というものだ。
伝統的なメディアでは批評家は一方的に評価するだけで、アーティストはそれについて論評することは不可能だったが、ハイパーリンクの特徴を生かして彼は批評家の文言をいわば批評する身振りを示したのだった。バンティングが「メディア・アクティヴィスト」と呼ばれる所以である。
こうしたバンティングの試みは、インターネットアートが新しい芸術表現であるだけでなく、芸術そのものの概念を変えてしまうこと、芸術と批評、社会や政治との境界線を揺るがせてしまう可能性を予感させた。バンティングのインターネットに関する驚くべき見通しは、これらの作品から20年近く経った今振り返っても色褪せることはない。
エキソニモとインターネットアート
続いてインターネットアートの日本代表とも言えるアーティスト、エキソニモを紹介する。
エキソニモは赤岩やえと千房けん輔による2人組ユニットで、1996年にインターネット上の実験的プロジェクトを開始し、現在も旺盛に作品を発表し続けている。
大学の同級生だった彼らは就活もせず、まだインターネットも繋がっていないパソコンでHTMLを書くバイトをしていた。二人は当時をこう振り返る。
千房:ネットに実際接続できた時は、やっぱりインパクトが大きかった。当時はいまとは違う意味でのカオスで、しかも誰でも参加できる感じがあって。たとえば、詩を自動生成して投稿するサイトとかね。
赤岩:あの頃は特に、クオリティよりもアイデアが光るものが多かった。たとえば画面一杯にボタンだけ! とか(笑)。これクリックしたらどこに飛ばされて何が起こるんだ? っていう世界をいろいろ見まくって。そういう自由でアンダーグラウンドっぽい部分に、すごく惹かれた。
2004年には初の絵画作品「A Web Page」を製作した。Google.comのトップページをそっくりそのまま模写して絵画にし、それが美術館に展示さ れている様子をウェブカメラでネット上に配信し続ける、という一種のインスタレーション・システムだ。この作品はネット上で反響を呼び、なんと後にGoogle本社が購入することになる。

―― [Web ページがアナログ(絵画)に変換され]→[美術館にインストールされ]→[展覧会という場を通して]→[再びデジタルに変換され]→[インターネットに送信される]、Web から来て Web に戻っていく、おそらく世界一遠回りなややこしいプロセス!! そして、間に美術館がはさまるという事で、この情報の流れは劣化するのか?発酵するのか!!!!!!? 実物のWebページの絵を実際に見に行く? 会場経由の「Webページ」をWebから開く?――
2006年に発表された移動型インスタレーション「The Road Movie」 は、20日間移動するバスにウェブカメラを仕掛けて定期的に周囲の風景を撮影、それをバスの形の折り紙の型紙に映し込んでWeb上にアップし続ける作品である。鑑賞者はホームページから型紙をダウンロードしてプリントアウトして折ることで、ある瞬間のバスとそこから見える周囲の風景が部屋の中に出現する。
実際に走っているバスの現実の風景なのに、インターネットを通すことで非現実的なイメージに加工され、出力され、拡散される。また同時に、まったく知らない遠い場所の風景のはずなのに、部屋の中には実際に具現化された「バス」が出現している。

現実と非現実を行き来するこの作品は、メディアアートに関する世界最大のイベントであるアルス・エレクトロニカで、“メディアアート界のオスカー”と呼ばれる最も権威ある賞「ゴールデン・ニカ賞」を受賞した。
2009年にはNTT ICC で一風変わった展覧会が行われた。その名も「ゴットは、存在する。」。
千房:じゃあれはどうでしょう、《噂》ってやつ。これは「ゴットは、存在する。」っていう展覧会をやったときに作った作品で。モニターが天井からぶら下がってるんですが、そこにTwitterの画面みたいなものが流れてます。それをよく見ると、「ゴット」 ということについてみんながつぶやいている。見てると「ゴット」っていうのがあたかも存在するように見えるんだけど、なかでやってることは実は「神」という言葉をTwitterでサーチして、その「神」を「ゴット」に置き換えて出してるんですよ。
ただ文字が出てくるだけなんだけど、ツイートをしたことがある人から見ると、こんだけの人がこんだけツイートしてるってことの、すごいザワザワ感みたいなのが感じられ るじゃないですか。Twitter のストリームの“のどごし”みたいな(一同笑) 。その感覚が作品にできると思って、やったんですよ。あと、これただ「神」を「ゴット」に置換してるだけで、よく見るとほんとにおかしいんですよ。「ゴット奈川県」とか「東方ゴット起」とか(笑)。
ここでやってるのって、実は小説だと思ってて。つまり、ふつうに正しいTwitterのタイムラインが流れてくるっていうのは、いまのこの世界を反映してるじゃないですか。でもそこをちょっと書き換えるとフィクション......ゴットが存在する世界が、これだけで表現できちゃうっていうか。それだけで小説を一つ書くぐらいのことが実現できるっていう。だから、そういうサーヴィスのもってる力みたいなものをすごい使ってやってる。これもほんと Twitterみたいなことをみんながやってるからこそ、できるようになった作品ですね。
この展覧会が行われた当時はiPhoneが日本で発売されて1年半ほどであり、Twitterを利用したアート作品がギャラリーに展示された世界でも最も早い例の一つであろう。
おわりに
最後に「インターネット時代の美術館について」を考える上で、特にソーシャル・メディア全盛期の現状を踏まえて興味深い発言を紹介しようと思う。冒頭で取り上げた「インターネット アート これから――ポスト・インターネットのリアリティ」展開催のきっかけとなった、「インターネット・リアリティ研究会」による2011年の座談会である。
少し長くなるが、インターネットアートの最先端で活躍してきた彼らが9年前に予測していたことは今後のインターネットとアートとの関係を考える上で示唆に富むものである。
畠中(畠中実。NTT ICC 主任学芸員):これからやろうとしてるのはさらに先にいった、もう展示空間がなくても成立するような展覧会。そういうインターネット・オリエンテッドな展覧会を、構想するとしたら?っていう話になってくるわけですよね。
千房:さっき、既存のネット展への違和感について話してくれって(TwitterのTLに)あったんで、ちょっと話しましょうか。普通の展覧会って、たとえば展覧会場に行った時点ですごい特別な空間に入ってる。そのうえで展示会場を歩いて、作品に出会うわけじゃないですか。そういうことのデザインがちゃんと練られているような気がしてて。歴史があるっていうか。で、観終わって会場から出てくると「ああなんかいい経験した」みたいなことになってるんですけど、ネット展だと、たとえば作家名があって作品(へのリンクを)クリックすれば見られる。それを見て、観終わって閉じて、また次クリックして見て......ということが、作品を見るうえで作品が特別なものに見えないというか、クリックするという行為の意味や重さと作品を観るということとの関係性がつりあってないような感じがしてて。やっぱり作品とどこで出会うかみたいなこととかも全部含めて成立してないと、いい体験にならない気がするんですよね。
畠中:美術館を順路どおりに見ていくっていう現実世界の経験の代わりをインターネット上で展開してもダメで、そこではその空間なりの、つまりインターネットの空間なりの歩き回りかたがあるはずだっていうことになりますよね。
渡邉(渡邉朋也。メディアアーティスト):座談会の最初の方でも、これまでのネット・アートの展覧会は、実際の美術館での展覧会の劣化コピーだという話がありましたが、まさにそのとおりだと思うんですよね。僕としては、もしいまインターネットで展覧会をやるのだとすれば、TwitterとかFacebookのタイムラインにbit.lyとかの素性の知れない短縮URLを流して、なんとなくそれをクリックした人のブラウザで突如として何かが始まるとか、あるいは展覧会の出品作品となる画像や映像を放流するTumblrのアカウントや、「インターネット・リアリティ」的なものをリブログしまくるアカウントを用意して、それをフォローした人のダッシュボードを占拠する、とかそういう感じがいいのかなと思っています。要するに、そういったSNSを通じたコミュニケーションが普遍的な生活様式の一部になり、日常の一部となっている。そこに作品を を通じたコミュニケーションが普遍的な生活様式の一部になり、日常の一部となっている。そこに作品を埋め込むことで、日常と展覧会が交錯した状況を作り出すのがいいのかなと思います。セレンディピティに訴えるというか。
千房:でもその流れていっちゃう部分を、ひとつ(筋を)通すっていうか、「これはこういうもんなんじゃないか」みたいなのをズバッと言って、まとめるみたいな。
渡邉:実際、去年ぐらいからソーシャル・メディア界隈で「キュレーション」というキーワードがブレイクしていますから、逆輸入的にTogetterとかNaverまとめをつかったネット・アートの展覧会というのはアリかもしれない。さっき言ったような小品のすくい上げとか、延命にもつながりますよね。
栗田:ネット展をどうやるかというのとは別に、インターネットを題材にした作品をどう見せられるかっていうところもあると思うんですけど。インターネットそのものを使った作品って、解釈が難しいというか一般の人には伝わりにくいと思うんですが、それを——ネットじゃなくて展示会場でもいいんですけど——どう見せられるか? 物理的なモノじゃないものとか、いまのところプロジェクターしかないっていうか。そのへんも考える余地があると思う。
千房:あと、ネットがそれだけ普通になってっちゃうわけじゃないですか。美術ってなんか美術館だから成立してるみたいなところあるじゃない? 別にたいしたことないものも、美術館に置いたらすごく見えて、そこで価値がついちゃうとか。そういう、ギャラリーで見せることに最適化された作り方がされてるじゃないですか。ネット展って全然そういうことじゃない。ふつうの美術展だったら、朝コーヒー飲んだり新聞読んだりしながら、作品見てるわけじゃないじゃないですか。わざわざ来て「ありがたく拝見させていただく」みたいな。そういうのとは全然違いますよね。やっぱ、その構造が。
畠中:美術館が制度だっていうのは確かにそのとおりだけど、一方では、インターネットもおそらく制度だから。制度っていうものに対してどうアプローチしていくかっていう問題は、美術館だろうがインターネットだろうが等しくあると思うんです。
谷口(谷口暁彦。メディアアーティスト):美術館に行かなきゃ見られないのは、作品が物質的なものですよね。同じように、インターネットだったら「クリックして見なきゃいけない」っていうルールとか制約があると思うんですよね。そういった制約というか、どうしようもなさを引き受ける形っていうか、もしくはそれに対して抗うみたいなことを、なんか考えられないかなと思うんですけど。最小単位からこう、積み上げていけないかな、と。○○しなくちゃいけないどうしようもなさっていうのは、物質的な質感とか抵抗だと思うんですよね。そういったものを正しく捉えるってことが、重要なのかなという気がします。
(思い出横丁情報科学芸術アカデミー(谷口暁彦+渡邉朋也)・栗田洋・畠中実・youpy 『座談会「インターネット・リアリティとは?」』 2011.7.24)
果たしてこの座談会の9年後、東京都写真美術館という既存の権威たるホワイトキューブで、エキソニモによるインターネットアートの大規模展覧会が行われることとなった。それがどういう形で結実しているのかぜひあなたの目で確かめてほしい。
あらゆる対象物のうちで、芸術作品はたしかに現実世界から一番遠いものだ。文字どおりの意味で、純粋なオブジェとして把握すべき対象物であり、この点で例外的な対象物となる。
参考文献
伊藤俊治 (1991) 『機械美術論―もうひとつの 20世紀美術史』 岩波書店
海野弘 (2012)『二十世紀美術 1900‐2010』新曜社
河原啓子 (2011) 『「空想美術館」を超えて』 美術年鑑社
喜多村明里 (2001)「電子情報と美術館」 加藤哲弘ほか編 『変貌する美術館』 昭和堂
暮沢剛巳 「未来派からメディア・アートまで 芸術と科学の同床異夢」 (2005) 美術手帖編集部 『現代美術の教科書』 美術出版社
小池志保子・中川理 (2001)「変貌する美術館建築 制度から場所へ」加藤哲弘ほか編 『変貌する美術館』 昭和堂
坂根厳夫 (2010) 『メディア・アート創世記―科学と芸術の出会い』 工作舎
佐藤雅彦・中村至男 (2000)「新しい『表現』の居場所をめぐる冒険 インターネット時代のクリエイターの課題」 『美術手帖』 2000 年 9 月号
白井雅人 (2000) 「インタラクティヴィティの創造論」小林康夫・松浦寿輝編 『表象のディスクール 第 6 巻 創造』 東京大学出版会
白井雅人 (2008) 「メディアアートの流れ」「メディアアートの諸相」 白井雅人ほか編 『メディアアートの教科書』 フィルムアート社
水沢勉 「混在による解放のための工場」 (2000) 太田泰人ほか編 『美術館は生まれ変わる 21 世紀の現代美術館』 鹿島出版会
畠中実 (2009) 「メディア・アート」美術手帖編『現代アート辞典』 美術出版社
日向あき子 (1977) 『現代美術の地平』 日本放送協会出版
三井秀樹 (1994) 『テクノロジー・アート 20 世紀芸術論』 青土社
三井秀樹 (2002) 『メディアと芸術』 集英社新書
アンドレ・マルロー 小松清訳 (1957) 『空想の美術館』 新潮社
ヴァルター・ベンヤミン 高木久雄・高原宏平訳「複製技術の時代における芸術作品」 (1936) 佐々木基一編集解説 (1970) 『複製技術時代の芸術』 晶文社
ジャン・ボードリヤール 塚原史訳 (2002) 『不可能な交換』 紀伊国屋書店
ノルベルト・ボルツ 村上淳一訳 (2002) 『世界コミュニケーション』 東京大学出版会
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
