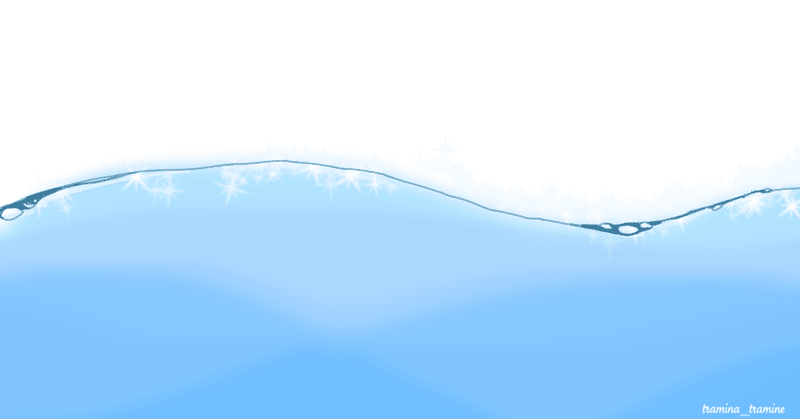
【共感力】で人の気持ちを背負いすぎないためには、相手と自分の境界をクリアにすることが大切だ。
日本人だからなのか。
人が集まる場の雰囲気、相手の気持ちを理解しようとして【共感力】を研ぎ澄ましあう文化があると思う。
言葉にしなくても察しようとする文化。
「子どもの心の内を察して見守る」
「状況を察して、周囲の人の仕事を手伝う」
「相手の気持ちを害してしまったかも、と察して言いかたを変える」
「空気を読む」「阿吽の呼吸」なんて表現もある。
チームワークで仕事をするような場合、他の人の仕事の状況にまで意識を向けて、頼まれなくとも「やっておきましょうか?」なんて声をかけられると「仕事ができる」と評価されることもある。
互いに気を配ることもあるし、それを美徳とする風潮もある。
この共感力。
もう第六感みたいだ。
素晴らしい力だよね、共感力があるから出来ることもたくさんある。
私も研ぎ澄まして生活してるところがあって、子育てや仕事に生かしてる。それと同時に、苦労したこともあるし、丁寧な調整が必要だと思う力だ。
研ぎ澄まし頑張っている方、実は結構いるんじゃないかなー?
と周囲を見ていて思う。そこも共感力でそう思うのかもしれない。
HSPと呼ばれるくらい共感力が繊細な方もいるしね。
共感力の強い方は、感じても受け流す。ある意味鈍感に近づけることとのバランスがとっても大切だ。
相手の想いを感覚的に吸収しすぎると、その気持ちに飲まれやすくなる。
「相手が困っているのがわかるから、放っておくのが苦しい」
なんて感情が生まれて、疲れすぎたりする。
そうして、自分の本心がどこにあるのかわからないまま、私の場合は人のために頑張りすぎたこともあったなーと思い出す。
【バウンダリー】
この共感力を調整する時、バウンダリー(境界線)について考えることはとても大切だそうだ。
バウンダリーとは心理学的な用語で、人と人の間にある心理的な境界線のこと。境界は誰との間でも必要で、多くの人間関係のトラブルはこのバウンダリーが守られていない事によって起きるという。
さっきの「相手が困っているのがわかるから、ほっとくのが苦しい」も、バウンダリーを意識すると見え方が変わってくる。
「相手が解決することで成長する困り事」は相手の課題だし、「見ていて苦しいと思う気持ち」は私のものだ。
その境目にあるバウンダリーは、固い壁ではなくて膜のようなもの。
細胞内外の物質の出入りを制御してくれる細胞膜みたいなもののイメージが近いみたい。自分で膜を通してどんな栄養を取り入れるか、自分で選ぶことができる。その膜によって相手を守り尊重し、自分のことも大切に守ることが出来るという。
じゃあ、そのバウンダリーやスペースはどうやって作るのか?
相手という細胞と自分という細胞がどこがどのように違うのかを明らかにすると、膜のある場所を発見することができる、そんなイメージ。
相手がどう違うのかを最初から見つけるのはとても難しいから、まずは自分の細胞の輪郭をよくよーく知ることが大切だそうだ。すると相手と自分の違いが自然とわかるらしい。
私は息子への教育と親子関係を考える時にバウンダリーという概念を知った。そしてこの考え方は、どの親子関係でもどの教育現場でも、子どもが意欲を持ち自分らしく過ごすためにとても大切な事だと思い、心揺さぶられたことがある。
ひそかに啓蒙活動をしたいくらいの気持ちになった。
それからバウンダリーについて考えなかった日はないくらい、人間関係の中でいつも意識してることだ。「私はバウンダリーの形成が下手なんだ~」とさんざん自分を責めた時期もあったけれど、今は長所と短所は紙一重だと分かるし、共感力に感謝もしてる。
私の場合だけれど、共感力の調整をする事はバウンダリーの形成をする上で大きな助けになる。そして自分をよく知り、自分の細胞の輪郭を明らかにすることが、バウンダリーを作る事に繋がる。逆もまたしかり。バウンダリーが引けると、共感力の調整もしやすくなる。
そして最近、日常の中で前よりは少しだけ調整しやすくなった気がしてる。
自分を知るというのは、本当に毎日の積み重ねで時間がかかる。
行動して振り返ることの繰り返し。人との関わりの積み重ねで、自分の感情の動きを丁寧に追っていく。
自分を知り、深めていくためのプロセスも一人一人違うのだと思う。
きっと一生かかっても分かり切らないのかもしれないけど、少しずつ少しずつ知っていくのを楽しんでいく。そんな感覚。
その間には、きっと私の共感力ももっと楽しめるときがくるのかもしれないな。
よろしければサポートお願いします。頂いたサポートは、公教育以外の学びの場の運営に役立ててもらう寄付に充てたいと思います。
