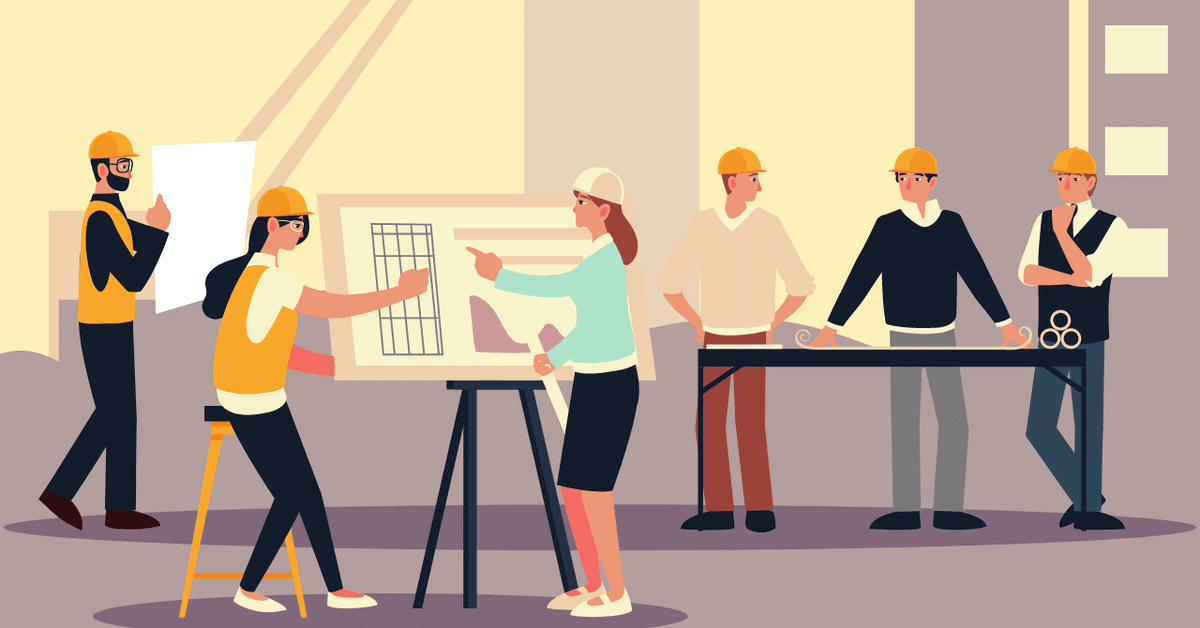
土木現場におけるダイバーシティ&インクルージョン(D&I)の推進
阿部 友美
論説委員
株式会社奥村組東北支店土木部
このほど中山間地域での山岳トンネル工事(NATM)の現場から、市街地で道路の下にトンネルを非開削工法により構築するアンダーパス工事(R&C工法、ESA工法併用)の現場に異動となった。施工場所の周辺環境は一変し、通勤も車で片道27kmであったのが、今は徒歩で1km未満である。労働基準監督署に提出する「建設工事計画届」の事業種類が「ずい道」に分類される点は同じだが、施工方法は大きく異なり、多様な工法に携われることを非常に有意義に感じている。
さて、現在の現場の施工開始以降、外国人技能実習生と接する機会が格段に増えた。親子ほども年齢の違う彼らは、ぎこちない日本語で明るく元気に挨拶し、「きょうもいちにちガンバロー!」と、各々の作業場所へ向かう。危険予知活動(現地KY)においても、日本人の職長のもと、作業内容の確認、危険ポイントの洗い出し、リスク回避のための方策について、日本語で話し合う。そして、話し合った内容をたどたどしいひらがなとカタカナで記録する。日本人による危険予知活動に比べ、およそ倍の時間を要するが、技能実習生を指導する職長も、私たち元請職員も、これを急かしたり、省略したりするようなことはしない。彼らには、技能を習得してもらうことはもちろん、作業中は「安全最優先」が重要だということを理解してもらい、どのように行動すべきかを考え、実践してもらうことが必要だからだ。
外国人技能実習法(通称)における「外国人技能実習制度」は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ、国際社会との調和ある発展を図るため、開発途上国等への技能、技術または知識の移転や経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としている。
いわば「実践的な技術や技能・知識を学び、帰国後、母国の経済発展に役立ててもらう」ための教育制度である。技能実習生を受け入れる企業側には、人手不足の解消や組織の活性化など、多くのメリットをもたらす一方、さまざまな問題や課題も顕在化してきた。例えば、日本人労働者が就労したがらない分野の労働を技能実習生に頼っている一面が挙げられ、単純労働の受け皿になっているのではないかという指摘や報道も多く聞く。制度の目的と運営との間にギャップが生じているのである。これまでにも、制度の改善が行われてきたが、技能実習生本人がスキルアップをして帰国できるかは、制度の改善だけでなく、むしろ、職場での人間関係や、技能実習生たちを見守る周囲の日本人の意識の持ち方に左右されるように思える。技能実習生と周囲の日本人との関係が良好に構築されるには、さまざまなパターンがあると思うが、そのひとつに「家族の一員のように接する職場」があると考えられる。そもそも、技能実習生の多くが家族を大切に考えており、彼らが日本に来る理由としては、家族のために家を建てたい、新しい家具や家電を買いたい、子どもを大学まで進学させたい、など家族に対する思いが大きいと聞く。当現場の日本人作業員は、技能実習生たちを息子のように可愛がり、世話をしている。休憩時間に談笑したり、文字の書き方を教えたり、トイレ清掃などを一緒に行っている光景を見ると、良好な関係を築いていることに安堵する。技能実習制度の問題点を告発する報道で、人権侵害に至るケースを耳にすることもあり心が痛むが、それらは一部の事象であると思う。外国人技能実習生を受け入れ、どのように指導・教育して、技能を身に付けてもらうかは、受け入れる会社にとって、その存続にかかわる切実な課題であろう。ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)を実現し、日本社会がさらに発展していくためには、多種・多様な「人財」を受け入れ、互いに認め合い、感謝・共感し、一緒におもしろがったりすることが必要だと考える。
DX(デジタルトランスフォーメーション)やAI(人工知能)など、技術革新では賄うことのできない人財育成やコミュニティ構築を、ローカルな現場でも地道に取り組んでいる。
土木学会 第180回 論説・オピニオン(2022年5月版)
この記事が参加している募集
国内有数の工学系団体である土木学会は、「土木工学の進歩および土木事業の発達ならびに土木技術者の資質向上を図り、もって学術文化の進展と社会の発展に寄与する」ことを目指し、さまざまな活動を展開しています。 http://www.jsce.or.jp/
