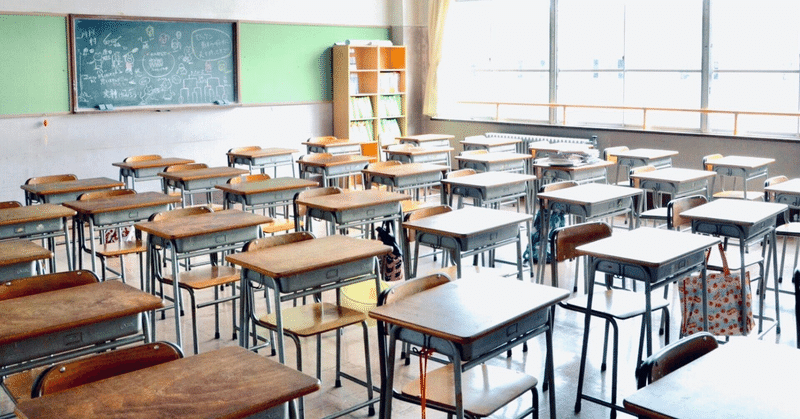
じいじ 保育士を目指す! 連休だから
何故か
リフレッシュ休暇という3日間連続取得が条件の休暇を取る。今年から、お盆休みも導入されたので、夏休みという概念がなくなった(訳ではないが)ので、この連休を充実させるべく取ってみた。
もちろん、やる事は大学院生として論文を一本でも読む、レポートを進める事がプライオリティ最高位だけど。。。
そこは、人間。ついつい、Amazonで本を買ってしまった。
これは、保育学をやっている身としては読みたかった本。
これは、立命館の公開講座で知った本。
立命館は結構勢力的に公開講座をオンラインでやっているから利用している。
これは、私の問題意識にある何故公教育があるのに、塾というものが必要なのか?大学(高校)に行く為にどうして公教育という教育システムが機能しないのか(授業だけで、何故入試対応できないのか?これは、国立大学も含めて!)というのがあって、今の時代(少子化)に何故、入試選抜システムで子供達を落とす必要があるのか?
大学は望む者が入って、学業を遂行する者に単位を与える。当たり前のシステムで、望ましい(サボる)者には単位を与えなければいい。その大学の教育水準に到達しない学生は落とす。それだけだ。
私はこの国の未来を考える上で、全ての望む子供に高等教育を無償で提供し、公教育は個々の子供の多様性を伸ばす教育を提供すべき(選抜システムとしての装置から、個々の可能性を伸ばすシステムに大転換する最後のチャンスだと思っている。)だと考えている。
この国が最貧国へ没落し自滅する前に、教育という資源を投下して、人口数が少数でも豊かな社会を維持できる国になって欲しいと願うからだ。そもそも、人口増の経済成長モデルは既に終焉を迎えた事を自覚しなければ、終わると思っている。
これも、上の問題意識から買った本。教育学の講義でやった親の経済力によって生み出される学力格差と選抜システムとしての教育システムがこの格差をさらに助長し固定化を(結果として)進めているという現状。だから、私は個々の子供達に公教育がやるべき事は、全ての望む子供達に高等教育を提供し、全ての子供達の個々の多様な能力を伸ばす教育へ今すぐ(間に合ううちに)転換すべきと思っている。
これもその一環。
こうやって買い込んだけど、どこまで読めるかな?
保育学が目指しているのは、個々の子供達の個々の生きていく力を個々に応じて伸ばして行くかをどう実現できるか。それって、保育学の守備範囲である幼児教育の範囲を超えて、そもそもこの国の未来を守る為に現在の教育学がやるべき事ではないか?と思っている。
私は、保育学が進む方向性を、解放の神学に準えて、解放の保育学、解放の教育学と呼んでいる。特にキリスト教やマルクス主義に感化されたという意味ではなく、全ての望む子供達にその個々の興味や関心や進む方向に応じて、オーダーメイド的に教育を提供するシステムを構築する事。格差という問題をこの国の未来を守る為に、変革する運動としての学問という意味でそう希求している。
さて、今日はこの辺で。
解放の神学
解放の神学(かいほうのしんがく、英語: Liberation theology)とは、第2バチカン公会議以降にグスタボ・グティエレスら主に中南米のカトリック司祭により実践として興った神学の運動とそれをまとめたもので、それに対する議論も多く、教皇庁でも批判者がいるが、世界的には広く受け入れられている。一部には1930年代のディートリヒ・ボンヘッファーをその先駆けとみる見方もある。
キリスト教社会主義の一形態とされ、民衆の中で実践することが福音そのものであるというような立場を取り、多くの実践がなされている。中南米のプエブラ司教会議でも支持されたが、階級的視点などにおいて「マルクス主義方法論をベースにした共産主義」と意図的にも無知からも混同されて中傷される事も多く、各国で政府側からも反政府側からも聖職者や修道士などが暗殺される事が多い。一方でフィリピンやインドネシア、東ティモール、ハイチなどでは実践が重ねられている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
