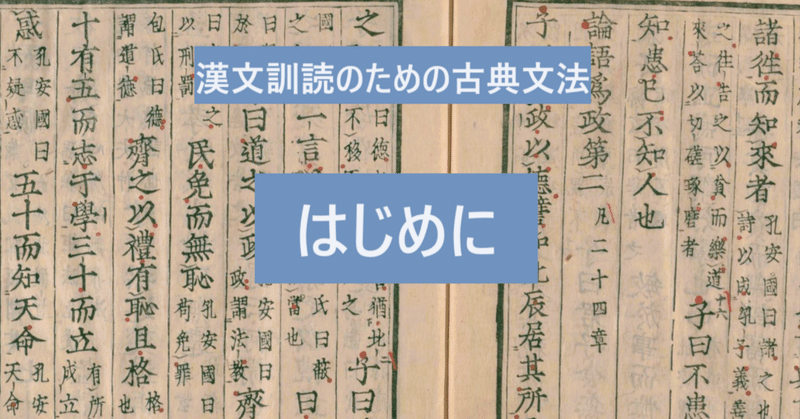
漢文訓読のための古典文法~はじめに~
本企画の目的
本企画の目的は、漢文を訓読していくために必要な日本語の古典文法(訓読文法ということにします)を、なるべく網羅的にまとめることです。
とはいえ、漢文訓読の方法は、人により時代により、それぞれ異なっており、100%網羅するなんてことは出来ませんし、仮に100%を目指すのであれば分量が膨大になり、読者の労力、そしてこの記事を書いている私の労力が大変なものになります。
そこで、レアな話・個別性の高い話はカットして、頻度の高い文法事項のみを抽出していくこととします。
* * *
この記事を書こうと思ったキッカケ
蛇足っぽくなりますが、この記事を書こうと思ったキッカケについても記しておきます(不要な方は、次の章まで飛ばして下さい)。
最近、いくつかの受験系youtuberの動画を視聴していたら、高校漢文に関して、次のような主旨の話がされているのを、複数回、聞きました。
「日本における漢文は、日本語の古典文法に従って訓読するものだから、漢文にとりかかる前に、まずは古典文法をしっかり勉強すべきだ」
この話、間違ってはいないのですが、一方で、困ったことだとも思いました。その理由として2つあります。
一つめ。確かに、訓読文は日本語の古典文法に従ってはいるのですが、その全てが必要なわけではない、ということです。
例えば、古典文法で大きな関門となる「助動詞」、ここに登場する助動詞は30個近くあるそうですが、漢文訓読に一般的に現れるものは、その半分以下であり、私の勘定では13個です。その13個においても、漢文訓読ではめったに使われない意味、活用形、接続などがあったりもします。つまり、学習内容をうまく選べば、限定的な知識だけで、漢文訓読の文法を理解できてしまうはずなのです。
しかし、先のyoutuberのような言い方では、古典文法をみっちり勉強しないと漢文が理解できないような印象を与え、ハードルが無駄に上がってしまっているのではないか、と思うわけです。
二つめ。一つめとは逆に、一般的な古典文法だけではカバーできない、ほとんど漢文訓読でしか見られない言い回しがある、ということです。
例えば、訓読文で「ずんばあらず」なんて表現が出てきますが、高校でやる日本古典ではほとんど出てこない言い回しです。他にも、漢文訓読を学ぶために、追加すべき文法事項があるのですが、参考書などには個別に補足されているだけです。
結局、日本古典のための古典文法と、漢文訓読における古典文法は、重なっているところも多いけど、ずれているところもあるわけです。しかし、訓読文法としてのまとまった記載は、なかなか見当たりません。
おそらく、「どうせ高校生は古典文法をやるんだから、それで漢文訓読もカバーできるだろ」ということなのでしょう。しかしそれでは、訓読文法について断片的な知識を積み重ねるしかないので不便ではないでしょうか。
また、社会人が漢文に興味を持ったとき、一から古典文法をフルに学びなおして、そこから漢文訓読のための必要事項を取捨選択していくのも億劫です。
私自身も、漢文をいくらか読んできて、訓読の文法が分かったような分からないような、隔靴掻痒の感を抱いてきた者であり、それならば自分で作ってしまおう、と考えたのが、そもそものキッカケです。
* * *
注意点
江戸時代とか平安時代などの古い訓読ではなく、現代日本で商業出版されている一般向け漢文書籍において、現代日本人が読み下した訓読が対象です。
日本人が書いた、日本化された漢文ではなく、中国人が書いた古典的な漢文の訓読が対象です。
漢文そのものではなく、訓読文の文法が対象です。
この世には、訓読文法として、古典文法並みに詳細に記述され、かつ広く通用しているものは多分ありません。そのため訓読者の違いによる揺れは避けられませんが、なるべく一般的と思われる内容を述べていきます。
文法を漢文訓読に限定することで、一般的な古典文法より簡素な形になることを狙っています。そのため、日本の古典文学を読む際は、追加で必要になる知識があります。
一方で、江戸・明治あたりの、文語で書かれた論文(学問のすすめ等)や新聞記事あたりは、本企画の知識でかなりの文法事項がカバーできると思います。
高校参考書や、明治45年の文部省から出された『漢文教授ニ關スル調査報告』(後述)などを参考にしておりますが、準拠しているものではありません。私の読書経験のなかで、ツールとして整理していったものであり、学術論文や受験参考書ではないことをご承知願います。
* * *
前提知識
日本語の各品詞の区別(現代・古典問わず)
歴史的仮名遣いの初歩的知識
古典動詞・形容詞の活用の初歩的知識
(形容動詞・助動詞は、おいおいでOK)現代日本語の言語感覚、やや古風な言い回し等
他にもあるかもしれませんが、大体、このくらいのレベルはクリアしているということを前提としていきます。
若干補足。
1番は、与えられた語が動詞なのか、助詞なのか、接続詞なのかなど、常識的なことが分かれば十分です。
2~3番は、古文・漢文に関わらず絶対に必要な知識で、かつ初歩の古典文法の参考書には必ず載っていますから、この記事で一から説明することはいたしません。
4番の「現代日本語の言語感覚」については、とりたてて何か勉強しろ、ということではありませんが、古文・漢文を学ぶのに最大の武器だと個人的には思っています。
古典文法をただ暗記しただけで文章を読めるようにはなりません。結局は、現代日本語の言語感覚をベースとして、そこに古文・漢文に特有の語感を追加していくというのが普通でしょう。
特に、漢文訓読で使われる文法内容は限られていて、現代人にも理解できる古風な言い回しや格言・セリフ等から類推できるものが結構あります(「~せざるを得ず」「~をもってして」「百聞は一見に如かず」「板垣死すとも~」等)。
100%カバーできるとは言えないまでも、これらを生かさない手は無いと思います。
* * *
参考文献
『漢文教授ニ關スル調査報告』
現代の日本教育で行われている漢文訓読は、明治45年に発表された「漢文教授ニ關スル調査報告」というものが、基準となっていて、これは、当時の文部省が、偉い学者を集めて検討したものようです。次のサイトから全文を見ることができます。
⇒漢文教授ニ關スル調査報告
訓読文法についてまとまった記載のある文献
辞書『漢辞海』の付録「訓読のための日本語文法」(iOS版)
その他
いちいち書名は記しませんが、自宅にある様々な書籍・辞書・参考書等を参照し、そこで古典文法をどのように説明されているのか確認したり、本の執筆者がどのように訓読しているのか、いろいろと用例をあたらせてもらっています。
* * *
活用表のpdfファイルについて
本企画では、様々な活用表を掲載しております。しかし、それらが各記事に分散していて不便ですので、一つのpdfファイルにまとめました。適宜、ダウンロードやプリントアウト等をしてご活用下さい。
* * *
訓読文法コンテンツ一覧
●はじめに
●動詞編
(1)動詞の活用と接続 (2)注意を要する動詞
●形容詞編
●助動詞編
(1)る/らる/しむ (2)たり/り/き
(3)ん(む)/べし (4)ごとし
(5)なり/たり/形容動詞
●疑問文と連体形
●助詞編
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
