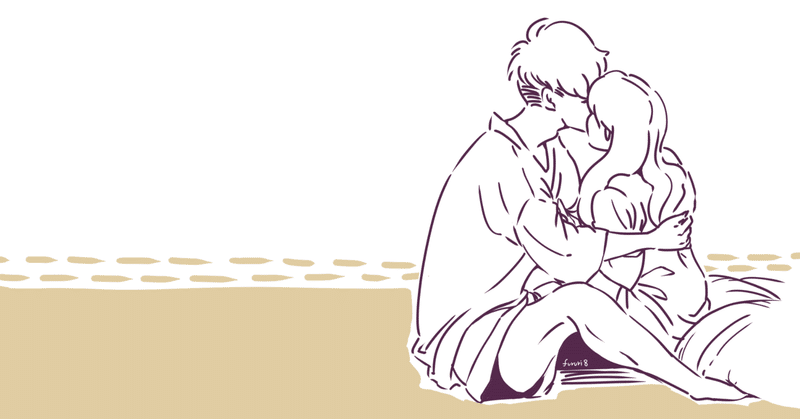
【短編小説・上】 君との愛を知りたい (約5500字)
<あらすじ>
フリーターの佐和子(さわこ)は、自由奔放な恋人・亮平(りょうへい)に振り回されながら、自分のイラストで食べていくという夢を叶えるために日々邁進している。
亮平の振る舞いに文句の一つも言えない佐和子は、疲れを感じ始めていた。
「佐和子、さみぃよ。暖房つけてよ」
グレーのスウェットに着替えている亮平(りょうへい)が不満気味に声をあげる。あぁ、そうだ、忘れていた。ごめんごめんと、小ネギを切る手を止めた。
数歩先の壁に備え付けてあるエアコンのリモコンを手に取り、スタートボタンを押すと、古いエアコンが動き出した。「コタツもすぐ温まるから」と、電源をプラグにさした。
「ここ数日で一番寒いのに。お前、よく耐えれるなー」
こんなの、全然寒くないじゃない。それが私の感想だった。二桁の気温なんて、地元では数ヶ月前の秋の気温だ。私にとって東京の冬は、冬じゃなかった。
育ちは北海道の道東だった。
沿岸部の田舎育ちの私の実家はボロで、とりわけ寒かった。
一方で亮平は温暖な静岡育ちだからか、寒いのが苦手だった。彼が来る日は暖房を事前につけておいてあげよう。そう思っていたのに、ついつい忘れてしまう。
「おでん、できたよ」
コタツの上に鍋敷きを引いて、鍋を置く。土鍋なんて持っていない。ただ普通の銀色の片手鍋を置いた。
「おでんかぁ……」
亮平がまた嫌そうな声を出す。
こういう反応があることは、薄々わかっていた。気にせず、緑茶の茶葉が入った急須にお湯を入れた。
「温まるから、いいじゃない」と、卵、大根、ちくわを取り皿によそって亮平の目の前に置いた。
そして緑茶を湯呑みに注いだ。
「肉体労働の後は、がっつりしたもんが食べたいんだよ」
亮平は物流倉庫勤務。一人暮らしをしている。週に数回、うちに泊まりに来るが、私がスーパーのシフトが入っている日の夜と決まっていた。
アパートのガスコンロは一口しかなく、料理をするのに不便な環境だった。お金をかけず、限られた時間で、寒がりさんを温める料理には、限りがあった。
バラエティ番組を見て笑う亮平を横目に、私はテレビの隣の自分の作業机を見ていた。
そこには、描きかけのエゾリスがいる。冬のエゾリスは、耳毛がうさぎのようになっていて、可愛らしい。絵の具で色付けをしている最中だった。
料理に時間をかけるより、絵を描きたい。そのために東京の専門学校に進学した。夢は自分のイラストで食べていくことだ。
でも、週に数回の手料理よりも、日課のイラスト作成を優先したいだなんて。そんなことを思う彼女って、冷たいかな。
ゆで卵を割って、パサパサした黄身をそのまま口に入れた。
「佐和子、お湯沸かしてー。カップ焼きそばも一緒に食べる」
「ご飯炊いてるよ?」
「それも食う」
少食で、ヘルシー思考な私には理解できない。私は見ているだけで胃もたれしそうな気分だった。
「お前のおでん、味薄いよな。コンビニと違って」
「実家から昆布送られてきたの。出汁をちゃんと取って……」
「あー肉食いたいわー」
口をつぐむ。いつもこうして、自分の言葉は胸にしまう。言ったところで何になる。文句があるなら出て行けなんて、私に言う度胸はない。
邪念を払うように、ゆっくりお椀に口をつけてスープを飲む。
こんなに美味しいのに。ぽつりと心の中でつぶやいた。昆布出汁は、優しい甘味とコクが深く、故郷の味がした。
***
「まじでエアコン消して寝るの?」
コタツでテレビを見ている亮平が、身を縮めて言う。今日ぐらいはつけたまま寝ようと、と言いたいのだろう。
「さっき、布団に湯たんぽ入れておいたから大丈夫」
歯磨き粉をつけた歯ブラシを亮平に渡し、作業机の上においているデスクトップのパソコンのスリープを解いた。
メールが複数届いている。そのうち一つを開いて、胸が弾んだ。
『……一度ご来社いただきまして』
この文面を見て両手でガッツポーズをした。すぐにスマホでLINEを開き、専門学校時代からの親友の真美(まみ)ちゃんに連絡した。
『来週、東光愛樹社(とうこうあいじゅしゃ)の担当者さんのアポ取れた!』
『まじ!おめでとう!』
勉強机の上に立てて置いているファイルや本のかたまりから、白いファイルを取り出す。自分のイラストのポートフォリオだった。
エゾリス、モモンガ、キツネ、エゾシカなどの北海道の野生の動物たち。北国の動物たちは、自分のイラストの原点だった。
出版社の人へのアポ取りは、簡単なことではない。事前に問い合わせをして、了承を得た場合はポートフォリオを郵送していた。
それでも連絡が来る可能性は極めて低いもの。だから来社の案内をもらえて、天にも登る気持ちだった。
上京して七年。この小さなアパートでコツコツやってきた。生活は厳しかったが、父親の反対にも負けずにやってきた。未来への扉が、私に開きかかっている。そう信じたい。
「亮平、聞いて聞いて!」
亮平を見ると、すでにベッドの布団の中で寝ていた。狭いシングルベットだが、壁側に身を寄せて寝ていた。いつものように、私のスペースを残して。
時計を見ると、0時を過ぎていた。
眠りこける彼の顔を見ると、急激に眠気が襲ってきた。今日は珍しく朝早いシフトだったことも思い出した。私も寝よう。楽しい夢を観よう。
メガネをとって、結んでいた髪をほどく。布団をめくって体を入れると、亮平と湯たんぽの温もりでとても暖かかった。
***
「なんで起こしてくれなかったんだよ!」
目を覚ました時には、慌てて作業着に着替えている亮平に怒鳴られていた。時計を見ると、八時を過ぎていた。
「え、別に間に合うでしょ……?」
寝ぼけながら、率直な言葉をかけた。
亮平の職場は、ここから三十分かからない。確かにいつもより寝坊かもしれないが、彼の会社の始業時刻の八時四十五分には間に合うはずだ。
北海道の冬の雪道のように、通勤時間が倍にかかることを見越す必要もあるまい。
「俺のルーティンは、始業の三十分前には出社していることなんだよ!」
子供のような叫び声を浴びて、私の瞼(まぶた)はつりあがった。亮平は紺色のニット帽をかぶり、突風のように出ていった。
はぁ、とため息をついた。
こんなことはいつものことだ。
ココアを作って、こたつでゆっくり飲んだ。スマホのアプリからラジオをかける。テレビより好きだった。
亮平との出会いは、春の路上だった。
真美ちゃんの家からの帰りだった。四月の夜にしては暖かい。そう思いながら駅の正面入口に向かう階段を登っていると、ギターの音色が聴こえてきた。
路上に座り込んでアコギを弾いている男性。それが亮平だった。誰も立ち止まらず、耳も目も傾けない。それ自体はありふれた景色だが、私はその音に異様さを感じた。
彼が歌っていたのは、実力はシンガーがウィスパーボイスや高音を駆使して、切なさを表現した「泣かせ歌」として昨年大ヒットした失恋ソングだった。
『こんなに悲しい1ページは見たことがない』
『君のいない人生って つらいものですね』
それを亮平は、ジャイアンのように元気いっぱいに笑顔で歌っていた。アコギをかき鳴らし、原曲の雰囲気とは真逆のスタイルだった。
私は呆気に取られて、亮平の前で足を止めてしまった。歌が下手なわけではない。ただ、窓ガラスを破壊するような、衝撃があった。彼は、あまりに自由だった。
「こんばんわ」
歌い終わった亮平が、声をかけてきた。振り返っても、横を見ても、立ち止まっているのは私だけだった。なんだか恥ずかしくなる。会釈して、すぐに立ち去ろうとした。すると亮平は「ねぇ」と声をかけてきた。
「俺の歌、どうだった?」
「え……っと。よかったです。元気いっぱいで」
「マジ!嬉しい」
亮平はにこっと笑った。
「ねぇ、これから夕飯に付き合ってくれない?」
これが出会いだった。口下手であまり友達がいない私。男友達すらいない。だけど亮平と話すのは、真美ちゃんと仲良くなった時のようにスムーズだった。
亮平曰く、路上ライブは趣味でしていたものだと言う。別にプロになりたいとか、そんな気持ちもないらしい。だから夏頃には「暑い」と言って、もう辞めてしまった。
気まぐれで、わがままで、猫みたいな男だった。悪い人ではない。明るい性格。
でも、付き合って数ヶ月しているうちに感じたこと。
会うと少し疲れる。この本音を言語化するのに、数ヶ月かかった。
初めての恋愛だった。私にはこれが普通なのか、普通じゃないのかもわからない。
亮平を好きかと尋ねられたら、好き、と言う。そう思う。亮平は、私にないものを持っている。磁石のように惹き寄せられる。
でも「好き」ってなんなんだろう。恋愛をすれば、わかると思っていた。
付き合って八ヶ月が経った。それでもまだ、答えには辿り着けていない気がした。
***
「イラストの雰囲気が個人的にすごく好きで。優しくて、暖かみのある世界ですね」
東光愛樹社の相原(あいはら)さんとの面談は、圧迫感なく、穏やかに始まった。丸みのあるショートカットがよく似合う、肉付きの少ない女性だった。
言葉にならない喜びが込み上げる。持ち込み経験はゼロではない。これまでは傷ついて帰ることが多かった。それだけに、こんな言葉をかけてもらって、手が震えた。
「うちの会社の出版物と雰囲気もあってますね」相原さんが事前に送っていたポートレートを見ながらにっこり笑う。
すぐに何か、仕事につながることではないというのは、重々承知していた。
でも相原さんは「このイラストは、何時間ぐらいで描く?」「デジタルでイラストは描ける?」など、いろいろ質問をしてくれた。
商業上でイラストを採用するときに見ているポイントなども教えてくれた。
東光愛樹社の正面玄関を出たときにも、自然とおじぎをした。顔がほころぶ。
近くのカフェに入り、真美ちゃんにLINEした。いつも良いことも悪いことも、いつも共有していた。
『持ち込み、めっちゃ勉強になった』
『いいね! 私も頑張らなきゃ』
『シンプルなイラストの方がウケがいい気がしたよ』
『まじ? 今描いてたの、すごい凝って作ってた』
『少ない線で実力を魅せるのがいい感じかも』
『今度また、詳しく教えて!電話しよっ』
『おけー』
カフェラテは、気づいたときには少しぬるくなっていた。熱々のホットドリンクが好きだけど、今日はそんなことは気にならない。
出版社から仕事をもらう。これは私の夢だ。コンペなども応募しているが、チャンスは増やしたい。一つずつ、進んでいるんだ。
手に力が入る。カウンター席から赤く染まる夕焼けをそっと見つめていた。充実感でいっぱいだった。
***
「緑茶がないとか、ありえない!」
夕食前の亮平は眉をしかめて言った。
そんなことを言われても、茶葉が切れてしまっている。ほうじ茶を提案したが「茶色いお茶なんて、お茶じゃない」と亮平は吠えた。
全くもって理解できないこの言動。
「お茶は緑茶以外認めない」という静岡県民ならではの価値観を理解するのには、交際して数ヶ月かかった。
「じゃあ悪いけどそこのスーパーで買ってきてくれない? 私、料理しているし」
「寒いから嫌だ!」
亮平はぴしゃりと言い切る。コタツから出る気はないらしい。それにどうもテレビで特番スペシャルも見たいようだった。
一体、どんだけ甘やかされて育てられたのだろうか。半分呆れながら、仕方なく茶葉を買いにスーパーへ行った。
自分自身も、買っておかなきゃと思いながら、忘れていた。そこを自分の非だと思うと、行かないといけない気がした。
なぜ断れないのだろう。自分でも思う。でも自分の両親もこうだった。
亭主関白で漁師の父と、それを受け止める母。母はいつも、少し困った顔をしながら「はいはい」と父のわがままがを聞いていた。
母は「それが愛だ」と私に教えてくれたことがある。
父も母も、同じ田舎町で生まれ育っていた。一度も他の地域で暮らしたことはない。今日もあの町で生きている。
そこで私は育った。いま、私は東京で、母と同じことをしている。
***
その日の夜、遅い夕食を食べた。食べ終わって、予定していたラフ画作業に入った。何か違う気がして、ネット上で資料を探したり、描いたりを繰り返した。
もうすぐ0時になる。今日中にラフ画を完成させて、明日から本格的に製作をしたかった。もう少しだけ作業を続けたい。
亮平を見ると、スマホでゲームをして、コタツに入っている。疲れている時は、こっちにかまわず布団に入って寝る人だ。
おそらく、今夜は私を待っているのだろう。
寝ていいよと言っても、寝ないこともわかっていた。亮平は、明日は仕事だ。彼を気にしないフリをしたが、描けない。もう集中できなかった。
寝る準備をすると、待っていたと言わんばかりに、布団の中で遊戯が始まる。
それが嫌いではなかった。でも初めての相手だったから、最初のころは立ち振る舞いに困った。黙って彼の行為を受け止めていたら「つまらないよ」と言われたことがある。
だから、なるべく声を出すようにした。そのうち演技でもなくなった。彼の喜ぶ顔が見れたとき、これが大人の恋愛だと、自分が一皮剥けた気がした。
「寒くない?」
「うん」
たまにしか提供されない腕枕サービスがあった。
「俺が寒がりだからなぁ」
そう言って抱き寄せられたときに、温もりを感じた。
時々考える。亮平に出会う前と今。あるものと、ないもの。
一人だったら、私は東京の冬もさほど寒いとも思わないし、温もりも知らない女だった。独りで絵を描き続ける日々と、どちらが良かっただろう。
散々わがまま言われても、振り解けないこの手は、罪深い。
(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
