
『あめいろぐ高齢者医療』出版記念・オンラインカンファレンス ~頭の体操? コペルニクス的転回? 肝心なことは何…?(第2回)~
モデレーター:反田 篤志(監修者)
コメンテーター:樋口 雅也(著者),植村 健司(著者)
(前回の続き)
あめいろぐ書籍化シリーズ第4弾は『あめいろぐ高齢者医療』です.8月に丸善出版から発売されました.
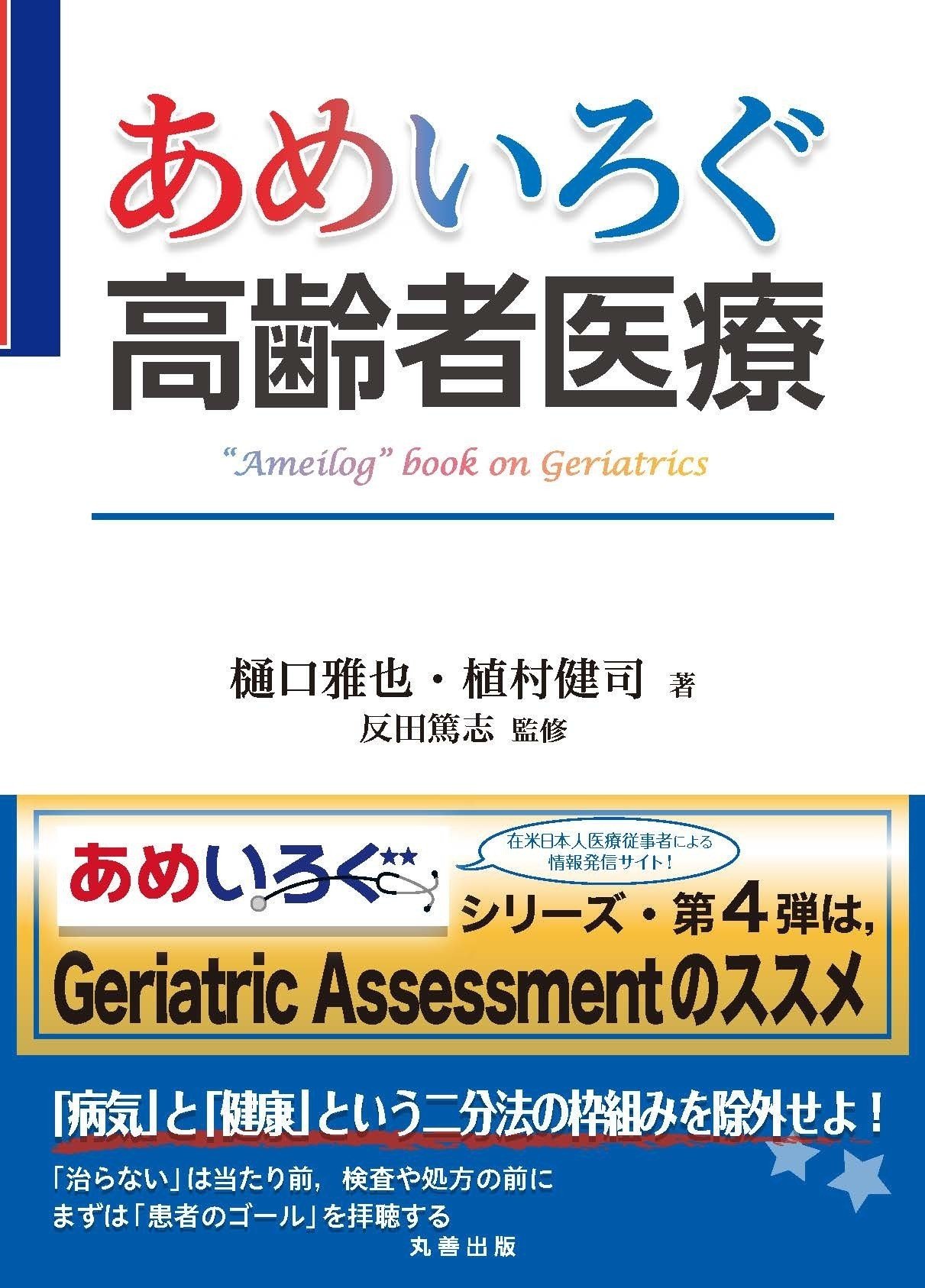
刊行を記念して,著者の樋口雅也先生と植村健司先生をお招きし,日米の高齢者医療事情や米国のコロナ問題など,本音ベースで語っていただきました.樋口先生は家庭医療の専門にして,老年医学とホスピス・緩和ケアのスペシャリスト,かの有名なMGH(マサチューセッツ総合病院)で働いています.植村先生は老年医学発祥のマウントサイナイ医科大学で老年医学と緩和ケアを修め,同じく老年医学とホスピス・緩和ケアのスペシャリストとしてハワイ大学で活躍されています.
そんな最強のお二人を迎えた今回のカンファレンス.ぜひお気軽にコメントやメッセージをお寄せください.
こちらの『あめいろぐ高齢者医療』紹介ページもぜひ訪れてみてください.担当編集部による制作秘話もイチ押しです.
モーフィアスがネオに赤と白の薬を提示するわけ
反田 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)の高齢者対応も含めて,高齢者医療のものの考え方がますます必要とされているようですね.翻って,日本はどうでしょうか.今の日本の現状や課題について思うところはありますか?
植村 樋口先生も同じ思いをずっと抱かれていると思うのですが,世界で高齢化が進んでいて,その急先鋒が日本.にもかかわらず,日本ではジェリアトリクス(老年科)がそれほど認知されておらず,そもそも「ジェリアトリクスとは何なのか」ということすら知られていません.僕も日本にいる頃は知らなかった.医学部の授業でも聞いた記憶がないのです.ちょうど自分が学生の頃,日本で総合内科医とかジェネラリストが流行りだしたのですが,そういう人たちは,フィジカルアセスメント(身体診察)をして,グラム染色して,鑑別上げて,難しい診断をするとか,いわばスーパードクターみたいなことを志向していたように思います.それは必要なスキルですが,それだけでは,どうしても高齢患者に対応できないのですね.でも,そのことに対して,誰も声を上げない.たぶんそれは,「それ以外の医療の形がある」ということを提示されていないからだと思うのです.日本で臨床をやっていたときは,寝たきりの認知症の末期の患者さんなのに,「認知症の末期」ということすら認識せず,救急車で運ばれてきたら,「このお婆ちゃん,病歴も取れないし,何でだろう…」みたいな感じで,僕が診た患者さんは肺炎だったのですが,ストレートに肺炎だけを治そうとしていたのです.つまり,
【95歳女性,発熱,呼吸困難,肺炎と診断】
で,「1時間以内に抗生剤を投与して,血培2セット,生食全開!」とか,そんなことばかりやっていたわけです.実際,日本の医療って,基本病院医療ですよね.多くの方が病院の中で死んでいく.当時の自分は,その95歳の寝たきりのお婆ちゃんが「病院の中にいる生活」しか知ろうとしなかったのです.本書の7章で,樋口先生が【認知症の疾患軌跡(trajectory・トラジェクトリ)】を解説されていますけど,「認知症患者はなだらかに身体機能が落ちてきてターミナル(終末期)に向かっていく」という認識が,あの頃の自分に全くなかったんです.そういうことを教えてくれる人が日本にいないというのが,すごく問題と思います.
反田 その気持ちよくわかります.自分も研修医時代,そういう患者さんに対して,インテンシブ(集中治療的なケア)ばかりをやっていたように思います.
植村 ほとんどの病院で行われているんですよ.それが患者さんにとってすごい苦痛であっても,誰もそのことに疑問を抱かない.だから「ほかの形もあるのですよ」ということを,この本で示したかったのです.
樋口 僕もそこは同感で,今まで可視化されていた世界が変わる,映画『マトリックス』のシーンで,モーフィアスがネオに「赤と白の薬のどちらを飲むか?」というセリフがあるじゃないですか.つまり,「この扉を開けると見える世界が変わる」ということだと思うのです.それと,疾患のtrajectoryを考えるのはものすごく大事で,やっぱり病院医療だと,ある患者の,ある生活の,ある人生の,いち部分しか見えてこないわけです.その前の段階でその患者さんに何があったのか,その前にどれくらい歩けて,逆に退院した後はどれくらい歩けるのか,そういう視点になかなか向きにくい現状があります.卒前教育であれ,卒後教育であれ,それから指導医や常勤医になった後も,「どういうふうに人が老化していくのか」「どうやって機能が変化していくのか」「どう評価して,どう介入するのか」,それを系統的に学ぶ機会が日本には少ないと思います.

2018年 Harvard Medical School にて(樋口医師)
「医学は線形思考」ではない
樋口 8章「せん妄」でも書きましたが,身体拘束にしても,医療者側の目線でみれば,病気を治療するということが最善なので,
・「肺炎だから抗生物質を与えなければいけない」
・「抗生物質を与えることを妨げたり,点滴を抜いてしまう,せん妄は悪いことだ」
・「だから,それを止めるために拘束しよう」
となるのですが,その前に
・「そもそも,どうしてせん妄が起きてしまうのか」
・「本当に治療が大事…?」
・「この拘束は,この人の人生をこの後どういうふうに変えてしまうだろうか」
・「(その上流部の要因として)どうしてこの肺炎が起きてしまったのだろうか」
・「肺炎の原因がばい菌ではなくて,じつはもう飲み込みができなかったのではないか」
・「(さらに,その前段階として)ほとんど咀嚼や嚥下ができないターミナルな認知症があったのではないか」
こう考える必要もあるわけです.もともとの根底にある問題は肺炎でなくて,認知症のターミナルなのかもしれない.そこに気づけるチャンスはなかなかないし,日本だと系統的に高齢者医療を学べる機会も限られているのかもしれません.
反田 今のお話を聞くと,自分が研修医のときに行っていた医療が本当にあれでよかったのか…と思われるエピソードがたくさん思い浮かびますね.本書の「監修者のことば」で書いたのですが,医学は,基本的に線形思考ですよね.症状があって,診断があると,その次に介入があって….つまり病気を線形に捉えて,それを,こうだから,こうってロジックで詰めていくみたいな.診断学って,特にそうじゃないですか.すると,どうしても「病気,イコール治療する」というスタンスになります.優秀な研修医は,そういうのをパンパンパンと診断で決めて,ある意味,患者と話すというよりも「ロジックで,どれだけ早く鑑別診断に投げられるか」となってしまう.僕は高齢者率の高い沖縄県立中部病院で研修しましたが,まさに救急のメッカでいろいろ勉強になりましたけど,よ~く振り返ると8割くらいは線形思考で対処していたかもしれません.
植村 僕も思い起こすと恥ずかしくなります.でもそれが,みんなふつうなんですよね.当時は何の疑問も抱かなかった.だから,本書をきっかけに,そういうスタイルが少しでも変わっていけばいいなと思いますね.

マウントサイナイ病院の緩和ケアのオフィス(植村医師)
「え? そうなの?」が当たり前になる社会に
樋口 そういう意味で,編集部の程田さんが書いてくれた本書の紹介記事(「やさしく寄り添う医書のあり方 『あめいろぐ高齢者医療』・原稿前(?)整理の気づき」)の「え? そうなの?」という気づきはすごく大事だと思うのですよ.ある人には見えていて,ある人には見えてない.それがわかると,見えてくる世界が全く変わってくる.それが「高齢者医療の可能性」というか,ポテンシャルになるわけです.つまり,この分野はすごく劇的に変わる可能性があると思いますね.高齢化と長寿が達成された今の日本にすごく必要な考え方ではないかと.
反田 なるほど.
樋口 見え方が変われば,対応の仕方が変わる.「え? そうなの?」ではなく,それが当たり前になってくる.「あ,こういうふうにしたら,こういうふうに考えようね」という対応が全員で,どんな科でも,どんな先生でもできるようになったら,これ,すごくみんながハッピーになれるんじゃないかなって思うのです.
反田 「この部分をこう捉えると,日常の臨床がもっと変わる」といったポイントはほかにありますか.認知症や身体拘束の話がありましたが,この部分の,この考え方をテコ入れすると,もっと劇的に変わるみたいなお話があればぜひお聞かせください.
植村 日本にいたときからずっと思っていたことは,患者さんが本当に受けたいと思っている医療と,提供されている医療とのあいだに,すごくギャップがあるのではないかと思うのです.先ほどの認知症のお婆ちゃんの話とかぶるのですが,僕の同僚の患者さんで,気管挿管されて,気切(気管切開)になって,その後6カ月ぐらい生きていた方がいます.でも家族がもう医療費を払えないからと蒸発しちゃって,連絡も取れなくなるし,でも本人はずっと機械につながれたまま.痰をガーッてやって,超ゲホゲホって苦しそうにしている.尿路感染症になれば抗生剤を打って,さらに数カ月生きる.でも本人は認知症だし,何も言えないわけです.
「誰のためにこんなことをやっているんだろう」
って.極端な例ですが,こうした医療者側と患者側のギャップはたくさんあると思うのですよ.患者側にしたって,「本当に受けたい医療はこんなはずじゃなかった」「こんなつもりで病院に来たわけじゃなかった」ときっと感じていたはず.病院の一室に閉じ込められて,6カ月も機械につながれたまま,苦しかったと思います.でも,誰もその現実を確認せずに,ガイドラインがこうだから,教科書はこうだから,病気がこうだからって,ず~っと科学や医学の成果として,医療者が「治療」をやってきたわけです.
反田 考えさせられますね.
植村 だから何が大事なのかといえば,まずは,「患者や家族が何を求めているのか」「何がゴールなのか」をきちんと把握する.くり返しになりますけど,それが第一歩と思います.そのことを編集部も本書のメッセージとして受け止めてくれたからこそ,本書の帯に「まずは『患者のゴール』を拝聴する」とか,「医療ソムリエのように,患者と家族の価値観に寄り添った医の役割を提案できるか?」とキャッチコピーを入れてくれたのでしょう.本当に患者さんが受けたいと思っている医療を探して,それを提供する.それだけでだいぶ変わると思います.
ファイブ・エムズの考え方
樋口 今,植村先生がいってくださったのは,本書の2章でも取り上げた高齢者評価の5Ms(ファイブ・エムズ)の考え方,つまり「ジェリアトリクスに大切な5つのM」のうちの,Matters most(肝心なことは何か?)の部分だと思います.それとこの5つのMのうち,僕がもう1つ強調したいのは,Mobility(モビリティ,機能)です.高齢患者は病気の存在としてではなく,人として生きている,社会的に生きている人間なのです.医療の現場では,ともすると,患者から人の部分を外し,本人から病気だけを切り取って,それを無理くりに治療しようとします.でもそうではなくて,その方は「どういう機能の人で,どのくらいの認知機能で,身体機能はどうで,こんな社会的な機能をおもちで,そのうえで,こういう病気をもっている」というコンテクスト(文脈)を常に考えることがジェリアトリクス(老年科)で一番のポイントかもしれません.肺炎1つとっても,元気な80歳の肺炎と寝たきり状態の肺炎では,同じばい菌が起こした肺炎で,同じCTの写り方であっても,アプローチは変わるかもしれません.いや,変えてしかるべきかと.もちろんもともとの身体機能が違うとか,その後にどういうことが起こるのか,もしくは薬の副作用が起こる確率がどのくらいか,といったことも変数的に考えなければいけません.でも,どういう人がどのようにその病気をもつに至ったのか,そう点をしっかり考えることが重要です.
反田 本書では、5Msの考え方が何度も出てきますね.さらに,もう1つMを挙げるとしたら何でしょう.
樋口 Multi-complexity(複数のコンプレックスな問題)でしょうか.1章の植村先生の解説(Geriatrician・9カ条)で,「①老年科医は…,臓器別・疾患別ではない横断的な視点をもち,老年症候群に対応できる」と述べていますが,老年症候群に代表されるように高齢者の医療の現場では,患者の病気は1つではありません.症状の前面に出てくるのは,肺炎であったり,尿路感染症であるとしても,それと同時に認知症があり,体重減少があり,褥瘡があり,褥瘡があり,便秘がある.そういうさまざまな症状を1つひとつ拾い上げ丁寧に対応していくことと同時に,それぞれの症状への対応が煩雑になりすぎて,患者や家族の負担になっていないかにも気を配る.そのバランスを取ることで,高齢患者の前面に表出している病気も軽快していく.そういう姿勢が問われます.
反田 高齢者は複雑系なので,医学部や研修時で学んだセオリ―が当てはまらない部分があり,1つの正解というのがありません.日本の受験システムでは点数がつかない領域だし,研修医的にもやりづらいわけです.それこそ理系の行動様式とか,思考様式に当てはまらない感じがして,だからちょっと敬遠されてしまうのかもしれません.でも現在も,そしてこの先も,高齢の患者さんは目の前にたくさんいますし,お二方のように,シンプルかつ系統立ててアプローチしていく姿勢が求められるのでしょうね.

2017年ナーシングホームのチームメンバーと(左から4人目・樋口医師)
(最終回に続く)
※本カンファレンスは「あめいろぐ」の了解を得て、紹介しています.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
