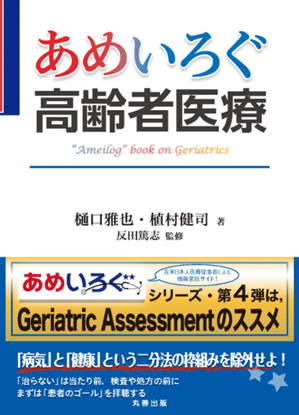やさしく寄り添う医書のあり方 『あめいろぐ高齢者医療』・原稿前(?)整理の気づき
こんにちは。
いち編集部のリアルです。
『あめいろぐ高齢者医療』について、Note4回目です。いよいよ中核のお話。前回は、本書の著者として、老年医学(Geriatrics、じぇりあとりくす)発祥の地・アメリカから老年医学とホスピス・緩和ケアを学ばれたドクター樋口とドクター植村を迎えたことを述べました。この2人、当然ですが、高齢者医療に関する情報量が半端ないです。
原稿が送られてくるたびに2人の原稿を読むと、日本で高齢患者を相手にされている医療者が述べる解説とは、記述の立脚点が異なるように感じました。アメリカで確立された老年科のエッセンスですから、その解説の軸もシステマティックにオーガナイズされたアプローチであるのはいうまでもありませんが、その前に、まず「高齢者医療とは何か?」の定義づけが明確なのです。
もっといえば、「高齢者とは何か?」「高齢患者とは何か?」。さらにいえば、「高齢者にやさしく寄り添う医療者のあり方とは何か?」になりますね。なので、冒頭章で、ドクター植村はいきなり【老年科医・9箇条】を打ち出します。
高齢者医療について、日本のドクターに話を聞いたり、執筆してもらうと、圧倒的に多い解説は、「こういう患者さんがいた」「ああいう症例があった」「そのときはこのように処置した」「ゆえに、こうするとよい」みたいな経験訓に基づく臨床知であったりします。もちろんそれは貴重な経験知であり、ある意味、エビデンス的にも裏づけされたアプローチなのですが、いち編集者として、そのような解説を読むと、「何か物足りない」と感じることがありました。
でもこれまで、それが何だったのか、よくわからなかったのです。
いち読者の目線で、今回本書を改めて読み直して気づいたことは、「高齢者医療に関する包括的な視野」の有無の違いでした。つまり1人の医療者が体得した高齢者医療の教訓やコツの伝授ではなく、
・高齢患者とはそもそもどういうもので、
・そのアプローチは成人患者の診療の延長という議論では対処しきれず、
・かつ死や家族ケアの問題を含むだけに、
・より多くの集合知で構築された考え方のほうが、
・結局、「もっとも無理のないものですよ」
・ゆえに、高齢患者がいた場合、患者個人や個々の疾患対処だけでなく
・その生活や家族も含め、患者像の全体を俯瞰しましょう
・高齢者医療は、そこから始まる
その語り掛けの連続のように思えたのです。なので、このビック・ビジョンを冒頭章でドクター植村は提示したのでした。
《高齢者医療に関する俯瞰的な視野》、これが第2の気づきのヒントでしょうか。
ビック・ビジョンを受け、こんどはドクター樋口は続く章で、そのアプローチの仕方のヒントを【老年医療の5Ms】として、さりげなく述べるのです。章ごとの解説者が立ち代わり話をつなぎ、ちょっと漫才の掛け合いのようですが、それぞれが、甲といえば、受け皿として乙を掬い、丙と投げかければ、丁と応じる。2人の論旨がどんどん連動していく感じです。
あれ、これって、どういうことなの…?
こんな理想的な共著のカタチって、ある…?
あ、そういうことか…。
標準治療か。
この2人は意識せずに老年科医としての標準治療を淡々と述べられていたのですね。標準治療だから、誰が述べても高齢者医療の語りの軸がブレない。仮に1章をドクター植村の代わりにドクター樋口が執筆したとしても、論旨はきっと同じ。それはある医療者の経験則ではなくて、誰が行ってもある一定の治療のアウトカムが提供できる、臨床上のアカデミックの知恵の集積だからでしょう。米国の老年科研修のトレーニングを積んだ彼らにしてみれば、それは当たり前のふつう(標準にして最良)の表白なのでしょう。
《標準治療、やっぱり大事》。第3の気づきのヒントはここですかね。
さて、本書の制作では、今まで経験したことのないある事態に遭遇しました。高齢者医療に関するあまりにも多くのアプローチ、あまりにも多くの視野をお持ちのドクターですから、途中で原稿がストップしてしまったのです。それも、かなりの期間。どういうことか…。
例えば、高齢患者の代表的な症状といえば、認知症ですが、認知症について書き出すと、あれも、これも、それも…と認知症の高齢患者に対する診たての仕方やアプローチのストックが豊富過ぎて、「何を書くべきか」の取捨選択でオーバーヒートしてしまったのです。原稿に書くことがないから(煩悶・筆が停滞)はよくありますが、異例ですね。
そこで行ったのが、「原稿(執筆)前整理」。原稿整理は原稿をいただいた後に編集部で行う作業ですが、原稿が執筆される前に原稿内容を整理しようと、米国におられる2人の著者とスカイプ会議で日本時間の午前11時(米国時間夜10時頃)に、月1回「原稿前整理」を行うことになりました。
• まず、会議の前にドクター樋口が原稿のプロットとなる長大なワード原稿を用意します
• 事前に編集部で目を通しますが、プロット原稿なので難しすぎて理解しきれません(焦ります)
• 開始時間になり、オブザーバーとしてハワイからドクター植村も参加
• 開始、ドクター樋口が和やかな調子で、本日の議題を提示し、考え方の整理の手順をざっくり説明。「それでどうか」と編集部に賛同を求めますが、この段階では正直まだ呑み込めてません(焦り・2回目)
• そこに助け船的にドクター植村が的確なコメント(助かった)
• ドクター樋口がとうとうと説明をはじめます
• すると、どうでしょう、コメントの端々に「え、そうなの…?」という驚きが次から次へとやってくるのです
今でも覚えているのは、ドクター樋口のコメントで、
「認知症はがんや心筋梗塞と同じく、死を至る疾患なのです」
「え、そうなの…?」(2回目)。
日本人の死因の第一位は「悪性新生物(がん)」、次に「心疾患」「脳血管疾患」「肺炎」「その他」(75歳以上)と続きますが、ここには「認知症」がありません。
すかさず編集部が聞き返します。「認知症が死因というのは、どういう意味ですか?」。するとドクター樋口は静かに「ああ、日本ではそういう認識があまりないかもしれませんね。認知症の高齢患者が辿る疾患のトラジェクトリー(軌跡)をご覧いただければわかるのですが、認知症は、進行性であり、不可逆的で、「いずれ死に至る病」であり,死に至るまでその状況が続きます。しかも認知症薬では治せません。だからその徐々に下る命の軌跡を患者さんと家族に寄り添い、どうしましょうか?と共に考え、提案するのが老年科医の役割なのです」と答えます。
「まずその認識がないと、患者と家族が考えるゴール(価値観)を見誤ります。それは患者目線ではなく、疾患を科学的に治療しようとする医療者目線のアプローチです」。
その後も、月1回「原稿前整理」は何度も行われました。
臆面もなく申し上げますが、この本には2人の老年科医がひも解く、高齢者医療の気づきがとにかく多くあります。(今、ざっと数えたら28箇所ありました。付箋を入れたので。この数は本当です)。長年医書編集をしていますが、「え、そのうなの…?」の気づきが、1章から最終章までずっと続く本というのもなかなか珍しいと思います。
《え、そのうなの…?》、これが第4の気づきのヒントです。詳しくは本書をご覧ください。
次回、最終回に続きます。
ご清聴(読)ありがとうございました。
2020.8.22
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?